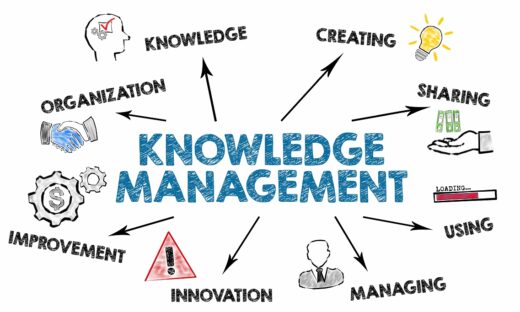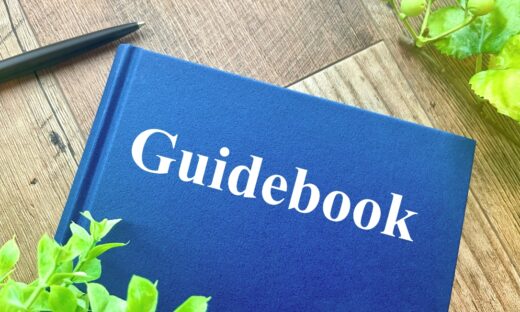初めて起業する人のための資金計画・人材採用・法人化ガイド

初めて起業する際に最も不安要素となるのは「お金」に関することではないでしょうか。事業ビジョンがしっかりしていても、必要な資金が準備できなければ起業を軌道に乗せることはできません。
この記事では、法人設立に必要な開業資金の内訳や業種別の初期費用の違い、そして資金調達の方法を解説します。
また、創業初期に従業員を採用するメリット・デメリットや人件費と社会保険コストの計算方法、さらに個人事業主から法人化するタイミングと費用についても詳しく紹介。
具体的な金額目安や最新の公的支援制度・補助金情報も織り交ぜていますので、これから初めて起業する方の参考になれば幸いです。
目次
開業資金の内訳と業種別の相場
初めての起業では「いったい何に、いくらかかるのか」が見えにくいものです。
法人設立時に必要となる資金の内訳をわかりやすく分類し、あわせてIT業、小売業、飲食業など業種ごとの開業費用の相場を詳しく紹介します。
具体的な金額感や、想定すべき費用項目を押さえることで、無理のない資金計画を立てる第一歩となるはずです。

開業資金の平均額と必要性
起業にあたってまず押さえておきたいのは、開業時にどれくらい資金が必要になるかという点です。
日本政策金融公庫の調査によれば、新規開業時に必要な資金は平均約1,027万円(中央値550万円)と報告されています。
ただし、この数字は業種や事業規模によって大きく異なり、1,000万円以上かかるケースも珍しくありません。
法人を設立する場合と個人事業で開業する場合でも必要資金は変わります。
個人事業主として開業するなら、開業届を提出するだけで登録費用は不要です(税金や資本金も不要)。
一方、法人を設立する場合は登記費用や定款認証料など最低でも10万円程度の法定費用が必要になります。
会社形態によっても異なりますが、たとえば株式会社設立時には登録免許税15万円(または資本金の0.7%)、定款認証手数料約5万円、定款の収入印紙代4万円(電子定款なら不要)など合計約25万円前後の費用がかかるのが一般的。
このように、起業形態によって初期費用の規模感が変わるため、自分のケースでどれくらい資金を準備すべきか最初に把握しておきましょう。
また、開業資金には事業立ち上げに必要な設備費だけでなく、運転資金(開業後しばらくの経費)や予備資金(生活費等の蓄え)も含めて検討することが重要です。
特に開業直後は売上が軌道に乗るまで赤字が続くことも多いため、固定費の3〜6か月分程度の運転資金を余裕をもって用意しておくと安心です。
仮に数ヶ月赤字が続いても事業を継続できるだけの余剰資金を計画に入れておきましょう。
開業資金の主な内訳項目
開業資金には様々な費用項目が含まれます。
主な内訳としては以下のようなものが挙げられます。

物件取得費(オフィス・店舗関連費)
賃貸物件の敷金・礼金・保証金、仲介手数料、看板設置料、駐車場契約料など、事業拠点を確保するための費用です。
例えば店舗を構える場合、契約時に数か月分の賃料の保証金が必要になることが一般的です。
オフィス開設でも、初期費として数十万円~数百万円の物件取得費を見込んでおく必要があります。
設備費・内装工事費
店舗の内外装工事、電気・水道・ガス等の工事、空調設備、厨房設備(飲食業の場合)など、事業に必要な設備投資費用です。
店舗型ビジネスでは改装費・設備費が開業資金の中で大きな割合を占めます。
備品・機器購入費
事務所の机や椅子、パソコンやプリンターなどのOA機器、業種によっては専門機械や工具類、ユニフォームや消耗品などの購入費です。
IT系であれば高性能なPCやソフトウェア購入費、飲食店であれば調理器具や食器類の購入費も含まれます。
システム導入費
最近ではキャッシュレス決済端末やPOSレジなどのITシステム導入費も見逃せません。業種によって必要なシステムは異なりますが、効率化のためのソフトウェア導入費用なども考慮しましょう。
登記関連費
法人設立の場合は前述の登録免許税や定款認証料、会社実印の作成代、印鑑証明の取得費などの法定費用が必要です。
合同会社であれば定款の認証が不要な分費用は抑えられますが、それでも設立登記に約10万円+資本金が必要になります。
運転資金
開業後、事業が安定するまでの家賃、人件費、仕入れ代、光熱費などの運転資金も開業資金に含めて準備しておきます。
事業開始直後から黒字になるとは限らないため、最低3か月分、余裕があれば6か月分程度の固定費・変動費を賄える資金を確保することが理想です。
予備資金(生活費)
起業後しばらく自身の役員報酬や収入が不安定になる可能性があります。
半年から数年は赤字が続くケースもあると言われますので、その間の生活費としての蓄えも含め、余裕をもった資金計画を立てましょう。
業種別に異なる初期費用の相場
開業資金は事業内容や業種によって大きく異なります。
業種によってはほとんど資金をかけずに始められるケースもあれば、1,000万円を超える初期投資が必要になるケースもあります。
自分が参入する業界ではどの程度の資金が一般的に必要とされるのか、事前に把握しておきましょう。
以下、代表的な業種の初期費用の目安と内訳の特徴です。
小売業(店舗販売型ビジネス)
リアル店舗で小売業を始める場合、設備資金の割合が非常に大きくなります。
店舗物件の取得費や内外装工事費、什器備品の購入費など、多岐にわたる初期費用が発生します。
コンビニエンスストアをフランチャイズで開業する場合、加盟金だけで100万~300万円ほどかかると言われています。
自前で店舗を構える場合やオーナーが内装費を負担する場合はさらに多額の資金が必要です。
一般的な小売店でも、物件取得費(保証金・敷金等)、内装改装費、機器設備費(レジや空調など)、在庫仕入れ費などが発生し、数百万円~1000万円超の資金が必要となるケースもあります。
飲食業(レストラン・カフェ等)
飲食店の開業資金は特に高額になりがち。
東京都内で小さな飲食店を開く場合でも最低1000万~1500万円程度は必要とされることが多く、自己資金だけでなく金融機関からの融資を活用するケースが一般的です。
内訳としては小売業と同様に店舗取得費、内装・厨房設備費、備品費に大きな割合を占めますが、加えて開店前のメニュー開発費や広告宣伝費などもかかる場合があります。
費用が大きい分、見直せる項目を洗い出して初期投資を抑える工夫も重要になります。
中古設備の活用や内装を簡素にすることでコストダウンを図るケースもあります。
IT・ソフトウェア業(オンラインサービス・開発業)
IT系の事業は他業種に比べて比較的少ない資金で開業しやすい傾向があります。
パソコンとインターネット環境さえあれば自宅でも開始でき、人を雇わず一人で始めるのであれば開業資金はごく小額に抑えられるでしょう。
オフィスを構える場合でも、主な初期費用は物件取得費とPC・ソフトウェア導入費、通信費くらいで済みます。
例えばフリーランスのプログラマーが起業するケースでは、50万~100万円程度のパソコン・開発ソフト費用と数か月分の生活費程度でスタートする例もあります。
ただし、事業拡大に伴いサーバー代や追加人件費などが発生すれば、その都度資金ニーズが高まります。
またIT業界は市場変化が速く、事業機会が豊富な反面競争も激しいため、開業後の運転資金にも余裕を持っておくことが望ましいでしょう。
サービス業(サロン・教室・各種サービス提供)
サービス業は業種によって必要な設備や規模が様々です。
例えばエステサロンや美容院、ヨガスタジオなど店舗型サービス業の場合は小売・飲食に近い項目の費用がかかりますが、自宅の一室で開業するようなケースでは初期費用を大幅に抑えることも可能です。
サービス業では集客のための広告宣伝費も重要で、開業時に販促費用が必要となる点が特徴です。
費用項目としては店舗取得費、内装設備費、備品購入費に加え、販売促進費(チラシやウェブ広告等)が挙げられます。
規模にもよりますが、小規模サロンなら数十万~数百万円、店舗を構える場合は数百万円以上の資金準備が目安となります。
開業資金の調達方法(自己資金・融資・補助金)
「やりたい事業はあるが自己資金が足りない」という場合でも、適切な方法を取れば必要な開業資金を調達することが可能です。
主な資金調達方法としては自己資金の投入、金融機関からの融資、そして補助金・助成金など公的支援の活用が挙げられます。
自己資金の準備
可能な限り自己資金を増やしておくことは、後述する融資審査の面でも非常に重要です。開業にあたり借入をする場合でも、借入希望額の1/2〜1/3程度の自己資金を用意しておくのが望ましいとされています。
自己資金は借入以外で蓄えたお金である必要があり、金融機関は預金通帳の提出などを求めて「その資金が計画的に貯蓄されたものか」を厳しくチェックします。
短期間に借り集めた資金などは自己資金と認められず融資を断られるケースもあるため注意しましょう。
起業を志したら早めに貯蓄計画を立て、可能なら親族からの支援なども検討しつつ、自己資金をできるだけ厚くしておくことが大切です。
金融機関からの融資
創業資金の融資を受ける代表的な手段が日本政策金融公庫(政府系金融機関)の創業融資制度です。
日本政策金融公庫では「新創業融資制度」や「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」「再挑戦支援資金」等、起業・開業向けの様々な融資メニューを用意しています。
国が100%出資する政府系金融機関であり、民間からの借入が難しい小規模事業者にも積極的に融資を行っている点が特徴です。
このほか、各都道府県や市区町村などの自治体の制度融資も利用できます。
例えば東京都の「中小企業制度融資・創業」は申込対象のハードルが低く、多くの創業者が活用しています。自治体によっては、クラウドファンディングを活用した資金調達に対する補助(東京都ではクラウドファンディングの手数料を補助する制度など)を設けているところもあります。
民間の銀行からの融資ももちろん可能ですが、都市銀行など大手は創業間もない個人・小規模事業には消極的な傾向があります。
一方で地方銀行や信用金庫など地域金融機関は中小企業への融資実績が豊富な場合が多いですが、金利が高めだったり担保や保証人を求められる場合もあります。
金融機関から借入を検討する際は、事業計画書をしっかり作成し、自己資金割合や自身の業界経験など強みをアピールすることが重要です。
実務経験が豊富であれば融資は受けやすく、逆に全くの未経験分野での起業だと審査は厳しくなります。

補助金・助成金の活用
国や自治体は起業・新事業向けに様々な補助金・助成金制度を提供しています。
これらは返済不要の資金援助で、大きな助けとなる反面、公募期間や採択件数に限りがあり必ず受給できるものではない点に注意が必要です。
代表的なものに、中小企業庁関連の「小規模事業者持続化補助金」(小規模事業者が行う販路開拓等の経費を最大50万円補助)や「ものづくり補助金」(革新的サービス開発等の設備投資を補助)、「IT導入補助金」(業務効率化のITツール導入費を補助)などがあります。
他にも厚生労働省系の「キャリアアップ助成金」や「地域雇用開発助成金」、自治体独自の創業支援助成など多彩なメニューがあります。
条件に合致し活用できそうなものがあれば是非検討してみましょう。
ただし補助金は応募書類の準備や事務手続きも煩雑なため、申請には時間的余裕を持ち、採択基準や使途制限をよく確認することが大切です。
助成金については以下の記事も参考にしてください。
「中小企業向け助成金の種類と特徴!どの助成金が活用できる?」
創業融資を受ける際のポイント
資金調達方法の中でも特に融資を利用する場合、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
まず借入額は必要最小限に留めること。
借りたお金には利息が付く以上、事業の返済負担になりますので、無理なく返済できる範囲で計画することが重要です。
「借りられるだけ借りておこう」と安易に考えるのではなく、開業時期を少し延ばして自己資金を増やす努力をしたり、親族からの支援で借入額を減らすなど工夫しましょう。
また融資審査では前述のように自己資金の額と形成過程、起業分野での経験・実績が重視されます。
加えて事業計画の整合性(収支計画が現実的か、返済原資となる利益が見込めるか)もチェックされます。
金融機関担当者に自社のビジネスモデルや将来見通しを説明できるよう、しっかり準備して臨みましょう。
万一希望額の融資が難しい場合でも、創業融資に強い制度(日本政策金融公庫の新創業融資などは無担保・無保証人で借りやすい)や、自治体の創業支援融資(信用保証協会の保証付き融資)など複数の選択肢を検討するのがおすすめです。
なお、融資以外の選択肢として、エクイティファイナンス(出資を募る)やクラウドファンディングなどもあります。
特に将来大きな成長を見込むビジネスであれば、創業当初にベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から出資を受ける道もあります。
出資による資金調達は返済不要ですが、自社株式を渡すことで経営権に影響が及ぶ可能性もあるため慎重に判断しましょう。
いずれにしても、調達した資金は開業資金のどの項目に充当するかを明確にし、計画的に使うことが重要です。
お金を確保できた安心感から無駄遣いしてしまわぬよう、資金使途を常に管理して起業初期を乗り切りましょう。
起業初期の従業員採用と人件費の考え方
起業したばかりの時期に従業員を採用するべきかどうかは、多くの起業家が悩むポイントです。
創業初期における採用のメリット・デメリットを整理し、人件費や社会保険料などの具体的なコスト計算、採用の適切なタイミング、人件費を抑える工夫について詳しく解説します。
限られた資金で無理なく人を雇うために、知っておきたい基礎知識になりますので参考にしてください。
従業員を採用するメリット
創業直後は何もかも経営者一人で対応しなければならず、多忙を極めます。
そんな中で従業員を雇用することには大きなメリットがあります。まず、雑多な業務や事務作業を任せられる点です。
一人で事業を回していると、メール返信や電話対応、請求書発行や経理処理など本業以外の事務作業に追われがちです。
そこでスタッフを雇ってこれら事務作業を委ねれば、経営者は本来の事業活動により集中できるようになります。
また、従業員を増やすことで業務処理能力が向上し事業拡大につながる可能性もあります。人手が足りず受注を断っていた仕事も、人員が増えれば対応できるようになり、結果として売上・業績アップが期待できます。
もちろん雇用した直後は新人教育に時間がかかりますが、スタッフが仕事に習熟し一人前になれば、任せられる範囲が広がり経営者の負担軽減と売上拡大の両面でプラスに作用するでしょう。
さらに、家族を従業員として雇用する場合には節税メリットも得られます。
個人事業主が生計を共にする配偶者や親族に給与を支払う場合、青色申告の届出をして「青色事業専従者給与」とすればその給与を全額経費に算入できます(一定の要件と事前届出が必要)。家族の協力を得て事業を手伝ってもらい、その対価を経費処理できれば、事業主の税負担を軽減しつつ事業の手を広げられるメリットがあります。
ただし青色申告を行うには複式簿記による帳簿付けが必要になるなど手間も増えるため、会計ソフトの導入や専門家への相談も検討しましょう。
以上のように、創業者が自分だけでは手が回らない仕事を任せられること、事業拡大のスピードを上げられること、場合によっては税務上のメリットも得られることが、従業員を採用する主なメリットです。

従業員を採用するデメリットとリスク
一方で、創業初期に従業員を雇うことにはいくつかのデメリットやリスクもあります。
まず採用活動そのものの大変さがあります。
良い人材を見つけるのは容易ではなく、求人に応募が来てもその人が本当に必要な戦力か見極めるには時間と面接などの労力を要します。
採用したもののミスマッチだった場合でも、法律上簡単に解雇することはできず、問題社員であっても対処に苦慮するケースがあります。
人を雇う以上は雇用責任が発生し、業績が悪化したからといってすぐ解雇とはいきません。
労働法上、従業員は手厚く保護されているため、経営者は一度雇った従業員とその家族の生活も背負う覚悟が求められます。
次にコスト負担の問題があります。
従業員に給与を支払うだけでなく、雇用した途端に会社(事業主)には様々な法定福利費の負担義務が生じます。
従業員を1人でも雇えば労災保険・雇用保険(労働保険)の加入が必要となり、さらに常時5人以上(従業員規模や業種による)雇用する場合は社会保険(健康保険・厚生年金)の事業主負担が発生します。
社会保険に加入すると会社は従業員給与の約半分の保険料を負担しなければなりません。
人件費が増えることで毎月の固定費が大きく膨らみ、売上が不安定な創業期には重いプレッシャーとなるでしょう。
また、創業当初は経営者自身が営業から経理まで全てをこなして事業を軌道に乗せる時期ですが、その最中に新人従業員の教育やマネジメントに時間を割く負担も無視できません。
事業の全容が固まっていない創業直後に他人に指示を出すのは難しく、自分でやった方が早いという状況も。
未経験の新人を採用した場合は特に教育に手間取り、経営者の時間が取られて肝心の事業推進に支障が出る恐れもあります。
以上のように、採用・雇用には手間とリスクが伴うこと、人件費や社会保険料の負担でコスト増となることが創業時に従業員を抱えるデメリット。
対策として、社会保険の負担が生じない範囲(例えば短時間のパート勤務など)で人に手伝ってもらう方法も検討できます。
実際、初めのうちは正社員ではなくアルバイトや業務委託で様子を見て、事業規模拡大とともに正社員登用するという段階的な採用を行うケースが一般的になりつつあります。
採用を急ぐあまり早計に正社員を増やしてしまうと、想定外のコスト増に後から気付いて苦労する—という失敗も起こり得ますので注意が必要です。
従業員を採用するタイミングの考え方
最初の従業員をいつ採用すべきかは創業者にとって悩ましい問題です。
結論から言えば、「どうしても最初から従業員が必要な業種」(例:24時間営業の店舗など)を除き、事業が軌道に乗る前の数ヶ月は極力、役員(創業メンバー)だけで回すのが望ましいとされています。
理由の一つは前述した資金面のリスク。
安定した売上が確保できていない状態で毎月の給与を払い続けることは、会社のお金が減っていく一方になりかねません。
まずは売上と支出のバランスが取れるまで自力で踏ん張る期間を設け、その後、人件費を支払っても利益が残る見通しが立った段階で初めて従業員採用に踏み切るのが安全です。
もう一つの理由は、創業直後は経営者自身が手探りで事業モデルを固めていく時期であり、人に教えたり指揮したりする余裕がないことです。
事業開始直後は「自分が何から何まで動かないと前に進まない」状態になります。
このタイミングで従業員を迎えても、仕事を教える暇がなく持て余してしまったり、逆に教育に時間を取られて肝心の事業構築が遅れたりという事態になりがちです。
さらに一度雇用契約を結べば簡単に解消できないため、早まった採用で人件費の固定負担を抱えてしまうと身動きが取れなくなる危険も。
総合的に見て、「売上が社員の給料を十分まかなえる見通しが立った時」が従業員採用の一つの目安と言えます。
例えば、ある程度継続案件の受注が確保できており、自分一人ではさばききれないほど仕事量が増えてきた時が採用時期でしょう。
また、外部から資金調達(融資や出資)を受けていて当面の運転資金に余裕がある場合には、将来を見越して戦略的に早めに人材を投入する判断もあり得ます。
プロジェクトを素早く推進するために、創業初期から優秀な人材(エンジニアや営業など)を迎え入れるスタートアップ企業も存在します。
その場合でも、採用した人が十分に力を発揮できる環境や、将来的に継続雇用できる資金計画を用意しておく必要があります。

人件費と社会保険コストの計算方法
人件費には支払う給与だけでなく、会社が負担する社会保険料や福利厚生費など様々な要素が含まれます。
創業時に初めて従業員を雇う場合、想定以上に費用がかかることに驚く経営者も少なくありません。
給与額だけに目を向けず、付随するコストも把握しておきましょう。日本の社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料率は労使合計でおよそ給与の30%前後にのぼり、会社と従業員がこの保険料を半分ずつ負担します。
つまり会社は給与とは別に約15%程度を社会保険料として負担する計算になります。
例えば月給30万円の従業員を1人雇用すると、会社はその人に対して実質約34万5千円(30万円+会社負担分約4万5千円)を支払っているのと同じになります。
この会社負担分の社会保険料は、給与支払翌月などにまとめて請求が来るため、後から「こんなに高いのか」と驚く経営者もいます。
さらに賞与(ボーナス)を支給する場合にも同様に社会保険料がかかり、賞与額の約15%を会社が追加負担する必要があります。
従業員に夏の賞与100万円を支給すれば、会社は別途約15万円の社会保険料を負担しなければなりません。
社会保険料以外にも、雇用保険料(労働者負担と会社負担があり、会社負担は給与の0.6%前後)、労災保険料(業種によるが0.3%~数%)といった労働保険料も発生します。
また従業員一人増えるごとに、通勤交通費(定期代)や備品購入費(机・イス・PCなど)、福利厚生費(健康診断費用等)も追加でかかります。
総合すると、給与以外に少なくとも給与額の2~5割のコストが発生すると見ておくべきです。
人件費試算の一例として、月給30万円の社員3人を雇用した場合を考えてみましょう。
単純計算で月の給与総額は90万円ですが、社会保険料の会社負担分だけで約13万5千円(90万円×15%)が必要です。
給与振込が終わってホッとした頃に、まるで4人目の社員を雇ったかのような額の社会保険料請求が来る、と表現されることもあります。
したがって人件費を見積もる際は、「月給×人数」に加えて「法定福利費(社会保険料等)」や「賞与想定額×15%」なども織り込んだ上で資金計画を立てることが大事です。
人件費率(売上に占める人件費割合)も合わせて計算し、適正な水準に収まっているか確認しましょう。
人を増やすことで売上も増える見込みがあるのか、あるいは固定費負担が利益を圧迫しすぎないか、数値でシミュレーションしておくことをおすすめします。
人件費負担を抑える工夫
助成金の活用も検討しましょう。
国や自治体には雇用に関する助成金(例:厚労省の「トライアル雇用助成金」や「キャリアアップ助成金」等)があり、一定条件を満たす採用に対して奨励金が支給される場合があります。
該当しそうな制度があれば積極的に申請することで、人件費の一部補填を受けられるかもしれません。
ただし助成金は一時的な支援策なので、あくまで自社の利益で継続的に人件費をまかなえる体力をつけることが最終目標です。

個人事業主と法人の違い・法人化のタイミングと費用
起業を始めたばかりの方にとって、「いつ法人化すべきか?」は重要な判断ポイント。
この章では、個人事業と法人の税制や社会的信用の違いを明確にし、法人化によるメリット・デメリット、適切なタイミング、実際にかかる費用について丁寧に解説します。
節税や資金調達を見据えた判断の材料として、ぜひ参考にしてください。
税金面で見る個人事業と法人の違い
税制の仕組みは個人事業と法人で大きく異なります。
個人事業主の場合、事業で得た利益に対して課せられるのは「所得税」であり、累進課税(利益が増えるほど段階的に税率が上がる仕組み)となっています。
一方、法人が支払う「法人税」は一定の税率で課税され、少なくとも中小企業の場合は所得800万円まではほぼ一律の税率で、それを超える部分にやや高い税率が適用される程度です(現在の法人税等実効税率は中小法人で約20〜23%前後です)。
個人事業主の所得税は、課税所得330万円超~695万円以下なら20%、695万円超~900万円以下は23%と上がっていきますが、法人税は800万円以下の所得に対して約15%(法人住民税・事業税含め約21%)と個人より低率に抑えられています。
このため利益水準がある程度高くなると、個人より法人の方が税負担が有利になる傾向があります。
一般に年間所得が800〜900万円を超えてくると法人化した方が節税できる可能性が高いと言われています。
実際の有利不利は経費の状況や所得控除(青色申告特別控除65万円など)の適用にもよりますが、1つの目安として覚えておきましょう。
なお、個人事業主には事業所得に対して青色申告特別控除(最大65万円)が適用できるなどの優遇もありますが、法人化すればそれは使えなくなります。
しかし法人は経営者自身の給与(役員報酬)を経費にできるため、個人事業では控除しきれなかった利益を法人では役員報酬として落とすことで課税所得を減らすことができます。
事業利益500万円を個人で計上すればその全額に所得税が課されますが、法人にして役員報酬400万円・法人利益100万円とすれば、法人税と役員個人の所得税に分散でき税率区分も抑えられる可能性があります。
このように法人は利益を役員給与として振り替えることで実質的な圧縮が可能なのです。さらに法人には消費税に関する節税メリットもあります。
個人・法人問わず前々年の売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になりますが、法人を新設すれば設立から原則2期は売上1,000万円以下なら消費税免税となる特例があります(資本金1,000万円未満など一定要件を満たす必要あり)。
そのため、個人事業で売上が1,000万円を超えて消費税納税義務が発生しそうな場合に法人化して消費税負担を一時的に回避するといった節税策も取られます。
ただし令和5年開始のインボイス制度の影響で免税によるメリットも変わってきているため、専門家と相談のうえ判断するのが望ましいでしょう。
まとめると、税金面では利益規模や売上規模に応じて法人化のメリットが現れるため、現在および将来の利益水準を見据えて検討することが重要です。
法人化のメリット:節税効果と経費の拡大
前述のように、法人化最大のメリットの一つは節税効果です。
個人の所得税は利益が増えるごとに累進的に税率が上がりますが、法人税は中小企業であれば所得800万円を境にほぼフラットな税率となります。
そのため一定以上儲かる事業であれば、個人で払い続けるより法人にした方が税率が頭打ちになりトータルの税負担が軽減されます。
極端な例を言えば、所得1,000万円超を個人事業で稼ぐと所得税・住民税だけで30〜40%以上取られることもありますが、法人にして役員報酬と法人利益に配分すれば、それぞれ20数%程度で済む可能性があります(※正確な税負担率は所得配分の仕方で変動します)。また法人化すると経費に計上できる範囲が広がる点も見逃せません。
個人事業主の場合、家族への給与は一定の制限下でしか経費にできませんが、法人なら家族でも従業員として適正な給与を支払えば全額経費にできます。
自宅兼事務所の場合の家賃や光熱費も、法人であれば経営者個人との賃貸契約を結ぶことで会社経費として計上できるケースがあります(いわゆる自宅オフィスの家賃を法人負担にする方法)。
交際費(取引先との会食等)についても、中小法人には年間800万円まで全額損金算入できる特例があり、個人事業主より経費計上の自由度が高いです。
さらに役員報酬の支給により、利益を役員給与として分散させれば所得税と法人税の両面で控除・非課税枠を活用できます。
例えば役員に家族を加えて給与を分散すれば、各人の所得税の基礎控除や低率の課税枠をフルに使えるわけです。
場合によっては法人化することで年間数百万円~数千万円規模の節税になることもあります。
ただし注意点として、役員給与を不自然に高額に設定して利益をゼロに近づけるような行為は、税務上「不相当に高額な役員報酬」とみなされ否認される可能性があります。
節税メリットを享受できるとはいえ、税法の範囲内で適正に行う必要があります。
まとめれば、法人化により税率構造が有利になることと経費算入の幅が広がることで節税余地が大きくなるのが利点。
特に利益が増えてきた場合は、法人成りによって税引後キャッシュを増やし、その分を設備投資や人件費に再投資できるなど、事業拡大の資金を生み出しやすくなります。

法人化のメリット:信用力・資金調達力の向上
法人化には税金以外にも社会的信用の向上という大きなメリットがあります。
一般に取引先から見ると、個人より法人の方が信頼感が高い傾向があります。
特にBtoB(企業間取引)ではその差が顕著で、個人事業主だと取引先企業から契約を敬遠される場合があります。
一方、株式会社や合同会社など法人格があれば、「組織として責任を持って事業を行っている」という印象を与えられ、取引の土俵に乗りやすくなります。
大企業や官公庁の案件では法人でないと参加すらできないケースもありますし、法人名義の銀行口座・法人住所があるだけで与信面の評価が上がる場面もあります。
さらに資金調達の面でも法人は有利です。
銀行融資においても、創業時は代表者個人の保証など求められることが多いものの、事業が軌道に乗れば法人の信用で融資枠を拡大しやすくなります。
また投資家からの出資を募るには法人であることが前提です。
特に株式会社は株式発行による出資受け入れが可能なので、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの資金調達には株式会社設立が必須となります。
合同会社(LLC)は持分の譲渡はできますが株式発行制度が無いため、大規模な資金調達には不向きです。
このように法人化すると、金融機関や投資家からの信頼が増し、資金調達力が高まる効果が期待できます。
加えて、法人は組織として永続性がある点も信用力アップにつながります。
代表者個人に万一のことがあっても法人は存続できますし、対外的にも「ちゃんと法人登記している=簡単に消えない」という安心感を与えます。
その他、法人化すれば社名(商号)に「株式会社〇〇」等を冠することになり、社会的な見映え・ブランディング面でもプラスに働く場合があります。
採用活動でも「法人の方が応募が集まりやすい」「信用力が高い会社の方が人材を確保しやすい」という声があります。
まとめると、法人化は取引上の信頼性を高め、より大きなビジネスチャンスや資金調達の機会を掴みやすくするというメリットがあります。
特に将来的に事業拡大を目指すなら、しかるべき段階で法人化しておくことで得られる恩恵は大きいでしょう。
法人化のデメリット:費用負担と事務手続き
もちろん法人化にはデメリットや留意点もあります。
まず設立・維持にコストがかかることです。法人を設立するには先述のように20万円前後(株式会社)または10万円前後(合同会社)の登記費用が必要です。
この初期費用は個人事業には不要な出費です。
また法人設立後も、毎年法人住民税の均等割(たとえ赤字でも最低7万円程度)を納付する必要があります。
個人事業なら利益がゼロなら所得税・住民税もゼロですが、法人は利益がなくても一定の税金負担が発生する点は注意が必要です。
さらに社会保険加入の義務も法人には課されます。
法人は従業員が一人もいなくても代表者=役員がいれば社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所となり、役員報酬に対して会社と役員本人で保険料を納めなくてはなりません。
個人事業主の場合、従業員5人未満なら社会保険加入は任意(業種による)で自らは国民健康保険・国民年金に加入する選択肢がありますが、法人化すると強制的に社保加入となるため、その分の負担増も考慮しましょう。
次に事務手続きや帳簿管理の煩雑さがあります。
法人は毎期ごとに決算を行い、法人税の確定申告をする義務があります。
個人の確定申告と比べて法人決算は専門知識を要するため、税理士に依頼する場合は顧問料など費用も発生します。
加えて、役員変更や本店移転など会社の重要事項に変更がある度に法務局へ登記申請しなければならず、そのたびに数万円の登録免許税がかかります。
官公庁へ提出する各種届出(社会保険・労働保険の手続き、事業年度ごとの法人事業概況説明書の提出など)も増えます。
つまり法人化すると事務管理コストと外部専門家への支払いが個人事業に比べて増える傾向にあります。
さらに、法人は利益が出れば法人税が課せられ、利益がゼロでも前述のように最低限の税金負担があり、仮に赤字でも毎年決算申告が必要というプレッシャーも。
一方個人事業であれば、事業がうまくいかなくても廃業届を出すだけで比較的身軽にやめられるのに対し、法人をたたむには清算手続きや費用がかかります。
最後に利益の取り扱いについて、法人にすると事業で上げた利益は原則として全部会社のものになるため、経営者が自由に使うには役員報酬や配当という形でいったん税金を払ってからでないと引き出せません(俗に「法人は財布が別になる」と言われる点です)。
個人事業なら儲かった分はすべて自分のものであり、生活費にも自由に流用できますが、法人では会社と個人の財布を明確に分けなければならず、そこに不便さを感じる人もいます。
まとめ:法人化するなら十分な計画を
初めての起業では、資金計画・人材戦略・法人化の是非といった決断が数多く求められます。
開業資金は項目ごとに洗い出して必要額を見積もり、自己資金・融資・補助金を組み合わせて無理のない方法で調達しましょう。
創業初期の人員計画については、メリット・デメリットを踏まえ、慎重にタイミングを見極めて採用することが重要です。
人件費には社会保険料など付随コストもあるため十分計算し、必要に応じて段階的な雇用や外部リソース活用で負担を調整してください。
法人化に関しては、税金面・信用面で一定のメリットがある一方、早すぎる法人化はコスト増につながる恐れも。
売上や利益の状況を見ながら、適切なタイミングで法人成りを検討するのがおすすめです。最新の公的支援策や専門家の力も積極的に活用しながら、堅実かつ成長志向の起業準備を進めましょう。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら