中小企業向け助成金の申請手順:申請から助成金を受け取るところまでの流れ
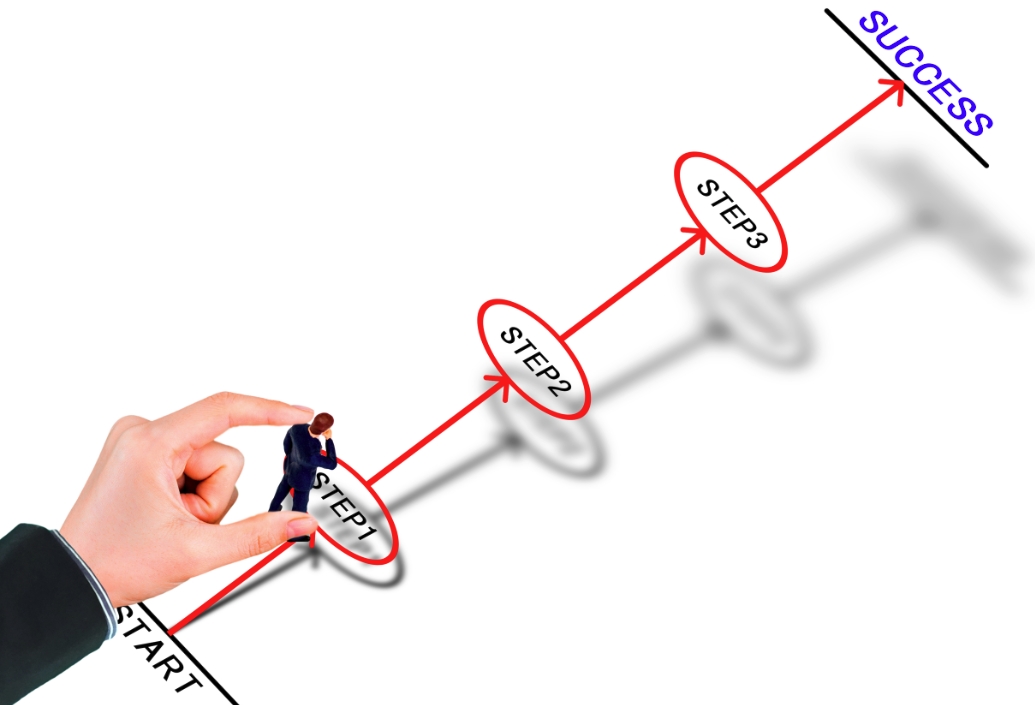
中小企業にとって、助成金は資金繰りを支え、事業成長を後押しする貴重な支援制度。
しかし、どの助成金を活用すればよいのか、申請の手続きが複雑でわかりにくいと感じる経営者も多いのではないでしょうか。
本記事では、中小企業が活用しやすい助成金の種類や、申請時のポイントをわかりやすく解説。
人材育成や設備投資、働き方改革など、さまざまな目的に応じた助成金の活用法を紹介し、経営を安定させるためのヒントを提供します。
適切な助成金を賢く活用し、事業の成長につなげましょう。
近年では、企業のDXをAIを使って進めるケースも急増しています。
補助金申請をAIがサポートし、採択率を高めてくれるサービスもありますので参考にしてください。
「中小企業のDXなら経営参謀AI」
(シェアモル株式会社)
目次
中小企業向け助成金の基本
中小企業が経営を安定させ、成長を促進するためには、助成金の活用が有効です。
助成金は返済不要な資金支援であり、人材育成や設備投資など、さまざまな用途に利用できます。
助成金と補助金の違い、代表的な助成金の種類、活用のメリット、申請時の要件について解説します。
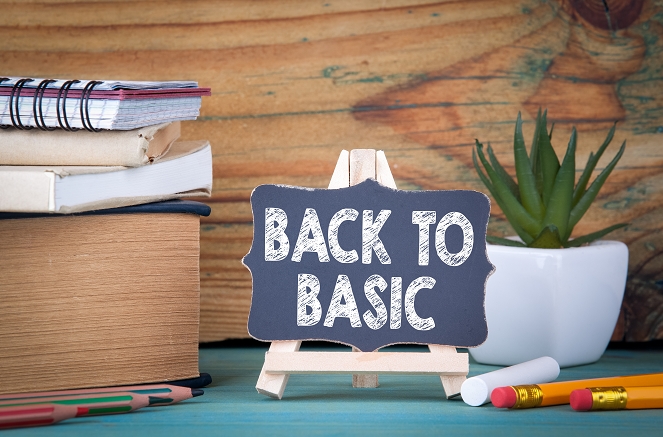
助成金とは?補助金との違い
助成金と補助金は、どちらも企業を支援する公的制度ですが、その性質や受給条件に違いがあります。
助成金は、一定の要件を満たせば受給しやすく、厚生労働省などが主に管轄しています。
例えば、雇用維持や人材育成のための助成金は、要件を満たせば申請が可能です。
一方、補助金は競争型の制度が多く、審査を通過しなければ支給されません。
経済産業省などが管轄する「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などが代表例です。助成金は比較的受け取りやすい一方、補助金は事業計画の質が問われるため、しっかりと準備する必要があります。
中小企業が活用できる主な助成金の種類
中小企業向けの助成金にはさまざまな種類があります。
代表的なものとして、雇用関連の「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」、設備投資に使える「ものづくり補助金」、IT化を支援する「IT導入補助金」などがあります。
これらの助成金は、企業の成長や経営改善に役立ちます。
また、業種や事業目的に応じた助成金も多数存在しており、地域限定の支援制度も。
自社に適した助成金を選ぶためには、制度の概要を正しく理解し、活用可能なものを見極めることが重要です。
助成金を活用するメリットと注意点
助成金を活用する最大のメリットは、返済不要な資金を得られる点にあります。
特に中小企業にとっては、財務負担を軽減しつつ、事業成長の加速が期待できます。
社員教育に助成金を使えば、スキル向上と企業競争力の強化が図れるかもしれません。
また、設備投資に活用することで、新たな市場への参入や生産性向上が可能になるかもしれません。
一方で、助成金には注意点も。
申請には細かな要件があり、提出書類の不備があると支給されないケースがあります。
さらに、受給後も報告義務があるため、適切な管理が必要です。
計画的に活用し、要件を満たせるかどうか慎重に検討しましょう。
申請に必要な基本的な要件
助成金を申請するには、事前にいくつかの要件を確認しておく必要があります。
まず、事業の目的が助成金の趣旨に合致しているかをチェックしましょう。
多くの助成金では、一定の経営年数や従業員数の条件が設けられています。
次に、適切な書類の準備が不可欠です。
具体的には、事業計画書、財務諸表、給与支払い実績などが求められることが多いです。
申請期限も重要なポイント。
助成金には公募期間が設定されており、締切を過ぎると申請できません。
受給後は用途に応じた報告義務があるため、事後の手続きについても理解しておくことが大切です。
これらの要件を満たし、計画的に申請を進めることで、スムーズな受給が可能になります。
中小企業が助成金を受け取るまで
助成金を受け取るには、適用可能な制度を見極めることが重要です。
まずは情報を収集し、自社に最適な助成金を選ぶ必要があります。
ここでは、助成金のリサーチ方法を~受け取るまでの流れをもう少し細かく紹介します。
活用可能な助成金のリサーチ
助成金の種類は多岐にわたり、業種や事業目的によって活用できる制度が異なります。
そのため、まずは適用可能な助成金を把握し、自社の状況に合ったものを選定することが重要です。
情報収集の手段としては、公的機関や専門家の活用、インターネットを利用した調査などが挙げられます。
正確な情報を得ることで、申請手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

中小企業支援機関(商工会議所・中小企業庁など)に相談
中小企業向けの助成金を探す際には、公的な支援機関を活用するのが効果的。
例えば、商工会議所では企業の規模や業種に応じた助成金の案内を行っており、申請方法についての相談も可能です。
中小企業庁や都道府県の産業振興機関も、地域特有の助成金情報を提供しています。
これらの機関を活用することで、自社に適した助成金の選定がしやすくなります。
また、一部の自治体では、無料の個別相談会を実施していることがあります。
申請の流れや要件を詳しく知ることができるため、助成金の活用を検討する際には積極的に利用するとよいでしょう。
事業計画のブラッシュアップや書類作成のアドバイスを受けられるケースもあるため、初めて助成金を申請する企業にとっては心強いサポートとなります。
専門家(税理士・社会保険労務士・中小企業診断士など)に相談
助成金の申請には、財務状況の確認や労務管理が関わることが多いため、専門家のサポートを受けるのも有効な方法です。
税理士は企業の財務状況を分析し、適用可能な助成金の選定を手助けしてくれます。
社会保険労務士は雇用関連の助成金の申請サポートを行い、必要な書類の作成や提出手続きをスムーズに進めることができます。
また、中小企業診断士であれば経営戦略の視点から助成金活用のアドバイスを提供し、事業計画の策定をサポートしもしてくれるでしょう。
特に、「事業計画書」の内容が審査の重要なポイントとなるものについては、専門家に相談することで説得力のある申請書を作成しやすくなります。
専門家への依頼には費用がかかるものの、適切な助成金の選定と申請成功の可能性を高めるためには、検討する価値があるでしょう。
助成金情報サイトや民間の補助金・助成金検索サービスを活用
インターネットを活用すれば、最新の助成金情報を手軽に入手できます。
例えば、厚生労働省や経済産業省の公式サイトでは、現在公募中の助成金や補助金の詳細を確認することが可能です。
また、各自治体のホームページでも、地域特有の助成金や補助金についての情報が掲載されています。
さらに、民間の補助金・助成金検索サービスを活用するのも一つの手。
「J-Net21(中小企業基盤整備機構)」や「ミラサポ」などのサイトでは、業種や事業内容に応じた助成金を検索できます。
また、「補助金ポータル」などの民間サービスでは、最新の助成金情報をメールで受け取ることができ、申請のタイミングを逃しにくくなります。
助成金の要件と申請条件を確認
助成金の受給には、対象となる業種や取り組み内容、必要書類などの条件を満たすことが求められます。
申請要件を事前に確認し、適切な準備を進めることで、スムーズに受給につなげることができるでしょう。
対象となる業種・事業規模(従業員数や資本金の制限)
助成金の多くは、中小企業を対象としていますが、業種や事業規模によって適用可否が分かれます。
製造業や小売業、サービス業など、それぞれの業界ごとに異なる基準が設けられています。
中小企業の定義としては、資本金の額や従業員数が一定の基準を超えないことが求められるケースが一般的。
製造業では「資本金3億円以下または従業員数300人以下」、小売業では「資本金5,000万円以下または従業員数50人以下」といった基準があります。
これらの要件を満たしているかどうか、申請前に確認しておくことが必要です。
また、一部の助成金では、創業後の年数や売上高の条件が加わることもありますので、詳細な条件をしっかりと把握しておきましょう。
助成金の支給対象となる取り組み(雇用創出・設備投資・デジタル化など)
助成金は、特定の事業活動を支援する目的で支給されるため、企業の取り組みが該当するかどうかを確認することが重要です。
代表的な支給対象として、以下のようなものが挙げられます。
– 雇用創出に関する取り組み(新規採用や雇用継続の支援)
設備投資を伴う事業拡大や生産性向上の取り組み
– 業務のデジタル化やIT導入による業務効率化
省エネルギー設備の導入や環境対策への取り組み
各助成金の目的に合致した取り組みを計画し、その活用方法を明確にすることが重要です。自社が計画している施策が助成金の要件に適合しているかどうか、事前にチェックしておきましょう。
申請に必要な書類(事業計画書・決算書・雇用契約書など)
助成金の申請には、正確な書類の提出が求められます。
助成金の種類によって必要書類は異なりますが、主に以下のようなものが必要になります。
– 事業計画書(助成金の活用目的、期待される効果を明記)
– 決算書や財務諸表(企業の財務状況を証明するための書類)
– 雇用契約書や給与台帳(雇用関連の助成金を申請する場合)
– 設備投資に関する見積書・契約書(設備導入に関する助成金の場合)
助成金の審査では、事業の実現性や経営の安定性が評価されるため、書類の不備がないよう慎重に準備しましょう。
また、一部の助成金では、申請後に追加書類の提出を求められることがあるため、迅速に対応できるよう準備を整えておくことが望ましいです。
申請受付期間と締切
助成金には公募期間が設けられており、申請のタイミングを逃すと受給が難しくなります。申請受付期間は助成金ごとに異なり、数か月ごとに募集されるものもあれば、通年で申請を受け付けているものも。
特に人気のある助成金は募集枠が早期に埋まることがあるため、できるだけ早めの申請が推奨されます。
例えば、ものづくり補助金やIT導入補助金は年に数回の公募が行われ、各回ごとに申請締切が異なります。
一方で、雇用関係の助成金の中には、採用前の事前申請が必要なものもあるため、計画的にスケジュールを立てることが重要です。
申請にあたっては、公式サイトや公的機関の案内を随時確認し、最新の情報を把握することが求められます。
助成金申請書の提出
助成金の申請には、指定された方法で申請書を提出する必要があります。
オンライン申請、郵送申請、窓口での直接申請の3つの方法があり、それぞれにメリットや注意点があります。
適した方法を選び、スムーズに申請を進めましょう。

オンライン申請(電子申請システムを利用)
近年、多くの助成金がオンライン申請に対応しています。
厚生労働省や経済産業省などの行政機関が提供する電子申請システムを利用することで、24時間いつでも申請が可能です。
申請の流れとしては、専用サイトにアクセスし、必要事項を入力したうえで書類をアップロードし、送信する形になります。
オンライン申請のメリットは、手続きがスピーディーであり、郵送の手間を省ける点にあります。
また、申請状況をリアルタイムで確認できるシステムが用意されていることも多く、進捗管理がしやすいという特徴も。
一方で、電子証明書の取得やシステム登録が必要な場合もあり、初めて利用する際には準備に時間がかかることがあります。
データの入力ミスや添付ファイルの不備があると、審査の遅延や申請の却下につながる可能性があるため、送信前にしっかりと確認しておくことが大切です。
郵送による申請(必要書類を郵送で提出)
郵送による申請は、紙の書類を作成し、指定された宛先に送付する方法です。
オンライン申請が難しい場合や、書類の原本提出が求められる助成金では、郵送申請が一般的に採用されています。
申請の流れとしては、必要書類を準備し、チェックリストをもとに漏れがないか確認したうえで、期日までに発送します。
郵送申請のメリットは、書類を手元で確認しながら準備できる点にあります。
特に、データ入力に慣れていない場合や、手書きの書類提出が必要な助成金では、郵送のほうが確実な手続きが可能になります。
申請期限ギリギリの発送では、遅延のリスクがあるため、余裕をもって提出するよう心がけましょう。
窓口での直接申請(自治体や支援機関の窓口で申請)
助成金によっては、自治体や支援機関の窓口で直接申請を受け付けている場合があります。特に地域密着型の助成金や、小規模事業者向けの支援制度では、窓口申請が基本となることが多いです。
申請時には、指定の窓口に必要書類を持参し、担当者と確認を行いながら提出する形になります。 直接申請の最大のメリットは、申請時に担当者へ相談できる点にあります。
書類の不備があればその場で修正が可能な場合があり、誤った申請による却下を防ぐことができます。
また、助成金制度についての詳細な説明を受けることができるため、今後の活用についてもアドバイスを得られる可能性があります。
ただし、窓口申請は受付時間が限られており、事前予約が必要な場合もあるため、訪問前に確認しておくことが重要です。
申請書類をすべて揃えてから向かうことで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
審査と面談(必要に応じて)
助成金の申請後、審査が行われ、場合によっては面談が実施されることがあります。
審査では、事業計画の妥当性や資金計画の明確性、不正受給の有無などがチェックされます
事業計画の妥当性や助成金の適切な活用目的
審査の重要なポイントの一つが、助成金を適切に活用する計画が立てられているかどうか。助成金の目的に沿った事業計画が求められ、実現可能性が審査されます。
特に、成長戦略や収益向上につながるかどうかが評価の対象となるため、具体的な目標を明記することが重要です。
また、雇用助成金の場合、採用予定の人材の役割や研修内容が具体的であるほど審査に通りやすくなります。
曖昧な計画は減点対象になるため、数値データや実績を交えて説得力のある事業計画を作成しましょう。
経営状況や資金計画の明確性
助成金の審査では、申請企業の経営状況が安定しているかも確認されます。
過去の決算書や財務諸表をもとに、助成金の活用が適切かどうかが判断されるため、収支の透明性が求められます。
審査側は、企業が助成金を適切に運用し、持続的に事業を発展させられるかを見極めようとします。
具体的には、現在の収益状況や資金繰りの計画、助成金がどのように事業成長に寄与するのかを説明することが求められるのです。
特に、設備投資系の助成金では、投資後の回収計画が明確になっているかが重要視されるため、資金の流れを具体的に示すことが望ましいでしょう。
財務的な安定性を証明するためにも、収益見込みやコスト削減の計画を整理しておくと、より審査を有利に進められるかもしれません。
過去に不正受給などの履歴がないか
助成金の審査では、過去に不正受給を行っていないかが厳しくチェックされます。
一度でも不正受給の履歴がある場合、申請が却下されるだけでなく、一定期間助成金の申請資格を失うことがあります。
そのため、過去に助成金を受給した経験がある場合は、その利用状況を適切に管理しておくことが大切です。
審査では、助成金の適正な使用が確認されるほか、雇用助成金の場合は労働法令を遵守しているかどうかも調査対象となります。
従業員の給与が適切に支払われているか、社内の労務管理に問題がないかなどがチェックされると思ってください。
不正とみなされる要因には、架空の雇用契約や助成金の目的外使用などが含まれるため、過去の受給履歴を整理し、適切な申請を行うことが求められます。
助成金の交付決定と事業実施
審査を通過すると、助成金の交付決定通知が届きます。
助成金には、事前に支給されるタイプ(前払い)と、事業完了後に精算されるタイプ(後払い)があり、それぞれ手続きや資金繰りの考え方が異なります。
事前に支給されるタイプ(前払い)
一部の助成金では、事業実施前に資金が支給される「前払い型」が採用されています。
これは、資金調達が難しい中小企業が円滑に事業を進められるようにするための仕組みで、主に設備投資や研究開発系の助成金で見られます。
前払い型のメリットは、事業開始時点で資金を確保できるため、資金繰りに余裕を持って計画を進められる点にあります。
しかし、助成金が適正に使われているかを確認するため、事業実施後に詳細な報告が求められます。
支給後に要件を満たしていないと判断された場合、返還を求められることもあるため、資金の使途管理には注意が必要です。
また、前払いを受けるためには、保証金の預託や銀行保証が必要になるケースもあり、手続きの手間がかかる点も考慮する必要があります。
事後精算型(後払い)
多くの助成金は、事業が完了した後に支給される「後払い型」となっています。
この方式では、企業が自己資金で事業を進め、完了後に実績報告を提出し、それが認められることで助成金が支給される仕組みです。
主に、雇用助成金やIT導入補助金、ものづくり補助金などがこの形式を採用しています。 後払い型の利点は、不正受給を防ぎやすく、助成金の適正な運用を確保できることにあります。
ただし、企業側としては、一時的に自己資金を用意する必要があり、資金繰りに余裕がないと負担が大きくなる可能性があります。
そのため、金融機関の融資と組み合わせるなど、資金計画を事前にしっかり立てることが重要です。
また、助成金が支給されるまでに数か月を要する場合もあるため、申請時にスケジュールを確認し、余裕を持って準備を進めることが求められます。
事業完了後の報告と助成金の受給
助成金を受給するためには、事業が計画通りに実施されたことを証明し、適正な資金の使用を示す必要があります。
事業実施報告書の作成や支払い証明書類の提出、雇用助成金の場合は従業員の雇用記録などを忘れないようにしておきましょう。
事業実施報告書(計画通りに実施したことの証明)
助成金の審査を通過した後、事業が完了したことを証明するために「事業実施報告書」の提出が求められます。
これは、助成金が適切に使用されたことを記録する重要な書類であり、計画内容に沿った事業実施が行われたかが確認されます。
報告書には、事業の成果や進捗状況、助成金を活用した具体的な内容を詳しく記載します。設備投資の助成金を受けた場合は、導入した機器の種類や稼働状況を説明し、業務効率の向上につながったかを示す必要があります。
事業計画から逸脱した点がある場合は、その理由を明確にし、必要な補足資料を添付することで審査がスムーズに進みます。
領収書・支払い証明書類(助成金の適正使用を確認するため)
助成金が適正に使用されたことを示すため、支出に関する証明書類の提出が求められます。具体的には、設備やサービスの購入費用に関する領収書、請求書、振込明細書などが該当します。
これらの書類は、助成金が申請時の計画通りに使われたかを検証するための重要な資料となります。
審査の過程では、領収書と実施内容の整合性が厳しくチェックされるため、不備がないよう整理しておくことが大切です。
例えば、助成金を活用したITシステムの導入であれば、購入したソフトウェアやサービスの明細を明確に記載し、実際の業務改善にどのように貢献しているかを示すとよいでしょう。
万が一、記載ミスや不足書類があると再提出が求められることがあるため、事前にチェックリストを作成し、抜け漏れのないよう準備することが大切です。
従業員の雇用記録(雇用関連助成金の場合)
雇用関連の助成金を受給する場合、助成金の目的通りに従業員の雇用が維持されているかを示す記録の提出が必要です。
具体的には、雇用契約書、給与台帳、出勤簿、社会保険加入記録などのこと。
これらの書類をもとに、助成金の対象となる従業員が適正な条件で雇用され、助成金の支給要件を満たしているかが確認されます。
例えば、キャリアアップ助成金の場合、非正規雇用者を正社員に転換したことを証明する雇用契約書や、転換後の給与が適切に支払われているかを示す給与明細が必要に。
雇用調整助成金では、休業期間中の給与支払いが助成金の規定に基づいているかがチェックされるため、勤務実績や賃金支払い状況を正確に記録しておくことが求められます。
これらの書類は一定期間保管する義務があるため、助成金を受給した後も適切に管理しておきましょう。
適切な管理とアフターフォロー
助成金の活用後も、適切に記録を保管し、必要に応じて行政機関の監査に対応できるよう準備しておくことが重要です。
不正受給が発覚すると返還を求められるだけでなく、今後の助成金申請が難しくなることがあるため、適切な運用を心がけましょう。
まとめ:助成金の申請は委託した方が効率がいい
助成金の申請には、要件の確認、書類準備、審査対応など多くの手続きが必要です。
不備があると支給が遅れたり、不受理となる可能性もあります。
そのため、専門家に委託することで、申請の成功率を高め、企業の負担を軽減できます。
助成金の活用を検討する際は、専門家のサポートを受けることで、時間と手間を削減し、確実な受給につなげましょう。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら




















