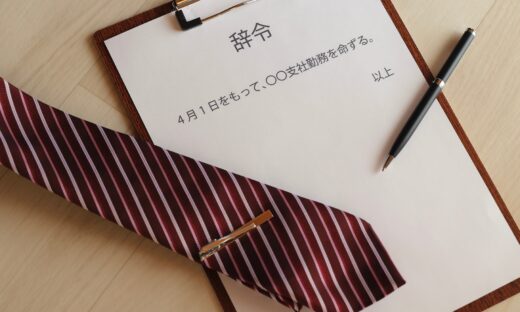助成金の申請に必要な書類は何?助成金申請に必要になる書類について解説
-6673bbfb46aba.jpg)
助成金は、中小企業にとって返済不要の心強い支援金です。
しかし、「どんな書類を用意すればいいのか分からない」「手続きが複雑で不安…」と初めて申請する経営者の方は感じていないでしょうか?
本コラムでは、助成金申請に必要な書類を徹底解説します。
雇用調整助成金を例に挙げつつ、準備すべき書類の一覧や作成のポイント、そして初めての申請を成功させるための注意点まで詳しく紹介します。
必要書類を漏れなく揃え、助成金活用の第一歩を踏み出す参考にしてください。
目次
助成金申請の基礎知識
助成金とは何か?
助成金とは、国や自治体が企業の取り組みを支援する目的で支給する返済不要の資金のこと。
人件費の補助や職場環境の改善などに活用でき、資金繰りに悩む中小企業にとって非常に心強
補助金も助成金と同じく返済不要の公的資金ですが、その性質には違いがあります。
助成金は条件(受給要件)を満たし法令遵守していれば基本的に受給できますが、補助金は条件を満たしていても審査によって不採択となる可能性がある点に注意が必要です。い制度と言えます。
要件を満たせば基本的にもらえる公的支援金であり、多くの企業が積極的に活用しています。
補助金との違い
また、補助金は公募期間や予算が設定され、事業計画の書類審査・選考を経て採択企業が決まるケースが多いです。
一方で助成金は厚生労働省系のものが中心で、年度途中でも要件さえ満たせば申請でき、予算が尽きない限り原則申請順に支給される制度が多い傾向があります。
このように「基本的にもらえる助成金」と「審査で競争がある補助金」という違いを理解しておきましょう。
助成金のメリットと活用例
助成金の最大のメリットは返済不要であることです。
借入金と異なり返済義務がないため、企業の資金繰りを圧迫せずに必要な資金を調達できます。
「従業員の研修費用を補助してもらいたい」「雇用を維持するための人件費支援が欲しい」といった場合、該当する助成金を受給できれば企業負担を大きく軽減できます。
また雇用環境の整備(有給取得推進やテレワーク導入等)や非正規社員の正社員化、創業時の人材確保など、企業の成長や労務改善につながる取り組みを後押ししてくれる制度です。
中小企業の経営者にとって、適切な助成金の活用は人材育成や職場環境改善の強力な原動力となるでしょう。
助成金申請の全体的な流れ
助成金申請は単に書類を出せば終わりではありません。
大まかに以下のステップで進みます。
1. 情報収集と制度選定
まず自社が使える助成金を調べ、適した制度を選びます。
取り組み内容や従業員数などによって利用できる助成金は異なるため、自社の目的に合うものを探しましょう。
最新情報の確認や公募期間のチェックも欠かせません。
2. 計画書の作成・提出(事前申請)
多くの助成金では、実際の取組みを始める前に「計画書」を提出し、行政の認定を受ける必要があります。
例えば「〇月〇日から研修開始」「新制度を導入する予定」等を事前に届け出ることで、後日の本申請につなげます。
事前に計画届を出さずに取り組みを始めてしまうと、要件を満たしていても助成金を受け取れないケースもあるため注意が必要です。
3. 取組みの実施と記録
計画が受理されたら、計画書どおりに社内施策を実行します。
同時に実施した証拠(出席記録や写真、報告書など)をしっかり残すことが重要です。
助成金によっては後日の申請時に「本当に実施したか」を証明する資料(研修の出席簿、購入設備の領収書等)の提出が求められます。
4. 申請書類の作成・提出(本申請)
取り組み完了後、支給申請に必要な書類一式を作成し、期日までに提出します。
ここで多くの申請書類や添付資料を揃えることになります(詳細は後述)。
提出後、行政側で審査が行われ、問題なければ支給決定となります。
5. 受給と事後報告
助成金が支給された後も、制度によっては報告義務が続く場合があります。
一定期間経過後の状況報告や、使途の実績報告などです。
最後まで適切に対応し、助成金を目的どおりに活用しましょう。
初めて申請する際のハードル
初めて助成金を申請する方にとって、いくつもの条件確認や膨大な書類準備は大きなハードルに感じられるでしょう。
実際、「助成金は難しそう…」という印象を持つ経営者も少なくありません。
しかし、正しい情報を集めて計画的に準備すれば決して不可能ではありません。
特に注意したいのは書類の不備。
どんなに有望な計画でも、申請書類に不備や不足があると審査以前の問題として不採択になることもあります。
また、必要書類は助成金ごとに異なるため、「何が必要か分からない」まま着手すると混乱しがち。
助成金申請に共通して求められる基本書類を確認していきましょう。
必要な書類を事前に理解し揃えておくことで、「書類漏れ」による躓きを防ぐことができます。
労働条件通知書・雇用契約書
労働条件通知書(または雇用契約書)は、従業員との労働条件を明示した書類です。
企業が労働基準法に基づき、賃金や労働時間、雇用期間などを労働者に通知した記録であり、助成金申請時には「適切な雇用契約を結んでいる証拠」として提出を求められます。
雇用関係の助成金では必須の書類で、書面またはデジタルで労働者ごとに整備しておきましょう。
提出時は就業場所や労働時間、賃金支払方法など重要事項がきちんと記載されているか確認してください。
正社員・有期社員いずれの場合も契約内容が明文化された書類が必要です。
賃金台帳
賃金台帳は、従業員一人ひとりの給与支払い状況を記録した帳簿です。
毎月の基本給や残業代、控除項目など給与の詳細が記載されています。
助成金申請では「適切に賃金を支払っているか」「申請対象期間中の給与額」などを確認するために提出が求められます。
ポイント
賃金台帳には支給日、支給額、各種手当や控除の内容が漏れなく記録されていることが重要です。
助成金申請で指定された期間(例:申請対象月の前後数ヶ月分など)の賃金台帳を用意しましょう。
また、賃金台帳の数値(支給額や控除額)が就業規則の規定や出勤簿の記録と整合しているか事前にチェックしておくと、不備防止につながります。
出勤簿・タイムカード
出勤簿やタイムカードは、従業員の勤務状況(出退勤時間や労働日数)を証明する書類です。
助成金によっては、所定労働時間の管理や休業の実績を確認するために出勤記録の提出が必須となります。
例えば雇用調整助成金では「何日に休業したか」を示すため、休業期間中の出勤簿写しやシフト表の提出が求められます。
ポイント
出退勤時刻や休日・残業の記録が正確につけられていることを確認しましょう。
タイムカードの打刻漏れがないか、手書き出勤簿の場合は労働者のサインをもらうなど、日頃から適正な勤怠管理を行い、いざという時に提出できる状態にしておきます。
就業規則
就業規則は、会社の労働条件や職場ルールを定めた文書で、常時10人以上の従業員がいる企業では作成・届け出が義務付けられています。
助成金申請では「適切な労務管理が行われている企業か」を判断する材料として、就業規則の写しを提出させるケースがあります。
特に人事制度や働き方改革系の助成金(例:テレワーク助成金、両立支援助成金など)では、制度導入前後で就業規則を変更した場合にその写しを添付するよう求められます。
ポイント
最新の法改正に対応した就業規則になっているか確認しましょう。
助成金の要件によっては、「育児介護休業制度を規定していること」「有給休暇の計画的付与制度を盛り込んでいること」といった条件を就業規則で定めている必要があります。
提出前に助成金要件と照らし合わせ、該当箇所に不備がないか点検してください。
企業情報を証明する書類(各種番号・登記簿など)
助成金の申請には、自社が要件を満たす適格な事業者であることを示す企業情報の書類も必要です。
雇用保険適用事業所番号・労働保険番号
雇用関係の助成金では、自社が雇用保険や労災保険に適正に加入していることを証明するために、申請書類に雇用保険の事業所番号や労働保険番号を記載します。
番号自体の証明書(加入証明書)の添付は通常不要ですが、正しい番号を申請書に記入することが重要です。
事前に労働保険の控えなどで自社番号を確認しておきましょう。
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
会社の基本情報(設立日・資本金・役員構成等)が記載された法務局発行の証明書です。かつて雇用関係助成金でも提出必須でしたが、2022年8月以降は一部を除き提出不要となりました。
しかし経済産業省系の補助金など多くの補助金申請では法人登記簿謄本の提出が求められます。
発行から3ヶ月以内という有効期限付きですので、必要な場合は期限に注意して取得します。
税務関係書類(納税証明書等)
助成金によっては直近の納税証明書(法人税や消費税などの未納がない証明)の提出が求められることもあります。
税の滞納がないことは公的支援を受ける基本要件のひとつです。
必要な税目や証明範囲は助成金の公募要領に明記されていますので、指示に従って取得しましょう(こちらも発行後1〜3ヶ月以内の有効期限に注意が必要です)。
財務諸表
補助金などでは会社の財政状況を示す決算書類(貸借対照表、損益計算書など)が必要になるケースがあります。
助成金(特に厚労省系)では要求されないことも多いですが、企業規模の確認のため従業員数確認資料や資本金額確認資料の提出を初回申請時に求められる場合があります。
その場合、現行の労働者名簿や直近期の貸借対照表などで代替することも可能です。
補足
申請する助成金によっては、これら基本書類に加えて特定の追加書類が必要です。
例えば人材開発支援助成金なら「研修に係る経費の領収書」[39]、設備導入の補助金なら「購入予定設備の見積書(しかも原則複数社からの相見積もり)」、さらには「従業員名簿」や「許認可証の写し」など多岐にわたります。
申請前に必ず公式の必要書類リストを確認し、追加書類も漏れなく用意しましょう。
雇用調整助成金に必要な書類(具体例)
では、助成金の具体例として「雇用調整助成金」の場合にどのような書類が必要となるか見てみましょう。
雇用調整助成金は景気の変動等で事業活動を縮小せざるを得ない企業が、従業員の雇用維持のために行った休業や研修などに対して助成される制度です。
初めて申請する場合、どんな書類を用意するのか不安に思われるかもしれませんが、以下に申請までの流れと必要書類をポイントごとに解説します。
雇用調整助成金の制度概要と申請の流れ
雇用調整助成金(雇調金)とは、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた企業が、一時的な休業・教育訓練・出向などによって雇用を維持する場合に、その休業手当や訓練費用の一部を助成する制度です。
コロナ禍で一躍注目を浴びた助成金でもあり、景気悪化時の雇用セーフティネットとして機能します。
1. 計画届の提出(事前手続き)
助成金を受けるには、まず休業等を実施する前に「雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届」等の計画届を提出します。
計画届では、いつからいつまで何人の従業員を休業または訓練させる予定か等を記載します。
※計画届を出さずに休業してしまった期間は助成対象になりません。
この計画届は初回申請時に必須で、提出先は所在地管轄の都道府県労働局またはハローワークです。
2. 初回の添付書類準備
計画届と同時または初回申請時に提出する書類として、「事業活動の状況に関する申出書」や「休業協定書の写し」などがあります。
事業活動の状況に関する申出書では、自社の売上高や生産量が一定程度減少していることを報告し、証拠として月次の売上台帳や収入簿のコピーを添付します。
また休業協定書は、休業実施について労使で結んだ協定書です(労働組合がある場合は労使協定、ない場合は従業員代表との協定書)。
初めて休業を行う際にこの協定書のコピー提出が必要で、労働者代表の選任書や労組員名簿も併せて提出します。
さらに、「事業所の規模を確認する書類」として従業員数や資本金が分かる資料(労働者名簿や会社登記簿など)も初回のみ提出します。
3. 休業等の実施・記録
計画届提出後、計画に沿って休業や研修を実施します。
休業期間中は、誰を何日休ませたかを正確に記録しましょう。
先述したとおり、出勤簿やシフト表、タイムカードで休業日・時間を示す書類を残します。同時に、休業手当の支払い額も記録・証拠化します。
賃金台帳や給与明細書にて、休業手当として何円支払ったかが分かるようにしておきます。これらは後述の支給申請時に提出が必要です。
4. 支給申請の提出
休業(または教育訓練や出向)の実施が終わったら、いよいよ助成金の支給申請を行います。
提出する主な書類は以下のとおりです
雇用調整助成金・支給申請時の必要書類
雇用調整助成金の支給申請で毎回提出する代表的な書類は次のとおりです。
支給申請書(様式第5号(1))
助成金を請求するためのメインの申請書です。
会社情報や休業等の概要、助成金の支給要望額などを記入します。
助成額算定書(様式第5号(2)の2)
支給申請額を計算する明細書です。
休業手当の支払い率や助成率に基づき、企業が求める助成額を算出します。
休業・教育訓練実績一覧表(様式第5号(3))
実際に休業または訓練を行った日ごとの実績を一覧にまとめた書類です。
何月何日に誰を休業させたか、所定外労働や教育訓練の実績も含めて記載します。
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
助成金の支給要件を満たしていることを申立てる書類です。
例えば「解雇を行っていない」「不正受給をしていない」等の事項を確認します(役員一覧の提出で代替するケースもあります)。
労働・休日の実績に関する書類(確認書類⑤)
休業等を実施した証拠として、休業日や労働日の出勤状況が分かる資料です。
具体的には出勤簿、タイムカードの写し、シフト表などを提出します。
これにより「計画どおりに休業した」ことを証明します。
休業手当・賃金の実績に関する書類(確認書類⑨)
休業手当や給与を支払った証拠となる資料です。
通常、賃金台帳や給与明細のコピー(申請期間を含む直近数ヶ月分)を提出し、休業手当額や賃金額を示します。
(教育訓練を実施した場合)訓練の実施状況に関する書類(確認書類⑥)
教育訓練を行った場合は、その受講者リストやカリキュラム、訓練の出席記録なども必要です。
重要ポイント
雇用調整助成金では申請様式が度々変更・簡素化されてきました。
例えばコロナ特例では書類項目の削減や、添付書類は既存資料のコピーで代用可とする緩和措置が取られています。
申請時には必ず最新バージョンの様式を厚労省サイトからダウンロードし、古い様式は使わないよう注意してください。
また、初めて申請する際は書類が多く感じられますが、厚生労働省や労働局が公開している提出書類チェックリストを活用すると便利です。
公式チェックリストに沿って一つひとつ書類を揃えれば、「どの書類がまだ準備できていないか」を把握できます。
書類作成・申請時の注意点(雇調金編)
雇用調整助成金の書類準備で特に注意したい点をまとめます。
休業協定書の整備
初回提出書類である休業協定書は、従業員代表の署名・押印が必要です。
代表者の選出手続きを経ていない場合、助成金申請前に選任書を用意するなど段取りを忘れないようにしましょう。
支給額の算定ミスに注意
助成額算定書の計算は複雑ですが、記入ミスがあると訂正のため申請処理が遅れます。
わからない場合は無理に自己流で計算せず、労働局の相談窓口に問い合わせたり、計算シート(エクセル等)を利用したりして正確を期してください。
実績と書類の整合性
提出する出勤簿や賃金台帳の内容と、申請書に記入した休業日数・手当額が食い違わないよう最終チェックしましょう。
書類間の数字の不一致は審査側から追加確認を求められる原因になります。
事前にダブルチェックし、整合性を確保します。
追加提出依頼への迅速対応
書類提出後、労働局から不明点について問い合わせや追加資料の提出依頼が来る場合があります。
そんなときはできるだけ早く対応することが、支給決定をスムーズに受けるコツ。
連絡が来たら放置せず、必要資料を速やかに提出しましょう。
最新情報の収集
雇用調整助成金は特例期間の延長や要件変更が頻繁に行われています。
厚生労働省の公式発表や通知を随時チェックし、最新の支給要領・様式を入手してください。
特に締切や提出期限の変更には注意が必要です。
初めて助成金申請をする際の注意点
助成金の書類一式を準備するにあたり、初心者の方が特に気を付けるべきポイントをまとめます。
不備なくスムーズに申請するための5つのチェックポイントです。
申請要領(公募要領)の熟読
まず公式の申請要領を隅々まで読むことが基本中の基本です。
助成金ごとに、「必要書類一覧」「様式の指定」「記入方法」「提出方法」など詳細な指示が要領に書かれています。
これを読み飛ばして自己判断で進めると、書類不足や形式ミスに繋がります。
分厚い要領でも根気強く目を通し、マーカーやメモで重要箇所をチェックしましょう。
専門用語が多く難解に感じる場合は、要領記載の相談窓口に問い合わせて解釈を確認することもできます。
「公式要領に書かれていること=ルール」ですので、まず公式情報に忠実に従う姿勢が大切です。
最新様式・最新情報の確認
助成金の公募期間中に、申請様式や要領が更新されることがあります。
知らずに古い様式のまま書類を作成すると「この書式では受理できません」となりかねません。
必ず公式サイトで最新の情報を確認し、提出直前にも改めて様式の改訂有無をチェックしましょう。
特に年度切り替わり時期や制度延長時には様式番号が変わる場合があります。
また、Q&Aや追加の注意事項が発表されることもあるので、厚生労働省や所轄機関のホームページを定期的に確認する習慣をつけてください。
書類の有効期限・形式に注意
登記事項証明書や納税証明書など、一部の添付書類には有効期限があります。
「発行後3ヶ月以内のものに限る」「交付日から2ヶ月以内」といった具合です。
期限切れの書類を出すと無効扱いとなりますので、取得時期に気を付けましょう。
また、書類の形式面にも注意が必要です。
公的証明書は原本提出が原則のもの(写し不可のもの)もあれば、コピー提出で良いものもあります。
押印が必要な書類についても、電子申請の場合は押印省略可だったりとケースバイケース。
要領に記載のルール(原本or写し、押印要否など)を確認し、その指示どおりに用意しましょう。
不備・不足がないかダブルチェック
書類をすべて揃え終えたら、提出前に綿密なチェックを行います。
●必要書類がもれなく全て揃っているか(チェックリストを活用)。
●各書類の記入欄に空欄や記載漏れがないか。
※特に日付・署名・押印など見落としやすい箇所に注意します。
●数字や社名等に誤字・脱字がないか。
●正式名称(株式会社○○○○ 等)は統一して正しく記載されているか。
●添付資料の枚数や写り具合
(不鮮明なコピーになっていないか、ホチキス止めの有無など指示どおりか)。
時間に余裕を持った準備とスケジュール管理
助成金申請はとにかく早めの準備が肝心です。
必要書類の中には取得に時間がかかるものがあります。
例えば法人登記簿や納税証明の発行に数日~1週間程度かかることがありますし、事業計画書の作成には社内調整も含め相応の時間を要します。
締切間際に慌てて役所に駆け込む…という事態は避けたいところ。
理想的には締切日の2週間以上前には主要書類が揃い始めている状態が望ましいです。
加えて、申請期限(受付期間)は厳守です。
期間を過ぎると一切受け付けてもらえませんので、カレンダーに余裕を持った締切日を設定し逆算して準備を進めましょう。
電子申請の事前準備
近年、助成金・補助金はオンライン申請(電子申請)に移行していく傾向にあります。
国の補助金では「Jグランツ」という共通システムが使われており、これを利用するには事前にGビズID(法人向けの電子認証ID)の取得が必要です。
GビズIDの発行には2〜3週間程度かかる場合があるため、電子申請を予定している場合は早めに手続きを始めてください。
初めてだと戸惑うかもしれませんが、一度IDを取得すれば他の申請にも使えるので、この機会に整備しておくとよいでしょう。
専門家や支援機関の活用方法
初めて助成金を申請する際、「自社だけでやり切るのは不安…」と感じることもあるでしょう。
そんなときは、助成金申請のプロに相談したり、各種支援機関のサポートを活用したりするのがおすすめ。
ここでは代表的な相談先とそのメリットを紹介します。
社会保険労務士(社労士)への相談・依頼
社会保険労務士(社労士)は労務管理の専門家であり、厚生労働省管轄の助成金申請代行を唯一認められた資格者です。
特に雇用関係助成金については、社労士に依頼すれば書類作成から申請手続きまで代行してもらうことが可能です。
社労士に相談・依頼するメリットは多岐にわたります。
複雑な書類作成のサポート
経験豊富な社労士なら、企業の状況に合わせて必要書類を漏れなく準備してくれます。
自社だけでは見落としがちなミスを防ぎ、書類の完成度を高めてくれます。
不支給リスクの軽減
助成金制度を熟知したプロの目でチェックしてもらうことで、要件漏れや手続きミスによる不支給のリスクを大幅に減らせます。
業務負担の軽減
面倒な申請業務をアウトソーシングできるため、経営者や総務担当者は本来の業務に集中できます。
特に人手が限られる中小企業では助かるポイントです。
労務管理全般のアドバイス
社労士は助成金だけでなく就業規則の整備や人事制度構築のプロでもあります。
助成金申請をきっかけに労務管理の改善点を指摘してもらえるなど、プラスアルファの効果も期待できます。
「どの助成金が自社に合っているか分からない」「書類作成に自信がない」という場合、早めに社労士に相談すると安心です。
相談だけなら無料で対応してくれる社労士事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。
その他の専門家(行政書士・中小企業診断士など)
助成金以外の補助金申請や事業計画のブラッシュアップについては、行政書士や中小企業診断士、税理士・公認会計士などの専門家に相談できる場合もあります。
補助金申請代行に法定の資格要件はありませんが、計画書の作成支援や事業計画策定のノウハウを持つ専門家に依頼すると、採択可能性を高める助言が得られます。
例えば、中小企業診断士は経営計画のプロとして補助金事業のポイントを指導してくれますし、行政書士は官公署提出書類の代理作成を業務範囲としているため申請書類の体裁を整えるのに慣れています。
もっとも、これら専門家もそれぞれ得意分野が異なるため、「助成金・補助金の支援実績が豊富か」を事前に確認することが大切。
実績豊富な専門家であれば心強いパートナーとなってくれるでしょう。
商工会議所・中小企業支援センター等の公的支援
各地の商工会議所や商工会、都道府県の中小企業支援センターなど公的機関でも、助成金・補助金に関する相談窓口を設けていることがあります。
例えば商工会議所は、小規模事業者持続化補助金の申請支援窓口となっており、会員向けに書類の書き方指導や計画書のチェックを行っています。
また、各都道府県労働局には企業向けの助成金相談コーナーがあり、電話や対面で質問に答えてもらえます。
こうした公的支援は無料もしくは低廉な費用で利用できるものが多いのがメリットです。初めてで右も左も分からないというときは、まず地元の商工会議所や労働局に問い合わせてみるのも良いでしょう。
「どんな助成金があるか知りたい」「申請書類の書き方で悩んでいる」など具体的に相談すれば、適切なアドバイスをもらえるはずです。
専門家に依頼・相談する際のポイント
実際に専門家に依頼する際は、以下の点に留意しましょう。
依頼範囲と費用を確認
書類作成代行の場合、成功報酬型(助成金受給額の○%)や定額料金など費用体系が様々です。
契約前にサービス範囲(書類作成のみか、計画づくりから代行か等)と料金を明確にしましょう。
助成金額が少額だとかえって手数料負けするケースもあるため、費用対効果を考慮します。
「助成金の申請代行を使うと手数料はいくらかかる?助成金申請代行業者の選び方や注意点を解説」
自社状況の整理
専門家に相談する前に、自社の基本情報(業種・従業員数・資本金など)や過去の助成金受給歴、現在検討中の取り組み内容を簡潔にまとめておくと話がスムーズです。
「何を実現したくて助成金を利用したいのか」を伝えられるよう準備しておきましょう。
信頼できる相手を選ぶ
助成金コンサルタントを名乗る業者の中には、社労士資格を持たずに不適切な関与をするケースも報告されています。
基本的に雇用関係助成金の代行は社労士だけに限定されていますので、依頼先が信頼に足る資格者・企業かどうかチェックしましょう。
実績や口コミを調べるのも有効です。
終わりに
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら