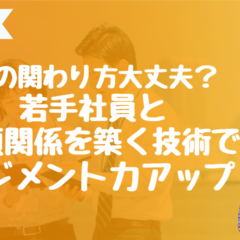DXとは何?デジタル化の先にあるDXを詳しく解説
-scaled.jpeg)
目次
DXとは?DXの定義
DXとは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略で、企業がデジタル技術を活用してプロセスを変革することを指します。
DXの導入は、企業のプロセスを効率化し、収益を増大させるための重要な手段です。
デジタル技術を活用することにより、企業のプロセスをより効率的に運営することができ、さらに、企業はコスト削減、生産性の向上、可視化や分析などを実現することができます。
デジタル化を経て、新たなサービスを開発したり、新たなビジネスモデルを構築したりすることがDXです。
DXの提唱者
日本国内にもDXの推進に力を入れている企業はありますが、その多くが目先のデジタル化であるという指摘もあります。
DXの提唱時には何を狙って推進すべきとしたのかを知っておくことは、方向性を間違わないためにも重要なことと言えます。
DXを提唱したエリック・ストルターマン氏(スウェーデン)とその重要性を強調しているマイケル・ウェイド氏(スイス)らが考えたDXの本質と、日本の経済産業省がDXレポートの中で紹介したDXについての考えを紹介します。

エリック・ストルターマン氏(スウェーデン)
DXを最初に定義した人が、エリック・ストルターマン氏です。
彼の定義によれば、DXとは、「デジタル技術が人間の生活のすべての側面に引き起こす変化」とされています。
デジタル技術が私たちの生活環境、生活様式そのものを変えていくという意味が含まれています。
DXはビジネスという狭い範囲だけにとどまらず、あらゆる側面に浸透していくものと想定されていたのです。
マイケル・ウェイド(スイス)
マイケル・ウェイド氏はIMD大学の教授であり、DXの重要性を最も強調している人の一人です。
予測することが不可能な事態への遭遇パターンとしては、新型コロナウイルスのように前触れなく起こるようなケース(ブラックスワン現象)と事前にその予兆が少しずつ見えているケース(灰色のサイ)があると言います。
予兆が分かっているものの代表例としては地球温暖化や日本の人口減少問題も含まれます。
これら予測不可能な事態を脱却するためにはDXが欠かせないというのです。
ここで言うDXとは単なるデジタル化とは違い、ビジネスモデルを根底から変えていくものにまで広がります。
経済産業省(日本)
経済産業省が発表したレポートによると、DXを議論するようになった背景には次のようなものがあると書いてあります。
あらゆる産業において、新たなデジタル技術を利用してこれまでにないビジネス・モデル を展開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起きつつある。こうした中で、各企業は、 競争力維持・強化のために、デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)をスピーディーに進めていくことが求められている。
日本におけるDXは企業が主役となっていることが分かります。
企業が新しい製品やサービスをつくり、市場において優位性をとっていくためにDXが必要とうたっています。
似ているようで少し違うDXと混同されやすい言葉
DXと同じ意味合いで使われがちな言葉に、デジタイゼーション(Digitization)、デジタライゼーション(Digitalization)があります。
これらは厳密にはDXとは違います。
それぞれの言葉の意味について細かく確認していきましょう。

デジタイゼーション(Digitization)
アナログとなっている部分の一部をデジタル化していくことをデジタイゼーション(Digitization)と呼びます。
以下はデジタイゼーション(Digitization)の例です。
・顧客の自宅に伺って営業販売をすることからオンラインでの営業に切り替える
・紙媒体の広告やDMからオンライン広告に切り替える
・紙での在庫管理からクラウドサービスを活用した管理に切り替える
業務の効率化とコストの削減が期待できます。
業務の効率化という意味ではIT化と呼ぶこともあります。
デジタライゼーション(Digitalization)
デジタイゼーションでデジタル化したものを通じて、個別の業務・製造プロセスをデジタル化することを指します。
独立した業務単体をデジタル化することをデジタイゼーション(Digitization)と言うのに対して、作業工程をまとめてデジタル化するのがデジタライゼーション(Digitalization)です。
・社員育成において、育成の様子をオンラインで録画し、教育係に共有し、そのフィードバックまでをすべてオンライン上で完結する仕組みを整える
・取引発生時に入力されたデータが会計システムにまで反映され、一連の数字が連動して自動的に入力される状態を整える
他にも、小売店でのPOSの導入、製造業での受注から請求までの工程を成果物に紐づけることで成果物がどの状態にあるのかをリアルタイムに管理する体制を整えることもデジタライゼーション(Digitalization)です。
なぜ今、DXが必要なのか?
今まで通りの仕組みではなく、どうしてDXが必要になるのでしょうか。
DXが必要な理由としては、
「市場競争において優位に立つことができるから」
「働き方改革によって既存の仕組みから抜け出すべきだから」
「環境変化に強い適応力のある組織が作れるから」
「2025年の崖問題に対応すべきだから」
などが挙げられます。
市場競争において優位に立つことができるから
企業が市場競争の激しい状況を生き残るためには、最新のテクノロジーに対応したDXを導入する必要があります。
DXを活用することで、新しいビジネスモデルを構築し、他社に先駆けて自社のビジネスを強化することができます。
また、コスト削減を実現できるのもDX導入の醍醐味です。
DXを活用することで、効率的かつ革新的なビジネスプロセスを構築することが可能です。
さらに、顧客とのエンゲージメントを高めることができます。
顧客のニーズを把握し、カスタマイズしたサービスを提供することもDXによって可能になります。
その他にも、DXを活用することでAIやIoTなどの最先端のテクノロジーを活用することも可能です。
※IoTとは?
IoTとは「Internet of Things」の略称で、日本語では「モノのインターネット」と呼ばれます。
現代ではあらゆるモノがインターネットに接続され、モノが意思を持っているかのように情報を、インターネットを介して伝えるようになっています。
スマホに内蔵されたGPSが現在地を私たちに伝えてくれることや、機器の調子が悪い時にその状態を私たちに伝えてくれることもIoTの具体例です。
働き方改革の観点から既存の仕組みを抜け出すべきだから
見込み顧客リストや商品管理を紙ベースで行っていて、データ化に移行しようとしていないなど、アナログに偏っている業務はないでしょうか?
業務の効率化を図ろうとしても限界があり、新システムの導入によってDXに近づけようとすると、導入コストの問題が頭をよぎります。
結果として、既存のシステムのまま運用を続けてしまうということになるのです。
しかし、働き方改革推進の背景にもあるように、限られた時間で成果を高めるためには業務の効率化は絶対です。
アナログだけに頼り切ってしまう仕組みから少しでも脱却することが業務の効率化になるということを自覚しましょう。
DXは働き方改革に次のような点で貢献します。
・有効な時間の使用
・労働環境の改善
・能力を最大限活用する新しい働き方の提供
DXは、ビジネス環境の変化を支援するだけでなく、働き方改革を実現するための重要な役割も果たします。
環境変化に強い適応力のある組織が作れるから
私たちの周りを取り巻く環境は、技術の進歩に伴って凄まじいスピードで変化していきます。
この環境の変化に対応した商品・サービスを提供することが企業にとって必要不可欠です。
数年前までは売れていたものも、ここ最近では売れなくなってしまったというような経験もあるのではないでしょうか。
以前は「商品・モノ」があれば何でも売れていた時代でしたが、近年では、そういかなくなってきています。
消費者の価値観に過敏に反応するためにもDXは必要です。
2025年の崖問題に対応すべきだから
「DX」という言葉と対照的に使われる用語に「レガシーシステム」という言葉があります。
レガシーシステムとは、PC普及当初の仕組みのことです。
また、より広義では、古い仕組みのことをまとめて「レガシーシステム」と呼んでいる場合もあります。
「2025年の崖」とは、経済産業省が発表した「DXレポート」の中で使われた用語であり、そのレポートの中では、2025年以降では、毎年およそ12兆円の経済的損失を被ることを発表しています。
ちなみに、この12兆円という数字は現在のおよそ3倍もの数字です。
先に述べたレガシーシステムから脱却し、新システムの移行が2025年の崖問題を乗り越えるには必要不可欠なのです。
それは、既存のレガシーシステムは修正と改善を何度も繰り返したために、かなり複雑になっており、今後の修復やアップデートにも専門のエンジニアの力が必要になります。
しかし、2025年になると、そこに携わっていたエンジニアの方々が定年となり、対応できなくなってしまうのです。
古いOSにしか対応していないレガシーシステムは、新しい技術を組み込むことが困難であるのと同時に、OSによってはすでにサポートが終了しているものもあるため、ウイルスなどのセキュリティ面でも心配されます。
レガシーシステムでも何とかなってしまっているからと言って、このまま使い続けることはセキュリティの脆弱性も心配されます。
これらの危機を乗り越えていくためにもDXの推進が求められています。
DXに向けた3つのステップ
DXの最終的なゴールは新しいビジネスの創出です。
今までなかった収益源を作り出すことこそが目標になります。
とは言え、いきなりゴールにたどり着くのは難しいでしょう。
そこで、DXのゴールに向けた3つのステップを段階ごとに解説していきます。

業務の効率化と合理化
DXの第一段階は業務の効率化と合理化になります。
DXに向けた準備段階であって、デジタル化と呼ぶべきステージになります。
この段階ではまだまだ社内の業績に貢献するほどの収益は期待できません。
社内に関するものと顧客に関するもので考えてみましょう。
◆社内目線で考える業務の効率化と合理化
社内での業務の効率化はDXへの第一歩です。
書類に必要な捺印のため、その都度、権限を持っている人のところまで行き捺印してもらう、時間の調整を何度もしながら会議の日時を決めている場合、脱ハンコやオンライン会議を推進するだけでも業務の効率化に期待が持てます。
同じ仕事をしている部署がいくつもある場合も業務の無駄が生じます。
ERP(Enterprise(企業) Resource(資源) Planning(計画)の略)ソフトを使って企業の経営に関する情報をまとめて管理することもいいでしょう。
一元管理をすることによって、問題点の分析もリアルタイムで行うことが可能になり、業務の効率化は課題解決のスピードにもつながります。
◆顧客目線で考える業務の効率化と合理化
オフラインでの集客や顧客対応を行っている部分をオンライン化することも必要かもしれません。
オフラインでの集客とは、チラシや広告、DMなどが挙げられます。
アナログ形式で慣れているという場合もありますが、伝える情報を絞らないといけないデメリットや修正をする場合には、思った以上にコストがかかるデメリットがあります。
オンライン集客は簡単で手身近なところではホームページの構築や、ECサイトの設立などが挙げられます。
サービス内容の変更があった場合にも、デジタル化されていた方が修正に柔軟に対応ができます。
また、最近ではオンライン形式のセミナー(通称ウェビナー)を行っている企業も多くなってきています。
ウェビナーの後に質問を個別に受け付けることによって、見込み顧客との関係性が築きやすくもなります。
既存収益モデルの再構築・増収
ここからが収益に本格的に関わってくるステージですが、まだDXとは呼べません。
社内での業務、顧客との接点のオンライン化が進んだら、既存のサービスのアップデートを行うことによって収益をより強固なものに進化させていきます。
◆社内目線で考える既存収益モデルの再構築・増収
社内業務のデジタル化を進めることができたら、判断基準もデジタル化していきます。
これは数値的な予測を立てる上でも大変重要です。
社内で年間予算を組むこともあると思いますが、過去のデータをあれこれと調べていくうちに、数字としての正確さが活かされずに最後は適当になってはいないでしょうか。
また、在庫を抱えたくない、あるいは抱えすぎているといった状況を数日前までの売れ行きで主観的に判断してはいないでしょうか。
数字を判断基準にしておけば、意思決定のスピードも格段に上がります。
そのためにも数値の管理が重要で、数値をできるだけ一か所に集め、それらをすぐに一覧としてみることができる状態が理想的です。
したがって、「業務の効率化・合理化」の項目で紹介したような一元管理システムが整っていない場合には、意思決定スピードを高めるということも難しくなります。
◆顧客目線で考える既存収益モデルの再構築・増収
顧客との接点の場所を変えていくことで、既存のサービスを別の方法で販売し、そこから増収を期待することもできます。
CD販売を例に出してみましょう。
今ではダウンロードによる販売が主流となっていますが、その昔はCDショップでCDを購入するというのがスタンダードでした。
ですが、時間も場所も選ばずに手軽に購入できるという点ではECサイトやダウンロードサイトでの購入の方が圧倒的に利便性は高いです。
もちろん、既存の販売方法の方がいい場合もあります。
アーティストとの握手券や特典をつけるといった方法も考えられるでしょう。
ですから、どちらかに一本化するだけではなく、増収が期待できる方法を選択することが重要になります。
接点を多くすると収益が上がるというのも重要な視点です。
新しい収益モデル・新ビジネスの確立(DX)
新しいビジネスモデルを立ち上げることや、DXに関わる人材を育成することがDXの最終目的地となります。
しかしながら、この領域はかなり難易度も高いため、「ここまでは目指さない」と考えている企業も多いことでしょう。
◆社内目線で考える新しい収益モデル・新ビジネスの確立
DXに関連する人材の育成、投資を積極的に行うことで、社内でのDX化に拍車がかかります。
効率化と収益性を同時に考えながらビジネスが自動化する仕組みをつくっていくステージです。
◆顧客目線で考える新しい収益モデル・新ビジネスの確立
この段階までくると、顧客との直接のやり取りをほぼ行う必要がないステージになってきます。
実店舗であっても、センサーを利用した買い物ができるところもあります。
来店した人はセルフレジさえも通過する必要がない場合もあり、店員は不要となります。
もちろん、現金で支払う必要もなければ、長蛇の列を作って並ぶこともありません。
ECショップであっても、アカウント情報と購入履歴を紐づけて、個人の好み・趣向がデータで管理され、個人へのおすすめ情報を次々と表示します。
「あなたと好みが似たお客様はこの商品も買っています。」のような項目は大きなプラットフォームを利用すれば必ずと言っていいほど目にします。
顧客対応までもが自動化された最終形態となります。
国内DXの現状
経済産業省が発表した「DX推進指標」を使って、IPAはそれぞれの企業(分析対象は305件)のDXの推進度を自己診断した結果をまとめています。
データは2020年までのものとなっており、この分析レポートはDXの推進度合いに応じてレベル0からレベル5の6段階で評価をしています。
それぞれのレベルは次のような基準で設定されています。
※IPAとは、日本のIT国家戦略を技術と人材の両極面から支えるために設立された独立行政法人のこと。正式名称は情報処理推進機構。
◆レベル0(未着手)
経営者が無関心であるか、関心があっても具体的に取り組んでいない段階
◆レベル1(一部での散発的実施)
全社戦略が明確でない状態で、部門ごとの試行と実施にとどまっている段階
◆レベル2(一部での戦略的実施)
全社戦略に基づいた上で一部の部門での推進がなされている段階
◆レベル3(全社戦略に基づく部門的横断的推進)
全社戦略が明確であって、その方針を部門が理解しており、関連のある複数の部門間で推進されている段階
◆レベル4(全社戦略に基づく持続的な実施)
定量的な指標などによる持続的な実施ができており、改善まで含めて持続的な推進が為されている段階
◆レベル5(グローバル市場におけるデジタル企業)
デジタル企業として、グローバル競争を勝ち抜くことができる段階
調査結果としては、
レベル0と回答した企業数が93(30.5%)
レベル1と回答した企業数が116(38.0%)
レベル2と回答した企業数が70(23.0%)
レベル3と回答した企業数が24(7.9%)
レベル4以上と回答した企業数が2(0.7%)
となっていました。
全体的にDXに向けた取り組みが本格的に国内企業で浸透しているとはまだまだ言いにくいのが現状です。
また、レポートでは、従業員の人数によって大規模企業(従業員1000人以上)、中規模企業(従業員100人以上1000人未満)、小規模企業(従業員100人未満)と分類していますが、大規模企業ほどDX推進の水準が高いということが指摘されています。
DX推進の課題
IPAによるレポートからも分かる通り、国内企業におけるDX推進の課題は多く残っています。
DX推進が進まない理由としては、今ある既存システムに慣れてしまい、新しいものへの切り替えが面倒と感じることや、コストの問題などが挙げられます。

DXを通じた経営戦略が不透明
「DXが大事なのは分かっているけど、実際にDXを目指して何をするのか?」が明確になっていない場合もあります。
経営戦略が曖昧な状態で、とりあえずDXを推進していくことは、「DXのためのDX」を実践していることになってしまい、本末転倒です。
DX化でよく誤解されがちなのは、長期的な目でコストの削減を期待しているケースです。
もちろん、コストの削減も長期的には見込まれますし、企業としても大事にしたいところです。
しかし、DXの最終ゴールはビジネスモデルの変革により、増収を実現させることです。
自社内でDXがどのような役割を担うのかを考えることが大切です。
そのためにも経営戦略ありきの推進をしなければ表面上のデジタル化で終わってしまうリスクも考えられます。
現に日本の企業の多くがDX化を目指すものの途中で頓挫してしまっているのです。
コスト問題
ここでのコスト問題とは、初期投資におけるコストです。
どうしても一時的な支出が大きくなるので、その部分だけをクローズアップしてしまいがちです。
貴重な経営資源を本当にここに投資していいのかどうかの判断基準が明確でないことも背景にあるようです。
しかし、目の前の費用だけでなく、そのシステムで運用した場合の通算コストが現状と比較してどうなっているのかも見据えるようにしていきたいところです。
DX人材の不足
今後の日本では少子高齢化がますます進み、労働力が不足することが懸念されています。
さらにシステムエンジニア、技術職などDXに携われる人材ともなればさらに希少となります。
社内でDXに関わる人材を育成し、自社で活躍してもらうことは困難を極めるため、外部へのアウトソーシングによってこの問題を解決している企業もあります。
もちろん、アウトソーシングをしているからと言って、社内教育をおろそかにすることもできませんから、一定の教育制度を整える必要もあるでしょう。
一般社団法人日本能率協会の出した「日本企業の経営課題2021」の中で、DX推進の課題となるものとして88.5%の企業が「DXに関する人材の不足」を理由に挙げています。
それもそのはずで、労働力減少の問題によるものだけでなく、日本のITエンジニアの70%以上がIT企業で活躍しているので、自社内でIT関連に精通した人材を確保している企業の方が少数なのです。
DX化を目指さないことによる問題点
「今のままでも上手くやれているから今後も同じような仕組みでなんとかなる」という考えは立ち行かなくなる可能性があります。
DX化という課題を無視した場合に直面すると思われる課題を2つほど紹介しておきます。

Conflicts At Workplace. Business Team Suffering Communication Problem During Corporate Meeting In Office, Multiethnic Coworkers Arguing While Discussing Company Strategy In Boardroom, Closeup
既存システムの残存とコストの増大
既存のシステムの運用を行うにあたってメンテナンスは必要不可欠です。
2025年の崖問題でも触れましたが、今後そのメンテナンスができる技術者はごく限られた人たちになっていきます。
さらに、そのような技術者が少なくなるということはメンテナンスにかかるコストも増大することを意味します。
システムを使う側も、システム全体を知る人は減っており、すべての機能を使いこなすことができなくなっていることや、不要な機能が残っているケースも考えられます。
不要な機能が残っているぐらいであれば、業務に支障は出ないかもしれませんが、製品のサポートやアップデートに必要なサポートや部品の提供そのものが打ち切りになっているものもすでにあります。
この場合、技術的にシステム更新をする人がいたとしても、お手上げ状態となります。
今までは顧客に提供できていたサービスがシステム上の都合という理由によって提供できなくなったり、サービスの質が低下したりすることも起こり得ます。
機種によってはプラットフォームの乗り換えすら危うくなる可能性もあるのです。
「今と同じで大丈夫」と思える状態がいつまでも続くとは限りません。
業務が個人に依存する
DXに近づけるための業務最適化を行わない場合、特定の個人の能力によって業績や仕事の効率が左右される可能性があります。
いわゆる社内での頼れる人材にあたるのですが、その社員が退職した場合、その業務形態はしっかりと機能するのでしょうか。
本格的なDXにまでいかないまでも、特定の個人に依存してしまうようなモデルは不安定と言わざるを得ません。
社員育成によって個人の能力や資質を向上させることは社内で行っていくべきではありますが、それとは別に、誰がこなしても同じ結果になるような仕組みを社内で構築していくことも重要です。
まとめ:DX推進その前に
DXの推進には段階があります。
いきなりスタートさせようとしても上手くいかないことがほとんどでしょう。
自社の目標設定を明確にしたうえで、関係部署に共有しながら少しずつ進めていくことが大事です。
大きな流れとしては、
①経営ビジョンの明確化
②個別の業務をデジタル化するデジタイゼーション
③個々のフローをデジタル化するデジタライゼーション
④新しいビジネスモデルへの変革を起こすデジタルトランスフォーメーション
このように進んでいきます。
自社が今どの段階であるのかを振り返りながら、次の段階へと移行していきましょう。
DX人材の育成を考えるなら
Next HUB株式会社はDXを軸とした人材の育成から就職後の研修・キャリアコンサルタントまでをセットで提供しています。
人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら
—





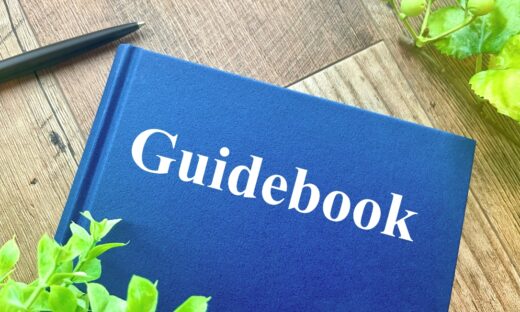



-520x312.jpg)