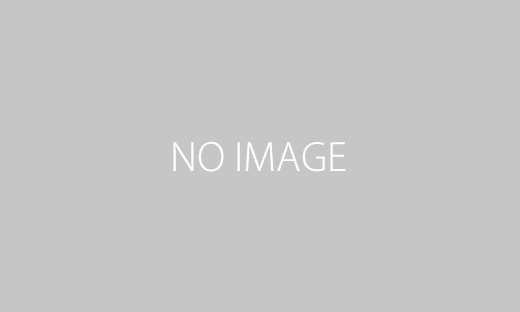組織の中でありがちな非効率な業務とは?組織の中で見直しが必要な業務や助成金で改善できる可能性のある業務も紹介!?

組織の中には、日々の業務の中で当たり前のように行われているものの、実は非効率で見直しが必要な作業が数多く存在します。
本記事では、会議・紙文化・情報共有・人材育成など、業種を問わず発生しがちな非効率な業務を具体的にリスト化。
また、それらの改善に活用できる「助成金制度」の可能性にも触れながら、中小企業でも実践できる業務改善のヒントを紹介します。
目次
会議関連の非効率業務
目的が不明瞭な定例会議や、関係者以外の出席、準備や記録にかかる手間など、会議の非効率さは多くの組織で悩みの種です。

毎週開催される目的不明の定例会議
定例会議がルーチン化し、本来の目的や効果が曖昧になっているケースは少なくありません。
会議そのものが目的になってしまい、参加者が「何のための会議か分からないまま出席している」と感じるようでは、生産性の低下を招く要因となります。
特に議題が毎回似通っていたり、進展がない話が繰り返されたりすると、参加者の集中力や意欲も下がりやすくなります。
必要な情報共有は別の手段に切り替えるなど、会議の在り方自体を見直すことが重要です。
全社員が参加する必要のない会議
本来は一部の関係者だけで十分な内容であるにもかかわらず、全社員が出席を求められるケースがあります。
これでは貴重な業務時間が浪費され、現場の生産性にも影響が出かねません。
参加者の数が多くなるほど議論が分散しやすく、会議時間が長引く傾向も見られます。
出席対象者を明確にすること、必要に応じて議事録や要点共有だけで済ませる仕組みを整えることが、効率化の第一歩です。
議事録作成や配信に時間がかかる
会議後に議事録を作成する担当者の負担が大きく、配信までに時間がかかるという声もよく聞かれます。
内容の精査に時間を要したり、フォーマットが統一されておらず手間がかかったりすることが背景にあります。
タイムリーな共有ができなければ、決定事項の認識違いやアクションの遅れにつながるため、議事録作成の効率化も大きな課題。
テンプレートの活用や音声認識ツールの導入などで省力化が可能です。
会議後のアクションプランが曖昧
せっかく会議を開いても、誰が何をいつまでにやるのかが明確になっていなければ、成果にはつながりません。
決定事項が共有されない、タスク管理が不十分といった状況が続けば、会議そのものの価値が疑問視されます。
アクションプランを明文化し、タスクを可視化して管理する仕組みを整えることが必要です。
会議の締めくくりには、必ず次の行動を具体化するステップを取り入れることが求められます。
紙文化・アナログ作業の非効率
紙による業務フローは、手間や時間、保管コストの増加を招きやすく、組織の生産性を下げる要因となります
書類の印刷・押印作業の多さ
日常的に必要とされる書類への印刷や押印は、業務全体の流れを止める原因となることがあります。
特に上長の押印を得るために物理的な移動が必要な場合、確認や承認が滞り、業務スピードが落ちてしまいます。
リモートワークの普及に伴い、紙ベースでの処理は一層の非効率さが浮き彫りになりました。
電子承認システムやクラウド上での管理に切り替えることで、業務の停滞を防ぎやすくなります。
紙の申請書や手続きの運用
社内の各種申請において、いまだに紙ベースの様式を使っている企業は少なくありません。出力・記入・提出・回覧・保管という一連の流れに多くの手間がかかり、担当者の業務負荷を高めます。
さらに、記入漏れや確認ミスなども発生しやすく、差し戻しによる時間的ロスも見逃せません。
申請業務はデジタル化により簡略化できる領域であり、電子申請への移行は業務効率化の大きな一歩となります。
FAXを使った取引や連絡
FAXによる情報のやり取りは、受信確認や再送の手間が発生しやすく、データとしての扱いにも限界があります。
手書きのFAXは読みづらく、誤認識のリスクも高まります。
また、印刷・保管の手間も無視できません。
特に外部取引先がFAXを主に利用している場合、対応する側もアナログに引きずられてしまいます。
可能であれば、メールやクラウドツールなど、より正確で迅速な手段へ移行することが望まれます。
デジタル化が進まず検索性が悪い
資料やデータが紙のまま保管されていると、必要な情報を探すのに膨大な時間がかかることがあります。
業務において「どこにあるか分からない」「探しても見つからない」といった状況が頻発すると、社員の業務効率は大きく低下します。
ファイル共有システムや文書管理ソフトを導入すれば、検索性を飛躍的に向上させることが可能です。
紙からの脱却は、スピードと正確性を両立する第一歩となります。
人材育成・研修の非効率
社員教育にかける時間や費用は重要な投資ですが、内容や方法によっては効果が薄れ、非効率な育成に陥ることもあります。
全員一律の研修内容の実施
職種や経験年数にかかわらず、すべての社員に同じ研修を課していると、必要な学びが得られない場合があります。
個々の業務やスキルレベルに合っていない内容では、実務への活用が難しく、参加者の学習意欲も低下しがち。
効果的な研修を行うためには、受講者ごとの課題に応じて柔軟にプログラムを設計し、実践に直結する学習機会を提供する工夫が求められます。
OJTが属人化している
現場での指導に依存するOJTは、教育担当者の力量や意識に左右されやすいという特徴があります。
教える人によって伝える内容や方法にバラつきが生じ、指導の質が一定にならないと、社員の育成スピードや成果にも差が出やすくなります。
OJTの質を安定させるには、事前に指導方針やマニュアルを整備し、担当者への育成サポートも併せて行う必要があります。
必要なスキルに合っていない内容
実際の業務に求められるスキルと、研修で扱う内容がかけ離れている場合、時間と費用をかけても成果が出にくくなります。
たとえば現場ではITツールの活用が必須であるにもかかわらず、研修では一般的なビジネスマナーだけを扱うといったケース。
実務と研修の接点を明確にし、必要なスキル習得に直結するテーマを厳選することが、研修の効果を高める鍵となります。
研修後の振り返りが不十分
研修を受けたまま振り返りの機会がないと、学んだ内容を現場で活かすことが難しくなります。
特に知識系の研修では、内容を定着させるための復習やフィードバックが欠かせません。また、上司や同僚との情報共有がないと、組織としての学びにもつながりません。
研修後にはレポート提出や1on1でのフォローアップを取り入れ、学習成果を確実に現場へ落とし込む体制を整えることが求められます。
情報共有の非効率
社内の情報が整理されておらず、伝達手段が乱立していると、連携ミスや確認漏れが発生しやすくなります。
同じ内容を複数媒体で通知
重要なお知らせをメール、チャット、掲示板など複数の手段で何度も発信することで、かえって情報が埋もれてしまうケースがあります。
結果として、全体への周知が行き渡らず、「知らなかった」「見落としていた」という状況が生まれます。
情報伝達のルールを明確にし、発信元を一元化することで、確認漏れを防ぎ、業務のスピードを保つことができるでしょう。
誰が何の情報を持っているか分からない
プロジェクトや業務の進行に必要な情報が、特定の社員の中にしか存在していない状態は、組織全体のリスクとなります。
引き継ぎや急な対応時に「誰に聞けばいいか分からない」「データの所在が不明」といった状況が頻発すると、業務がストップしかねません。
業務フローと担当範囲を見える化し、チームで情報を共有する文化を醸成することが必要です。
ファイル管理がバラバラ
社内資料が個人フォルダやUSB、クラウドなどバラバラに保管されていると、必要なファイルを探し出すのに無駄な時間を費やすことになります。
バージョン違いのファイルが複数存在するなど、情報の正確性にも疑問が残ります。
ファイル命名ルールや保存場所の統一、アクセス権限の整理を行うことで、ファイル管理の効率が大きく改善されます。
情報の伝達ミスによる二度手間
伝えたつもりが伝わっていなかったり、内容が誤って伝わってしまったりすると、業務のやり直しやクレーム対応といった二度手間が発生します。
特に口頭のみのやり取りや、曖昧な指示は誤解を招きやすい要因です。
文書化や議事録の活用、確認のプロセスをルール化することで、情報のズレを防ぎ、ミスの発生率を大幅に抑えることが可能になります。
業務の属人化
業務のやり方やノウハウが特定の社員に集中すると、離職や休職時に大きなリスクとなり、組織全体の業務停滞を招く恐れがあります。
担当者しかやり方がわからない業務
一部の業務が特定の担当者に依存していると、その人が不在になった瞬間に作業が止まってしまうケースがあります。
「あの人しかできない」という状態は見た目にはスムーズに見えても、非常に危ういものです。
業務プロセスを可視化し、複数人が対応可能な体制を整えておくことで、こうした属人化リスクは回避できます。
日頃からの情報共有が欠かせません。
マニュアルが未整備または形骸化
業務手順を記録したマニュアルがない、あるいは存在していても古くて実態と合っていないことは多くの現場で見られます。
その結果、業務を他の人が代行しようとしても再現性が低く、ミスや手戻りが発生しがちです。
実務に沿ったマニュアルを最新状態で維持し、定期的に見直す体制を整えることで、属人化の防止と業務品質の安定が図れます。
引き継ぎ期間が短すぎる
異動や退職時の引き継ぎが十分に行われないまま業務を受け継ぐと、内容の理解不足によりトラブルが起こる可能性が高まります。
特に急な人事異動や退職の場合、形だけの資料だけ渡されて終わると、実務で困る場面が多くなります。
余裕を持ったスケジュールでの引き継ぎ計画を立て、OJTや説明機会を設けることが業務の継続性を保つポイントです。
一部社員に業務が偏っている
「できる人にばかり仕事が集中する」といった状況は、効率的に見えて長期的には組織のバランスを崩す要因になります。
特定の社員の業務負荷が過剰になれば、離職のリスクも高まり、他のメンバーが成長する機会も奪われます。
業務配分を定期的に見直し、タスクの分散や教育の仕組みを整えることが、健全な組織運営に欠かせません。
非効率な採用・人事業務
人材確保の競争が激化する中で、採用や人事に関する業務が手間ばかりかかってしまい、成果に結びつかないケースも少なくありません。

求人情報が更新されていない
募集内容が古いまま放置されていると、求職者とのミスマッチを生み、応募数や質の低下につながります。
業務内容や勤務地、給与など、少しの変更が採用成果に大きく影響するため、定期的な見直しが必要です。
採用ページや求人媒体の情報を最新に保つことで、応募者に信頼感を与え、問い合わせや面接へのつながりやすさが高まります。
応募者対応が手作業で煩雑
履歴書の確認や面接案内、進捗管理などをメールやエクセルで個別対応していると、業務量が膨らみ担当者の負担になります。
対応の抜け漏れや連絡ミスも発生しやすく、応募者に悪印象を与えてしまうことも。
採用管理ツールやフォーム自動返信機能などを導入すれば、手作業を減らしながらスムーズな対応が可能になります。
面接スケジュールの調整に時間がかかる
応募者と面接官の予定調整に多くの時間を要し、面接日の確定までに数日を要するケースもあります。
特に複数人が関与する場合、候補日のやりとりが煩雑になりがちです。
日程調整ツールの活用や、事前に面接枠を共有しておくといった工夫により、やりとりの回数を減らし、スピーディーな選考フローを実現できます。
人材管理システムが導入されていない
社員情報や採用データを紙や表計算ソフトで管理している場合、更新作業やデータの連携に手間がかかりやすくなります。
また、情報の検索性が低いため、人事評価や異動の判断に時間がかかるケースも見受けられます。
クラウド型の人材管理システムを導入すれば、情報を一元化でき、管理の手間を削減しつつ、戦略的な人事運営がしやすくなります。
社内ルール・制度の見直し不足
組織内で長年使われてきたルールや制度が、現在の働き方や業務実態に合わなくなっていることは少なくありません。
時代に合わない規定の運用
旧来の労務規定や勤務ルールがそのまま残っていると、現場の柔軟な対応が妨げられる原因になります。
たとえば、テレワークや時差出勤が一般化しているにもかかわらず、出社前提のルールを適用していると、無用な混乱やストレスを生む可能性があります。
働き方改革や社会の変化に対応するためにも、定期的な規定の見直しが不可欠です。
不必要な申請手続きの継続
かつては必要だった申請書類や承認フローが、今では形骸化しているにもかかわらず、惰性で運用され続けていることがあります。
その結果、社員にとっては「やらなければならないけど意味が分からない」手続きが増え、生産性が下がる一因となっています。
申請業務の棚卸しを行い、不要な手続きを省くことが効率化につながります。
部署間で異なる運用ルール
同じ会社の中でも、部署によって独自のルールが存在し、対応がバラバラになるケースがあります。
経費精算の処理方法や勤怠入力のルールが統一されていないと、社内全体の手続きが煩雑になり、確認や修正に時間を取られます。
全社共通のルールを策定し、従業員に浸透させることで、無駄な作業を減らすことができます。
制度の目的が周知されていない
制度自体は良いものであっても、その背景や目的が社員に伝わっていなければ、形だけのルールとなってしまいます。
運用の意義が理解されていないと、形骸化や反発の原因になり、定着しにくくなるのです。導入時だけでなく、運用段階でも制度の目的や意義を丁寧に説明し、社内に共通認識を持たせる工夫が求められます。
ITツール導入の遅れ
業務効率化に直結するITツールの活用が進まないと、手作業が増え、情報の一元管理や連携にも支障をきたします。
表計算ソフトでの手作業集計
売上や勤怠、在庫などのデータを表計算ソフトで手作業入力・集計している企業では、転記ミスや計算ミスが起きやすく、確認や修正に時間を取られることが多くなります。
また、属人化やファイル管理の煩雑さも課題。
クラウド型の管理システムを導入すれば、自動集計やリアルタイム共有が可能になり、作業時間を大幅に削減できます。
メールによる手動報告の多用
日報や進捗報告をメールで送る運用は、担当者の作業負担が大きくなるうえ、情報の蓄積や分析にも適していません。
メールが埋もれて見落とされることもあり、情報伝達の確実性も下がります。
報告専用のツールやチャットボット、自動集計機能付きのフォームなどを導入することで、報告作業そのものの手間を軽減し、管理側の確認負担も軽くなります。
社内コミュニケーションが電話中心
社内のやり取りがいまだに電話中心という場合、履歴が残らず、言った言わないのトラブルにつながりやすくなります。
また、相手の時間を強制的に奪うことになり、生産性にも悪影響を及ぼします。
チャットやプロジェクト管理ツールを活用すれば、気軽かつ効率的にやり取りができ、記録の残る透明性の高いコミュニケーションが可能になります。
業務ごとに使うツールがバラバラ
プロジェクト管理はAツール、勤怠はB、チャットはCといったように、業務ごとに異なるツールを使っていると、情報が分散し、社員がそれぞれのツールに慣れるまで時間がかかります。
ツール間の連携が取れていない場合、二重入力や確認ミスが発生する要因にもなります。できるだけ統合性のあるシステムを選び、用途に合わせた集約を行うことで、混乱を避けることができます。
営業活動の非効率
営業担当者の時間や労力が無駄に使われる要因には、古い業務スタイルや情報管理方法が残っていることが多くあります。
移動時間が多い訪問営業
対面での営業活動は信頼構築に有効ですが、長時間の移動が続くと、業務効率は大きく低下します。
交通費や待ち時間も積み重なるとコスト負担になりがちです。
すべてを対面で行うのではなく、Web会議やオンライン商談ツールを活用することで、効率化と顧客対応の両立が可能になります。
訪問と非対面を使い分ける戦略が求められます。
名刺や紙資料に頼った情報管理
得意先の情報や案件メモを紙ベースで管理していると、情報の検索性が低く、社内での共有も困難です。
営業担当者が退職した際に情報が引き継がれず、顧客対応に支障をきたすリスクも。
顧客管理システム(CRM)やクラウドストレージを活用すれば、リアルタイムで情報を蓄積・活用でき、組織的な営業活動に繋がります
案件情報の社内共有が遅い
営業現場で得られた顧客の反応や要望などの情報が、すぐに社内に共有されない場合、対応の遅れや提案内容の重複が発生しやすくなります。
特にチーム営業体制を敷いている企業では、情報連携の遅さが成果に直結します。
報告のテンプレート化や共有ツールの整備により、スピーディーかつ確実な情報共有を実現することが重要です。
営業日報が手書きまたは表計算
日々の営業活動を手書きや表計算で記録していると、入力や確認の手間がかかるだけでなく、蓄積したデータの分析も困難になります。
業務時間を削って日報を作成するケースも多く、モチベーション低下の原因にもなりかねません。
営業支援システム(SFA)などを活用すれば、スマホやタブレットから簡単に入力・閲覧ができ、業務の可視化と負担軽減を同時に実現できます。
助成金で改善できる可能性がある業務
非効率な業務の見直しにはコストがかかることもありますが、助成金を活用することで、負担を抑えながら効率化を進めることが可能です。
社員研修のオンライン化
集合型の研修をすべて対面で実施していると、会場費・移動費・講師費用などがかさみます。
オンライン研修に切り替えることでコストを抑えつつ、社員が自分のペースで学習できる環境を整えることができます。
厚生労働省の人材開発支援助成金などでは、eラーニング導入やオンライン講座受講に対する補助が受けられる場合があり、導入ハードルを下げる手段として有効です。
業務マニュアルの整備・作成
属人化の解消や新入社員の早期戦力化を図るうえで、業務マニュアルの整備は欠かせません。
しかし、作成には時間と工数が必要なため、後回しにされがちです。
特定訓練や職業能力開発に関する助成制度を活用すれば、マニュアル作成の人件費や外注費の一部を補助対象にできる可能性があります。
制度を上手に活用することで、実務に役立つ教育体制を築きやすくなります。
テレワーク環境の整備支援
働き方改革の一環としてテレワークを導入したくても、システム整備や端末の購入にコストがかかり、なかなか踏み出せない企業も多いのが実情です。
テレワーク対応のための通信機器、勤怠管理システム、セキュリティ対策の導入費用などは、自治体や厚労省の助成金対象となる場合があります。
申請にあたっては要件確認が必要ですが、整備の一歩を踏み出すきっかけになります。
ITツール導入による業務効率化
表計算や手書き処理に頼った業務を、クラウドシステムや業務支援ソフトで自動化・効率化する取り組みも、助成金の対象となることがあります。
特に中小企業のデジタル化を支援するIT導入補助金などは、ソフトウェア購入費用の補助や、導入支援費用のカバーにも対応しており、業務改善の大きな後押しになります。
補助制度を活用することで、初期コストを抑えながら業務改革に着手できます。
まとめ:業務効率化は助成金が使えることもある
組織内の非効率な業務は、日常的に発生しているにもかかわらず、見過ごされがちです。しかし、少しの見直しや仕組みの改善で、大幅な生産性向上につながることも少なくありません。
特に、人材育成やIT導入、業務フローの整備といった取り組みは、国や自治体の助成金を活用することで、費用負担を抑えながら進めることが可能です。
まずは自社の業務を棚卸しし、改善の余地がある部分を見つけることから始めてみましょう。
補助制度を上手に活用すれば、無理なく、かつ効果的に業務効率化を実現できます。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら