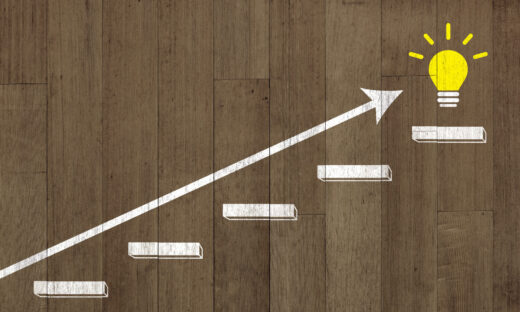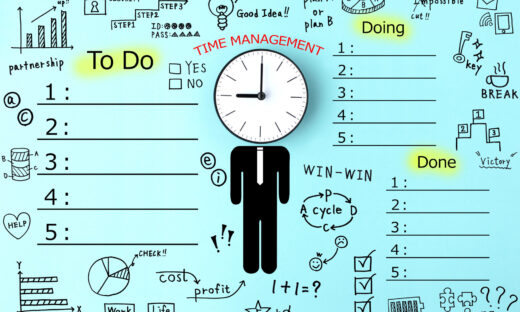本当の採用コストって知ってる?新卒・中途採用をするときにかかっている本当のコスト

採用活動には求人広告やエージェント費用だけでなく、面接の準備、内定者フォロー、教育コストなど、見えにくい費用が数多く発生しています。
新卒採用と中途採用ではコストの内訳や負担のかかるポイントが異なり、採用手法によっても費用は大きく変わります。
本記事では、採用にかかる本当のコストを詳しく解説し、企業が無駄なく効果的に採用を進めるためのポイントを紹介。
採用費用を最適化し、優秀な人材を確保するための戦略を考えましょう。
目次
採用コストとは?見落とされがちな本当の費用
採用活動には、求人広告費やエージェント費用だけでなく、社内の人的コストや研修費用など、見えにくい費用が多く発生します。
採用の実態を把握し、適切なコスト管理を行うことが重要です。

採用コストの基本的な定義
採用コストとは、企業が新たな人材を確保するためにかかる全ての費用を指します。
一般的に「外部コスト」と「内部コスト」の2種類に分類されます。
外部コストとは、求人広告費、採用エージェント手数料、説明会の開催費用など。
一方、内部コストには、採用担当者の人件費、面接官の時間コスト、入社後の教育・研修費用などが含まれます。
企業は採用にかかる総額を正しく認識し、効果的な費用配分を行うことが求められます。
新卒採用と中途採用のコスト比較
新卒採用と中途採用では、コストの構造が異なります。
新卒採用は、インターンシップ、会社説明会、内定者フォローなどに費用がかかる一方、一括採用が可能であるため、長期的な人材育成を前提にコストを回収しやすい特徴があります。
一方、中途採用は即戦力を求めるため、求人広告費、転職エージェント費用、採用面接の負担が大きくなります。
さらに、スキルセットや経験に応じて給与水準が高くなるため、企業によっては新卒採用よりも総コストがかさむのが一般的。
それぞれの採用方法の特徴を理解し、自社の採用戦略に合った手法を選ぶことが重要です。
企業が見落としがちな隠れたコスト
採用活動では、目に見える費用以外にも「隠れたコスト」が発生します。
例えば、採用活動に費やす社内の工数や、内定辞退による再募集のコストは見落とされがち。
また、新入社員の定着率が低いと、研修や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、再度の採用活動が必要になり、さらなる負担が発生します。
加えて、新入社員が業務に慣れるまでの生産性の低下も、実質的なコストとして考慮すべき要素。
これらの隠れたコストを見極め、長期的な視点で採用戦略を立てることが重要です。
採用コストを正確に把握する重要性
採用コストを適切に管理することは、企業の財務健全性や採用戦略の成功に直結します。コストを把握せずに採用を進めると、予算超過や採用の質の低下につながるリスクがあります。
また、効果的な採用を実現するためには、どのプロセスにどれだけの費用がかかっているのかをデータで分析し、無駄を省くことが不可欠。
特に、コスト対効果を意識しながら採用方法を見直すことで、適正な予算内でより良い人材を確保することが可能になります。
正確なコスト管理を行い、採用の質を向上させることで、企業の成長につなげていきましょう。
直接的なコスト(外部コスト)
企業が外部に支払う費用で、採用活動に明確に計上されるものです。
求人広告費
求人広告は、企業が人材を募集する際にかかる代表的なコストの一つです。
掲載媒体や広告手法によって費用が大きく異なり、採用ターゲットに応じた適切な選択が求められます。
求人サイトへの掲載費用(掲載プランによって変動)
求人サイトは、多くの求職者が利用するため、効果的な採用手法の一つです。
掲載費用は、サイトの知名度やプランによって異なります。
無料掲載が可能なものもありますが、基本的には有料プランの方が表示順位が高く、応募者の集まりやすさが向上します。
費用の目安としては、数万円〜数十万円の範囲で設定されることが一般的。
また、一括料金型と成果報酬型の料金体系があり、企業の採用ニーズに応じた選択が求められます。
掲載期間やオプション(スカウトメール、上位表示など)によってもコストが変わるため、事前に詳細を確認することが重要です。
新聞・雑誌・フリーペーパー広告
新聞や雑誌、フリーペーパーを活用した求人広告は、特定のターゲット層に向けた採用活動で有効です。
例えば、地方の求職者やシニア層を狙った求人では、地域新聞や無料配布される求人情報誌が有効な手段となります。
費用は媒体の発行部数や広告サイズによって異なり、数万円から数百万円まで幅広く設定されています。
特に大手新聞の全国版に求人広告を出す場合は、コストが高額になりがち。
一方で、フリーペーパーや地域情報誌は、比較的低コストで掲載できるため、中小企業やローカル採用に適しています。
SNS広告(Facebook、LinkedInなど)
SNS広告を活用することで、ターゲット層に対してピンポイントで求人情報を届けることが可能です。
特にFacebookやInstagramは、年齢・性別・興味関心を細かく設定できるため、企業の求める人物像に合った人材にリーチしやすいです。
LinkedInは、ビジネス特化型のSNSとして、専門職やハイクラス人材をターゲットにする場合に有効。
SNS広告の料金体系はクリック課金型(CPC)や表示回数課金型(CPM)が一般的で、1クリックあたり数十円〜数百円程度が相場です。
少額から運用可能ですが、広告の最適化やターゲティング設定が重要になります。
ダイレクトリクルーティングツールの利用料
ダイレクトリクルーティングとは、企業側が積極的に求職者にアプローチする採用手法です。
求人サイトへの掲載を待つのではなく、データベース内の人材を検索し、スカウトメールを送ることが可能です。
代表的なサービスには、ビズリーチ、リクナビNEXT、Greenなどがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。
利用料は、月額固定型と成果報酬型があり、一般的に数万円~数十万円の範囲で設定されています。
即戦力を確保しやすい反面、採用担当者が適切な人材を選定し、適切なメッセージを送るスキルが求められます。
採用エージェント・人材紹介会社の手数料
採用エージェントや人材紹介会社を利用すると、企業の採用負担を軽減できる一方で、手数料が発生します。
契約形態によってコストが異なるため、適切な選択が求められます。
成功報酬型(採用決定時に支払う):年収の20%〜35%が相場
成功報酬型は、採用が決定した時点で人材紹介会社に手数料を支払う仕組みです。
この手数料は採用者の年収の20%〜35%程度が一般的な相場となっています。
例えば、年収500万円の人材を採用すると、手数料は100万円〜175万円となる計算です。初期費用が不要なため、採用が確定するまでコストが発生しないメリットがあります。
ただし、ハイクラス人材や専門職の採用では手数料の割合が高くなることもあり、コストが膨らむ可能性があります。
採用予定人数が多い場合は、他の採用手法と組み合わせることで、費用対効果を最大化することが重要です。
求人掲載費+成功報酬型(契約時に一部費用発生)
このモデルでは、求人掲載費を事前に支払い、採用成功時には追加で成功報酬を支払う形になります。
初期費用は数万円〜数十万円程度が相場で、採用が決まった際には、成功報酬として年収の15%〜25%程度が発生します。
完全な成功報酬型と比較すると、採用が決まらなかった場合でも掲載費がかかるため、コストリスクが高まる点に注意が必要です。
しかし、成功報酬の割合が抑えられるため、特に採用予定人数が多い場合や長期間募集を行うケースでは有効な手法となります。
また、企業の採用ブランディングを兼ねた求人広告の露出効果も期待できるため、知名度向上を目的とする場合にも適した採用手法です。
採用イベント・説明会の開催費
採用イベントや説明会の開催には、会場費やブース出展費、資料作成などさまざまなコストが発生します。
企業の魅力を効果的に伝えるためには、適切な予算配分が重要です。
会場レンタル費用
自社で説明会を開催する場合、会場の広さや立地に応じたレンタル費用が発生します。
小規模な会議室であれば数万円程度で済みますが、大規模なホールやホテルの宴会場を利用すると、10万円〜50万円以上のコストがかかることも。
また、オンライン説明会を実施する場合でも、スタジオのレンタルや配信機材の準備が必要となることがあります。
会場選びは、求職者のアクセスのしやすさや参加人数を考慮し、コストと効果のバランスを見極めることが大切です。
企業ブース出展費(合同説明会・就職フェア)
合同企業説明会や就職フェアに参加する場合、企業ごとにブースの出展費用がかかります。一般的な合同説明会では、1ブースあたり10万円〜30万円程度が相場となっていますが、人気の高いイベントや大規模会場では50万円以上に達することもあります。
さらに、目立つブース設営や特別枠へのアップグレードを希望する場合は、追加料金が必要になります。
採用ターゲットの学生や求職者に効果的にアプローチできるイベントを選び、コスト対効果を考えながら出展計画を立てることが重要です。
配布資料の印刷費
説明会や採用イベントで求職者に配布する企業パンフレット、会社概要資料、エントリーシートなどの印刷費も見落とせないコストの一つ。
資料のデザインやページ数によって価格は変動しますが、1部あたり数十円〜数百円が目安となります。
例えば、1000部を印刷すると、5万円〜20万円程度の費用がかかるケースもあります。
コストを抑えるために、デジタルパンフレットの活用や、印刷部数を最適化する工夫が求められます。
プレゼンテーション用機材のレンタル費
採用説明会やイベントでプレゼンテーションを行う際には、プロジェクター、スクリーン、マイク、スピーカーなどの機材が必要になります。
会場によっては設備が完備されていることもありますが、別途レンタルが必要な場合、機材一式で5万円〜20万円程度の費用が発生することがあります。
特にオンライン配信を行う場合は、専用カメラや配信機材の手配、配信サポートの委託費などが加わるため、想定以上のコストがかかることもあります。
事前に必要な設備を確認し、レンタル費用を最小限に抑える工夫をすることが大切です。
スカウト・ダイレクトリクルーティング費用
スカウト・ダイレクトリクルーティングは、企業側から積極的に求職者にアプローチする採用手法です。
費用は利用するサービスやアプローチ方法によって異なり、計画的な運用が求められます。
スカウトメールの配信費用(1通あたり課金)
スカウト型採用では、企業が求職者に対して直接コンタクトを取るため、スカウトメールの配信費用が発生します。
一般的な料金体系は1通あたり数百円〜数千円の課金制で、利用する採用プラットフォームによって異なります。
例えば、LinkedInやビズリーチなどのサービスでは、ターゲットに応じたスカウトメールを送信できる一方、メールの開封率や返信率を高めるための工夫も必要になります。
大量に送ればよいわけではなく、効果的なメッセージ作成やターゲットの精査が重要です。また、一部のサービスでは、月額課金制で一定数のスカウトを送れるプランも提供されており、採用ニーズに応じて適切な方法を選ぶことが求められます。
リクルーティング専門の外部リサーチ会社への依頼費
ターゲット層に適した人材を見つけるため、リクルーティング専門の外部リサーチ会社に依頼するケースもあります。
これにより、企業が直接リサーチを行う負担を軽減し、より精度の高い候補者リストを入手できます。
費用は成功報酬型や固定費用型があり、業界や職種によって価格帯が異なります。
ハイクラス人材や専門職のリサーチでは1件あたり数十万円の費用がかかることもあります。
一方、大量採用向けのデータベース提供型のサービスでは、一定期間の利用料として月額数万円〜数十万円のプランが設定されていることが多いです。
採用成功率を高めるためには、リサーチ会社の得意分野や過去の実績を確認し、自社に合ったパートナーを選定することが重要です。
インターンシップ・企業見学会の実施費
インターンシップや企業見学会は、学生に企業文化や業務内容を知ってもらう機会ですが、その実施には多くのコストが発生します。
直接的な費用だけでなく、見落としがちなコストにも注意が必要です。
参加者の交通費・宿泊費負担(企業が負担する場合)
インターンシップや企業見学会では、参加者の交通費や宿泊費を企業側が負担するケースがあります。
特に全国から学生を募集する場合、移動費だけでも1人あたり1万円〜数万円かかることがあり、参加者数が多いほど費用が膨らみます。
また、遠方からの参加者向けに宿泊費を手配する場合は、1泊あたり数千円〜1万円以上のコストが発生するため、事前に予算をしっかり計算することが重要です。
企業によっては、オンラインインターンの導入や、近隣エリアの学生に限定することで、交通費の負担を抑える工夫をすることもあります。
社員の対応時間(※見落としがち)
インターンシップの運営には、担当社員の時間的コストが発生します。
例えば、プログラムの企画や準備、当日の説明や指導、質疑応答など、通常業務とは別に多くの時間を費やすことになります。
特に、現場社員がインターン生の指導を担当する場合、業務の生産性が一時的に低下することも考慮しなければなりません。
また、人事担当者や先輩社員が面談やフィードバックを行う時間も見逃せないコスト。
これらの負担を軽減するために、インターンプログラムの効率化やオンライン活用を検討することが求められます。
インターン用の特別プログラム作成費
インターンシップを効果的に運営するためには、企業紹介や業務体験に適したプログラムを設計する必要があります。
そのための資料作成、研修コンテンツの開発、実習用設備の準備などに費用が発生します。
例えば、参加者向けのマニュアルやプレゼン資料の制作費、業務体験用のシミュレーション環境の構築など、プログラム内容によっては数十万円以上のコストがかかることも。
特に、IT企業や技術職向けのインターンでは、専用のソフトウェアや機材の準備が必要になるため、費用負担が大きくなる傾向があります。
事前に必要なコストを明確にし、効率的に実施できる方法を検討することが重要です。
リファラル採用(社員紹介制度)に伴うコスト
リファラル採用は、社員が自らの人脈を活用して候補者を紹介する採用手法です。
採用成功率が高く、企業文化との適合性も期待できますが、適切なインセンティブや施策が必要となり、一定のコストが発生します。
紹介者へのインセンティブ(報酬やボーナス)
社員が優秀な人材を紹介しやすくするため、多くの企業では紹介者へのインセンティブを用意しています。
一般的な報酬体系として、採用成功時に数万円〜数十万円の紹介ボーナスを支給するケースが多く、特に高度なスキルを持つ人材や幹部候補の採用では、高額な報酬が設定されることもあります。
また、一括支給ではなく、試用期間終了後や一定期間勤務継続後に支給する仕組みにすることで、定着率を向上させる工夫も可能です。
報酬の種類も、現金支給、特別休暇の付与、社内表彰など、企業文化に合わせて柔軟に設計されることが一般的です。
紹介者向けのプロモーション施策費
リファラル採用を定着させるには、社員に制度を周知し、積極的に活用してもらうための施策が不可欠です。
そのため、企業は社内向けの説明会やキャンペーンを実施するほか、制度を継続的に活性化させるためのプロモーション費用も発生します。
例えば、社内ポータルサイトや掲示板に告知を行ったり、紹介キャンペーンとして特別なボーナスを期間限定で設定したりすることで、社員の関心を高める工夫がされています。さらに、リファラル成功事例を社内で共有することで、社員のモチベーション向上につなげる施策も効果的です。
適切なプロモーションを行うことで、リファラル採用の成功率を高め、採用コスト全体の削減につなげることができます。
間接的なコスト(内部コスト)
採用活動には、求人広告費やエージェント費用などの直接的なコストだけでなく、社内で発生する間接的なコストも無視できません。
採用担当者の労働時間や社内リソースの活用も、見落としがちなコスト要因の一つです。
採用担当者の人件費
採用活動には、求人広告やエージェント費用といった外部コストだけでなく、社内の人的リソースにも大きな負担がかかります。
採用担当者の給与や、関与する社員の業務時間を適切に管理することが重要です。
採用担当者の給与・福利厚生費
企業の採用活動を支える採用担当者には、その給与や福利厚生費が発生します。
特に、新卒・中途問わず年間を通じて採用業務を行う場合、1人の採用担当者にかかる年間コストは数百万円規模になることも珍しくありません。
さらに、採用活動が繁忙期を迎えると残業が発生し、追加の人件費負担が増えることもあります。
福利厚生費として、社内研修、通勤費、社用端末の支給なども考慮する必要があります。採用業務の効率化を図ることで、こうしたコストを削減し、他の業務リソースへの影響を抑えることが重要です。
社員の採用業務に費やす時間(他業務の機会損失)
採用プロセスには、採用担当者だけでなく、現場の管理職や面接官となる社員も多く関与します。
例えば、候補者の書類選考、面接の実施、内定者フォローなどに時間を割くことで、本来の業務に使える時間が削られてしまいます。
特に、複数回の面接を行う場合、管理職クラスの時間単価は高く、企業にとって大きなコストとなります。
1時間の面接を10回行えば、合計10時間分の労働コストが発生し、その分の業務効率が低下します。
こうした機会損失を最小限に抑えるためには、採用フローの効率化や面接官の事前準備を徹底することが求められます。
面接・選考プロセスにかかる費用
採用活動の中で、面接や選考プロセスには見えにくいコストが多く含まれます。
特に面接官の工数やオンライン面接ツール、応募者の交通費負担など、適切に管理しなければ予想以上のコスト増につながることがあります。
面接官の時間(書類選考、面接対応、フィードバック作成)
書類選考から面接、フィードバック作成までのプロセスには、面接官の業務時間が大きく関与します。
例えば、1人の候補者に対して書類選考、1次面接、2次面接、最終面接のプロセスを経る場合、面接官1人あたり合計数時間以上の工数がかかることもあります。
特に管理職や専門職が面接を担当する場合、彼らの時間単価は高いため、企業にとっては見えにくいコスト負担となります。
さらに、面接後の評価会議やフィードバック作成にも時間を要し、こうした業務が積み重なることで、本来の業務に割ける時間が減少することにもつながります。
面接プロセスの効率化や適切なスクリーニングを行うことで、不要な負担を削減することが求められます。
オンライン面接のツール利用費
遠方の応募者や多拠点の採用活動では、オンライン面接を導入する企業が増えています。これに伴い、Web会議システムや専用のオンライン面接ツールの利用費が発生します。
一般的なツールにはZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなど無料で利用できるものもありますが、録画機能や応募者管理機能が備わった採用特化型ツールを活用する場合、月額数万円~数十万円の費用がかかることがあります。
また、複数人での同時面接や、自動スケジュール調整機能を導入する場合、追加料金が発生することもあるため、採用規模に応じた適切なツール選定が重要になります。
内定者フォローのためのコスト
内定者フォローは、入社前の不安を解消し、内定辞退を防ぐために重要な施策。
企業は懇親会やフォローアップ施策を通じて、内定者とのつながりを維持し、スムーズな入社を促します。
内定者懇親会・イベント開催費
内定者同士の交流や企業理解を深めるために、懇親会やイベントを開催する企業は少なくありません。
例えば、オフィス見学を兼ねた食事会、社長や先輩社員との座談会、チームビルディング研修などがあります。
これらのイベントには、会場費、飲食代、ノベルティ制作費がかかるほか、遠方の内定者が参加する場合には交通費や宿泊費も発生します。
特に、宿泊を伴う研修形式のイベントを実施する場合は、1人あたり数万円~数十万円の費用がかかることもあります。
これらのコストを抑えるために、最近ではオンライン懇親会やバーチャルオフィスツアーを活用する企業も増えています。
定期的なフォローアップ施策の実施費
内定者との関係を維持し、モチベーションを高めるためには、継続的なフォローが欠かせません。
そのため、多くの企業が内定者向けメルマガ、LINE公式アカウントの運営、個別面談などを実施しています。
また、eラーニングによる事前研修や、同期とのつながりを深めるオンライン座談会など、デジタルを活用したフォロー施策も一般的です。
これらには、動画制作費、配信システムの利用料、資料作成費が発生し、施策の規模によっては年間数十万円以上のコストがかかることもあります。
フォローの質を向上させることで、内定辞退を減らし、入社後の定着率向上につなげることが期待されます。
採用関連のシステム・ツール導入費
採用業務を効率化し、より適切な人材を確保するために、システムやツールの導入を検討あるいはすでに導入している企業もあるでしょう。
採用管理やマッチング精度を向上させるためのソリューションには、それぞれ導入費用と運用コストが発生します。
採用管理システム(ATS)の導入・運用費用
採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、応募者の情報管理、選考状況の可視化、面接スケジュールの調整などを効率化するツール。
特に、応募者が多い企業や複数の採用チャネルを活用している企業では、ATSを導入することで採用業務の負担を軽減できます。
導入費用は、システムの種類によって異なりますが、初期導入費として数十万円~数百万円、月額利用料として数万円~数十万円が相場となります。
また、企業の規模や利用機能に応じてカスタマイズが必要になる場合、追加の開発費が発生することも。
適切なATSを選択することで、業務の効率化とデータ管理の精度向上を実現できます。
AIマッチングツールの利用料
AIを活用したマッチングツールは、求職者のスキルや適性を分析し、企業とのマッチ度を算出することで、より精度の高い採用を実現します。
履歴書や職務経歴書のデータを自動解析し、候補者のスクリーニングを支援する機能を備えているものもあります。
AIマッチングツールの導入費用は、月額数万円~数十万円程度が一般的ですが、採用規模や機能によって料金体系が異なります。
また、一部のサービスでは、成果報酬型で成功した採用ごとに課金されるケースも。
AIを活用することで、従来の採用フローでは見落としがちな潜在的な適性を発見し、より効率的なマッチングを実現できる点が大きなメリットです。
見落とされがちな隠れたコスト
採用活動には、直接的な費用だけでなく、見えにくいコストも多く発生します。
採用の長期化やミスマッチ、企業の評判リスクなど、隠れたコストを把握し、適切に対策を講じることが重要です。
採用の長期化によるコスト増
適切な人材がなかなか見つからず、採用活動が長期化すると、企業の負担が大きくなります。
求人広告を継続掲載する費用、採用エージェントとの契約延長費、追加の面接対応など、コストは時間とともに増加します。
さらに、ポジションが長期間埋まらないと、既存社員の業務負担が増え、モチベーションの低下や離職リスクの上昇にもつながります。
採用プロセスの最適化や、より効果的な採用手法の導入により、長期化によるコスト増を防ぐ工夫が求められます。
採用ミスマッチによる離職コスト
採用した人材が企業の文化や業務内容と合わず、早期離職してしまうと、そのコストは大きな損失となります。
新入社員の給与や研修費に加え、再度採用活動を行うための広告費、面接時間、教育コストなどが再び発生するためです。
特に、試用期間内での離職が増えると、採用の無駄が積み重なり、企業の採用力自体が低下する可能性もあります。
ミスマッチを防ぐためには、適切な選考プロセスを構築し、企業文化や業務内容を事前にしっかり伝えることが重要です。
新入社員の適応・定着支援のコスト
新入社員が組織に適応し、長期的に活躍するためには、定着支援のためのコストが必要です。
具体的には、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)、メンター制度、定期面談などが挙げられます。
これらの施策には、先輩社員や管理職の時間コストがかかるほか、外部研修の受講費や社内研修の運営費も発生します。
また、定着率向上を目的とした職場環境の整備や、キャリア開発の支援プログラムなども、長期的な視点での投資が求められます。
採用ブランディング費用
優秀な人材を獲得するためには、企業の魅力を発信し、ブランド価値を高めることが重要です。
そのため、採用専用のウェブサイト制作、企業紹介動画の作成、SNSやオウンドメディアを活用した情報発信など、採用ブランディングに関するコストが発生します。
特に、競争が激しい業界では、採用ブランドの強化が採用成功のカギとなるため、継続的な投資が必要です。
これらの取り組みは短期的な成果が出にくいため、長期的な視点で戦略を立てることが求められます。
採用失敗の評判リスク
採用活動がうまくいかず、応募者や新入社員の満足度が低いと、企業の評判に悪影響を与える可能性があります。
例えば、選考過程での対応が不十分だった場合、求職者からの口コミが広がり、企業のイメージ低下につながることもあります。
また、早期離職が相次ぐと、「定着率が低い企業」として認識され、優秀な人材の応募が減少するリスクも考えられます。
特に、SNSや企業口コミサイトの影響が強まる中、採用プロセス全体を通じた求職者への対応を慎重に行うことが重要です。
まとめ:助成金も活用しながら採用コストは最適化しよう!
採用活動には、求人広告やエージェント費用だけでなく、見えにくい隠れたコストも多く発生します。
採用の長期化やミスマッチによるコスト増を防ぐためには、選考プロセスの効率化や採用ブランディングの強化が不可欠です。
さらに、助成金制度を活用することで、研修費や雇用維持にかかる費用を軽減しながら、より戦略的な採用が可能になります。
無駄なコストを削減し、優秀な人材の確保と定着につなげる施策を取り入れましょう。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら






-520x312.jpeg)