助成金・補助金は業種によって申請すべきものは異なるの?業種ごとに見たおすすめの助成金・補助金を解説
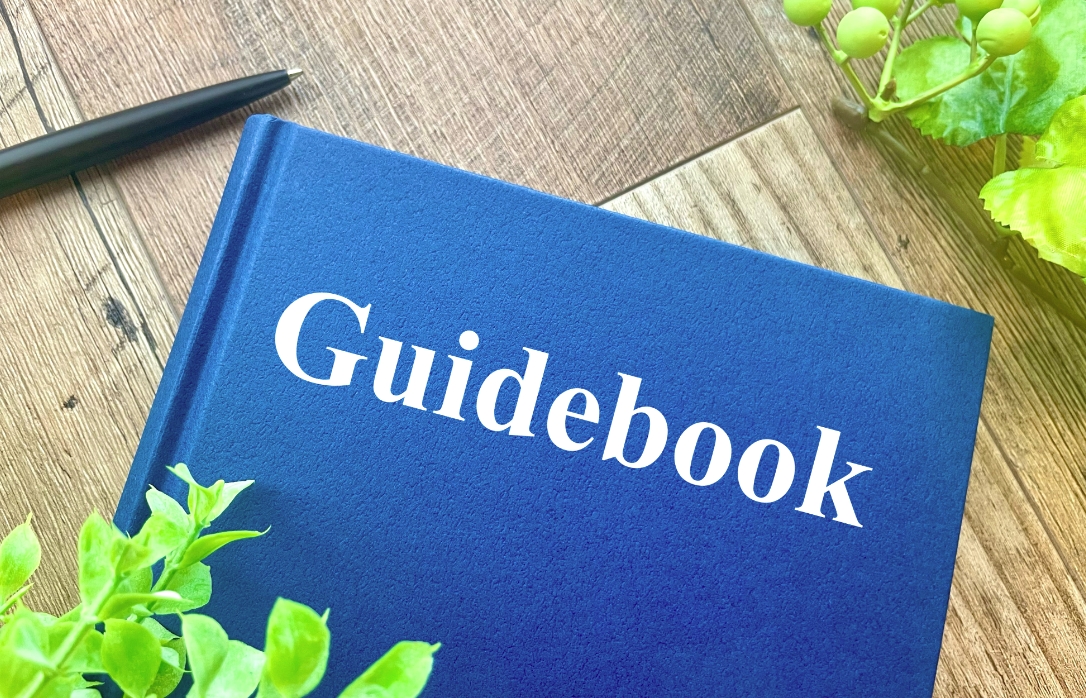
中小企業向けの助成金・補助金には、事業分野(業種)によって活用できる制度が異なります。
本記事では、IT業・小売業・建設業・サービス業(特に飲食業)を中心に、国の主要な補助制度から大阪府をはじめ関西エリアの自治体・支援機関による地域独自の制度までを網羅的に解説。
各業種ごとに、どのような補助金が利用しやすいのか、その概要やポイントを紹介します。
自社の業種に合った支援策を知り、賢く活用することで、デジタル化や設備投資、人材確保などの課題解決に役立ててください。
目次
IT業向け助成金・補助金
IT業を営む中小企業では、デジタル技術の導入や研究開発への投資が重要になる一方、中小企業全般を対象とした支援策も活用できます。
国と地方自治体の双方で、IT分野・DX推進に関連する補助制度が充実しています。
ここでは国の主要補助金と大阪府を中心とした地域独自の支援策を確認し、IT企業ならではの申請ポイントに触れます。
デジタル化推進とIT業界の支援ニーズ
政府は中小企業の生産性向上やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のため、ITツール導入や先端技術活用を支援しています。
IT業界は他業種に比べデジタル化が進んでいるように思われがちですが、中小のIT企業では資金や人材の制約から新サービス開発や自社DXに課題を抱えることもあります。
また、IT企業以外の中小企業でも業務効率化のためITツール導入補助金等を活用するケースが増えています。
国はこれら幅広い業種へのIT化支援に力を入れており、IT導入補助金やものづくり補助金など複数の補助金を組み合わせて活用することも可能。
例えば、自社の業務効率化にIT導入補助金を使い、新規事業に事業再構築補助金(現在は「新事業進出補助金」に移行)を使う、といった併用も認められています。
国の主要な補助金(ITツール導入・研究開発支援など)
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
中小企業がITツール(ソフトウェアやクラウドサービス等)を導入する費用の一部を補助する国の制度です。
業種を問わず利用でき、2025年はインボイス制度対応やセキュリティ強化に関するIT投資に対し補助率が最大4/5まで引き上げられています。
例えば、クラウド型の受発注システムやAIを活用した業務管理ツール導入なども対象となり、最大450万円の補助が受けられます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(いわゆる「ものづくり補助金」)
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(いわゆる「ものづくり補助金」)もIT業を含む幅広い中小企業が利用できます。
革新的サービスや製品の開発、生産プロセスの改善等に使える大型補助金で、一般型では補助上限1,250万円(特別枠で最大7,500万円超)・補助率1/2~2/3と高額。
IT企業が自社開発のソフトウェアに関連する設備を導入したり、新規プロダクト開発のための機器・クラウド環境を整備したりする場合にも適用可能です。
実際にAIを活用した受注予測システム導入にこの補助金を活用し、生産性向上につなげた事例もあります。
「中小企業新事業進出補助金
国の施策として2025年度より「中小企業新事業進出補助金」が開始されました。
これは従来の事業再構築補助金の後継にあたり、中小企業が異業種や新市場へ進出する際に使える補助金です。
IT企業が新たなサービス領域に挑戦する場合など、最大9,000万円(補助率1/2)の大型支援となっており、国が中小企業の新規事業展開を強力に後押ししています。
研究開発(R&D)支援系の補助金
IT分野の中小企業向けには研究開発(R&D)支援系の補助金も存在します。
大阪府では「成長型中小企業等研究開発支援事業」という制度があり、府内中小企業の技術開発を助成しています。
自社プロダクトの開発費用の一部補助など、技術革新につながる取組みを支援するものです。
国レベルでも、中小企業庁やNEDOを通じてSBIR支援、新技術実証支援の公募が行われることがあります。
IT企業はこうした技術開発系補助金もチェックするとよいでしょう。
大阪府・関西エリアのDX推進支援策
関西エリア、とりわけ大阪府は中小企業のデジタル化促進に熱心で、独自の補助制度を設けています。
代表的なのが、大阪産業局が実施する「中小企業DX支援補助金」です。
これはAI・IoT・RPA等の導入による業務効率化プロジェクトに対し、最大300万円、補助率2/3程度で支援する補助金です。
特徴として専門家によるコンサルティング支援が付帯し、企業側の負担を減らしつつ現場のDXを推進できる点が挙げられます。
現場作業のデジタル化やAIを使った自動化ツール導入など、IT企業が自社のサービスにAI実装を試みる場合や、非IT企業でもDXに取り組む場合に適した補助金です。
大阪市や堺市などでは、5GやAIの実証プロジェクトを支援する取り組みも。
例えば大阪市の「5G導入トライアル補助金」は、市内中小企業が5Gを活用した新製品・サービスの試験導入を行う際に、最大300万円(補助率1/2)を補助する制度。
採択枠は少ないものの、先端技術の現場実装を行政が支援するモデル事業であり、IT企業が最新技術のPoC(概念実証)を行う好機となります。
また大阪市や堺市では、自治体と企業が連携してAIソリューションの実証実験を行う際の支援策もあり、フィールド提供や専門家助言といった支援と補助金を組み合わせて企業の挑戦を後押ししています。
関西では大阪以外にも、京都市の「中小企業デジタル化支援補助金」(中小企業のクラウド導入等に最大100万円補助、補助率2/3)や、神戸市の「中小企業DX推進支援補助制度」(DX推進経費に最大250万円補助)など、各自治体ごとにDX支援策が存在します。
京都府は新サービス開発やDX推進を対象に「新事業チャレンジ補助金」(最大200万円、補助率2/3)を実施しており、京都市も地域産業の競争力強化や観光・製造・飲食業へのテクノロジー導入促進を目的に独自支援策を設けています。
IT企業はこうした地域のデジタル化補助も活用し、自社サービスの高度化や顧客企業へのDX支援策として役立てることができます。
IT企業が補助金を活用するポイント
IT業界で補助金を活用する際は、自社の成長戦略と補助金の目的をマッチさせることが重要です。
例えば、「業務効率化」がテーマの補助金であれば自社の開発プロセス改善や社内ITインフラ整備の計画を立てる、「新規事業支援」なら自社プロダクトの新展開や他業種向けサービス開発の事業計画を立案するといった具合です。
補助金申請では事業計画書が重視されるため、技術的な優位性だけでなく事業としての将来性や収益見込みを明確に示す必要があります。
小売業向け助成金・補助金
小売業(店舗販売業)では、販路開拓や店舗の改装・設備導入、集客支援に関する補助金が充実しています。
小規模な小売店ほど公的支援を活用するメリットが大きく、広告宣伝費やECサイト構築費まで補助対象になる制度。
また、商店街の活性化や空き店舗対策など、地域コミュニティと連携した支援策も各地で展開されています。
ここでは国の代表的な小売業向け補助金と大阪府を中心とした関西の地方施策を紹介し、効果的な活用ポイントを解説します。
小売業の課題と補助金活用の重要性
小売業界では、近年EC市場拡大や消費者ニーズの多様化に対応するため、従来の対面販売に加えてオンライン販売やキャッシュレス決済の導入が不可欠になっています。
また、コロナ禍を経て実店舗もDX対応や販促の強化が求められました。
これらに取り組む際、中小の小売事業者にとって助成金・補助金は大きな後押しとなります。
例えば、ネット販売やSNS広告、オンライン決済環境の整備といった取り組みは、小規模事業者持続化補助金などの対象経費となり得ます。
実際、小売業ではコロナ禍適応策としてECサイト構築やキャッシュレス端末導入が支援対象となり、採択事例も増えています。
店舗運営においても、消費者の利便性向上や感染症対策を兼ねて、自動ドアや空調設備更新などの設備投資を検討する店舗もあります。
このように売上拡大策と店舗環境改善の双方で活用できる補助制度を知っておくことが、経営改善のポイントになります。
国の主要補助金(販路開拓・IT化支援など)
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小売業にとって最も利用しやすい国の補助金の一つ。
従業員数が商業の場合5人以下の小規模事業者が対象で、販路開拓や業務効率化の取組みにかかった経費の2/3(赤字事業者は3/4)を補助します。
補助上限は通常枠で50万円ですが、条件次第では最大200万~250万円に拡充される特別枠も用意されています。
例えばチラシ作成・ポスティング費用、ウェブサイト制作費、ネットショップ開設費用、店舗改装費など幅広い経費が対象になります。
実際の採択事例として、雑貨店がEC販売を開始するためのホームページ構築に本補助金を活用したケースや、土産物店がインバウンド客向けに多言語対応の通販サイトを立ち上げたケースなどが報告されています。
小規模店舗が広告宣伝や新サービス開始に資金を投入する際、まず検討すべき定番の補助金と言えるでしょう。
IT導入補助金
POSレジや在庫管理システム、キャッシュレス決済端末の導入など、小売店のデジタル化に関わるツール導入費用を補助します。
補助率は1/2が基本ですが、インボイス制度対応やセキュリティ対策ITツールについては最大3/4〜4/5まで引き上げられる特例枠があります。
例えば、複数店舗を統合管理できるPOSレジの導入や、顧客データ分析ソフトの導入を計画している場合、この補助金の活用で費用負担を大幅に減らすことが可能です。
IT導入補助金は年に数回募集があり、公募期間を逃さないよう商工会議所等から情報収集しておきましょう。
ものづくり補助金
前述のものづくり補助金も小売業で活用された例があります。
例えば、ある食品小売業者が地方特産品の加工設備を導入しEC販売に乗り出す際、この補助金で大型設備費の2/3を補填したケースなどです。
ものづくり補助金は要件が「革新的取り組み」とややハードルが高いものの、商業・サービス業も対象であり、小売店が新製品開発(自社PB商品開発など)や画期的な販売手法を導入する場合には検討する価値があります。
中小企業新事業進出補助金
2025年度から始まった中小企業新事業進出補助金(事業再構築補助金の後継)も、小売業の業態転換に利用可能です。
例えば店舗販売中心の企業がサブスクリプション型のレンタルサービスを新事業として開始する、実店舗からオンライン専業に転換する、といった大きな事業転換にはこの補助金が適しています。
補助額は最大9,000万円(補助率1/2)と極めて大きく、思い切った転換を検討する際には有力な選択肢です。
もっとも、審査も厳しいため、採択を目指すなら事業計画のブラッシュアップに専門家の助言を得ることが望ましいでしょう。
大阪府・関西の地域支援策(商店街活性化等)
大阪府や関西各地では、小売業者向けの独自支援策が展開されています。
とりわけ商店街の活性化や空き店舗の有効活用に関する補助制度は、小売・飲食など地域密着型ビジネスに有益です。
大阪市では、空き店舗に新規出店する事業者に対して家賃の一部を補助する制度があります。
「大阪市 空き店舗活用支援」では、開業希望者が商店街等の空き店舗を賃借する場合に2~3年間の家賃補助が受けられます。
商店街の空洞化対策として実施されており、新規出店時のコスト負担を軽減できるため、地域で店舗を構えたい小売・サービス業者にとって魅力的な支援です。
大阪府レベルでは、設備導入に直接補助金を出すのではなく、公的機関が設備購入を代行して事業者に長期リースする「設備貸与制度」を提供しています。
「大阪府 小規模企業者等設備貸与制度」がその一例で、小規模事業者が厨房機器や製造設備などを導入する際に府が代わりに購入し、事業者は分割払いで利用する仕組みです。
実質的に低利のリースを受けられる形になり、自己資金が乏しい場合でも最新設備の導入が可能となります。
小売店においては冷凍・冷蔵ショーケースやPOSシステムなど、まとまった設備投資が必要な局面でこの制度が役立ちます。
その他、関西の各自治体で見られるのは商店街振興を目的とした補助事業です。
例えば、大阪府では商店街が行う集客イベントや共同施設整備に対し補助を行う「商店街魅力向上支援事業」などを公募しています。
また京都市や奈良県でも、伝統的な商店街の賑わい創出策(街路灯のLED化、案内看板の多言語化等)に補助を出す施策があります。
これらは商店街組合や自治体主体の事業になる場合が多いですが、結果的に個々の小売店にとっても集客環境の改善につながります。
自店が所属する商店街でこうした補助事業の採択が決まったら、積極的に協力・参加することで恩恵を受けられるでしょう。
小売業での補助金活用と成功のポイント
小売業における補助金活用の成功事例としては、実店舗とオンラインの融合を図ったケースが目立ちます。
例えば、ある地方の土産物店では持続化補助金を活用して多言語対応のECサイトを開設し、週末の観光客以外にも平日の全国顧客から注文を獲得することに成功しました。
その結果、週末の来店客数が平均5人から10人へ倍増し売上が向上したとの報告があります。
この事例では、補助金で初期費用を賄ったことでリスクを抑え、新規販路拡大に踏み切れた点がポイントです。
建設業向け助成金・補助金
建設業では、人手不足への対応や働き方改革、安全対策、そして建設DX(デジタル化)が大きな課題となっています。
2024年から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され(いわゆる「2024年問題」)、生産性向上や労務管理改善が急務となりました。
この状況を踏まえ、政府は建設企業向けの補助金・助成金に多くの予算を投じ、DX設備導入や人材確保策を支援しています。
以下では国が提供する主な建設業関連の補助金・助成金と、大阪府を中心とした地域独自の支援策について説明し、建設業での活用ポイントを探ります。
建設業界の現状:人材不足とDX推進の必要性
ご存知のように建設業は元来、紙の書類や手作業に頼る部分が大きく、デジタル化が他業種に比べ遅れていた傾向があります。
しかし慢性的な技能労働者不足や長時間労働の是正プレッシャーから、近年急速にDXの波が押し寄せています。
国土交通省も「i-Construction」施策を掲げ、ICT建機や3次元測量技術などの普及に力を入れています。
加えて、現場の安全性向上や災害対応力強化のため、ドローンやAIカメラ、ウェアラブル端末といった先端技術の導入が重要視されています。
一方で、建設業の資金繰りは工期の長さや手形決済などの慣行により厳しい局面が多く、設備投資資金を自己調達しにくい事情があります。
こうした背景から、DX機器導入費や人材育成費を補助金で賄う意義は他業種以上に大きいといえます。
国の主要補助金(ICT導入・事業転換支援、人材関連助成金、IT導入補助金)
施工管理ソフトや3次元CAD、ドローン測量システムなど、建設現場のデジタル化に資するITツール導入が幅広く対象になります。
近年では電子インボイス(適格請求書)制度への対応も重要テーマとなっており、建設業者が会計・受発注システムをクラウド化する際にもこの補助金が活用されています。
IT導入補助金は最大450万円・補助率1/2(条件により3/4)で、現場管理の効率化やテレワーク環境整備に取り組む中小建設企業を強力に支援します。
建設市場整備推進事業費補助金
国土交通省系の新たな補助制度にも注目が必要です。令和7年度(2025年)に新設された「建設市場整備推進事業費補助金」は、災害時の迅速な復旧活動や現場の安全確保に資するICT機器導入を支援するものです。
例えば、ウェアラブルカメラやドローン、四足歩行ロボットといった先端機器を用いた防災訓練や現場管理システムの導入が対象となり、補助率は2/3、補助上限は年度ごとに定められます(初年度の上限は数百万円規模)。
この補助金は被災地での活動や防災計画に基づく取組みであることが要件となっており、防災インフラ企業や地域建設業者が設備を高度化するチャンスと言えます。
事業再構築補助金(現在は新事業進出補助金)
建設業の事業転換を後押しする補助金として、前述の事業再構築補助金(現在は新事業進出補助金)があります。
第8回公募(旧制度)では、AI搭載の建機やドローンを活用した測量、新工法による省力化施工など、大胆なICT導入事例が多数採択されました。さ
らに、建機の電動化(ゼロエミッション化)や建設副産物リサイクルなどSDGsに資する取組みも高評価を得ています。
新制度でも基本は同様で、例えば土木業者が太陽光発電設備の設置事業に乗り出すとか、住宅施工業者がIoTスマートホーム分野に進出するような場合に、この大型補助金(最大9,000万円規模、補助率1/2)が適用可能です。
建設業界では既存事業の枠にとらわれず、新分野に挑戦する動きも出てきており、その際の資金面のリスク低減に非常に有用です。
人材確保や働き方改革関連の助成金
厚生労働省管轄の助成金で、要件を満たせば必ず交付されるタイプのものが多く、建設業者も活用できます。
代表的なのは「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進コース)」です。
建設業でも2024年から時間外労働の上限規制が適用されたため、勤怠管理システムの導入や休暇取得推進の取り組みに対し、この助成金で費用補助を受けられます。
具体的には、工事現場への人員配置ソフト導入やノー残業デー制度の導入等により所定労働時間を削減した企業に対し、導入経費や目標達成にかかった費用の一部を助成します(支給額は取り組み内容により数十~数百万円)。
さらに、「人材確保等支援助成金」の中には建設業特有のコースが用意されています。
例えば、建設業での女性や若年者の就業促進を目的とした助成メニューでは、職場環境の整備(更衣室やトイレの改善等)や研修実施費用が補助されます。
また、トライアル雇用助成金(正式にはトライアル雇用奨励金)も、新人技術者や未経験者を試行雇用する建設企業にとって有用です。
一定期間の試用雇用後に正規採用すれば、一人当たり数十万円の奨励金が支給され、人手不足解消の取り組みを後押しします。
これら労働分野の助成金は通年申請できるものも多いため、ハローワークや労働局の情報を随時確認し、自社の人事施策に役立てましょう。
大阪府・関西の地域独自支援策(DX導入・人材育成など)
大阪府や周辺自治体でも、建設業に関連する支援策が存在します。
大阪府産業労働部や大阪産業局は業種を問わないDX支援補助金を提供しており、建設業のICT化プロジェクトでも利用可能です(前述の中小企業DX支援補助金など)。
例えば、府内の中小建設会社がRPAを導入して受発注事務を自動化する場合、要件に合致すれば大阪府のDX補助金で経費の一部(2/3など)を賄えます。
また、大阪市が支援する5G導入トライアル補助金も、建設業での活用が期待されます。
5G通信を活用した重機の遠隔操作や高精細映像による遠隔監督といった試みは既に始まっており、これら新技術の実証に補助が出るのは大阪ならではのメリットです。
採択数は限られますが、選ばれれば全国的なモデルケースとして注目を集めるでしょう。 人材面では、大阪府が運営する「大阪府技能研修・人材育成支援」のような事業もあります。
具体的には府内の職業能力開発施設と連携して、若手土木技術者の育成講座を格安で提供したり、中小企業向けに建設現場のDX人材育成研修を補助したりする取り組み。
兵庫県でも「ものづくり企業のDX実践・人材育成支援事業」を行っており、IoTやAI活用のための社員研修に補助を出しています。
建設業も対象に含まれるため、社員のITスキル向上や資格取得支援に使うことができます。 奈良県や滋賀県などでは、地元建設業の経営力向上を狙い経営相談や専門家派遣を無料または安価で提供する事業所があります(奈良県中小企業支援センター等)。
直接のお金の給付ではありませんが、補助金活用を検討する際の計画策定をプロに手伝ってもらえる機会ですので、ぜひ地域の中小企業支援策も有効活用してください。
建設業での補助金活用ポイント
建設業が補助金を活用する際のポイントは、「現場の課題を具体的に示し、その解決策としての投資」であることを明確化することです。
例えば、「人手不足で工期遅延のリスク→工程管理システム導入で○%効率化」「安全管理強化が課題→AI監視カメラ導入でヒヤリハット件数○件削減見込み」など、課題と導入効果を数字で結びつけると審査員にも伝わりやすくなります。
また、補助金申請では自治体発行の業界動向や統計データを引用すると説得力が増します。建設業界の場合、国交省や建設業協会が公表する人材動向、事故発生件数の推移などを用いて「業界全体として○○の必要性が高まっている。
その中で自社も○○に取り組む」などと書き込むと、政策目的との合致をアピールできます。
資金計画については、他業種以上に支払いサイトのズレに注意が必要です。補助金が下りるまで1年近くかかるケースもあります。
建設業では完工まで売上が入らないことも多いため、補助対象事業と平行して進行中の工事の資金繰りに支障が出ないよう、金融機関のブリッジローン(つなぎ融資)も検討しましょう。
サービス業(飲食業)向け助成金・補助金
サービス業の中でも特に飲食業は、コロナ禍以降の物価高や人手不足で経営環境が厳しく、各種補助金・助成金の活用が欠かせない業種です。
店舗設備の更新、デジタル化、業態転換、人材確保など課題は多岐にわたりますが、幸い国や自治体から提供されている支援策も豊富です。
飲食店経営者が使える主な国の補助金・助成金と、大阪府を中心とした地域独自の支援制度を整理。
併せて、2025年時点での補助金トレンドや活用上の注意点についても触れ、飲食業の未来を切り開くヒントを提供します。
飲食業の経営課題と補助金活用の必要性
飲食業は設備投資負担が大きく、さらに近年は人件費高騰や食材価格の上昇もあり、収益確保が難しい状況です。
その一方で、DX(デジタル化)対応による効率化や、新サービス(テイクアウト・デリバリー等)への対応も不可避となっています。
こうした中、補助金による資金支援は経営改善の大きな助けとなります。
例えば、注文の自動化やセルフレジ導入による省力化、客席数拡張やキッチン設備更新による売上アップ、新メニュー開発や店舗デザイン刷新による集客強化――これらの施策で多くの飲食店が国・自治体の補助制度を活用しています。
特に2025年現在、飲食業向け支援策のキーワードとして「DX(デジタル化)」「省エネ・脱炭素」「インバウンド対応」「バリアフリー化」「人材確保・賃上げ支援」が挙げられます。
具体的には、モバイルオーダーや予約管理システムの導入補助、高効率厨房機器やLED照明導入の補助、訪日客受け入れのための多言語メニュー作成・キャッシュレス決済導入支援、トイレの段差解消や多機能トイレ設置への補助、そして非正規スタッフの正社員化支援や最低賃金引上げと連動した設備補助などが注目されています。
飲食店はこれらのトレンドに対応した補助金を上手に取り込み、「ポストコロナ」に適応した強い経営基盤を築くことが求められています。
国の主要補助金(販路開拓・省力化・新事業支援など)
小規模事業者持続化補助金
販路開拓を目的とした補助金で、広告費だけでも申請可能な使い勝手の良さから小規模飲食店に支持されています。
従業員5人以下の飲食店が対象で、補助率2/3(赤字なら3/4)、上限50万円(条件により最大250万円)まで、店舗改装費・チラシやWeb広告費・設備購入費など幅広い経費に使えます。
例えば、グルメサイト掲載料やLINE公式アカウント開設費、テイクアウト用メニュー表作成費なども対象に含まれます。
実際に、和食店が地元食材を活かした新メニューPRに活用した例や、ラーメン店が焼肉メニュー導入による業態転換で新客層獲得を狙った例など、多くの採択事例があります。
IT導入補助金
飲食店のデジタル化ニーズに対応した補助金です。ポスレジやモバイルオーダー、予約管理システム、テーブル注文端末等、現場のIT化ツール導入費用の大半を補助してくれます。
2025年はインボイス制度対応も重視され、対象事業者には最大補助率4/5という手厚い枠も用意されています。
例えば、セルフオーダーシステム導入で回転率を40%改善したカフェや、POS連携のセルフレジと冷凍ストッカー導入で客単価20%アップ・食品ロス40%削減を実現した焼肉チェーンの事例も報告されています。
ものづくり補助金
大規模な設備投資を伴う飲食店の革新的取組みに使えます。
セントラルキッチンの新設、大型冷凍庫や最新調理機器の導入、新商品(惣菜やデザート)の開発などが該当し、補助上限1,250万円(特別枠で最大8,000万円)、補助率2/3という大型支援。
採択には「革新性」が求められますが、中央厨房導入による効率化や、飲食物の加工ライン構築による小売進出(例:焼肉店が自社加工肉のギフト販売開始)などが認められています。
新事業進出補助金
2025年開始の注目制度で、旧事業再構築補助金に相当します。
飲食店が通販事業に乗り出す、惣菜の製造販売を始める、無人店舗を展開する等、新分野への挑戦に使えます。
補助額最大9,000万円(補助率1/2)と桁違いですが、賃上げ実施企業には上乗せ枠もあり、政府の「中小企業の新しい挑戦」支援の本気度がうかがえます。
中小企業省力化投資補助金
飲食店の省人化・自動化に特化した最新補助金です。
券売機、セルフレジ、配膳ロボット、自動調理機器など、導入すればすぐ効果が出るような省力化設備の購入費が対象で、補助率2/3(小規模は3/4)、上限なんと1億円(カタログ掲載の定型モデルなら1,500万円)という手厚さです。
申請書類も簡素化されており、ホール業務のロボット化や厨房の自動化を図りたい飲食店には非常に使いやすい制度です。
2024年には配膳ロボット+自動精算レジ導入でホール業務を効率化した居酒屋や、券売機設置で注文オペレーションを簡素化したラーメン店が採択されています。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
人材面の助成金として、パート・アルバイトを正社員に登用した際に1人あたり最大80万円が支給される制度です。
飲食店は多くの非正規スタッフを抱えるため、人件費確保が悩みですが、この助成金は雇用保険料を財源に従業員の処遇改善を支援するものです。
複数人を転換すればその人数分支給されるため、長年働いている戦力を正社員化して定着を図る際に活用するとよいでしょう。
業務改善助成金
こちらは最低賃金引上げと生産性向上設備投資をセットで支援する厚労省の助成金です。例えば、時給を一定額アップする代わりに厨房機器を導入して業務効率化を図ると、設備費の一部(5~7割)を助成金が負担します。
飲食業は最低賃金に近い水準のスタッフも多いため、賃上げと機械化を同時に進めるこのスキームはマッチしやすく、フライヤーの自動化設備導入や食洗機導入などの例が多数あります。
賃上げ額に応じて上限50万円から数百万円までコースがあり、中小企業なら比較的要件も満たしやすいです。
大阪府・関西の地域支援策(設備投資・店舗支援など)
大阪府をはじめ関西各地でも、飲食店向けの特色ある支援制度が展開されています。
まず大阪府では、「小規模企業者等設備貸与制度」というユニークな仕組みで飲食店の設備投資を支援しています。
これは、飲食店が高額な厨房機器等を導入する際に、大阪府の関連機関が設備を代わりに購入して事業者へ貸与(リース)する制度。
事業者は分割払いで利用できるため、自己資金や融資負担を抑えて最新設備を導入できます。
老朽化した厨房機器の更新や、新店舗開業時の初期設備調達などで、この貸与制度を活用する事例が増えています。
大阪市では前述の空き店舗活用家賃補助が飲食店にも適用されます。
例えば、新たに飲食店を開業する際、商店街のシャッター街に出店すれば家賃の一部補助を2~3年間受けられるため、初期の家賃負担を減らし軌道に乗るまで支援してもらえます。
コロナで閉店した飲食店舗跡への新規出店促進策として、関西では大阪市以外にも京都市や神戸市、奈良市などが空き店舗出店補助を実施しています。
地域差はありますが、家賃○万円までの一定割合(例:奈良市は月額上限10万円・最長1年など)の補助が一般的。
省エネや衛生対策に関する補助も地域独自であります。
たとえば京都府では、飲食店組合加盟店向けに高効率な業務用冷蔵庫への買替補助を行った実績があります。
また滋賀県では感染症対策の一環で、飲食店の換気設備工事費を補助した例もあります。2025年現在、インバウンド需要回復に合わせて大阪市では外国語メニューやハラール対応設備への補助、京都市ではバリアフリー改修補助など、観光客受入れ体制強化策も見られます。
自店の立地する自治体の施策を確認し、観光都市であればインバウンド・バリアフリー系の支援、郊外であればマイカー客向けの駐車場整備補助など、地域性に合った制度を探してみましょう。
補助金活用事例と2025年の最新トレンド
2025年時点での飲食業向け補助金制度の傾向として、前述のとおりDX対応、脱炭素対応、インバウンド・バリアフリー対応、人材支援がキーワードになっています。
いくつか具体的な事例やトレンドを紹介します。
DX・省力化の事例
大阪市内のあるラーメン店では、券売機導入と厨房オートメーション化により人手を減らしつつ売上を維持する計画を立て、省力化投資補助金で券売機代の2/3補助を受けました。その結果、ピーク時の注文対応がスムーズになり、スタッフの負担軽減と人件費圧縮に成功しています。
また、京都の和食店ではIT導入補助金を活用して予約管理をクラウド化し、予約漏れゼロとキャンセル減少を実現しました。
これらはデジタル技術で生産性を上げた好例です。
省エネ・脱炭素の事例
神戸市の居酒屋チェーンでは、古い冷蔵庫や空調を省エネ型に更新する設備投資を行い、これに兵庫県の中小企業向け省エネ補助金(国のエネルギー効率化補助金に上乗せする形)を活用しました。
結果として電気代を年間数十万円削減でき、SDGsに取り組む店としてPR効果も得ています。
厨房機器の高効率化や食品ロス削減(例:コンポスト導入)は環境省系の補助金対象にもなり得るので、環境志向の店舗づくりも経営戦略になります。
インバウンド・バリアフリー対応
大阪ミナミの飲食店街では、インバウンド需要回復に向け大阪府の多言語メニュー作成補助を利用し、英語・中国語・韓国語のメニューや看板を整備する店舗が増えています。
また奈良市では、高齢者や障がい者が利用しやすい店づくりへの改装補助があり、段差解消スロープ設置や車椅子対応テーブル導入で補助を受けたカフェもあります。
観光客や高齢層を取り込む施策は売上拡大につながりやすく、その初期費用を補助金でまかなえるのは大きなメリットです。
人材確保・賃上げの事例
京都のある老舗料亭では、人手不足解消のためアルバイト数名を正社員登用し、キャリアアップ助成金で1人あたり数十万円を受け取りました。
これにより従業員の定着率が上がり、人材育成に腰を据えて取り組めるようになったそうです。
また大阪府内のファミリーレストランでは、最低賃金の引上げに踏み切る代わりに業務改善助成金を活用して最新型食洗機を導入し、従業員の時短効果で生産性を向上させています。
人材への投資と機械化は二律背反ではなく、補助金を使えば両立できる好例と言えます。
まとめ:自社に合った支援策を戦略的に活用しよう
業種別に見てきた通り、中小企業向けの助成金・補助金は国の普遍的な制度から地域限定のユニークな施策まで非常に多岐にわたります。
IT業、小売業、建設業、飲食業それぞれで経営課題は違いますが、それに対応する形で支援メニューも用意されています。
大切なのは、自社の状況を客観的に分析し、「どの補助金を使えば課題解決に直結するか」を見極めることです。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら




















