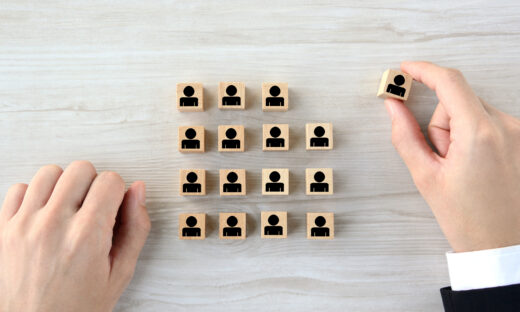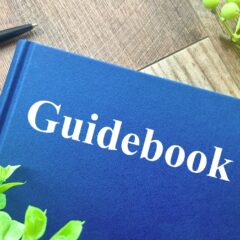はじめての助成金申請!通る事業計画書の書き方とポイントを解説

中小企業の創業初期段階では、事業拡大や設備投資のために公的な助成金(補助金)を活用する機会があります。
助成金は返済不要の資金援助であり、国や地方自治体の支援方針に合致した事業計画を提出すれば採択率が高まります。
本記事では、初めて助成金申請を行う経営者向けに、申請に必須の事業計画書の作り方と審査で評価されるポイントを詳しく解説します。
創業支援型や設備投資型の助成金を想定しつつ、特に大阪府・市で活用できる制度例にも触れ、事業計画書作成のヒントにして下さい。
目次
助成金・補助金の基礎知識
助成金や補助金は、創業期や設備投資における資金調達手段として非常に有効ですが、その違いや仕組みを正しく理解していないと申請時に戸惑うこともあります。
助成金とは何か?
助成金とは、国や地方自治体が中小企業等の事業活動を支援するために交付する返済不要の資金援助のこと。
特に創業支援や設備投資支援など、政策的な目的に沿った事業に対して支給されます。
助成金を受けるには、所定の申請書類(計画書や見積書など)を作成し、審査に通過する必要があります。
補助金との違い
助成金と補助金は混同されがちですが、一般的に補助金は事業の一部費用を補助する広義の制度を指し、助成金も同様に返済不要の支援金です。
補助金用の事業計画書では公共性や地域貢献度、事業の実現可能性が特に重視される点で、一般の融資向け計画書と異なります。
つまり、助成金・補助金申請用の計画書では「社会的意義や地域経済への貢献」と「事業の実行可能性」が審査で強く問われます。
助成金のメリット
助成金の最大のメリットは返済義務がないこと。
自己資金や金融機関融資と組み合わせて用いれば、創業・投資コストの大部分を公的資金でまかなえます。
ただし多くの場合、事業費の一部を補助する仕組みなので、自己資金や借入を含む資金計画が求められます。
審査では「十分な自己資金があるか」「金融機関からの融資内諾があるか」もチェック項目になるため、計画書には具体的な資金調達策を盛り込む必要があります。
申請時のポイント
助成金を申請する際は公募要領に沿った申請書類を準備し、期限を厳守することが重要です。
締切後は申請できないため、提出前に提出期限の再確認や必要書類の漏れ確認(登記簿謄本や財務資料など)のチェックを徹底しましょう。
また、助成金ごとに求められる証明書(例:創業支援等事業の受講証明など)がある場合もあるため、要件を事前に調べて備えておくことが必要です。
事業計画書の役割と基本構成
助成金申請の成否を左右する最も重要な書類が「事業計画書」です。
単なる申請用の資料ではなく、事業の構想や実行可能性を審査員に伝える“勝負の一枚”とも言える存在。
事業計画書の目的や基本構成、一般的な計画書との違い、見やすさや説得力を高めるための工夫など、申請に通る計画書づくりの土台となるポイントを簡潔に解説します。
申請における計画書の役割
助成金申請において事業計画書は最も重要な提出書類であり、事業の目的や意義、実行手順、収支計画などを審査員に伝える役割があります。
具体的には、「なぜその事業を行うのか」「どのように実現し利益を生むのか」「補助金を何に使うのか」を明確に示すことが必要です。
審査員は多くの計画書を比較するため、主旨がわかりやすく、説得力のある内容であることが採択率を左右します。
事業計画書に必要な項目と構成
助成金申請で提出する事業計画書には、一定の構成や内容が求められます。
審査員に事業の全体像と実行力を伝えるため、各項目を具体的かつ分かりやすく記載することが重要です。
●事業概要・目的:事業のコンセプト、理念、創業の背景
●製品・サービス内容:提供する商品・サービスの特徴や優位性
●市場・顧客分析:ターゲット市場の規模・成長性、顧客ニーズ、競合状況
●販売・マーケティング戦略:販売方法、販路、価格設定、プロモーション計画
●組織・体制:経営者やチームの経歴・役割、事業推進体制
●収支・財務計画:売上予測、費用計画、利益予測、キャッシュフロー
●資金計画:自己資金比率、借入計画、補助金の使途明細
●スケジュール:導入・施策実施のタイムライン
●リスク管理策:トラブル想定時の対応策など
一般的な事業計画書との違い
助成金・補助金申請用の計画書は、銀行融資や投資家向けの計画書とは重点が異なります。前者では特に公共性・社会的意義や実行可能性が重視されます。
具体的には、計画する事業が地域経済や産業にどのような好影響を与えるかを示す必要があります。
一方、投資家向けでは収益性や成長性が重視されますが、助成金用では社会への貢献度を明確に打ち出すことが採択への鍵となります。
目標設定のポイント
事業計画では、達成目標を数値・期限付きで具体化することが重要です。
例えば「3年後に売上高を○○万円に伸ばし、利益率を△△%に向上させる」といった具合です。
数字や時期が明確でないと、審査員は計画の成功イメージをつかめません。
一方で実現困難な過大目標は逆効果です。
市場規模や現実の販売能力など根拠を示し、無理のない範囲で目標を設定しましょう。
図表と見やすさ
グラフや表を活用すると、データや計画の内容を直感的に伝えられます。
例えば、市場規模や売上予測をグラフ化したり、投資金額と期待効果の表を掲載すると信頼性が増します。
また、専門用語や長文を避け、見出しや箇条書きで要点を整理すると、第三者が読みやすい計画書になります。
文章は明瞭で簡潔にし、ストーリー性をもたせて書くことが心掛けましょう。
創業支援型助成金向け計画書
創業支援型の助成金は、これから起業する人や創業後間もない事業者にとって貴重な資金源です。
しかし、その審査では「なぜこの事業を始めるのか」「どんな市場で勝負するのか」「どのように収益化するのか」といった点が重視されます。
事業概要・目的の明確化
創業支援型助成金では、なぜその事業を始めるのかという背景・目的を丁寧に説明します。例えば、自社代表の経験や事業を起こすきっかけなどを述べ、事業を通じて解決したい社会課題を提示します。
序盤で「地域○○で○○が不足している」という課題やビジョンを示し、審査員に共感と納得感を与えるストーリーを構築しましょう。
市場・顧客分析
ターゲット市場や顧客ニーズを具体的な数値で示し、自社の位置づけを明確にします。
例えば「国内市場規模は○○億円で年平均○%成長中」といったデータを示し、需要の裏付けを行います。
また競合他社の動向・シェアを分析し、「自社の強み(品質、価格、サービス等)でどこに差別化点があるか」をわかりやすく示すことが求められます。
事業内容・差別化のアピール
商品・サービスの特徴を具体的に説明し、他社にない強みをアピールします。
技術革新や独自ノウハウがあれば強調し、なぜそれが顧客価値を生むのかを論理的に述べます。
必要に応じて開発スケジュールや拠点計画、提携予定の仕入先・販路など、事業を実行する具体策を加えることで、計画の信頼性が増します。
収支計画・資金調達
売上・利益予測や資金使途は、具体的な数字で示すことが必須です。
例えば「1年目:売上○○万円、利益△△万円」など、年度別に数値を明記すると説得力が増します。
設備投資や広告費などの費用項目も詳細に記載し、利益率や収支の見込みを明確にしておきます。
資金調達計画では、自己資金・融資・補助金の割合を示しましょう。
例として「補助金40%、銀行融資40%、自己資金20%」のように内訳を提示すると、資金計画の現実性が伝わります。
創業メンバーの強み
創業チームや経営者の経歴・専門性も計画書に含め、事業遂行能力をアピールします。
チーム内での役割分担や、技術的・営業的な実績があれば明記しましょう。
たとえば「代表は業界10年の経験があり、自社販売チャネルを持つ」「技術担当は○○の特許を保有」といった具体例があると、審査員の安心感につながります。
専門家やメンターとの連携体制があれば、その点も盛り込むと良いでしょう。
設備投資型助成金向け計画書
生産性の向上や業務効率化、新たな商品・サービスの提供などを目的とした設備投資には、多くの助成金制度が用意されています。
こうした助成金を活用するためには、設備導入の必要性と具体的な効果を、事業計画書でしっかりと示すことが求められます。
設備投資型助成金の申請に適した計画書の構成や、審査で評価されやすいポイントについて解説します。
導入効果を数値で示す方法や、資金・スケジュール計画の立て方もあわせて紹介します。
設備投資の必要性と効果
設備投資型では、なぜ設備が必要なのかを明確に示します。
旧来の生産方式や欠陥が事業の阻害要因になっている場合、それを課題として提示し、新設備導入で解決策を提示します(例:省エネ機器の導入でCO₂削減を実現)。
設備投資による効果として、増産・品質向上・コスト削減などがどう生まれるかを論理的に説明し、売上や利益の具体的な増加見込みまでつなげて書くことが重要です。
具体的な設備内容・コスト
導入する設備の種類、仕様、数量、導入予定の時期など、具体的に記載します。
また、各設備の導入費用や維持費、導入に伴う外注費(工事費など)も明示し、総額見積もりを示します。
見積りは見積書やカタログを根拠資料として添付すると説得力が増します。
さらに、設備設置までのステップ(ベンダー選定、レイアウト変更、試運転など)をタイムライン形式で示すと、計画の実行性が伝わりやすくなります。
投資効果の予測
投資後に得られる事業成果を数値で説明します。
例えば「新設備導入で生産量が20%増加し、その結果として年間売上が○○万円増加見込み」といった試算を示します。
売上増や原価低減効果の根拠には市場価格や生産ライン稼働率のデータを用いると信頼性が高まります。
投資回収期間(ROI)の見込みも示せれば、計画の経済合理性を証明する材料になります。
資金計画
先述の通り、助成金は事業費の一部補助です。自己資金や金融機関借入を含めた資金計画を具体化します。
自己資金の投入額と借入額(希望額)を明示し、審査で問われる「自己資金の拠出状況」や「借入見込」が判断できるようにしましょう。
また、補助金交付までの資金繰りに不足が出ないかシミュレーションし、不足時の対策(追加借入やリース利用など)も併せて記載します。
スケジュールとリスク管理
設備導入から稼働開始までのスケジュールは詳細に記載します。
例えば「4~6月:調達・準備、7~9月:導入・試運転、10月:本稼働開始」といったマイルストーン表を示すと、実効性のイメージが伝わります。
同時に、工事遅延や経済変動などのリスクシナリオについても触れ、対策を明記すると安心感が増します。
採択率を高める計画書のポイント
せっかく事業計画書を作成しても、審査で評価されなければ助成金は採択されません。
審査員が何を重視しているかを理解し、計画書にその視点を反映させることが、採択率アップのカギ。
審査基準への対応方法や数値目標の立て方、根拠の示し方など、計画書の説得力を高めるための具体的なテクニックを紹介します。
採択される事業計画書に共通する特徴を押さえ、より効果的な申請につなげましょう。
審査項目と加点要素の確認
まず公募要領に記載された審査項目や加点対象を必ず確認しましょう。ものづくり補助金の場合、技術面・事業化面・政策面などが挙げられています。
例えば「開発する製品の革新性」「具体的な事業化スケジュールと市場性」「地域経済への貢献」といった項目です。
これらを文中で網羅する形で計画書を組み立てることが採択への第一歩です。
また、政府は採択企業に対し「革新性・成長性・社会的意義・財務的安定性」を重視する傾向を示しています。
つまり国の政策目標(DX推進、環境対応、地域活性化など)に自社計画がどのように貢献するかをストーリー立てて示せば、高評価につながります。
数値目標と具体策を明確に
事業目標は数値と期限付きで具体化し、それを達成する手段(アクションプラン)を明確に示しましょう。
売上高や利益率、CO₂削減量などの数値目標があると、審査員に事業成功後のイメージを掴ませやすくなります。
数値は楽観的すぎない根拠あるものにし、根拠(市場調査や過去実績)を明示すると信頼性が増します。
データ・根拠の活用
計画書には客観的データや根拠資料を積極的に盛り込み、裏付けを強化しましょう。
政府統計や業界レポートから数値を引用し、グラフ化して示すと説得力が高まります。
市場規模や顧客ニーズ、機器の性能比較表などは、文字情報だけよりも視覚的に訴える効果があります。
また、過去の実績や自社データを活用して算出した収益シミュレーションを載せることも重要です。
政策・地域貢献との一致
前述の通り、政策目標との連携性をアピールしましょう。
計画書中に「この事業は○○分野の目標達成に資する」と明示すれば、審査員の納得感が高まります。
例えば「地域の人口減少対策」「脱炭素化推進」など、応募する助成金の目的に合ったキーワードを計画の説明中に散りばめると効果的です。
専門家・第三者の活用
事業計画書の完成度を高めるため、第三者の視点を取り入れましょう。
経験豊富なコンサルタントや行政機関にレビューを依頼したり、地域の事業計画コンテストで審査員の意見をもらったりするのも有効です。
客観的なアドバイスを受けることで抜けや誤りを減らし、より説得力のある計画書に仕上げられます。
大阪で活用できる創業支援制度・事例
大阪では、創業支援や設備導入を後押しする独自の助成制度やサポートが豊富に整っています。
ここでは、大阪府・市の制度や支援機関の活用事例、創業者が実際に得られるメリットを具体的にご紹介します。
大阪市の特定創業支援等事業
大阪市には「特定創業支援等事業」と呼ばれる創業支援制度があり、創業準備者や創業5年未満の企業向けにセミナーや専門家派遣、個別相談などを提供しています。
この支援を受けて証明書を取得すると、会社設立時の登録免許税軽減や信用保証枠の拡大などの優遇措置が得られます。
助成金申請には直接関係しないものの、創業コスト削減や資金調達で有利になるため、活用検討をお勧めします。
大阪府の補助金例:起業家グローイングアップ補助金
大阪府が実施する「大阪起業家グローイングアップ補助金」は、大阪府内で創業・創業予定の起業家を支援するものです。
対象となるのは、府内のビジネスプランコンテストで優秀な成績を収めた起業家などで、補助金は補助対象経費の1/2以内(上限100万円または50万円)で支給されます。
創業関連の補助金は多岐にわたるため、計画に合う制度を調べてみると良いでしょう。
大阪商工会議所の持続化補助金(創業型)
大阪商工会議所が管轄する「小規模事業者持続化補助金<創業型>」では、認定市区町村の創業支援を受けた創業3年以内の小規模事業者が対象です。
補助率は2/3で、補助上限は200万円(免税→課税事業者になった場合は50万円上乗せ)です。
対象経費の例には、HP制作、店舗改装、展示会出展、機械・機器の購入などがあり、設備投資にも活用できます。
このような補助金は全国共通ですが、大阪商工会議所など地元機関が説明会や計画書添削を行っていることもあります。
支援窓口・相談機関
大阪府内には、産業創造館(サンソウカン)や商工会議所など公的相談機関があり、創業時の計画書作成相談に対応しています。
例えば大阪産業創造館の経営相談室では創業融資・補助金申請用の事業計画書作成を支援しています。
地元自治体や商工会議所の創業セミナーにも積極的に参加し、制度の最新情報や他社事例を収集しましょう。
他地域の参考情報
本記事は全国向けですが、類似の創業支援制度は都道府県・市町村ごとに実施されています。他地域での創業・補助金事業計画書作成の事例(例えば東京都や他府県の制度案内)を参考に、自社の計画に活かすのも有効です。
まとめ:事業計画書は経営の羅針盤
採択される事業計画書を作成するには、公募要領に沿った構成と根拠ある数値、政策目標への合致、説得力のあるストーリー展開が不可欠です。
上記のポイントを押さえ、専門家の助言も得ながら練り上げた計画書を提出すれば、助成金獲得の可能性は大きく高まります。
なお、計画書は一度作成すれば終わりではなく、事業運営の指南書としてその後も活用できます。
助成金をきっかけに事業を確実に進め、長期的な経営計画としても磨き上げていきましょう。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら