開業1年目法人のための創業期助成金ガイド(大阪府の制度も詳しく解説)
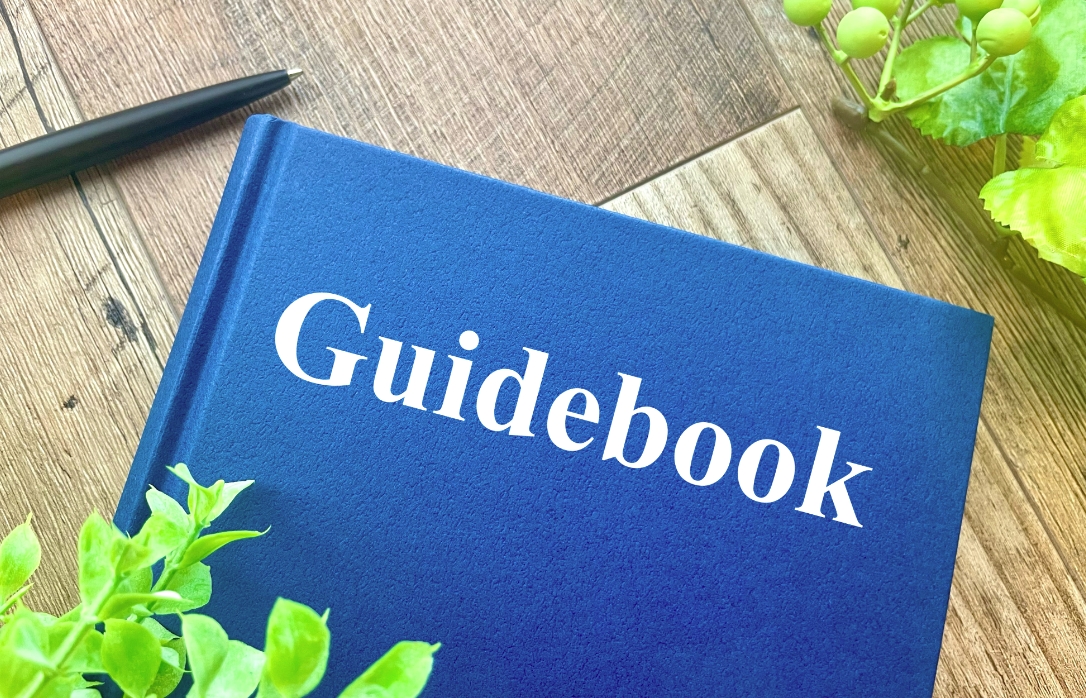
創業間もない法人経営者にとって、返済不要の助成金・補助金は事業スタートを強力に後押しする資金調達手段です。
国や自治体、支援機関が提供する様々な制度があり、設備投資や販路開拓、人材採用など創業初期の課題に対応した資金支援を受けられます。
特に大阪府では独自の創業支援策が充実しており、全国共通の制度に加えて大阪ならではの助成金も活用可能です。
この記事では、国の助成金制度、大阪府および自治体の創業支援制度、商工会・支援機関による支援制度に分けて、各制度の概要・条件・支給額・申請方法・注意点・活用事例を詳しく解説します。
公式サイトのリンクや問い合わせ先も適宜紹介し、読者の皆様が実際に制度を活用できるよう信頼性の高い情報をお届けします。
最後に、創業初期に助成金を活用するメリットと上手な制度活用のポイントもまとめますので、ぜひ参考にしてください。

目次
国の創業期向け主要補助金・助成金制度
創業直後の法人が活用できる国の主な補助金・助成金には、中小企業庁や厚生労働省が所管する事業拡大支援策と人材支援策があります。
ここでは設備投資や販路開拓を支援する補助金と、雇用創出を支援する助成金に分け、代表的な制度をご紹介します。
申請には事業計画の策定や一定の要件充足が必要ですが、採択されれば創業期の資金負担軽減につながります。
それぞれ概要とポイントを見ていきましょう。

小規模事業者持続化補助金【販路開拓支援】
「小規模事業者持続化補助金」は、全国の小規模企業や個人事業主が対象で、販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する国の補助金です。
例えばチラシ作成、ウェブサイト制作、店舗改装、新商品開発等にかかる経費の2/3が補助されます(通常枠上限50万円)。
申請には商工会議所・商工会の助言を受けながら経営計画書(事業計画)を作成する必要があり、計画に沿った販路開拓活動が求められます。
2024年度からは、一定の要件を満たす特別枠も用意されており、中でも「創業枠」に該当すれば補助上限が200万円に拡大されます。
創業枠の適用条件として、過去3年以内に自治体等が実施する特定創業支援事業の支援を受けて創業したことが挙げられます(詳細は後述)。補助金は基本的に後払い(精算払い)で交付されるため、いったん事業者が全額立て替える必要がありますが、採択されれば販促費用の大部分を公的資金でまかなえるため、創業期の販路拡大に非常に心強い制度です。
【申請条件・支給額】
資本金や従業員数が中小企業庁の定める「小規模事業者」範囲内である法人が対象です。通常枠の補助率は経費の2/3(上限50万円)ですが、賃上げ・後継者育成・創業等の特別枠適用時は上限100万~200万円に拡充されます。
例えば創業1年目で特定創業支援を受けている場合は創業枠200万円(補助率3/4)での申請が可能です。
採択率は毎回おおむね50~60%台と言われ、比較的チャレンジしやすい補助金とされています。
【申請の流れ】
日本商工会議所等が公募窓口を担い、年数回の公募期間内に経営計画書・支出明細等を提出して申請します。
地元の商工会議所で事前に相談し書類に支援機関の確認印をもらう手続きが求められます。
審査に通れば交付決定通知が出て事業実施→実績報告後に補助金が支払われます(不採択の場合もあり)。
書類準備に時間がかかるため早めの着手が重要です。
【注意点】
補助対象経費や細かな条件は年度ごとの公募要領で変更があるため、最新の公式要領の確認が必須です。
また補助金は使い道が限定され、交付決定前に発生した経費は対象外になる点にも注意しましょう。
「持続化」の名の通り、補助事業終了後も事業を継続する意思が求められ、補助金受給後すぐ廃業した場合など不適切な利用は認められません。
【活用事例】
美容室を開業したAさんは持続化補助金(創業枠)に採択され、自己資金700万円に補助金200万円を加えて計900万円の開業資金を確保しました。
補助金でシャンプー台やHP制作費をまかない、予算超過することなく店舗オープンに漕ぎつけた例があります。
このように創業初期の資金不足を補いながら、計画的な販路開拓投資に踏み切れる点が持続化補助金のメリットです。

ものづくり補助金【設備投資・革新支援】
「ものづくり補助金」(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業の設備投資や新事業展開を支援する大規模な補助金制度です。
製造業のみならず幅広い業種の中小企業が対象で、生産プロセスの効率化、製品開発、サービス創出等につながる設備導入や試作品開発費などを補助します。
補助率は原則2/3、補助上限額は企業規模や枠により750万円から最大4,000万円超と高額です。
ただし交付を受けるには、付加価値額の向上や従業員給与総額の増加など複数の成果目標を盛り込んだ事業計画の策定・実行が求められます。
審査も競争的で、革新的な取り組みであることを示す必要があります。
【申請条件・支給額】
中小企業基本法の定義に合致する中小企業であること。
採択枠がいくつかあり、小規模型の設備投資なら上限750万円、企業成長に資する大きな設備投資では上限3,000万~4,000万円といった幅があります。
例えば従業員20名以下の企業が高度なIoT機器を導入するケースでは最大2,500万円まで補助対象になる枠もあります。
【申請の流れ】
中小企業庁の委託事務局(電子申請システムJグランツ等)を通じて申請します。
事業計画書には事業概要・市場性・収益性・投資効果(付加価値向上や給与増加見込み)など詳細な記載が必要です。
外部有識者による書面審査ののち採択企業が決定します。採択後は交付申請→事業実施→報告・検査を経て補助金が支払われます。
資金需要が大きいため、つなぎ融資で一時立替資金を確保しておくと安心です。
【注意点】
採択率は回によって異なりますがおおむね3~5割程度といわれ、要求される書類水準も高いため専門家(中小企業診断士や支援機関)の助言を得ながら準備すると良いでしょう。また、補助対象とならない経費も細かく定められている(汎用品や汎用ソフトウェアは不可等)ため、公募要領を熟読し計画段階から要件に合うよう留意が必要です。
交付後一定期間は設備の処分や用途変更に制限があり、報告義務も続きます。
大きな資金が得られる分、事務負担や遵守事項も多い点を認識しておきましょう。
【活用事例】
大阪府内のある飲食店C社はコロナ禍で売上が落ち込んだ際、自社料理の冷凍食品オンライン販売に活路を見出し、ものづくり補助金を申請しました。
採択により補助金で業務用急速冷凍機を導入し、新たな冷凍食品事業を立ち上げることができました。
このように、環境変化に対応した事業転換や設備導入にも補助金を活用することで、創業間もない企業が新規事業へ踏み出すリスクを抑えることができます。

IT導入補助金【業務効率化支援】
「IT導入補助金」は、中小企業が業務効率化や生産性向上のためにITツールを導入する際に利用できる補助金です。
会計ソフトや顧客管理システム、予約・決済アプリ、ECサイト構築など様々なITツール導入費用の一部を国が補助します。
IT化によるデジタル化・自動化を進め、生産性向上や働き方改革、ひいては賃金アップにつなげることが期待されています。
補助率は1/2もしくは2/3、補助上限額は類型によって数十万円から数百万円規模です。
比較的小規模な投資でも申請しやすい制度で、創業時に業務基盤を整える際に有用です。
【申請条件・支給額】
認定されたITツール(IT導入補助金の公式サイト上のツール一覧に掲載)をIT導入支援事業者の支援のもとで導入することが条件です。
自社独自開発ではなく、登録されたパッケージソフトやクラウドサービス等が対象になります。
補助枠は「デジタル化基盤導入枠」等いくつかに分かれ、例えば会計ソフト・POSレジ等の導入なら上限50万円(補助率3/4~2/3)、より高度なシステム導入は上限350万円(補助率1/2)といった設定です。
ハードウェア(PC・タブレット等)の購入費用も一部含められる枠もあります。
創業まもない企業でも要件を満たせば申請可能で、多くの業種で利用されています。
【申請の流れ】
まずIT導入補助金事務局サイトで希望のITツールと支援事業者を選定し、見積もり等を取得します。
事業者と相談しながら補助事業計画を作成し、オンライン申請を行います。審査は書面審査のみで比較的結果も早く判明します。
採択後に対象ITツールを購入・導入し、実績報告を経て補助金が支払われます。
年度内に複数回公募があり、創業初年度からでもタイミングが合えば利用しやすいでしょう。
【注意点】
希望するITツールが補助金の登録対象であるか事前に確認する必要があります(全てのソフトウェアが対象ではない)。
また、ITツール導入によってどのように業務効率・売上が向上するかを計画書で示す必要があります。
導入後に事業効果報告(売上や業務時間の変化など)を一定期間行う義務もあります。
なお申請や実績報告は全てシステム上で行うため、電子申請の操作に不慣れな場合はIT導入支援事業者のサポートを受けながら進めると良いでしょう。
公式サイトには操作ガイドやQ&Aも充実しています。

中小企業新事業進出補助金【新市場チャレンジ支援】
「中小企業新事業進出補助金」は、2025年創設の新規事業進出支援のための国の補助金制度です。
既存事業とは異なる新市場での高付加価値事業に挑戦する中小企業を対象に、必要な設備投資等の費用を補助します。
ポストコロナ時代の成長産業への転換や、多角化による企業成長を後押しするのが目的です。
補助率は2/3以内、補助上限額は従業員規模に応じ2,500万円~7,000万円超と大型で、ものづくり補助金にも匹敵する支援規模。
創業から間もない企業であっても、将来の成長を見据えて新規事業に乗り出す場合に活用が期待できます。
【申請条件・支給額】
中小企業基本法における中小企業等で、新事業進出の計画が明確であることが条件です。具体的には「3~5年で付加価値額年率+4%以上」の成長目標を掲げた事業計画を策定する必要があります。
補助上限額は企業規模により異なり、例えば従業員20人以下の小規模企業では上限2,500万円(一定の要件下で3,000万円)、21~50人規模では4,000万円(特例5,000万円)とされています。
資金使途も設備投資のほか人材育成費や広報費まで幅広く認められる見込みです。
【申請の流れ】
経済産業省系の外郭団体である中小企業基盤整備機構などが窓口。
事業計画には新規性や成長可能性、市場ニーズをしっかり盛り込む必要があり、専門家支援を受けることも検討しましょう。
採択後のフロー(交付申請・実績報告等)は他の補助金と同様ですが、補助額が大きい分、事前着手禁止期間や完了後の事業化報告など厳格な運用となる可能性があります。
2025年創設の制度ですので最新情報は中小企業庁やミラサポplusの公式発表を確認してください。
【注意点】
新設制度のため詳細な要件は公募要領で確認する必要があります。
既存事業と明確に異なる新事業であること、かつ高い成長目標を掲げることがポイントで、単なる業容拡大では採択は難しいと予想されます。
創業間もない企業がチャレンジする場合は、自社の経営リソースとのバランスも考慮し、無理のない計画を立てることが肝要。
採択後は計画達成に向けたフォローアップも入る可能性があるため、覚悟を持って取り組みましょう。
その他の国の創業期支援策(事業再構築補助金・事業承継補助金など)
上記以外にも、創業初期に関係し得る国の補助金・助成制度があります。代表的なものをいくつか挙げます。

事業再構築補助金
コロナ禍で売上が減少した中小企業の思い切った事業転換を支援する補助金。
ポストコロナの成長分野への業態転換等に使え、補助上限は最大1.5億円(中小企業の場合)と極めて大きいですが、創業1年目企業の場合は直近決算等の実績が乏しく、またコロナ以前との売上比較要件を満たしにくいため、本補助金の恩恵を受けられるケースは限定的です。
ただし例外的に、「創業枠」が設けられた公募回もあり、要件緩和措置がある場合は検討の余地があります。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継を契機に新たな取組を行う中小企業を支援する補助金。
創業というより既存企業の第二創業支援策ですが、「会社を買って起業」するケース(他社の事業を引き継いで自ら代表となる)では創業と同様の意味を持ちます。
この場合、後継者が設備投資や新商品開発を行う費用を最大2000万円まで補助。
創業1年目でもM&A型創業なら活用可能です。
中小企業省力化投資補助金
2023年度補正で創設された中小企業向けの生産性向上・省力化投資支援策です。
設備のカタログ注文型等ユニークな類型もあり、小規模事業者の省力化投資に幅広く使えます。
補助率は原則1/2、上限は類型によりますが数百万円規模です。
創業間もない企業でも、人手不足解消や効率化を目的とした設備導入時に検討できます。
各都道府県に選定された実行団体が公募・支給を行っており、大阪府も対象地域に含まれます。
例えば地方にUIターンして社会的事業を起こすようなケースが典型で、地域活性化を伴う創業なら狙える助成金です。
大阪府内でも過疎地域等で起業する場合は地域要件に合致すれば利用可能な場合があります。
以上のように国レベルでは多様な補助金が用意されています。自社の状況に応じて、活用できるものがないか常にアンテナを張って情報収集しましょう。
中小企業庁のミラサポPlusやJ-Net21といった公式サイトでは最新の公募情報をまとめています。
大阪府および自治体の創業支援助成金制度
大阪府は全国でも創業支援に積極的な地域で、府および府内各市町村が多彩な独自助成制度を設けています。
ここでは大阪府が提供する代表的な補助金と、大阪府内の主要自治体による創業支援策を紹介します。
自治体の制度は地域特性や産業分野に応じて様々ですが、大阪で創業する場合はぜひ地元の補助金も併せて検討しましょう。
公式サイトや窓口情報も案内しますので、有効にご活用ください。

大阪起業家グローイングアップ補助金(大阪府)
「大阪起業家グローイングアップ補助金」は、大阪府が将来の大阪経済を担う起業家を発掘・支援するために設けたビジネスプランコンテスト連動型の補助金制度です。
大阪産業局が事務局となり年数回開催するビジネスプランコンテスト「ドリームDASH!」において優秀な成績を収めた起業家に対し、創業または新事業立ち上げに必要な経費の一部を助成します。
優勝者には最大100万円、準優勝者には最大50万円が交付され、受賞後1年間にわたり補助対象経費の1/2以内が支給されます。
この補助金の特徴は、コンテストでのブラッシュアップ支援と資金支援がセットになっている点で、単にお金を給付するだけでなくメンタリング等の成長支援も受けられることです。
大阪府内で起業予定の方、または既に府内で事業を営む創業5年未満の方が対象となります。
【申請条件・対象経費】
補助金交付対象者はビジネスプランコンテストの優勝・準優勝者に限られます。
コンテスト応募資格としては、大阪府内に主たる事業所を置く中小企業者または府内で起業予定の個人であることが要件です。
補助対象経費は「創業や新事業の展開に要する経費」と定義されており、具体的には事業計画の実現に必要な設備費・開発費・販路開拓費等が含まれます。
補助率は1/2、年度あたり補助限度額は100万円または50万円(受賞区分による)で、交付期間は最大1年間です。
なお未創業の場合は交付決定日から1年以内に創業することが条件とされています。
【申請の流れ】
まず大阪産業局等が募集する「大阪起業家グローイングアップ・ビジネスプランコンテスト」にエントリーし、書類・プレゼン審査を経て優秀提案者に選ばれる必要があります。受賞後、所定の補助金交付申請書を提出し交付決定を受けます。
その後は事業計画に沿って事業を実施し、実績報告を提出することで補助金が支払われます。
コンテストへの応募から含めると長期戦になりますが、エコシステム内での人脈形成や専門家ハンズオン支援も得られるため、単なる資金以上の価値があります。
詳細は大阪府商工労働部スタートアップ支援課または大阪産業局の公式サイトをご確認ください。
【注意点】
補助対象となるにはコンテストで入賞しなければならないため、ハードルは高めです。事前に事業計画を磨き上げ、プレゼンテーション能力も含め準備しましょう。
また補助金の交付要綱に基づき、経費の使途報告や証憑の提出など求められるため、事務処理も確実に行う必要があります。
万一途中で事業を断念した場合、補助金が打ち切られるか返還義務が生じる可能性もあります。
いわば「コンテストで勝ち抜いた者だけが得られるご褒美」的な助成金ですが、その分採択後のフォロー体制も整っており、有望な起業家にとってはチャレンジする価値の大きい制度です。
エネルギー産業創出促進事業補助金(大阪府)
大阪府は成長分野であるエネルギー産業の育成にも注力しており、「エネルギー産業創出促進事業補助金」という独自の補助制度を設けています。
この補助金は、水素エネルギーや蓄電池など新エネルギー分野における事業化の可能性調査や研究開発に要する経費を支援するもので、府内企業が新たにエネルギー関連ビジネスを立ち上げる際の調査検討費を補助します。
補助率は1/2、補助上限額は300万円で、予算の範囲内で複数案件が採択されます。
創業初期であってもエネルギー産業に参入する場合は心強い助成となります。
【申請条件・支給額】
大阪府内に本店または主たる事業所を有する中小企業等で、新エネルギー産業分野の事業化調査を行う者が対象です。
公募要領で対象分野(例:水素利用、蓄電技術、新エネルギー供給システム等)が示されており、そのテーマに合致した取り組みであることが求められます。
補助金額は上限300万円、補助率1/2で、例えば600万円の調査費用に対し最大300万円の補助が受けられます。
採択件数に限りがあるため、事業の新規性・公益性などが審査されます。
【申請の流れ】
毎年度1回程度、公募期間が設定されます。
大阪府の産業振興関連部署(エネルギー分野担当)にて要綱が公表され、所定の申請書類(事業計画書、経費明細、企業概要等)を提出します。
学識経験者等で構成される審査会にて書面審査が行われ、採択プロジェクトが決定されます。
交付決定後に事業着手し、年度末までに調査研究を完了、実績報告を経て補助金額確定となる流れです。
専門性の高い分野ゆえに計画書でも技術内容や将来性を的確に伝える必要があります。
【注意点】
エネルギー産業分野に特化した補助金であるため、対象となる事業領域が限定されています。
自社の事業が該当分野に当たるか、公募要領で詳細を確認してください。
また研究開発要素が強い支援なので、成果がすぐ事業収益に直結しないケースもあります。補助金終了後も事業化に向けたフォローアップを大阪府が実施する場合があります。
専門用語が飛び交う世界ですが、申請書は第三者にも分かる平易な記述を心がけましょう。問い合わせ先は大阪府の成長産業振興室などとなっているので、応募検討段階で積極的に相談するのがおすすめです。
豊中市チャレンジ事業補助金(豊中市)
大阪府内の各自治体も独自の創業支援策を展開しています。
例えば豊中市の「チャレンジ事業補助金」は、市内で新たに創業する事業や創業後間もない事業の立ち上げ・拡大に必要な経費を支援する制度です。
補助率は経費の2/3と手厚く、補助上限額はなんと150万円と市町村レベルでは高額な部類に入ります。
対象経費には創業時の各種経費(店舗等の賃借料、設備費、広告宣伝費など)が幅広く含まれ、創業直後の資金負担軽減に役立ちます。
豊中市は大阪都市圏の一部で競争環境も厳しい中、思い切った補助額で起業家を後押ししています。
【申請条件・支給額】
豊中市内で令和5年度以降に創業した、または新事業を開始した中小企業者等が対象です。応募時点で創業から概ね5年未満であることなど条件があります(詳細は豊中市産業振興課の募集要項を参照)。
補助額は上限150万円、補助率2/3で、市予算の範囲内で採択件数が決まります。
例えば創業時に総額225万円の経費がかかった場合、その2/3である150万円の補助を受けられる計算です。
なお人件費や汎用性の高い備品など一部対象外経費も設定されています。
【申請の流れ】
毎年1回程度公募が行われ、所定の申請書(事業計画書、収支計画、経費明細等)と必要書類を豊中市へ提出します。
審査は書面および必要に応じ面談で行われ、予算の範囲で交付対象者が選定されます。
採択後、交付決定通知に従い事業を実施し、完了後に実績報告書を提出して補助金額の確定・支払いとなります。
審査では地域経済への波及効果や事業の継続性などが重視されるため、事業計画書で熱意と実現可能性を示すことが大切です。
【注意点】
本補助金は市内定着を促す狙いがあるため、一定期間豊中市内で事業を継続する意思が求められます。
補助金受給後すぐに市外へ転出・移転した場合は返還を求められる可能性もあります。
また交付対象とならなかった経費(例:創業者自身の人件費など)は全額自己負担となるため、申請時に何が補助対象かを明確にしておきましょう。
採択件数には限りがあるため、予算オーバーの場合は減額交付や不採択も起こりえます。市の広報やHPで公募情報が出ますので見逃さないようにしてください。
空き店舗活用・家賃補助等の地域支援策(大阪府内各市町村)
大阪府内の多くの市町村では、商店街の活性化や創業支援を目的とした空き店舗活用補助金や賃借料補助などユニークな制度も用意されています。
例えば岸和田市の「がんばる岸和田企業経営支援補助金(創業・起業区分)」では、新規創業や販路開拓に必要な経費の1/2、上限10万円が補助されます。
金額は小さいものの創業時の広告費等に使えるでしょう。また泉大津市では「創業時設備導入支援事業補助金」により設備購入費を1/2・上限20万円補助、併せて「創業支援事業補助金」で店舗等賃借料を月額5万円・最大6ヶ月補助するといった手厚い支援があります。
さらに富田林市や東大阪市では空き店舗への出店費用を一部補助する制度があり、改装費や家賃の補助が受けられます。
これら地域密着型の補助金は、地元商工会議所や市役所の産業振興課が窓口となっていることが多いです。
地域によって名称や内容が異なるため、創業予定地・所在地の自治体HPを確認し、自社が使える制度がないか調べてみましょう。大阪府内だけでも20以上の市町村で独自の創業支援補助金が確認できます。
例えば上記のほか、高槻市「魅力あるお店応援プロジェクト」(新規出店改装費補助 最大50万円)、阪南市「起業創業支援バウチャー補助金」(創業準備に使えるクーポン的補助)など多彩です。
自治体の補助金は公募時期・予算額が限られるため、タイミングと情報収集が勝負です。地域の商工会議所・商工会や大阪産業局の運営するスタートアップ支援サイト「スタートアップ支援マップ大阪」なども活用して、地元の制度をもれなくチェックしましょう。
【活用事例】
大阪市内の繁華街で創業した飲食店では、物件取得費用の負担軽減のために大阪市商店街空き店舗活用事業補助金を利用し、店舗改装費の一部について50万円の補助を受けました。さらに別の事例では、泉佐野市にUターン創業した起業家が、市の創業支援補助金によりコワーキングスペース利用料の補助を受けつつ事業を軌道に乗せています。
このように少額でも地元の補助金を組み合わせることで初期コストを下げ、地域コミュニティの支援を得ながら創業できたケースが多々報告されています。
創業者にとって自治体とのつながりは信用力向上にもつながるため、ぜひ居住地・開業地の制度を有効に活用しましょう。

商工会・中小企業支援機関による創業支援制度
国や自治体の助成金のほかに、商工会議所・商工会や中小企業支援機関が提供する創業支援制度も見逃せません。
資金給付ではなく相談支援や認定制度、金融支援が中心ですが、これらを活用することで結果的に助成金の活用要件を満たしたり、創業をスムーズに進めたりできるメリットがあります。
創業期にぜひ知っておきたい支援制度をいくつか紹介します。
特定創業支援等事業(創業支援計画に基づく支援制度)
「特定創業支援等事業」とは、各自治体が国の産業競争力強化法に基づき策定した創業支援事業計画に沿って実施する、創業希望者向けの継続的支援プログラムです。
一般に、自治体やその委託を受けた商工会議所等が主催する創業スクール・創業セミナー、個別相談などがこれに該当します。
一定の要件(例:1か月以上にわたり計4回以上の講義や相談を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得)を満たすと自治体から「特定創業支援を受けたことの証明書」が発行されます。
この証明書を取得することで、登録免許税の軽減(株式会社設立時の登録免許税が通常資本金の0.7%→0.35%に半減)、信用保証枠の拡充(信用保証協会の創業関連保証の対象拡大・上限引き上げ)等のメリットが得られます。
さらに前述の持続化補助金の創業枠に応募する際の要件にもなるなど、各種優遇制度へのパスポートとなります。
特定創業支援事業は全国各地の自治体で展開されており、大阪市をはじめ府内多数の市町村でも創業セミナーや創業相談窓口の形で実施されています。
例えば大阪市では創業スクール受講者に証明書を発行しており、この証明書を持って会社設立すると登録免許税が軽減されます。また茨木市や八尾市などでも同様のセミナーを開催し証明書発行を行っています。
証明書の発行申請方法は各自治体の担当課に必要書類を提出する形です(受講修了後に申請)。
創業前に取得しておけば後々役立つ場面が多いので、時間が許せば受講を検討しましょう。証明書の有効期限は発行からおおむね1年間程度です。
商工会議所・商工会の創業支援サービス
各地の商工会議所や商工会では、創業者向けの相談サービスや会員向け特典など様々な支援を行っています。
とりわけ重要なのが補助金申請のサポートです。
先述の小規模事業者持続化補助金では商工会議所等が相談窓口かつ申請書類確認機関となっており、会員でなくても経営相談や計画書の書き方指導を受けることができます。
創業時は何かとわからないことだらけですが、商工会議所の窓口では資金調達、補助金、公的融資、創業計画作りなど幅広い相談に応じてもらえます。
大阪商工会議所でも「OSAKAビジネスサポートデスク」を設置し創業希望者の相談を無料で受け付けています。
また商工会議所が独自に創業助成事業を行うケースもあります。
例えば大阪府忠岡町では商工会等の主催でビジネスプランコンテストを開催し、優秀者に町の創業支援補助金(最大50万円)を授与する取り組みがあります。
このように地域の商工団体が中心となり、創業者に小口の支援金やビジネスマッチング機会を提供する例も増えています。
商工会議所への入会メリットとしては、各種専門家紹介制度、会員交流会での人脈構築、共済制度や会報誌による情報入手なども挙げられます。
年会費は企業規模によりますが創業時は減免制度を設ける所もありますので、地元の商工会議所・商工会への加入も前向きに検討しましょう。
中小企業支援センター・よろず支援拠点の活用
国や自治体が設置する中小企業支援センターやよろず支援拠点も創業期には非常に頼りになる存在です。
大阪府では「大阪産業局(大阪産業振興機構)」が中小企業支援の中核を担い、創業希望者向けに一歩踏み込んだ支援を提供しています。
具体的には、「経営革新等支援機関」の資格を持つ専門相談員による無料相談や、創業セミナーの開催、補助金情報の提供、創業者同士の交流イベントなどです。
支援センターでは事業計画のブラッシュアップから補助金の選び方まで包括的にアドバイスしてもらえます。
また、各都道府県に1か所以上設置されているよろず支援拠点(大阪府では大阪城近くに設置)は、国が委嘱したコーディネーターが経営全般の悩みに無料で対応する相談所です。創業間もない時期は、補助金以外にも資金繰り・集客・人材など課題が山積しますが、よろず支援拠点ではそれらを整理し適切な専門機関につないでくれます。
よろず拠点の利用は何度でも無料で、秘密厳守ですので気軽に相談できます。
例えば補助金申請書のチェックや、融資のための事業計画作成支援など具体的なサポートを受けられた事例もあります。
自社だけで悩まず、公的支援機関をフル活用することが成功への近道です。
日本政策金融公庫の創業融資制度(参考)
※助成金ではありませんが、創業期の資金調達手段として重要なため参考に記載します。
政府系金融機関の日本政策金融公庫(日本公庫)は、新規開業資金の融資制度を充実させています。
日本公庫の「新創業融資制度」は無担保・無保証人で最大3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで借入可能で、創業前後の企業が利用できます。
創業計画書を提出して審査を受け、事業の将来性が評価されれば無担保で資金調達できるため、多くのスタートアップが利用しています。
大阪府の場合、大阪ビジネスサポートセンターや商工会議所と日本公庫が連携し、融資斡旋や制度説明会を開催しています。
融資は返済が必要ですが、助成金と組み合わせて活用することで創業資金をさらに厚くできます。例えば持続化補助金で販促費を補い、公庫融資で運転資金を確保するといった組み合わせも有効です。
公庫融資を受けること自体が信用力アップにつながり、後々追加の助成金申請時に自己資金要件を充足させるのにも役立つでしょう。
創業期は助成金+融資+自己資金のバランスが大切ですので、資金繰り全体を見渡して計画を立ててください。

創業初期に助成金を活用するメリットと制度活用のアドバイス
創業初期に助成金を活用するメリットは何といっても、資金繰りに余裕が生まれることです。補助金・助成金は原則返済不要なので、調達した資金を将来の返済に充てる必要がありません。
自己資金や借入金だけでは賄いきれない設備投資や広告宣伝に踏み切ることができ、事業のスタートダッシュを切る助けとなります。
例えば補助金を活用して十分な設備やプロモーションを行えば、創業当初の売上不振リスクを減らし、失敗の可能性を下げることができます。
さらに、公的な補助事業に採択されたという事実は取引先や金融機関からの信用力向上にもつながります。
「国や自治体のお墨付きを得たビジネス」として、周囲から一目置かれる効果も期待できます。
加えて、助成金を活用することで事業計画を練り直す機会が得られたり、支援機関とのネットワークが構築できたりといった副次的メリットもあります。
一方で留意すべき点もあります。まず、助成金は申請から受給までタイムラグがあり、事業資金は一時的に自己で用意しなければなりません。
したがって、つなぎ資金の手当てや資金繰り計画が重要です。
また、助成金には細かな要件や報告義務が伴います。要件を満たすため事前に規定の手続きを踏む必要があったり、事業終了後も一定期間の経過報告が求められたりします。
これら事務負担を厭わずこなす覚悟が必要です。加えて、採択が競争的な補助金では不採択のリスクもあります。
仮に当てにしていた補助金が受けられなくても事業継続できるよう、資金計画には余裕を持たせましょう。
制度をうまく活かすためのアドバイスとしては、まず情報収集を徹底することが挙げられます。
国・自治体・支援機関の補助金公募情報は日々更新されていますので、ミラサポPlusやJ-Net21、自治体ホームページなどを定期的にチェックしましょう。
次に、自社が受けられる可能性のある助成金を見つけたら、早めに準備に着手することです。
募集開始を待って動くのではなく、日頃から事業計画書のブラッシュアップや必要書類の整備を進めておけば、公募時に慌てずに済みます。
商工会議所や専門家への相談も早めに行いましょう。
さらに、事業計画と助成金要件のすり合わせも重要です。
「自社に合う制度を探す」のではなく、「要件に合わせて事業計画を再構築する」柔軟さも時には求められます。
例えば販路開拓費用が欲しい場合、持続化補助金の要件に合わせて計画を作り直すことで採択率を上げる、といった工夫です。
ただし本末転倒にならないよう、自社のビジョンと補助金要件のバランスを取りましょう。
助成金はあくまで手段であり目的ではないことを肝に銘じてください。
助成金ありきで事業を進めると、受給できなかった場合に計画が頓挫しかねません。
自己資金や融資による資金調達も組み合わせ、助成金はプラスアルファとして活用するのが健全です。
助成金を上手に活かしつつ、本業そのものの競争力と収益力を高めることが創業初期を乗り切る最大のポイント。
公的支援策は賢く使いこなしましょう。
採用・育成の助成金申請ならNext HUB株式会社へお問い合わせください
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら




















