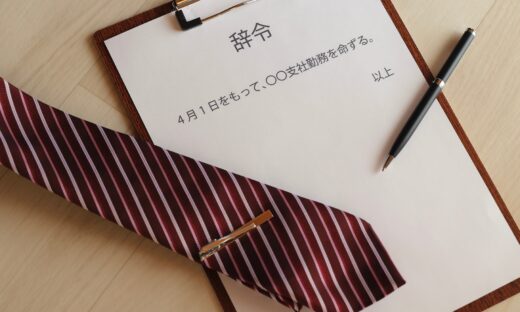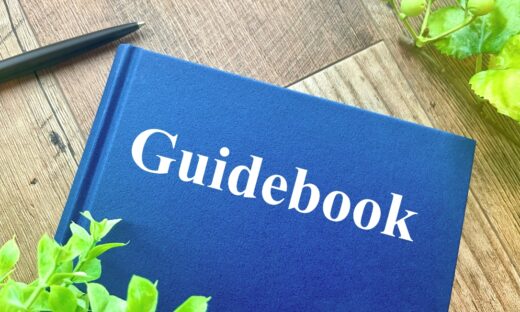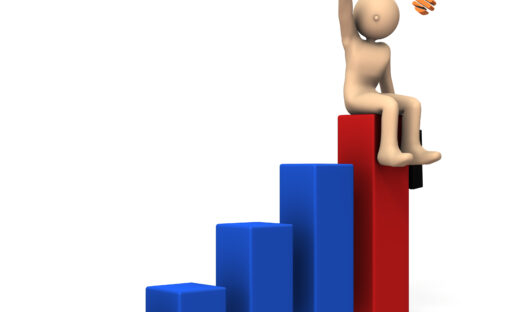若者の採用コストはどこにかけるべき?ムダを省く効率的な採用戦略を解説
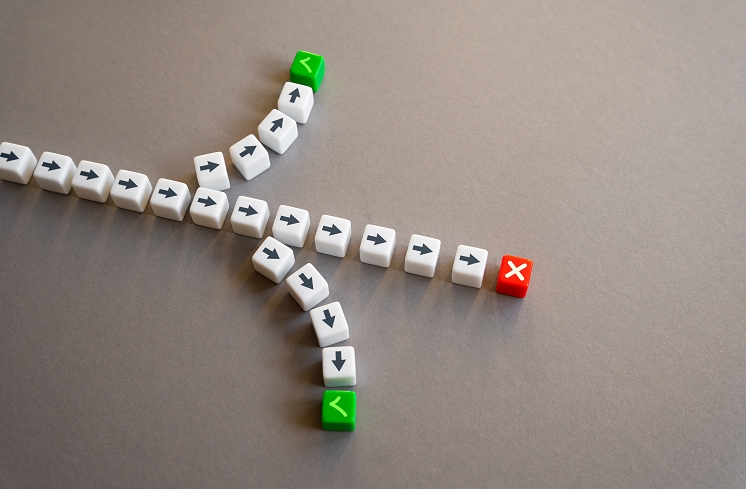
現代の少子高齢化・人口減少に伴い、新卒・第二新卒を含む若手人材の採用競争は一層激化。
特に中小企業では、限られた採用予算をどこに投じるかが経営課題となっています。
大企業に比べて知名度や待遇面で劣る中小企業は、優秀な若手が大企業に流出しやすい状況にあるのです。
そこで必要なのは、「採用単価」などの指標で費用対効果を可視化しながら、ターゲットに合致したチャネルに集中投下する戦略。
本記事では、中小企業の採用担当者向けに、SNS・自社HP・YouTubeといった主要チャネルごとの活用法を分析しつつ、運用の内製化・外注コストの最適化、無駄を省いた効率的な採用プロセスの構築方法を具体的に解説します。
目次
採用市場の現状と中小企業の課題
若者採用においては、市場環境の把握が不可欠です。
特に日本では求人倍率の高さから採用競争が厳しく、東京では「求職者1人当たりに対して求人が2件」存在するといわれるほどの状況です。
若年層はSNSを利用した情報収集を日常的に行うため、自社の情報発信が戦略の要となります。
中小企業は人手や予算が限られるうえ、大企業に比べて社名認知度・給与水準が劣るケースが多く、就職先として敬遠されがち。
このため、応募者の確保だけでなく、内定辞退や早期離職リスクへの対策も重要です。
実際、厚生労働省の調査では規模の小さい企業ほど若手の3年以内離職率が高く、再募集によって採用コストが膨らむ傾向があります。

若年層採用の競争環境
少子化・人口減少の中で若手人材は希少価値が高く、各企業は情報発信を工夫しています。SNSやWebサイトでの積極的な広報が求められ、従来型の紙媒体よりオンライン活用が主流になっています。
中小企業の弱点
大企業に比べて採用ブランディングが弱い、社内に専任担当者が少ない、求人サイト掲載数を増やさざるを得ない、などの事情で採用単価が高くなるケースが見られます。
コスト意識の向上
「採用単価(=採用コスト÷採用人数)」を採用効果の指標として設定しましょう。
単に「採用コスト総額」を見るより、1人採用に対していくらかかったかを追うことで、各施策の有効性や無駄を判断しやすくなります。
内定辞退・早期離職対策
中小企業では給与・福利厚生で大企業に劣る場合が多く、魅力的な中小企業でも内定後に大企業に流出する例が少なくありません。
内定辞退が続くと再募集コストが発生するため、企業の魅力発信や待遇改善、入社後フォローを強化する必要があります。
採用成功の鍵は、企業が求める人材像を明確にし(ターゲットペルソナ設定)、予算に見合った戦略を立てること。
専門スキル人材が欲しい場合は、大量に不特定多数に求人をかけるよりも、リファラル採用やダイレクトリクルーティングに絞って効率的に動くほうが効果的。
まずは自社の課題を洗い出し、採用目的に沿った人物像を定めましょう。
若者採用にかかるコストとは?まずは全体像を把握しよう
新卒・第二新卒・20代の若者を採用するには、求人広告費だけでなく、さまざまな目に見えにくいコストがかかっています。
まずは採用にかかる費用の全体像を明確にしましょう。
採用コストの内訳とは?求人広告費だけではない
採用にかかる費用は、「求人広告費」「人材紹介手数料」などの外部支出だけではありません。
求人サイトへの掲載料やSNS広告、合同説明会への出展費用などが直接的なコストとして発生します。
さらに、応募者対応のために使用する採用管理システム(ATS)の利用料や、選考会場のレンタル代も含まれます。
これらに加え、選考のために作成するパンフレットや企業説明資料、動画制作費などのコンテンツ制作関連費も無視できません。
採用活動は単なる求人掲載だけでは完結しないため、コストの内訳は多岐にわたる点を認識する必要があります。
見落としがちな「人的コスト」とは何か
採用活動では、人事担当者だけでなく現場社員や経営層が面接や対応に関与することが多くなります。
面接1回にかかる所要時間を1時間とすると、複数名で実施した場合の「人件費」は軽視できない金額になります。
説明会への参加、社内での資料作成、面談の日程調整などもすべて工数として積み上がっていきます。
これらは直接的な費用ではないため見過ごされがちですが、合計するとかなりの工数が費やされており、企業の生産性に影響する可能性も。
つまり、採用に関する「時間」もまた、重要なコストの一部だと考えるべきです。
採用単価を把握して適正かどうかを判断
採用活動の「効率性」を測る指標として有効なのが「採用単価」です。
これは、採用活動全体にかかったコストを、実際に採用できた人数で割って算出します。
求人広告費・人件費・説明会費などで合計100万円かけて5人採用できた場合、採用単価は20万円ということに。
この数字を基準に、年度ごとの比較を行ったり、チャネル別の費用対効果を分析することで、「どこにムダがあったのか」「どの施策が効率的だったのか」を客観的に把握できます。感覚だけでコストを見積もらず、数値化することで初めて最適化が可能になります。
新卒・第二新卒・20代採用にかかる平均的な費用とは
一般的に、新卒採用の平均採用単価は約50〜70万円程度といわれており、第二新卒や20代中途の場合は40〜60万円前後が相場とされています。
ただし、この金額は、業界・採用手法・地域によって変動します。
ダイレクトリクルーティングやリファラル(社員紹介)で採用できればコストは10万円以下で済む場合もありますし、逆に人材紹介会社を経由して高年収人材を採用すれば1人あたり100万円以上かかることもあります。
採用人数を少なく抑えたとしても、1人あたりの採用単価が極端に高くなってしまえば非効率です。
平均値だけでなく、自社の採用背景やターゲット層に応じて相場感を把握しておくことが重要です。
無駄な採用コストが発生する原因を見極める
採用活動でかかるコストは、知らず知らずのうちに膨らんでいることがあります。
成果につながらない「ムダな支出」を防ぐには、その根本原因を明確にして対処することが欠かせません。
想定ターゲットが曖昧なまま求人を出していないか
採用活動における無駄の典型が、「どんな人材を採用したいのか」を明確にしないまま、求人情報を広範囲に出してしまうことです。
「若手なら誰でも良い」といったぼんやりした条件で求人を出してしまうと、自社に合わない応募者ばかりが集まり、書類選考や面接に余計な労力と時間を要する結果になります。
さらに、面接で見極められなかった場合はミスマッチ採用となり、早期離職を招く可能性も。
ターゲット層の年齢、スキル、志向性、価値観まで細かく想定し、その人物像に合った求人文や発信媒体を選ぶことが、採用コストの効率化につながります。
運用しているSNSやHPが放置状態になっていないか
SNSアカウントや採用ページを立ち上げたまま、更新が止まっていないでしょうか。
更新頻度が低い、内容が古いままになっている、投稿の内容が業務や職場の実情と乖離しているといったケースは、企業イメージを損なう原因になります。
若年層は企業を選ぶ際、SNSやHPから社風や働き方を読み取ろうとする傾向が強いため、情報発信が滞っていると「この会社は魅力がない」「社内に活気がないのでは」といった誤解を招き、応募者離れにつながります。
また、外部にSNS運用を委託している場合、更新を続けても効果が出ていない内容であれば、委託費用そのものが無駄な支出になります。
まずは自社の発信が本当にターゲットに届いているかをチェックし、運用体制を見直す必要があります。
採用チャネルの制作を外部に委託している場合、「工務店」「建築業界」など、業界・業種を絞って実績を積んでいる場合は特に信頼できる傾向にあります。
参考)株式会社 アババイ
成果が出ない外部委託に漫然と費用をかけていないか
採用動画の制作、SNS運用、採用サイトの保守・更新などを外部委託している企業は多いですが、その成果を定量的に把握していないケースも少なくありません。
「動画を作って1年放置」「SNS更新を依頼しているが応募が来ない」「採用ページを作ったが流入経路がない」といった状態では、費用をかけていても成果が出ておらず、まさに“無駄な採用コスト”の典型です。
定期的にKPIを設定し、費用対効果を測定する体制が必要です。
アクセス数、エントリー数、面接通過率などの数字が一定の基準を下回っている場合、委託内容の見直しも検討するべきかもしれません。
選考プロセスが長すぎて応募者離脱が起きていないか
応募から内定までに時間がかかりすぎてしまうと、候補者はその間に他社の内定を受け取ったり、気持ちが冷めて辞退したりするリスクが高まります。
特に若手求職者は「スピード感」や「レスポンスの速さ」に敏感です。
一次選考から内定までに数週間以上かかっている場合、優秀な人材ほど途中で離脱してしまう傾向があります。
また、面接回数が多すぎたり、意思決定に複数の承認が必要な仕組みもスピードを損なう要因です。無駄なプロセスを見直し、初期段階で見極めができる評価手法を取り入れ、オンライン面接や録画選考を活用することで、選考全体を効率化できます。
選考がスムーズに進まないことで発生する“間接的な採用コスト”にも注目すべきです。
SNS採用の効率的な活用法
SNSは、若者にとって最も身近な情報収集ツールの一つです。
闇雲に運用するのではなく、ターゲット層の特性に合わせて的確に活用することで、採用コストを抑えつつ効果的な広報が可能になります。

採用ターゲットが使っているSNSに集中投下する
すべてのSNSを一律に運用するのは非効率です。
例えば、Instagramは20代の若年層に人気があり、写真や動画を通じて「社風」や「働く雰囲気」を直感的に伝えやすいのが特徴。
一方で、Xは即時性が高く、時事性のあるトピックや日々の様子を発信するのに適しています。
TikTokはエンタメ性に優れ、動画を通じた強烈な印象づけができますが、社内での制作体制が整っていないと運用が難しいことも。
自社の採用ターゲットとなる年齢層・職種・志向性に合ったSNSを絞り込み、そこに人とコストを集中投下することが、SNS採用を効率的に運用する第一歩です。
利用媒体の選定基準を明確にし、最初から手を広げすぎないことが重要です。
社員の日常を発信して親近感を演出する
SNSの最大の強みは、公式サイトでは伝えきれない「リアルな日常」が届けられる点にあります。
オフィスの雰囲気、ランチの様子、イベントや勉強会の風景、社員の素顔などを発信することで、求職者が「ここで働く自分」を想像しやすくなります。
Instagramで社員の1日密着ストーリーを投稿したり、Xで採用担当者が気軽に質問を受け付ける投稿をすることで、企業と応募者との心理的な距離を縮められます。
形式ばった内容よりも、社員の素朴な発言や表情が伝わるコンテンツのほうが反応を得やすく、投稿のエンゲージメントにもつながります。
こうした投稿は制作コストも抑えられるため、採用広報としての費用対効果も高いといえるでしょう。
有料広告は絞って使う、効果測定を忘れない
SNS広告は、少額から始められる手軽さが魅力ですが、投下するターゲットを誤ると費用対効果が著しく低下します。
Instagram広告で応募を促す場合、広告クリエイティブ(画像・動画・コピー)の内容がターゲット層に刺さっていなければ、クリックすらされず無駄な出費となってしまいます。
配信地域や年齢層、興味関心などを細かく設定し、必要最低限の広告予算でスタートするのが基本。
さらに、広告運用後は「クリック率」「滞在時間」「応募完了数」といった指標を確認し、改善を繰り返すことが重要です。
効果測定をしないまま出しっぱなしにするのは最も無駄な運用であり、広告のパフォーマンスを逐一チェックして、ABテストを行うなどして調整し続ける体制が求められます。
自社HP・採用サイトでコストを抑えつつ魅力を伝える
採用活動において、自社のホームページや採用専用サイトは「低コストで高い訴求力を持つツール」です。
中小企業でも、工夫次第で応募者に強い印象を与えることができます。
求職者が知りたい情報を整理して掲載する
採用サイトに掲載すべき情報は、会社概要や事業内容だけでは不十分です。求職者は「実際に働いたらどんな生活になるか」「どんな人が働いているのか」「社風や育成方針はどうか」といった具体的な情報を求めています。
仕事内容の紹介では、1日の流れや担当業務の比重、やりがいと課題の両方を記載することが望ましいです。
待遇面も、給与や賞与、福利厚生、休日制度、残業時間の平均など、数値を交えて記載すれば信頼感が高まります。
また、よくある質問(FAQ)ページを設けて、応募前の疑問を解消できる構成にすることで、問い合わせ対応の工数削減にもつながります。
社員インタビューや会社の雰囲気が伝わる写真を活用
文字情報だけでは伝えきれない「職場の空気感」を視覚的に補うために、社員インタビューや現場の写真を積極的に活用しましょう。
社員インタビューでは、入社理由、現在の仕事のやりがい、入社前後のギャップ、今後の目標などを具体的に語ってもらうと、読み手に説得力を与えられます。
また、写真は単なる集合写真よりも、業務中の自然な表情やチームでのやりとり、イベント風景などを含めると親近感が増します。
撮影費用をかけずにスマートフォンでも十分撮れる時代なので、内製でのコンテンツ制作も十分に検討可能です。写真や動画は定期的に更新することで、会社の「今」を伝え続ける役割も果たします。
採用チャネル別の活用法とコスト対策
若者採用でよく使われる主なチャネルはSNS(X、Facebook、Instagram、LINEなど)、企業HP・採用サイト、YouTubeなどの動画です。
各チャネルには独自の特性とコスト構造があるため、戦略的に選択・活用しましょう。

SNS採用(無料拡散 vs 運用コスト)
SNSは基本的にアカウント登録・利用料が無料で、フォロワーの拡散力を活かせば広告費ゼロで認知度アップが狙えます。
若者層の多くがSNSで情報収集し、企業選びもSNS経由になるケースが増えているため、自社の取り組みや社員紹介などを定期的に発信することで潜在的な応募者にリーチできます。
例えば、XやInstagramにオフィス風景や先輩社員の声を投稿しておけば、興味関心の高いユーザーに情報が届きやすくなります。
一方で注意点として、SNS運用は「無料だが手間がかかる」面があります。
投稿ルール策定や定期更新には人的リソース(担当者の人件費)が必要で、短期的に明確な成果が出ないことも多いです。
炎上リスクへの対策も含め、専任者が日常的に運用する仕組みを作るか、あるいは最低限の運用ガイドラインを社内で整備しておくことが重要です。
自社サイトの採用ページやオウンドメディアの運用は、外部広告費が不要で自由度が高い点が大きなメリット。
職場紹介や社長メッセージ、社員インタビュー、選考情報などを充実させれば、企業の魅力をしっかり伝えられます。
検索エンジン対策(SEO)も含めて自社HPの更新に注力すれば、中長期的に費用対効果の高い採用チャネルになります。
自社内で更新できる運用体制を作れば、外注費用をかけずにタイムリーな情報発信が可能です。
例えば、社員ブログの導入や採用オウンドメディアの開設などにより、自社独自のコンテンツを蓄積しながら認知度を高めることができます。
YouTube・動画採用の活用
動画は文字や写真よりも企業の雰囲気やカルチャーを伝えやすいため、若手にアピールするのに有効です。
YouTubeに企業紹介動画や社員インタビュー、社内イベントの様子などをアップすれば、視聴者は実際の職場イメージを持ちやすくなります。
また、説明会や体験会をオンライン動画で代替することで、会場費や移動時間などのコストを削減できます。
実際、採用動画を拡充するには企画・撮影・編集などでコストと時間がかかりますが、中長期的には“無駄のない効率的な採用活動”につながります。
YouTubeチャンネルは公開期限がなく資産として蓄積できるため、定期的に配信を続けていくことで総合的な費用対効果は非常に高くなります。
ただし、登録者数を増やすには継続的な努力が必要で、成果までには1年以上の時間を要することも。
短期的な即効性を期待せず、将来を見据えた中長期の発信計画を立てましょう。
求人広告・有料媒体の使い分け
Indeedや求人サイトの有料掲載、Google広告、SNS広告なども選択肢です。
これらは応募数を増やす手段として有効ですが、闇雲に投資するとコストが嵩むリスクがあります。
例えば、GoogleやFacebookのクリック課金広告は「応募者がクリックする時点で費用が発生する仕組み」です。
ターゲット設定を適切に行えば、無駄を抑えつつ効率的に募集できます。
しかし、広告の対象を絞り込み切れないと不適切な応募を集めてしまい、逆にコストパフォーマンスが悪化する恐れも。
予算に余裕がある場合は、SNS広告などを試験的に実施して効果測定するのも手です。
いずれの場合も、ROI(投資対効果)を常に把握することが重要です。
採用活動の効率化と無駄削減に向けた実践策
採用活動に無駄を省くには、計画段階から明確な目標と戦略を定め、数値指標で進捗を管理する姿勢が求められます。
以下のポイントを押さえ、PDCAサイクルを回していきましょう。
採用ターゲットと戦略の明確化
まず自社に必要な人材像を定義し(例:資格者、経験者、ポテンシャル層など)、その人物が集まるチャネルやメッセージを考えましょう。
曖昧な採用要件では無駄打ちが増え、採用単価が上昇してしまいます。
高度な専門職ならハイクラス求人やリファラル(社員紹介)が向く一方、20代の若手層にはSNSや大学との連携が効果的な場合があります。
目的に応じた手法を選び、限られたリソースを集中投入することで効率を高められます。
採用単価・KPIによる効果測定
採用コストはただ削減すれば良いわけではなく、投じた費用に見合う成果(新入社員の活躍・定着)を上げる必要があります。
その目安として「採用単価」を設定し、定期的に算出・比較しましょう。
業界平均と照らし合わせるなど、目標値を決めて運用できれば、費用対効果を客観的に判断できます。
応募数、面接通過率、内定承諾率、3年定着率など、プロセスごとにKPIを設定し、改善点を洗い出して改善策を打ちます。
応募チャネル別のコストも把握し、SNSや自社サイト経由の応募が高効率ならそこに注力するといった配分見直しに役立ちます。
社内運用と外注コストの最適化
SNSやWeb運用などは詳しい人材や部署があれば社内で内製化しましょう。
詳しい人材がいない場合には外部委託した方が人材を育成するよりも効率がいいケースが多いです。
社内運用であれば外部委託料が発生せず、予算を掛けずに自由度高く発信できます。
採用SNSやブログの更新、採用管理システムの基本設定などを自前で行える体制を構築すれば、コストを調整しやすくなります。
ただし、専門性が高い作業(例えば高品質な企業紹介動画やUI改善など)は外注も検討し、投資効果と人件リソースを天秤にかけて最適な選択を行いましょう。
例:SNS運用は効果が出るまで時間がかかるため、まずは自社で担当者を決めて地道に運用しつつ、必要に応じて広告運用を組み合わせる。
リファラル(社員紹介)の促進
リファラル採用は、自社の既存社員や取引先のネットワークを活用できるため、コスト効率が高い手法。
紹介者へのインセンティブ(紹介料)だけで採用でき、人材のミスマッチも起きにくくなります。
社内の知人紹介制度を整備し、成功報酬や表彰でモチベーションを高めましょう。
リファラルは社員のエンゲージメント向上にもつながり、社内コミュニケーション活性化の効果も期待できます。
選考プロセスの効率化
採用選考時の無駄を見直します。書類選考→面接の回数・担当者を最小限に抑え、ウェブ面接や事前課題を活用して候補者を絞り込む工夫が有効です。
また、ATS(採用管理システム)やスケジューリングツールを導入すれば、候補者対応の負担軽減と情報共有が進みます。
エントリー後の自動メール連絡や面接予約システムを整備れば、担当者の手作業を削減し、面接日程の調整漏れを防止できます。
オンライン説明会やウェビナーを定期開催し、効率よく情報提供する方法も有効です。
助成金・補助金の活用
若手採用に関しては、国の助成金制度の適用を検討するのも手です。
要件に合えば1人当たり数十万~数百万円が支給される制度もあるため、コストの一部を補填できます。
「トライアル雇用助成金」や「特定求職者雇用開発助成金」などは、新卒や第二新卒、障がい者・高齢者などを対象に雇用すると支給対象になります。
以上の施策を実施する際は、常にPDCAを意識し、効果測定と改善を繰り返すことが重要です。
採用単価が高止まりする場合は原因分析(例:ターゲット不一致、メッセージ不足、競合他社との差別化不足など)を行い、柔軟に戦略を修正しましょう。
まとめ:重点投資で無駄を省く採用戦略
若者採用におけるコストの最適化には、限られた予算を「効率の良いところ」に集中させる視点が不可欠です。
SNSや自社サイト、YouTubeは共に無料枠を活用できるため、自社での運用ノウハウを蓄積していくことが基本になります。
同時に、社内人材によるリファラル採用やオンライン面接システムの導入なども採用単価を下げる有力策。
一方、即効性を求めるなら、ターゲットを絞ったSNS広告やGoogle求人広告の利用も検討しましょう。
どの手法でも、*採用単価で成果を検証し続けること」でムダを省けます。
採用活動は中長期戦です。
目先の効率化だけでなく、将来を見据えたブランディング投資も重ねていきましょう。
自社の強みを伝えるコンテンツ作りや社員の声の発信が積み重なれば、長い目で見て高い採用効果を得られます。
経営者・採用担当者は、これらの知見を踏まえてPDCAを回し、無駄を省いた効率的な採用体制を構築してください。
実践ポイント(例)
採用単価を計算・目標設定し、予算配分の妥当性を評価する。
ターゲット像を具体化し、ターゲットのいるチャネルに優先投資する。
SNS・サイトは自社運用に切り替え、外注費用を削減する。
リファラル制度を整備し、紹介手数料で効率的に優秀人材を確保する。
採用フローを最短化し、オンラインツールで面接や説明会の効率を上げる。
以上のような取り組みを継続し、成果を定量的に評価することで、若者採用にかけるコストを効率化し、質の高い人材を獲得していきましょう。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら