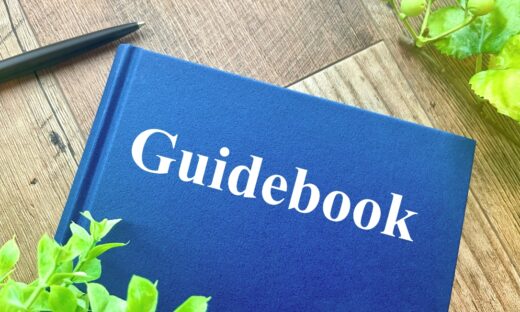助成金詐欺に注意!企業が安全に助成金を活用するためのチェックポイント

助成金は企業の人材育成や経営強化に役立つ制度ですが、不正な申請をあおる業者や、知らず知らずのうちに不正受給となるケースも増えています。
本記事では、企業が助成金を安全・適正に活用するために知っておくべきチェックポイントや、注意すべき業者の特徴、トラブルを避けるための対策をわかりやすく解説します。
目次
助成金詐欺とは何か
助成金詐欺とは、国や自治体の助成金制度を悪用した詐欺行為全般を指します。
典型的な例としては、本来受け取る資格のない助成金を虚偽の申請によってだまし取る「不正受給」や、助成金申請を餌に中小企業から高額な手数料を騙し取る行為などが挙げられます。
助成金制度自体は、中小企業の設備投資や雇用創出、経営改善を支援するために国や自治体が提供する返済不要の資金援助で、雇用調整助成金やIT導入補助金など様々な種類があります。
しかし、その「もらえるお金」を狙って詐欺師は中小企業をターゲットにしやすいのです。

中小企業が狙われる理由
中小企業が狙われる理由として、第一に助成金の手続きが複雑である点が挙げられます。申請には専門知識が必要であり、自社だけでは難しいため、コンサルタントなど外部の支援に頼るケースが多くなりがち。
このような状況につけ込み、「助成金を確実に受給できますよ」と甘い言葉で近づいてくる詐欺業者も存在します。
資金繰りに悩む中小企業ほど誘惑に乗りやすいため、結果的に被害に遭いやすくなってしまいます。
また、大企業に比べて法務・コンプライアンス部門が手薄で最新情報に疎い場合があることも、中小企業が標的になりやすい理由と言えるでしょう。
新型コロナ関連の給付金・助成金を悪用した詐欺も社会問題化しており、経営者は常に注意を払う必要があります。
助成金詐欺が増加する背景
近年、助成金詐欺が増加している背景には、いくつかの社会的・経済的な要因があります。特に、以下の点が助成金詐欺の温床となっています。
1. 経済不安と資金繰りの悪化
中小企業にとって資金繰りは常に大きな課題ですが、特に経済の低迷期やパンデミック後の回復期などには、資金確保のために助成金制度への依存度が高まります。
経営が苦しい企業ほど、助成金を受け取るために適正な審査を受けるよりも、簡単に「受給できる」と持ちかけてくる業者の話を信じてしまいやすい傾向があります。
2. 助成金制度の拡充と監査の甘さ
政府は中小企業支援のために助成金制度を拡充しており、新たな助成金・補助金が頻繁に創設されています。
しかし、助成金の申請数が急増する一方で、審査体制が十分に整わないケースもあり、不正受給や詐欺が発生しやすくなっています。
特に緊急対策として導入された助成金(例:新型コロナウイルス関連の持続化給付金)では、審査が簡素化された結果、詐欺グループによる組織的な不正受給が相次ぎました。
3. SNSやオンライン広告を利用した詐欺手口の巧妙化
従来の助成金詐欺は電話勧誘や訪問営業が主流でしたが、近年ではSNS広告やオンラインセミナーを通じた詐欺が増えています。
「今すぐ申請すれば100万円の助成金が受け取れます!」といった魅力的なキャッチコピーで広告を出し、公式サイトに似せた偽サイトへ誘導する手口もあります。
SNSの普及によって、より多くの企業が詐欺業者のターゲットになっているのです。
4. 企業側の助成金知識の不足
助成金の申請には細かい条件が設定されており、適切に理解していないと不正受給につながる可能性があります。
しかし、多くの中小企業は専門知識を持たないため、悪質なコンサルタントや代行業者に依存しがちです。
その結果、「適法な手続き」と信じて虚偽の申請を行ってしまうケースもあります。
5. 詐欺業者の組織化とグローバル化
助成金詐欺を行う業者は、個人ではなく組織化された詐欺グループである場合が多く、法律の抜け穴を利用して悪質な手口を繰り返しています。
特に海外に拠点を持つ詐欺業者も増えており、日本の中小企業をターゲットにした国際的な詐欺が報告されています。
日本国内の助成金詐欺の現状
日本国内でも助成金詐欺の被害は少ないとは言えません。
助成金詐欺の被害状況と統計
実際に発生したケースとして、石川県の老舗旅館が雇用調整助成金を不正受給していた例があります。
従業員に「タイムカードを押すな」と指示するなど勤務実態を偽り、最終的に1億円以上を不正に受給していたことが発覚。
この旅館では返還命令を受け、巨額の返還と社会的信用の失墜という大きな代償を払うことになりました。
また、新型コロナウイルス関連の給付金・助成金でも不正が多発しています。
中小企業庁の発表によれば、持続化給付金を不正受給した事業者は約1,500者、総額15.6億円以上にのぼります(2022年10月時点)}。
このうち約3億円は未返還となっており、行政が返還を求めても応じない悪質なケースも存在します。
さらに、厚生労働省の集計では、雇用調整助成金等で判明している不正受給額が2022年9月末時点で135億円に達しており、実際にはそれ以上に不正が潜んでいる可能性も指摘されています。
これらの数字からも、助成金詐欺が社会的に大きな問題となっている現状がうかがえます。
行政の取り組みと課題
行政も対策に乗り出しており、不正受給が発覚した事業者名の公表や、詐欺グループの摘発が進められています。
持続化給付金の不正では多数の逮捕者が出てニュースにもなりました。
国は公式サイトやパンフレットで注意喚起を行い、「それは不正受給ではありませんか?」と呼びかけています。
また、各省庁は助成金の適正利用に関する監査を強化し、不審な申請には現地調査を実施するなどチェック体制を厳しくしています。
とはいえ、不正の手口も年々巧妙化しており、「自分は大丈夫」と油断しているといつ被害に巻き込まれるかわかりません。
実際に悪意がなくても結果的に不正受給とみなされ、処罰対象となる事例もあるため、経営者として最新の手口や対策を知っておくことが重要です。
よくある助成金詐欺の手口
助成金詐欺師たちは様々な手口で中小企業を陥れようとします。
ここでは特に注意すべき典型的な手口をいくつか紹介します。

公的機関を装った勧誘
「◯◯省から委託を受けた支援機関です」などと名乗り、あたかも公的な立場であるかのように装うケースです。
実際には無資格の民間業者にもかかわらず信用させ、助成金の相談に乗るふりをして近づいてきます。
行政が直接企業に助成金申請を勧誘することは通常ありませんので、このような連絡には警戒が必要です。
虚偽申請への誘導
受給資格のない助成金を「あなたの会社でももらえるようにしてあげます」と持ちかけられるケースです。
本来対象外なのに申請できるとうたって契約を迫り、虚偽の書類作成をそそのかします。
詐欺業者は自分たちが直接不正に関与した証拠を残さないために、企業側に嘘の申請書を提出させることが多い点も特徴です。
例えば在籍していない架空の従業員を雇用しているように見せかけたり、売上が減少していないのに減少したと装ったりといった方法で申請させ、受給させようとします。
高額手数料の要求
「助成金を確実に受給させる」と謳い、通常では考えられない高額な手数料や着手金を要求するパターンです。
正規の専門家である社会保険労務士に依頼した場合の相場は着手金2〜5万円、成功報酬は受給額の10〜20%程度ですが、詐欺業者はそれを遥かに上回る報酬設定をしてきます。
中には着手金を受け取った後に音信不通になってしまう悪質業者も報告されています。
相場とかけ離れた金額を提示されたら要注意です。
不要なサービス契約の強要
助成金の手続き支援と称して、実際には関係のない高額なサービスや情報商材を購入させる手口です。
例えば「申請に必要なマニュアルを買ってください」「有料会員になれば最新の助成金情報を提供します」と言って契約を迫ります。
提供される情報は公表されている内容に過ぎないことが多く、本来無料で入手できるものに高額な料金を支払わせる詐欺的商法です。
無料セミナーでの勧誘
中小企業向けの「助成金活用セミナー」などを無料で開催し、参加者を集めて信用させてから勧誘する方法です。
セミナー自体は無料でも、終了後に「本当にためになるサポートは有料会員限定です」などと言って高額な有料サービスに誘導します。
その場の熱気で契約させ、その後冷静になって解約したいと申し出ても「契約済みなので無理」と取り合わないケースもあります。
無料に惹かれて安易に飛びつかないよう注意しましょう。
以上のような手口は氷山の一角ですが、特に「公的機関」「今だけ」「必ずもらえる」といったキーワードが出てきたら詐欺を疑ってください。
助成金制度では原則として不正な申請は許されず、もし業者に勧められるまま虚偽の申請をすれば、最終的に責任を負うのは申請した企業側です。
甘い話には裏があることを念頭に置き、慎重に対応しましょう。
助成金申請に潜むリスクと注意点
助成金詐欺に関わってしまった場合、中小企業には様々なリスクと不利益が生じます。
不正受給による法的リスク
まず第一に法的リスクです。
虚偽申請による不正受給が発覚すれば、支給された助成金は全額返還を求められるのは当然として、さらに受給額に年3%の延滞金と20%の加算金(ペナルティ)を上乗せして納付しなければなりません。
要するに、受け取った額以上のお金を返す結果になるということです。
また厚生労働省所管の助成金の場合、不正が判明した日から最長5年間はあらゆる助成金の利用を禁止される処分もあります。
この禁止期間は未返還額が残っていると延長されるため、将来的な事業計画にも支障をきたしかねません。
企業信用低下のリスク
さらに、企業の社会的信用の低下も深刻なリスクです。不正受給が明るみに出れば、社名や不正の概要が公表される場合があります。
公表まではされなくとも、噂は業界内外に広まり、取引先や金融機関からの信頼は大きく損なわれるでしょう。
実際に「助成金不正受給」で社名が公表された企業は、銀行から新規融資を断られたり、取引停止に追い込まれるなどの影響が出ています。
企業イメージが悪化すれば優秀な人材の採用にも支障が出る可能性があり、経営全般にマイナスです。
刑事罰のリスク
悪質な場合は刑事罰も免れません。不正受給が明確な詐欺行為と認定され刑事告発に至った場合、詐欺罪として起訴されることもあります}。
刑事裁判で有罪となれば懲役刑など重い罰則を科される可能性があり(法定刑は最大で懲役10年程度)、経営者自身が前科を負う事態にもなりかねません。
たとえ刑事事件にならなくとも、行政処分や返還命令に従わなければ民事訴訟に発展する恐れもあります。
情報漏洩や個人情報悪用のリスク
詐欺業者に社内の機密情報を渡してしまうリスクも見逃せません。
申請代行を依頼する際には会社の財務資料や人事情報などを提供しますが、悪徳業者に渡ったこれらの情報が不正に利用されたり外部に流出したりする可能性があります。
一度漏れた情報を回収することは困難であり、知らぬ間に別の詐欺に悪用される二次被害にも繋がりかねません。
助成金詐欺に関与すると金銭的損失(返還・罰金)、信用失墜、法的制裁、情報漏洩など多方面にわたるリスクを負うことになります。
経営者として「多少ズルをしてもバレないだろう」「言われるがまま申請すれば得をするかも」などと安易に考えるのは非常に危険です。
助成金は本来、企業活動を支援する善意の制度ですが、不正に手を出せば企業経営を揺るがす凶器にもなり得ることを肝に銘じておきましょう。
助成金詐欺に遭わないための基本対策
助成金詐欺の被害に遭わないためには、経営者自身が正しい知識を持ち、慎重に行動することが何より重要です。
以下に基本的な対策のポイントをまとめます。
1. 公式情報源の確認
助成金の募集情報や申請手続きは、必ず公式の情報源で確認しましょう。
具体的には各省庁や自治体の公式ウェブサイト、中小企業支援機関(商工会や中小企業基盤整備機構など)の発表資料です。
怪しい業者から「今しか申請できない助成金があります」と言われても、一旦立ち止まり、その助成金名でインターネット検索をかけたり、公的機関に問い合わせたりして、本当に存在する制度なのか、募集要項はどうなっているかを確認してください。
制度の有無すらあやふやにしたまま話を進めるのは厳禁です。
また、公的機関が直接営業電話やDMで助成金申請を勧誘することは基本的にないため、そのような連絡は疑ってかかりましょう。
2. 専門家の活用と見極め
助成金申請には社会保険労務士(雇用関係助成金)や行政書士・中小企業診断士(経済産業省系補助金)など、専門知識を持つプロの力を借りるのが有効です。
ただし、誰に頼むかの見極めが肝心。
依頼する前にその人物・会社の実績や資格をチェックしましょう。
例えば厚労省所管の助成金申請代行は社労士しか行えませんので、社労士資格のない業者から持ちかけられた場合はアウトです。
過去の支援実績や顧客の声を確認し、契約書を交わす際も内容を細かく確認してください。少しでも不信感があれば他の専門家に相談する勇気も必要です。
3. 勧誘への適切な対処
知らない業者や突然の電話勧誘には警戒心を持ちましょう。
「ちょっと話を聞くだけ」と安易に会ってしまうとペースを握られがちです。
必要ない勧誘はきっぱり断る、興味がある場合でもその場で契約や決定をしない、を徹底してください。
特に「今日契約すれば間に合います」「今すぐ決めないと損します」と急かしてくる相手は要注意です。
重要な決定ほど一旦持ち帰って熟慮し、第三者の意見も聞いてから判断する習慣をつけましょう。
また、公的機関を装う人物からの連絡で怪しいと感じたら、相手にせず直接所管官庁や労働局等に問い合わせて真偽を確かめることも有効です。
4. 社内教育と内部牽制
経営者だけでなく社員にも助成金詐欺の手口や注意点を周知しておきましょう。
特に総務・経理担当者は怪しい連絡を最初に受ける可能性が高いため、「不審な勧誘電話があったらすぐ経営者に報告する」「怪しいメールは開かない」といったルールを設けておくと安心です。
また、社内で助成金申請プロジェクトを進める際も、複数人で内容をチェックし合う仕組み(四つ目の原則)を取り入れれば、不正やミスの発見につながります。
ワンマン経営者が独断で進めてしまうとブレーキが利かなくなるので、社員からの進言にも耳を傾ける姿勢が大切です。
基本対策としては、「公式情報の確認」「信頼できる専門家の活用」「即断即決しない慎重さ」「社内での情報共有」の4点に集約されます。
特別なことではありませんが、これらを怠らないだけで詐欺被害に遭う可能性は格段に減らせます。
助成金申請時のチェックポイント
実際に助成金の申請を行う際には、以下のポイントをチェックして進めることで不正やトラブルを未然に防げます。

公募要領・支給要件の遵守
提出前に応募要件・支給要件を満たしているか最終確認しましょう。
当たり前のようですが、要件に合致しない申請は通りませんし、無理に通そうと虚偽を書くのは論外です。
公募要項やガイドラインを熟読し、自社がクリアしている条件・不足している条件を整理してください。
申請書類の正確性
申請書の記載内容や添付書類に誤りや漏れがないか、ダブルチェックが必要です。
数字の計算違いや書類不備は不支給の原因に。
第三者の目で確認してもらうか、チェックリストを作って項目ごとに確認すると良いでしょう。
提出前に写しを控えとして保管し、いつ何を提出したか記録に残すことも重要です。
申請代行者の信頼性確認
申請代行やコンサルタントに依頼する場合、その業者の信頼性を十分確認しましょう。
前述の通り資格や実績がポイントです。契約書には成果報酬や守秘義務の取り決めが明記されているか、不自然な条項がないかを確認してください。
着手金無料を謳いながら異常に高い成功報酬を要求するような業者は避けるべきです。
また、「書類はこちらで用意するのでハンコだけ押しておいてください」といった依頼にも注意が必要です。
自社名義で出す書類は自社でも内容を把握しておかないと、後で何を書かれていたか分からず困る事態になりかねません。
不明点は確認・相談
書類作成や手続きで不明な点があれば、自己判断せずに必ず問い合わせましょう。
補助金・助成金ごとに設置されている問い合わせ窓口や地域の中小企業支援センターなど、公的な相談先を活用してください。
曖昧なまま提出してしまうと、後日修正や追加提出を求められ手間が増えますし、間違った情報では審査にも通りません。
役所の担当者に直接質問するのは気が引けるかもしれませんが、適切に利用すれば親切に教えてくれるものです。
社内承認プロセス
助成金申請は会社にとって重要な活動なので、社内で経営陣の承認を経てから実行しましょう。
経営者自身が申請を進める場合でも、念のため役員や顧問などに目を通してもらうことで、不備の指摘やリスクの洗い出しが期待できます。
「自分一人で全部やる」より「他の人にもチェックしてもらう」ほうが安全です。
以上のチェックポイントを守って申請すれば、よほどのことがない限り不正受給に手を染めることは避けられるはずです。
助成金受給後のフォローと管理
助成金は受給して終わりではなく、その後のフォローと適切な管理が求められます。
受給企業として守るべきポイントを押さえておきましょう。
実績報告と監査への備え
多くの助成金・補助金では、資金を受け取った後にその使途や事業成果を報告する義務があります。
定められた期限までに「何にいくら使い、どのような成果が得られたか」をまとめた実績報告書を提出しなければなりません。
これを怠ると最悪の場合助成金の返還指示を受けたり、次回以降の応募資格を失ったりするので注意しましょう。
報告書作成のためにも、日頃から証拠資料を整理保管しておくことが大切です。
領収書や契約書、工事写真、出勤簿など、助成事業に関連する記録類は一定期間きちんと保存してください。
助成金の適正な使用と記録
を心がけること。助成金は交付決定を受けた事業計画の範囲内で使用しなければなりません。
受給後に「使い道が余ったから別のことに流用しよう」などと考えるのは厳禁です。
当初計画と支出内容が大きく変わる場合は、事前に担当窓口へ相談して許可をもらう必要があります。
勝手な判断で用途変更すると不正使用とみなされるリスクがあるので、計画通りに資金を使うよう徹底しましょう。
監査への備え
助成金によっては後日、監査や検査が入ることがあります。
特に金額の大きい補助金では数年後に会計検査院の調査対象となることもあります。
突然チェックが入っても困らないよう、帳簿類や証憑類は整理された状態で保管し、担当者が変わっても引き継ぎできるようにしておきましょう。
もし書類不備や軽微なミスが見つかった場合でも、悪質なものでなければすぐに訂正報告することで大事に至らないこともあります。
大切なのは「隠さない」姿勢です。
不正が疑われるとかえって調査が厳しくなりますので、ミスは正直に報告・修正し、適切な対応に努めましょう。
受給した助成金で実施した事業の成果を最大化
せっかく得た支援金ですから、それを活用して業績向上や生産性アップといった目に見える結果を出すことが理想です。
助成金を有効活用できれば会社の成長につながり、次回以降も正々堂々と助成金に応募しやすくなります。
受給後も気を緩めず計画を遂行し、得られた設備や人材をフル活用して、企業の発展に繋げましょう。
万が一被害に遭った場合の対応
どんなに気をつけていても、「巧妙な詐欺に引っかかってしまった…」という事態は起こり得ます。
万が一助成金詐欺の被害に遭った場合、あるいは不正受給に手を染めてしまった場合の対応策を確認しておきましょう。
速やかに関係機関へ相談
詐欺被害に気づいたら、一人で抱え込まず速やかに警察や行政機関に相談してください。金銭を騙し取られた場合は迷わず警察に被害届を出しましょう。
詐欺グループの口座が凍結され、被害金が一部でも戻ってくる可能性があります。
また、所管の役所(経産省や労働局など)にも事情を説明し、指示を仰ぐことが大切。
不正受給に関与してしまった場合でも、早めに自主的に申し出て返還すれば、行政処分が軽減される可能性もあります。
発覚を恐れて隠すほど状況は悪化するので、誠意をもって対応しましょう。
証拠の確保
詐欺業者とのやり取りの証拠(契約書、メール、支払い記録など)があれば可能な限り確保しておきます。
これらは警察への提供資料や後日の法的手続きで重要な証拠となります。
電話での会話内容も、思い出せる限りメモに残しておきましょう。
また、不正申請の書類コピー等も捨てずに保管し、専門家に見せてアドバイスを受けることをお勧めします。
クーリングオフの検討
詐欺まがいの有料サービス契約を結んでしまった場合、契約日を含めて8日以内であればクーリングオフ(無条件解約)が可能なケースがあります。
例えばセミナー会場で高額な情報提供サービスに加入してしまったような場合は、「特定商取引法」に基づき書面でクーリングオフを申し出ることで契約解除できる可能性があります。
契約書にクーリングオフに関する記載がないか確認し、該当しそうであれば早急に手続きを取りましょう。
被害に気づいたのが遅れた場合でも、中途解約や返金交渉の余地がないか、消費生活センター等に相談してみてください。
再発防止策の検討
被害に遭った原因を分析し、今後同じ轍を踏まないよう社内体制を見直します。
例えば「担当者が一人で判断してしまっていた」「公募情報のチェックを怠っていた」などの要因が見つかれば、それを改善するルールや仕組みを作りましょう。
社員教育を強化することも有効です。痛い経験を教訓に、次からは決して騙されないという強い意志で臨むことが大事です。
被害回復には時間と労力がかかりますが、決して泣き寝入りせずにできる限りの対応を取りましょう。
同時に、精神的なケアも忘れずに。不正に加担してしまった罪悪感や、騙された悔しさで落ち込むかもしれませんが、速やかに対処すれば立ち直るチャンスはあります。
必要に応じて専門家(弁護士など)に依頼しつつ、被害の拡大防止と再スタートに向けた行動を起こしてください。
まとめ:助成金詐欺は倒産につながる恐れもある
助成金は中小企業の成長を支援する貴重な制度ですが、不正受給や詐欺に巻き込まれると、企業の存続を揺るがす大きなリスクとなります。
不正が発覚すれば、助成金の全額返還に加えて高額なペナルティが課され、企業の信用も大きく失墜します。
場合によっては取引先や金融機関からの信頼を失い、資金調達が困難になり倒産に至るケースもあります。
助成金を活用する際は、公式情報を確認し、不審な勧誘や代行業者には慎重に対応することが重要です。
また、社内でのチェック体制を整え、適正な手続きで申請・受給することが、企業の健全な成長につながります。
甘い話に惑わされず、正しい知識と対策をもって助成金を活用しましょう。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら