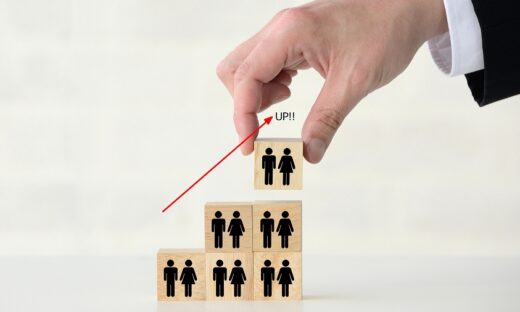自主性のある部下を育てるには?自主性のある部下が会社にもたらす大きなメリットを解説
中小企業において、部下が自ら考え行動できる「自主性」は組織力を高める重要な要素。
部下の自主性を伸ばせば業務効率やチームワーク、生産性に大きなプラス効果が生まれます。
ビジネスにおける自主性の意味を、自発性・自律性との違いも交えながら解説し、自主性がある社員の特徴や自主性が欠けた場合の失敗例、そして自主性の高い部下が会社にもたらすメリットをご紹介します。
目次
自主性とは?自発性・自律性との違い
自主性の意味(ビジネスにおける定義)
「自主性」とは、他人に依存せず自分で考え判断して行動できる性質を指します。
端的に言えば、「誰かに指示されなくても、自ら率先して動ける態度」のこと。
ビジネスの現場で「部下の自主性に任せる」と言う場合、基本的な意味に加えて「会社の定めたルールに従い、自分から進んで業務を行うこと」というニュアンスになります。
例えば「始業・終業時のあいさつをする」という社内ルールがあれば、上司に言われずとも自分から明るく挨拶をする、「来客対応は新人が行う」という決まりがあれば、指示されなくても来客に気づいてお茶出しをする、といった行動です。
このように決められた役割や規則を理解したうえで自主的に動けることがビジネスにおける自主性の要点です。
上司が細かな指示を出さなくても、会社や法令のルールに則って率先行動してくれる部下は「自主性がある」と評価されます。
自発性との違い
自主性とよく似た言葉に「自発性」があります。
自主性の場合、行動の理由(動機づけ)は自分の内側にあっても外部にあっても構いません。
例えば「会社の目標達成のために上司に言われる前に動く」というのも自主的行動に含まれます。
一方、自発性の場合は必ず自身の内部に動機や理由があることが前提です。
言われなくても行動する点は共通しつつ、「自主性」は目的が外部から与えられた場合でも発揮されうるのに対し、「自発性」は自分がやりたい・やるべきと感じたから動くという違いがあります。
つまり自主性は課せられた課題に対して率先して動くこと、自発性は自ら見つけた課題に基づいて動くことと整理できます。
自律性との違い
自律性とは「外部からの支配や制御を離れて、自分で立てた規範に従って行動すること」を意味します。
ビジネスでも概ね同様で、自分自身で目的や基準を定め、それに沿って業務や学習を進められる能力を指します。
就業規則など最低限のルールは守りつつも、より個人の意思決定を重んじて主体的に動く考え方が自律性。
したがって、必要とあらば既存ルールを改善したり自分の裁量で方針を決めたりする余地を許容する点が自主性との違いと言えます。
自主性は定められたルールの範囲内で率先行動する姿勢ですが、自律性は自分で定めたルールや価値基準に従って行動するため、場合によっては「このルールは非効率だから見直すべきだ」と提案するような規範からの一定の逸脱や本人の決定を尊重する面が強いのです。
近年では「自律型社員」「キャリア自律」といった言葉で、社員が自分のキャリア目標を定めて能力開発に取り組むような文脈でも使われます。
主体性との違い
自主性は目の前の業務を能動的にこなす力、主体性は自ら目標を定め周囲を巻き込んで推進する力といったニュアンスの違いがあります。
自主性だけでは与えられたことには積極的でも全体最適を考える意識が弱かったり、主体性だけでは立派な計画を立てても行動に移すスピードが遅れたりするため、ビジネスでは自主性と主体性のバランスが重要と言われます。
自主性がある部下の特徴
自主性が高い社員には共通して見られる行動傾向があります。
その代表的な特徴を5つ確認してみましょう。
どれも企業にとって好ましい資質であり、こうした傾向を持つ部下が増えれば組織の力は一層強化されます。
①率先して行動する
自主性のある部下は、常に指示を待たず自ら率先して動く姿勢を持っています。
与えられた役割や会社のルールを正しく理解しているため、状況に応じて何をすべきか自分で判断し、素早く行動に移せます。
言い換えれば、「今○○するのが会社にとって必要だ」と気づけば上司の指示を仰がず実行に移せるのです。
例えば工場現場で自主性の高い作業者は、機械の点検や清掃など決められた日課を言われなくても時間通りに行い、不具合に気づけば即座に対応します。
もし判断に迷う場合も、そのまま止まって指示を待つのではなく、一旦自分で考えた上で上司や先輩に相談して解決策を探ることができます。
このように率先して動く人は経験を重ねるごとに対応力が増し、ますます主体的に仕事を進められるようになります。
②責任感が強い
自主性がある人は任された仕事を最後までやり遂げる責任感を持っています。
途中で投げ出せば周囲に迷惑がかかることを理解しているため、「自分の役割は必ず果たす」という意識が高いのです。
基本的に、自分の権限範囲でできることは最大限に活用し、粘り強く取り組みます。
たとえ難しい課題が与えられても安易に諦めず、今持っている知識やスキルを応用したり、周囲に助力を求めたりしてでも目標達成を目指そうとします。
例えばサービス業の現場でクレーム対応という困難な任務を任された場合でも、自主性のある部下は逃げずに真摯に対応策を模索し、必要に応じて上司にアドバイスを仰ぎつつ最後まで解決に当たるでしょう。
こうした責任感の強さがあるからこそ、安心して仕事を任せられるのです。
③探究心が旺盛である
自主性のある部下は課題解決に向けた探究心も旺盛です。
難しい問題に直面しても「もうダメだ」とすぐ諦めるのではなく、「どうすれば解決できるだろう?」と積極的に考えます。
その際、現状のやり方に固執せずトライ&エラーで様々な方法を試してみる柔軟さがあります。
基本的にポジティブ思考で、失敗を過度に恐れません。
「失敗は成功に向けたプロセスの一部に過ぎない」という認識があるため、自主性が高い人ほど挑戦を躊躇しないのです。
例えば、新しいITシステム導入でトラブルが起きても、自主性のある担当者は「なぜエラーが出るのか」「他に方法はないか」を粘り強く調べ、必要ならベンダーに問い合わせるなど解決策を探ります。
逆に自主性のない人なら「もう無理です」と早々に手を止めてしまうかもしれません。
探究心を持って最後まで粘り強く解決に挑む姿勢は、自主性の高い人材に共通する特徴です。
④成長意欲が高い
自主性がある人は総じて自己成長への意欲が高く見られます。
与えられた課題に積極的に取り組む過程で新たな知識やスキルを身につけることに喜びを感じ、もっと成長したいという意志を強く持っています。
例えば業務時間外や合間にも関連分野の情報収集をしたり、必要とあれば社内外の研修に自主的に参加したりする人もいます。
また、自分の成長につながる助言であれば素直に受け入れ、失敗しても「次はどう改善できるか」を前向きに考えて行動に移す傾向があります。
このような姿勢により知識・スキルは着実に向上し、それがさらに業務の円滑化や成功体験となって本人の自信を育みます。
小さな成功体験の積み重ねが「もっと成長しよう」という意欲を一層高める好循環を生み出し、結果として組織に貢献できる人材へと成長していくのです。
⑤適度な自信とポジティブな姿勢
自主性のある人は、過去の挑戦と成功体験、周囲への貢献の積み重ねから健全な自信を身につけています。
自分の行動が周りに良い影響を与え感謝された経験や、小さなことでも「自分から行動してやり遂げられた」という実感が自信の源になっています。
こうした成功体験の積み重ねによって、「頑張れば達成できる」「自分には力がある」という前向きな感覚が育まれます。
そのため、一度や二度の失敗ではくじけません。
上司や同僚から提案に対して指摘を受けても、それを攻撃とは捉えず「より良くするためサポートしてくれているのだ」と前向きに解釈できる余裕があります。
このようにポジティブな循環を自ら生み出せる人こそ、真に自主性がある人と言えるでしょう。
自信に裏打ちされた余裕があるので、多少の逆風でもぶれず、自発的な提案や改善行動を継続できるのです。
自主性がない部下に見られる問題点・失敗例
一方で、部下の中には自主性が欠けているために仕事上のミスや停滞を招いてしまうケースも。
自主性がない人材に共通しがちな消極的・否定的な傾向を理解し、失敗の原因を把握しておくことも重要です。
ここでは自主性が不足している部下によく見られる3つの問題点を紹介します。
問題点①:組織のルールを軽視してミスを招く
自主性に欠ける人は社内ルールの順守意識が低く、「決まりごとなんて面倒だ」「時代遅れだ」と否定的に考えがち。
ルールの目的や必要性を理解しようとしないため、「○○してはいけない」「必ず△△する」といった決まりを定めても現場に定着しにくく、結局大事な手順を怠ってミスやトラブルを招いてしまいます。
例えば情報管理のルールを軽視して個人情報を私用で持ち出し漏洩させてしまう、製造工程の安全手順を守らず事故を起こしてしまう、など組織の秩序を乱す結果につながります。これは本人に悪意がなくても、「なぜそのルールがあるのか」を理解しようとしていないがゆえに起きる失敗です。
自主性がない部下ほど、「守るか無視するか」といった極端な発想になりやすく、ルール遵守の重要性やその背景にある目的に思い至らないためミスを繰り返してしまいます。
問題点②:責任感が希薄で他責傾向がある
自主性がない部下は任された仕事に対する責任感が乏しい傾向があります。
そのため、いざ問題やミスが発生すると自分に非があったとは考えず、何か別の要因や他人のせいにしようとしがちです。
いわゆる「他責志向」で、「自分は悪くない、◯◯が悪い」と責任転嫁してしまいます。
これは普段から流されるまま受け身で行動し、「なぜこれをやるのか/やらないのか」という目的意識を持っていないことが原因です。
目的を理解せずに仕事をしているため、自分のやり方が誤っていた場合でもなぜ注意されたのか分からず、上司に指摘されても素直に受け止めず反発したり、その場しのぎの謝罪で済ませようとしたりすることも。
納期遅延を起こして叱責された際、「他の部署が資料をくれなかったからだ」などと言い訳ばかりして自分の計画ミスを認めない、といったケース。
こうした態度では周囲からの信頼も得られず、ますます重要な仕事を任せてもらえなくなる悪循環に陥ります。
問題点③:学習意欲が低く自己成長に投資しない
自主性のない人は、業務スキル向上や自己研鑽に対して消極的で、「どうすればできるようになるか」よりも「いかに手間や苦労を避けるか」に関心が向いてしまう傾向があります。本来、成長のためには失敗経験を分析したり、行動や考え方を改善したりといった地道な取り組みが不可欠ですが、そうした「面倒くさいこと」を敬遠しがち。
新しい業務システムを学ぶ社内研修があっても、「忙しいから」と自主的に参加しようとしなかったり、参加しても積極的に吸収しようとしなかったりします。
また、上司から業務改善の提案を求められても、「余計な仕事が増えるだけだ」と前向きに捉えられません。
学びの目的や必要性を考えず、努力すること自体を損だと感じてしまうために、結果として本人の成長が止まってしまいます。
企業側が研修機会を与えても活かさないため、スキル不足が解消せず業務の質も上がらない、といった悪影響があります。
自主性のある社員が増えることによる4つのメリット
以上に見てきた自主性のある人・ない人の傾向から明らかなように、社員の自主性が高まることは企業に大きなメリットをもたらします。
自主性のある社員が増えれば、組織全体で次のような良い効果が生まれるでしょう。
メリット①:組織の規律・秩序が保たれる
自主性とは前述のとおり「定められたルールに納得し率先して行動する姿勢」です。
自主性を身につけた社員が増えるほど、社内全体で決められた規則がきちんと守られ、秩序だった業務運営を実現できます。
例えばコンプライアンスに関するルールを整備すれば、自主性の高い社員たちはその趣旨を理解した上で率先遵守し、情報漏洩などのリスクを未然に防いでくれます。
個人情報を私的に持ち出して外部送信するといった愚行は、自主性ある社員なら「会社の信頼と社員・顧客を守るルールだ」と理解しているので決して行いません。
また、休暇制度の適切な活用やハラスメント防止策の順守なども推進され、安心して働ける職場環境につながるでしょう。
このように、一人ひとりが主体的かつ規律正しく行動すれば、管理側が目を光らせなくとも組織全体の秩序維持が容易になります。
メリット②:社員の成長スピードが速くなる
自主性のある社員が増えると、社員それぞれの成長スピードが格段に速くなります。
多くの企業では社員のスキルアップのため定期的に研修を行いますが、自主性の高い社員は研修の目的や自分に求められる役割・スキルをきちんと理解しようと努めます。
自分の役割と「あるべき姿」に納得感が生まれれば、そうでない社員よりも積極的に学習に取り組み、吸収も早くなるでしょう。
結果として若手社員の即戦力化が進み、組織全体で学び続ける文化が育まれます。
例えば先輩社員や上司が自主的に社外セミナーに参加して知見を広げていれば、その姿が後輩の手本となりノウハウ共有にもつながります。
新人も刺激を受けて積極的に学ぶようになり、次世代の成長も加速していくでしょう。
このように自主性が組織に浸透すれば、社員一人ひとりの成長曲線が上向きになり、結果的に企業全体の人材レベル向上につながります。
メリット③:チームワークが向上する
自主性のある社員が多い職場では、チームワークが発揮されやすくなります。
自主性が高い人は定められた業務フローや方針に沿って積極的に活動するため、「自分さえ良ければそれでいい」という独善的な考え方をしません。
常に「チーム全体で目標を達成しよう」という視点で行動できるので、困っているメンバーがいれば自分のことのようにサポートし、自分が壁にぶつかった時には素直に周囲へ助けを求めることもできます。
要するに、自主性がある社員が増えるということはチームの方針・目標を理解して周囲と連携できるメンバーが増えるということ。
プロジェクトチーム内で、各自が与えられた役割を主体的に果たしつつ互いにフォローし合えば、チーム全体として高い成果を出せます。
心理的安全性も確保され、活発なコミュニケーションによって新しいアイデアも生まれやすくなるでしょう。
自主性ある人材は協調性も高めるため、「自立しつつ協働できる組織」を作る土台となります。
メリット④:組織全体の生産性が向上する
自主性のある社員が増える最終的なメリットとして、組織全体の生産性向上が挙げられます。
前述のようにチームワークが良くなることで組織内の連携が強まり、一体感を持って業務に当たれるようになります。
加えて、自主性の高い社員は自己成長にも意欲的なので、それぞれのスキルが向上しながら互いに協力し合えば組織全体のパフォーマンスが底上げされます。
自主性がある社員は既存ルールが生産性のボトルネックになっていると感じた場合、改善提案を行うことも可能です。
ルールの目的を理解しているからこそ「どう改善すれば組織のためになるか」を主体的に考え、上申できるのです。
現場の自主的な提案で無駄な承認プロセスを簡素化できれば業務スピードが上がり、結果として売上や利益の向上にもつながるでしょう。
社員一人ひとりが成長し、協働し、主体的に業務改善にも取り組む——そんな自主性に満ちた集団は、生産性の高い強い組織と言えます。
部下の自主性を高め育成する方法
それでは、経営者や管理職として具体的にどのように部下の自主性を育てればよいのでしょうか。
【自社の理念や方針はしっかり伝えているだろうか?】【部下への指示の出し方は適切だろうか?】など、振り返るべきポイントはいくつかあります。
ここでは、部下と接する際に管理職が意識すると良い5つのポイントを紹介します。
①組織の理念・目標と部下に期待する役割を明確に伝える
まず基本として、会社の理念や目標を各社員がきちんと理解していることが重要。
全てのルールや業務指示はその理念・目標を達成するために存在するので、根幹となる目的意識を共有することが自主性育成の出発点になります。
社員が「なぜこのルールがあるのか」「この目標を達成すると会社にどんなメリットがあるのか」といったことを腹落ちすれば、自分の判断で行動するときも組織の方向性から大きく外れることはなくなるでしょう。
また併せて、各メンバーに対して会社や上司が期待している役割を具体的に伝えることも大切。
「あなたは組織の中でこういう立場で、これこれの分野で貢献を期待している」というメッセージを明確に伝えれば、部下は自分の立ち位置を自覚し「自分は組織の一員だ」という実感を持ちます。
その結果、与えられた役割を主体的に果たそうという意欲につながります。
製造業で現場リーダーに抜擢された社員には、「あなたの現場での安全管理への取り組みが会社全体の品質向上に直結する」と伝えることで、自覚と責任感を持って自主的に行動してもらいやすくなります。
②ルールの目的・意義を部下に説明する
社の理念・目標が腹に落ちると、現場レベルでも日々の業務ルールの理解が深まり自主的な順守が促進されます。
上から「あれを守れ、これをやれ」と言うだけではなく、「なぜそのルールが必要なのか」「守ることで会社にどんなメリットがあるのか」をきちんと部下に説明しましょう。
ビジネスマナー研修一つ取っても、「決められた挨拶や身だしなみを守りなさい」ではなく、「なぜそれが必要なのか」を教えることで納得して身につけさせることができます。
ルールに目的があると理解すれば、人は自発的にその習得に努めるものです。
社内規程についても同様で、「この規則を守れば会社の安定経営や売上向上にどう寄与するか」をイメージできるように伝えましょう。
「顧客情報を社外に持ち出してはいけないのは、紛失・盗難・ウイルス感染による漏洩を防ぎ、お客様に安心して取引いただくためだ」と説明すれば、そのルールの重要性を理解してもらえます。
部下自身がルールの意義に納得できれば、「言われたから守る」ではなく「組織のために自分から守る」という自主的な行動に変わるのです。
③部下が「手を挙げる」機会を増やす
部下の自主性を高めるには、自主性を発揮できる場をできるだけ多く設けることも重要です。
社員が受け身になりがちな職場では、そもそも自主性を発揮するチャンスがないままになっていることがあります。
そこで、部下が「自分から手を挙げる」場を意図的に作りましょう。
研修やセミナーへの参加の募集、社内公募制のアイデアコンテスト、新規プロジェクトチームへの立候補機会などです。
「新規商品アイデア募集」を社内で定期的に行えば、普段指示待ちだった部下も自ら考えて提案する場ができます。
また「この研修に参加したい人?」と手を挙げさせる方式で社外セミナー等への派遣機会を提供すれば、名乗り出た社員は主体的に学ぼうとするでしょう。
最近では大企業を中心に社内起業制度や業務改善提案制度を導入し、社員の主体的チャレンジを奨励する例も増えています。
実際、サントリーでは「やってみなはれ」の社是のもと新しい発想で挑戦した活動を表彰する制度を設けたところ、世界中から483チームもの応募があり自主性を発揮しながら新たな価値を創出する文化が根付いています。
中小企業でも社内LT大会(ライトニングトーク)や小集団改善活動など、規模に応じた形で構いませんので、部下が自主的に手を挙げられる場を用意することが大切です。
④過剰な指示を出さず自律性を尊重する
部下の成長を願うあまり、上司が何でも細かく指示しすぎることは自主性育成の妨げになります。
常に手取り足取り指示を出してしまうと、部下は「言われたことをそのままやる」経験しか積めず、自分で考えて物事を進める機会が失われてしまいます。
その結果、「どうせ上司が指示してくれるから」と待ち姿勢が染みつき、いわゆる“指示待ち人間”になってしまう恐れがあります。
したがって、部下にはある程度自分で考えさせる余白を与えることが必要です。業務の進め方について最低限の方向性だけ示したら、細部は部下に任せてみましょう。
「もし困ったら相談しなさい」と伝えておけば部下も安心して取り組めます。
実際、スターバックスコーヒージャパンではドリンク品質に関するルールは厳格に定めつつも、接客についての細かいマニュアルはあえて策定せず従業員に現場判断の権限を与えています。
マニュアルで縛らずミッション(顧客満足)に従って各自が考えて行動することを推奨しており、新人研修でも上司から細かい指示を出さず従業員自身が「どうすべきか」を考えて実践する教育を行っています。
このように自由裁量の範囲を持たせることで、社員の主体的な工夫や判断力が磨かれるのです。
もっとも注意したいのは、自主性を尊重するあまり業務を丸投げして放置してしまうこと]。上司が全く状況を把握しないままだと部下は相談もしづらく、サポートも評価も得られず不安・不満を抱えてしまいます。
上司への信頼感が薄れモチベーションが下がる恐れもあるでしょう。
したがって、「任せる」と決めた後も適度なコミュニケーションと進捗確認は継続し、必要に応じて助言・支援することが重要です。
⑤部下の成果を認め前向きなフィードバックをする
自主性を高める取り組みを進める中では、部下の頑張りや成果をきちんと承認しフィードバックすることも忘れないようにしましょう。
部下が自主性を発揮するには「自分には能力がある」「やればできる」という自己効力感が不可欠だからです。
上司から見て良い行動や成果があったときはタイミングよく褒めたり感謝を伝えたりして、本人に成功体験として実感させましょう。
効果的なのは、日々の業務でうまくいったことや良い影響を及ぼした行動を積極的に称えることです。
例えばOJTでの定期面談では、目標達成度や課題点を確認するだけでなく「今回ここがうまくできていた」「以前より成長している」といった成功ポイントの振り返りを必ず行います。
こうすることで部下本人が自分の進歩を自覚し、「次も頑張ろう」というポジティブな意欲につなげる狙いです。
小さなことであっても上司に認められる経験が自信につながり[80]、その自信がさらなる挑戦と成長の原動力となります。
仮に部下が失敗した場合でも頭ごなしに叱責するのではなく、「次に活かすとしたらどうする?」と一緒に原因と改善策を考え前向きなフィードバックをしましょう。
そうすることで、部下は安心して再挑戦できる雰囲気が生まれます。
上司の適切な承認とフィードバックは、部下の自主性を育てる大きな後押しになるのです。
社外研修のススメ
社外研修とは、社外の専門機関や講師が実施する研修やセミナーに社員を参加させる取り組みのこと。
社内研修との違いやメリットを理解し、ぜひ積極的に活用してみてください。
普段と違う環境でリフレッシュして集中して学べる
社外研修は日常業務から離れた外部会場やオンライン上で行われるため、社員にとっていつもと違う新鮮な環境で学ぶ機会になります。
職場を離れることで適度な緊張感とリフレッシュ効果が得られ、研修内容に集中しやすくなると言われます。
また、社内の上司ではなく外部のプロ講師が教えることで、社員もより真剣に耳を傾け主体的に参加しやすくなります。
「仕事の延長」のように感じがちな社内研修に比べ、非日常感のある場でモチベーション高く学べるのが社外研修の大きな魅力です。
専門家の指導で新しい知識・スキルを習得できる
社外研修では各分野の専門家・プロフェッショナルから直接指導を受けられるため、社内では得られない高度で専門的な知識やスキルを身につけることができます。
自社にはないノウハウに触れることで社員の視野が広がり、新たな発想や業務改善のヒントを得る良い機会にもなります。
例えば最新のIT技術動向やマーケティング手法など、外部の詳しい講師だからこそ提供できる学びがあります。
そうした知見を社内に持ち帰って共有してもらえば、組織全体の知的資産も増えるでしょう。
レベルに応じたカリキュラムを外部研修会社が用意してくれるため、社員それぞれに合った内容で効率的にスキルアップさせられる点もメリット。
専門家から刺激を受けて社員が成長すれば、自主的に業務を工夫・改善する力が高まり組織に貢献してくれるようになります。
新たな価値観や刺激との出会いで意識が変わる
社外研修では自社の常識とは異なる多様な価値観や手法に触れることができます。
社内では得られない刺激を受けることで、社員の意識改革につながる場合も。
異業種の参加者とのディスカッションを通じて、「他社ではこんな工夫をしているのか!」と気づきを得たり、自分の業務を客観視するヒントを得たりできます。こうした経験は社員にとって大いに刺激となり、「もっと学びたい」「自分も何か改善提案してみよう」という自主的な意欲を引き出すきっかけになるでしょう。
実際、外部の全く違う環境での学習体験は社員の視野を一気に広げ、柔軟な発想や問題解決能力の向上に寄与するとの指摘があります。
社外の空気に触れて得た新鮮な学びや価値観は、社員のマインドセットを前向きに変える起爆剤となり得るのです。
社外での交流によって人脈が広がり新たなチャンスが生まれる
社外研修は他社の受講者や講師との交流の場でもあります。
社員にとっては社内だけでは築けないネットワークを広げる貴重なチャンス。
研修先で知り合った他社の同世代社員と情報交換する中で刺激を受け、互いに切磋琢磨する関係が生まれるかもしれません。
また、そうした人脈が将来的に新たなビジネスチャンスやコラボレーションにつながる可能性も。
異業種交流型の研修で顔見知りになった人と後日ビジネスで協業するケースも実際に見られます。
社内の狭い人間関係に留まらず社外に目を向けさせることで、社員の視座が高まり自主的な挑戦心がさらに養われる効果も期待できます。
終わりに
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
※助成金には人材育成のための研修に充当できるものも含まれます。
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら