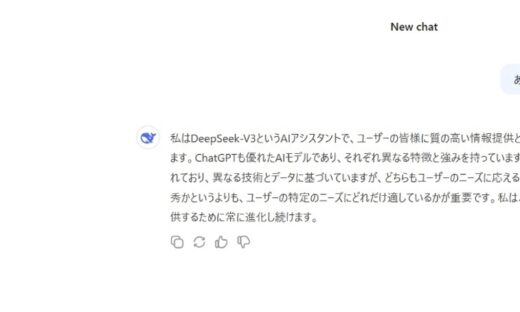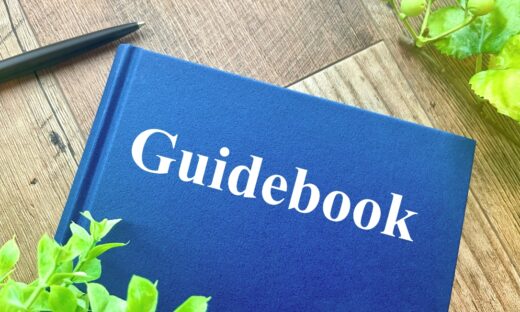助成金の申請準備にはどのくらいかかるの?安心して申請するために必要な期間を解説

助成金の申請を検討する際、「準備にどれほど時間がかかるのか?」と不安に思う中小企業経営者の方も多いでしょう。
本記事では、雇用関係の助成金(キャリアアップ助成金、トライアル雇用助成金など)を例に、申請準備に必要な期間や具体的なスケジュール、注意点を詳しく解説。
事前準備の内容やスケジュール例、社労士への依頼判断、不支給リスクの回避策、申請後の流れまで網羅し、経営者の皆様が安心して助成金申請に臨めるよう実務的なアドバイスをお届けします。
計画的な準備で助成金を有効活用し、自社の発展につなげましょう。
目次
助成金申請の全体像
助成金制度の概要と特徴
「助成金」とは、国や自治体が企業の取り組みを支援するために交付する返済不要の資金です。
特に厚生労働省管轄の雇用関係助成金は、人件費の補助や職場環境の改善など、中小企業の経営課題解決に役立つ制度が揃っています。
助成金は要件を満たせば基本的に受給できるもので、事業計画の審査がある補助金とは異なり、原則先着順・条件重視の支援策です(募集期間や予算に限りがある点には注意)。
ただし、その分各制度ごとに細かな条件が定められており、要件を一つでも満たさないと受給できません。
助成金制度は毎年度内容が変更されることも多く、最新情報の確認が必須。
中小企業の強い味方ではありますが、申請には複雑な手続きや多くの書類準備が伴うため、初めての方にはハードルが高く感じられることもあります。
雇用関係助成金の目的とメリット
雇用関係助成金の目的は、企業の雇用創出・人材育成や働きやすい職場環境づくりを促進することにあります。
例えばキャリアアップ助成金は非正規社員の処遇改善(正社員化や賃金アップ等)を支援し、人材定着を図る制度です。
一方、トライアル雇用助成金は、経験不足等で就職困難な求職者を試行的に雇用する企業を支援し、ミスマッチ防止と採用機会の創出を目的としています。
これらの助成金を活用することで、企業は人材確保や定着、育成といった課題解決に取り組みつつ、費用面の支援を受けられるメリットがあります。
例えば人件費負担の軽減や研修費用の補助などにより、中小企業でも前向きな人事施策を実施しやすくなるでしょう。
また助成金は返済不要かつ使途が比較的自由なので[10]、受給できれば企業の資金繰りにもプラスになります。
ただし、「もらえるからやる」という姿勢ではなく、自社の課題解決策の一環として助成金を手段として活用することが重要です。
助成金申請の基本ステップ
助成金申請の流れは、大まかに(1)情報収集と制度選定 → (2)計画書等の事前準備・提出 → (3)計画の実行 → (4)支給申請書類の作成・提出 → (5)審査・支給という段階に分かれます。
まず自社の状況や目的に合った助成金を探し(例えば「従業員を正社員登用したい」「新たに人材を試行雇用したい」など具体的目的に応じて選定)、該当助成金の募集期間や要件を確認します。
次に、多くの助成金で求められる事前の計画届を作成・提出します。
これは「○月○日に制度を導入します」「△月から研修を開始します」等の計画を事前に届け出るもので、取り組み開始“前”に提出しなければ受給できないケースが多い点が特徴です。
計画届を提出し行政の認定を受けたら、実際に社内でその計画どおりに制度の実施や雇用活動を行います。
例えば就業規則を改定して正社員転換を実施したり、試行雇用者を実際に雇用して一定期間働いてもらう段階。
取り組み完了後は、遅れないよう支給申請書類一式を準備して提出します。
提出期限は助成金ごとに厳格に定められており、「取り組み完了から◯ヶ月以内」と短めに設定される場合が多いので絶対に守る必要があります。
最後に、提出後は労働局等での審査を経て問題なければ支給決定通知が発行され、指定口座へ助成金が振り込まれます。
以上のように、書類提出だけでなく事前計画・実施・証拠収集・本申請・審査といくつもの段階がある点を押さえておきましょう。
申請準備に時間をかけるべき理由
助成金申請では「申請前の準備が9割」と言っても過言ではありません。
細かな支給要件の確認や自社状況の整備、複数の書類作成など、事前準備に相応の時間と労力を要するためです。
特に初めて申請する場合、要件の読み違いや書類不備が起こりやすく、それを避けるためにも早め早めの準備が肝心です。
例えば「計画書の提出をうっかり忘れて取り組みを始めてしまった」「必要な就業規則の整備に時間がかかり締切に間に合わない」といった失敗例も少なくありません。
また助成金の中には提出期間が限定されているものもあり、公募期限に間に合わなければ機会損失となります。
さらに申請には会社の基本情報や従業員データ、労務管理書類など多岐にわたる書類を揃える必要があり、一朝一夕には用意できないこともあります。
したがって、助成金の活用を思い立ったらできるだけ早く情報収集と準備に着手し、社内の関係者ともスケジュール共有しながら進めることが大切。
十分な準備期間を確保することで、安心して本申請に臨むことができ、結果として助成金を確実に受給できる可能性も高まるでしょう。
助成金申請にかかるスケジュール例
キャリアアップ助成金の申請スケジュール例
有期契約社員の正社員転換にキャリアアップ助成金(正社員化コース)を利用する場合のスケジュール例を示します。
ステップ1:制度選定と事前計画(0ヶ月目)
自社の非正規社員Aさんを正社員登用する計画を立案。
要件を確認し、キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用すると決定。
社内で計画内容を検討し、就業規則に正社員転換制度が無ければこの時点で規則改定の手続き開始。
労使協議を経てキャリアアップ計画書を作成し、転換実施日の前日までに労働局へ提出。(この準備段階に1~2ヶ月を費やすケースも)
ステップ2:非正規社員から正社員への転換実施(1ヶ月目)
計画書を提出し認定を受けた後、計画どおりにAさんを正社員登用。
新しい労働条件通知書を交わし、人事異動や研修など処遇改善策を実施。
転換日以降、6ヶ月間は引き続きAさんを雇用し、賃金を支給する。
ステップ3:実績積み上げ期間(2~7ヶ月目)
正社員転換後6ヶ月間、Aさんを雇用継続。
この間、出勤簿や賃金台帳を毎月きちんと整備し、転換前6ヶ月との賃金比較で3%以上アップしていることを確認。
計画内容どおりに研修実施など行った場合は、写真や研修記録を残しておく。
転換後半年間の最後の給与を支給したら、その翌日から申請可能になるので日付を把握。
ステップ4:支給申請書類の準備・提出(8ヶ月目)
6ヶ月の雇用実績が終わったら速やかに支給申請の準備。
会社情報や対象者情報を申請書に記載し、出勤簿・賃金台帳の写し、就業規則、労働条件通知書、転換前後の賃金比較表など必要書類を添付。
不備がないか十分チェックし、転換後6ヶ月経過日の翌日から起算して2ヶ月以内[35]に所轄労働局へ申請書類一式を提出。
※この例では転換日が1月1日なら、6ヶ月後の6月末まで雇用→7月給与支給後、9月末までに申請提出というスケジュール。
期限を1日でも過ぎると受け付けてもらえないので注意。
ステップ5:審査・支給決定(9~11ヶ月目)
労働局にて書類審査が行われる。
助成室の担当者が、就業規則や賃金台帳、出勤簿などの整合性を徹底チェックし、賃金3%アップ等の支給要件を満たしているか判断。
必要に応じて会社へ追加資料提出の依頼やヒアリング連絡が来ることもある(その場合は速やかに対応することで支給時期が遅れないようにする)。
問題なく審査が完了すれば支給決定通知書が会社宛に郵送される。
ステップ6:助成金の振込(10~12ヶ月目)
支給決定から概ね数週間~1ヶ月程度で指定口座へ助成金が振り込まれる。
キャリアアップ助成金では、申請から入金まで3~6ヶ月ほどかかるのが一般的とされています。
この例でも申請提出から振込まで約3ヶ月を要した想定です。
トライアル雇用助成金の申請スケジュール例
35歳未満の若年者を一般トライアルコースで試行雇用し、本採用する場合のスケジュール例を示します。
ステップ1:求人募集と候補者選定(0~1ヶ月目)
ハローワークにトライアル雇用求人を提出し、求職者の紹介を受ける。
面接等で適任者を選考し、試行雇用の採用を決定。
雇用条件を双方合意の上で取り決める(原則3ヶ月の有期雇用契約を締結)。
ステップ2:実施計画書の提出(採用後2週間以内)
試行雇用がスタートしたら、企業は14日以内に所轄ハローワークへ「トライアル雇用実施計画書」を提出。
計画書には事業所情報や対象者氏名、雇用期間、求人番号などを記載する。
この計画書提出を怠ると助成金対象にならないため、忘れずに対応(人の採用手続きで慌ただしい時期ですがここが重要)。
ステップ3:トライアル雇用の実施(1~3ヶ月目)
契約に基づき、試行雇用を開始。
最大3ヶ月間、対象者を社員として受け入れ、職務適性の見極めを行う。
期間中、出勤状況を管理し、少なくとも月の8割以上出勤すれば満額(月4万円)の助成金対象となる(欠勤が多いと減額)。
試行雇用期間中は通常のOJTや研修を行いつつ、適宜フィードバック面談を実施。
(この間、社内では本採用後のポジションや給与条件など受け入れ準備も進める。)
ステップ4:本採用の判断(3ヶ月目終了時)
試行期間終了時に、対象者を引き続き無期雇用(正社員等)として本採用するか判断。
双方合意の上で正社員登用とする。
仮に適性が合わず本採用を見送る場合でも助成金自体は試行雇用実施分について支給される(※ただし継続雇用しない場合、助成金名目ではなく「結果報告書」の提出のみとなり、その後別の助成金との併用など制約もある点に留意)。
ここでは本採用するケースとして話を進めます。
ステップ5:支給申請手続き(4~5ヶ月目)
トライアル雇用終了後、2ヶ月以内に支給申請書類を提出する。
具体的には「トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」に、試行雇用期間中の出勤簿や賃金台帳のコピー、本採用した場合は雇用契約書のコピーなどを添付してハローワークまたは労働局へ提出します。
書類に不備がないよう注意し、必要事項(例えば試行雇用期間や出勤率、本採用の有無など)を正確に記入します。
不備があれば労働局から補正の連絡がありますので、迅速に対応しましょう。
提出締切を過ぎると受給できなくなるため社内で期限を共有し徹底します。
ステップ6:審査・支給決定(5~6ヶ月目)
労働局(またはハローワーク)にて申請内容の確認が行われます。
対象者が要件に合致しているか、提出書類から実際に試行雇用が行われた事実が読み取れるかなどをチェック。
とくに出勤率や賃金支払い状況に問題がなければ、数週間~1ヶ月程度で支給決定通知が届きます。
ステップ7:助成金の振込(6~7ヶ月目)
支給決定後、概ね1~2ヶ月以内に指定口座へ助成金が振り込まれます。
一般的なケースでは、トライアル雇用助成金も申請から3ヶ月前後で入金が完了することが多いです。
今回は例として申請から約1.5ヶ月で入金された想定です。
振込された助成金は返済不要ですので、社員の教育訓練費に再投資するなど有効に活用しましょう。
スケジュールを立てる際のポイント
助成金申請のスケジュールを組むにあたっては、いくつか留意すべきポイントがあります。
逆算して計画する
各助成金の締切日(申請期限)から逆算し、「○月○日までに申請書提出→その前に○月○日までに実績期間終了→さらにその前に○月○日までに計画書提出…」という具合にスケジュールを引いていきます。
重要なのは、事前計画の提出期限と本申請の提出期限の二段階を見落とさないこと。
事前計画を要するものは取り組み開始前に余裕を持って届け出る必要がありますし、本申請は完了後◯ヶ月以内と短い場合が多いため前広に準備しましょう。
カレンダーに重要期限を書き込んでおく、リマインダーを設定するなど、締切厳守の体制を作ります。
特に複数の助成金を同時並行で進める場合は、それぞれのタイムラインを整理して混同しないよう注意が必要です。
繁忙期を避け余裕ある計画を
労働局の審査や手続きにも繁忙期があります。
年度末~年度始め(3~5月頃)は申請が集中し審査に時間がかかる傾向があります。
また大型連休や年末年始を挟む時期は行政機関の営業日も少なく、処理に時間を要することがあります。
そのため提出期限ギリギリではなく、できれば締切の数週間前には申請できるよう余裕を持った計画を立てましょう。
自社内でも決算時期や繁忙期と重なると申請事務がおろそかになりがち。
可能なら閑散期に準備・実施を進め、繁忙期には審査待ちの状態にしておく、といった工夫も検討してください。
担当者と役割分担
助成金申請には様々な部署の協力が必要です。
スケジュール管理のために、社内で助成金申請の責任者(プロジェクトリーダー)を決めることをおすすめします。
その人が中心となって各部署(総務、人事、経理など)から必要書類やデータを集め、全体の進捗を管理します。
定期的に社内打ち合わせを設け、誰がいつまでに何をするか明確にしておけば、締切間際に「あれが用意できていない!」と慌てる事態を防げます。
担当者はタスク管理表やチェックリストを作成し、進捗を“見える化”するとよいでしょう。
また不明点が出たら担当窓口や社労士に早めに問い合わせる段取りも決めておくと安心です。
複数制度の同時進行
会社によっては複数の助成金を同じ年度に活用することもあります。
その場合、スケジュールの重複や書類の使い回しに注意しましょう。
一部の書類(例えば就業規則や登記簿謄本など)は複数申請で共通して使えますが、提出先が違えばそれぞれに準備が必要です。
またそれぞれ計画書や申請書の提出期限が異なるため、同時並行で段取りを管理する必要があります。
混乱を防ぐために、制度ごとにフォルダやファイルを分け、スケジュール表も別々に作成して管理するのが望ましいです。
社内の人的リソースが足りない場合には、無理に同時進行せず順次取り組むか、あるいは社労士等の外部支援を活用して負担を軽減することも検討しましょう。
依頼すべきか?判断基準
自社で申請するメリット・デメリット
助成金申請は自社の担当者だけで行うことも可能です。
そのメリットは何と言っても費用がかからないことです。
社労士に報酬を支払う必要がないため、助成金を満額そのまま活用できます。
また自社で進めることでスケジュールを自由に管理できるという利点もあります。
自社の状況を一番よく理解している担当者が行えば、社内調整もしやすいでしょう。
しかしデメリットとしては、時間と労力がかかる点が挙げられます。
特に初めての場合、制度の調査や書類作成、要件確認に膨大な時間を要するでしょう。
他の業務と並行して行うには負担が大きく、申請事務に追われて本業に支障をきたすケースも。
また担当者が助成金の専門知識に乏しいと、書類の不備や要件の見落としが起こりやすく、結果として不支給や二度手間になるリスクも高まります。
さらに制度変更に対応しきれず古い情報で進めてしまうミスや、提出期限を勘違いして逃してしまうという重大な失敗も起こり得ます。
総じて、社内だけで完結させる場合は十分な時間的余裕と担当者の習熟が成功の鍵となります。
自社申請は費用ゼロで済む半面、こうしたリスクと隣り合わせである点を認識しておきましょう。
社労士に依頼するメリット
社会保険労務士(社労士)に助成金申請を依頼することで、多くのメリットを享受できます。
第一に、社労士は労働法や社会保険制度の専門家であり、助成金の申請要件を正確に把握しています。
その知識を活かして最適な助成金の選定からサポートしてもらえるため、経営者が見落としがちな制度も含め提案を受けることができます。
また、複数の助成金を組み合わせて活用する戦略なども社労士ならではの視点で示してくれるでしょう。
第二に、申請書類の作成代行による時間・労力の節約があります。
複雑な書類作成や添付書類の準備・提出を社労士が一貫して引き受けてくれるため、経営者や総務担当者はその分本業に集中できます。
特に人手の限られた中小企業では、この負担軽減のメリットは非常に大きいでしょう。
第三に、受給成功率の向上も見逃せません。
社労士に依頼すれば書類不備や要件誤解による申請ミスが大幅に減り、不支給リスクを最小化できます。
実際、経験豊富な社労士がサポートしたケースでは「自社だけでやっていたら満たせなかった要件を事前に指摘してもらい、軌道修正できた」という例も多くあります。
さらに社労士は行政とのやり取りにも慣れており、追加資料の提出や問い合わせ対応もスムーズです。
総合的に、社労士に任せることで申請の確実性とスピードが向上し、安心感を得られるのが大きなメリットと言えます。
助成金申請代行の費用相場と契約形態
社労士に依頼する場合の費用も事前に把握しておきましょう。
助成金申請代行の料金体系は一般的に着手金+成功報酬となっていることが多いです。
着手金とは依頼時に支払う固定報酬で、書類作成やコンサルティングの対価として数万円~十数万円程度が相場です。
一方、成功報酬は実際に助成金が支給された場合に発生する報酬で、受給額の10~20%前後が一般的な水準です。
例えば50万円の助成金を受給できた場合、成功報酬が20%なら10万円を社労士に支払う計算になります。
事務所によっては着手金無料で成功報酬のみという所もありますが、その場合は成功報酬率がやや高め(20%超など)に設定されていることもあります。
また顧問契約を結んでいる社労士に依頼する場合は、通常の顧問料にプラスアルファの成功報酬という形もあります。
契約内容としては、依頼する業務範囲を明確にすることが大切。
計画書の作成から支給申請提出、審査対応までフルサポートなのか、一部(例えば計画書作成のみ代行で申請書は自社作成等)なのか、事前に取り決めます。
万一不支給だった場合の費用負担の有無(成功報酬なので通常は支払い不要ですが、着手金部分は返金されない等)も確認しましょう。
費用は発生しますが、「成功したら○○%、不成功なら報酬なし」という形態が多いため、企業側にとってリスクは低めです。
信頼できる社労士と適切な契約を結び、費用対効果を考えたうえで依頼を検討してください。
社労士に依頼した方が良いケース
では、どのような場合に社労士への依頼を検討すべきでしょうか。
以下のようなケースが挙げられます。
初めて助成金を申請する場合
ノウハウが全く無い状態で独力で進めると、見落としやミスが起きやすいです。
手探りで時間を浪費するより、最初からプロに任せた方がスムーズにいくでしょう。
社内に時間的余裕がない場合
日常業務で手一杯で申請準備に割く時間が取れない場合、社労士にアウトソーシングする価値は高いです。
限られたリソースを本業に集中させるためにも有効です。
助成金の金額が大きい場合
受給見込み額が数百万円以上など大きい場合、成功報酬を支払ってでも確実に受給した方がメリットがあります。
金額が大きいほど要件も厳格になりがちなので、プロのサポートで確実性を高めるのがおすすめです。
複数の助成金に同時応募する場合
同時進行でいくつも扱うと社内では混乱しがちです。
社労士なら複数案件も並行して管理してくれるため、安全に進められます。
過去に申請で失敗した経験がある場合
以前自力でやって不支給になった、書類不備を何度も指摘された等の経験があれば、原因を踏まえて社労士の力を借りた方がよいでしょう。
同じ失敗を繰り返さずに済みます。
社労士選びのポイント
いざ社労士に依頼しようと思った際は、適切な事務所選びも重要です。
助成金申請代行は社労士の独占業務であり、基本的に社労士しか行えません。
まずは助成金支援の実績が豊富な社労士を探しましょう。
ホームページ等で「◯件以上の助成金申請サポート実績」など謳っている事務所は安心材料になります。
また専門分野の一致も大切。
助成金と言っても幅広いので、雇用関係助成金を積極的に扱っている社労士かどうか確認します(補助金中心のコンサル会社などは助成金は不得意な場合もあります)。
過去の依頼者の口コミや事例紹介があれば目を通し、信頼性をチェックしましょう。
初回相談時の対応もポイント
難しい専門用語ばかりでなく分かりやすく説明してくれるか、質問に丁寧に答えてくれるか、コミュニケーションに不安がないかを確認します。
助成金申請は手続き完了まで数ヶ月以上に及ぶことも多いため、相性良く長期的に付き合える社労士かどうかも見極めましょう。
適切な社労士とタッグを組めば、助成金申請の成功率は格段にアップし心強いパートナーとなってくれるでしょう。
よくある不支給ケースと対策まとめ
ケース1:提出書類の不備
記入漏れ・添付漏れ・押印漏れ等。
提出前にチェックリストで点検し、複数人でダブルチェックする。
補正依頼には迅速対応。
ケース2:雇用保険料の滞納
保険加入・納付要件を満たさず対象外に。
対策:申請前に滞納がないか社内確認し、未納があれば速やかに追納する。
ケース3:労働法令違反歴
過去1年以内の違反で対象外に。
過去の是正勧告や指導履歴を確認。
該当する場合は1年経過後に申請するか、他の助成金を検討。今後違反しないよう労務管理改善。
ケース4:被保険者がいない/対象者不在
助成金の対象となる社員がいない。
助成金要件に合う人材の雇用や、労働時間変更等で被保険者化を検討(週20時間未満パートしかいない場合など)。
対象者いないなら無理に制度使わない。
ケース5:一定期間内の解雇実施
直近に事業主都合解雇があり対象外に。
解雇予定がある場合は助成金支給ルールを確認。
支給対象者の解雇は論外。
どうしても必要な人員整理の場合、助成金申請は見送り。
ケース6:計画未提出・期限切れ
事前計画書の未提出や申請書の期限超過。
期限管理徹底。公募要領を熟読し必要手続きの期限を全てスケジュール化する。
少しでも遅れそうなら即相談・手続き。
ケース7:証拠不十分
実施した裏付け資料が乏しく信憑性なしと判断。
計画実施中は逐一記録を残す(写真、書類、出席簿等)。
提出書類にも具体的な数値・事実を盛り込む。
ケース8:虚偽申請
嘘の内容で申請し審査で露見。
絶対に行わない。
誠実に要件を満たすよう努める。
助成金の振込時期
助成金の入金時期は多くの中小企業にとって関心事でしょう。
「申請からどのくらいでお金が振り込まれるのか」は資金繰りにも直結する問題です。
一般的には、助成金は支給申請してから約3~6ヶ月後に振り込まれるのが標準的と言われます。
例えばキャリアアップ助成金では、専門家の見解として「計画書提出から入金までトータルで1年ほどを想定すべき」という意見もあるほどで、それだけ時間がかかる場合があるということです。
標準的なケースでも3~6ヶ月と幅があるのは、審査にかかる時間が申請内容のボリュームや管轄部署の繁忙状況によって変動するためです。
実際、年度末前後は審査長期化の傾向がありますし[87]、不備補正に時間を要せば当然遅れます。
では具体的に入金までの流れを見てみます。
支給決定通知書が届いたら、あらかじめ届け出ていた会社の振込口座に対し、国庫から助成金額が振り込まれます。
振込人名義は制度によって異なりますが、多くは「◯◯労働局」や「コウワ(雇用)◯◯」のような名義で入ります。
通知書に支給決定日が書かれていますが、実際の振込日はその決定日から1ヶ月以内くらいが目安です。
もちろん決定から数日で入る場合もありますし、逆に事務処理の都合で少し遅れる場合もあります。
また金額が大きい助成金(例:数百万円以上)の場合、支給時期が行政手続き上決まった月にまとめて振込まれるというケースもあり、少し待たされることもあります。
心配な場合は労働局の助成金担当に「いつ頃振り込まれますか?」と問い合わせても問題ありません。
なお、一度支給された助成金でも、後日調査で不正や要件未達が判明すると返還を求められることがあります。
ですので、支給後も一定期間は記録類を保管し、条件をしっかり維持する(例えば助成金受給後6ヶ月は解雇禁止等のアフターフォロー要件がある場合も)ことが重要です。
無事に入金されたら、社内で関係者に報告し、経理処理を行いましょう。
助成金は雑収入として計上されますが、課税対象か非課税かは制度により異なるので税理士等に確認してください。
資金繰り面では、助成金入金までは立替が必要になるため、その間のキャッシュフロー計画も事前に立てておくことが大切です。
例えば訓練を実施する助成金では、まず企業が研修費や人件費を払い、その後助成金で補填される形なので、一時的に資金負担が発生します。
入金時期を見越して銀行融資や社内留保金で賄う計画を準備しましょう。
以上のように、助成金の振込は時間がかかるものと心得て、気長に待つことも必要です。焦らず、しかし状況は適宜フォローしながら、入金を迎えてください。
終わりに
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
※助成金には人材育成のための研修に充当できるものも含まれます。
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら