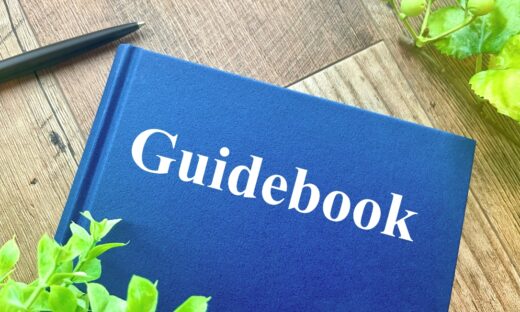部下の気持ちは変えようとしても変わらない!?部下は社内の仕組みで変えるのが正解

中小企業の経営者にとって、「部下が言われたことしかやらず主体性がない……」と嘆きたくなる場面は多いのではないでしょうか。
実際、社員30名規模のA社を率いる創業社長も「新人の頃はみんな目を輝かせていたのに、最近は指示を待つばかりだ」と悩んでいました。
社長自身は人一倍働いて会社を牽引してきましたが、いつしか部下たちは受け身になってしまったように感じる、といいます。
中小企業の経営者にとって、「部下の考え方ややる気を変えたいのになかなか変わってくれない」という悩みは共通ではないでしょうか。
社員数は20~50名程度と小規模で、経営者との距離が近い企業では特に、部下が思うように動かずもどかしさを感じる場面が多いかもしれません。
しかし、部下の気持ちは上司が外から働きかけても簡単には変わらないものです。他者からのアプローチで一時的にモチベーションを上げてもすぐ元に戻ってしまうのが実情で、頭ごなしに説教しても逆効果になりかねません。
外部から圧力をかけて人を変えようとする方法の限界と、社内の「仕組み」づくりによって部下が自発的に成長・変化するよう促す方法について解説。
創業社長や部門長といった経営層の方を主な読者と想定し、社員との距離が近い中小企業で実践できる組織づくりのヒントを具体的に述べていきます。
目次
部下の気持ちはそう簡単に変えられない
上司の悩み:「思った通りに動いてくれない」部下
「思ったように動いてくれない」「何も言わなくても察して動いてほしい。
できれば期待以上の成果を出してほしい」というのは、多くの中小企業の社長が抱く本音でしょう。
少人数ゆえに一人ひとりに目が届く反面、経営者の想い通りに部下が動かないことにもどかしさを感じる――そんなジレンマが起きがちです。
外からの働きかけには限界がある
上司が部下の意識改革を試みても、相手の心を根本から変えることは容易ではありません。他者からのアプローチによって相手の意識を変えることは現実的には難しく、一時的に意識を変化させてもすぐ元に戻ってしまうと指摘されています。
例えば、スポーツに感化されてその場でトレーニングを始めても三日坊主で終わってしまうようなもの。
研修や講話で一時的にやる気が出ても持続しないのでは、根本的な解決にはなりません。
「やらされ感」では人は動かない
部下が上司からの指示にただ従っているだけで、自分ごととして主体的に取り組んでいない状態は「やらされ感」があると言われます。
こうした「やらされ感」の下では、社員の意識や行動は長続きせず、たとえ他社で成果を出した仕組みやルールを導入して一時的に変化しても、すぐ元の状態に戻ってしまうことが多いのです。
結局、組織を動かしているのは人間であり、どんな改革もそこに参加する人たち自身が変われなければ成功しません。
部下に自発的かつ継続的な行動変容を起こさせるには、「内発的な動機付け」を引き出してあげる必要があるのです。
強制は逆効果になることも
上司が権威にものを言わせて力づくで部下を従わせようとすると、かえって反発心を招き逆効果になる恐れがあります。
強い命令や叱責で一時的に動かせたように見えても、部下の心には不信感が残り、信頼関係を損ねてしまいます。
上司の言葉で強引に丸め込もうとすれば、部下は「やらされている」という不満を募らせて言うことを聞かなくなってしまいます。
パワハラまがいに長時間叱り続けるようなアプローチは関係悪化を招くだけです。
そうではなく、部下と真正面から向き合い信頼関係を構築することが遠回りなようでいて最も確実な近道と言えます。
パワハラと捉えられてしまえば即転職という結果にもなりかねません。
「パワハラは転職のきっかけ?パワハラの境界線と職場環境で転職を考えるべきポイント」
部下を変えるには「仕組み」を変える
意識より「行動」を変えることに注力する
部下のモチベーションや価値観といった「意識」そのものを変えようとするよりも、まずは日々の「行動」を変えることに注力すべきだという意見があります。
人の内面を直接変えるのは難しいですが、行動が変われば自然と意識も後からついてくるものです。
また仮に意識が以前とあまり変わらなかったとしても、行動が改善され成果につながっていればビジネス上は問題ないでしょう。
重要なのは、部下の考え方を無理に変えさせようとするのではなく、行動を変えることで結果的に意識も変わっていくように仕向けることです。
行動を変えるには「仕組み」を変える
では部下の行動を変えるにはどうすれば良いのでしょうか。現場での行動パターンを変化させるには、その前提となる「仕組み」を変える必要があります。
社員が何も意識しなくても自然と望ましい行動を取れるような仕組みを作ることが、上司や人事担当者の重要な役割。
言い換えれば、個人の意識に直接働きかけるのではなく、行動が変わらざるを得ない環境やルールを整備することで間接的に人を変えていくのが賢明なのです。
例えば、営業社員の行動を変えたいなら評価制度を工夫する方法があります。
個人の売上目標達成度に応じて報奨金を支給する仕組みを導入すれば、多くの場合営業担当者は目標達成に向けての行動量を自然と増やすでしょう。
このように制度ひとつで現場の動きは大きく変わるため、組織として望ましい行動パターンを生み出す仕掛けを作ることが重要です。
「職場の問題の94%はシステム」が原因
実際、職場で起こる問題や非効率の大半は個人ではなく組織の仕組みに原因があります。品質管理の専門家エドワーズ・デミングは「職場の問題の94%はシステムに起因する」と述べています。
個人の特性に起因するものはわずか6%に過ぎないというのです。
したがって、部下のパフォーマンスが上がらない時にはその本人を責める前に、まず組織の制度やプロセス、職場環境などシステム面に改善余地がないかを検討すべきでしょう。人ではなく仕組みを変えることこそが問題解決の近道であるケースは非常に多いのです。
「仕組み」とは何を指すのか
ここでいう「仕組み」とは、組織内のあらゆるルール・制度・風土といった 人の行動に影響を与える環境要因 を指します。
人事評価の基準や目標管理の方法、権限委譲のルール、業務プロセス、組織構造、チーム編成、社内コミュニケーションの手段などが含まれます。
さらには企業文化や職場の雰囲気そのものも重要な仕組みの一部。
社員は企業の雰囲気や文化の影響を受けて行動しますから、経営者は意図的に「場づくり」(働く環境づくり)を行って、社員が動きやすい土壌を育てる必要があります。
例えば、人事評価制度が個人の売上数字だけを重視する内容だと、社員は目先の数字を追うあまり仲間と協力しなくなるかもしれません。
逆にチーム全体の成果やプロセスも評価する仕組みにすれば、自然と助け合いや改善提案といった行動が増えるでしょう。
このように仕組み次第で社員の行動パターンは変わるため、経営者は自社に適した環境設定を心がけることが大切です。
上司自身のマネジメントも仕組みの一部
社内の仕組みには、上司であるあなた自身のマネジメントスタイルも含まれます。
創業社長が何から何まで細かく指示を出していたら、社員は指示待ち姿勢になり自主性は育ちません。
一方で、現場に権限移譲して任せれば、社員は責任感を持って動くようになります。
部下を変えようとするなら、まずは上司である自分自身がマネジメントのやり方を変える――そんな心構えが必要な場合も多いのです。
上司が変われば組織全体の文化が変わり、結果として部下も変わっていくでしょう。
部下の行動を変える仕組みづくり:目標とフィードバック
具体的な目標を設定し共有する
部下の行動を変える第一歩は、明確な「目標」を設定して示すこと。
ゴールが定まらないままでは社員はどの方向に努力すればよいかわからず、行動を起こしようがありません。
したがって、目標はできるだけ具体的で測定可能な形に落とし込み、社員にとって現実的に達成可能な水準を定めます。
また、その目標は会社全体の経営目標と結びついた内容にすることが重要です。
さらに「〇月〇日までに○○を達成する」といった期限(タイムリミット)も設け、組織全員で目標を共有しましょう。
こうした目標設定は部下の行動の指針となり、努力の方向性を示します。
目標を行動レベルに落とし込む
大きな目標を設定したら、それを具体的な「行動」にブレイクダウンします。
年間・月間目標は週次・日次レベルのタスクにまで細分化し、今日明日やるべき行動まで明らかにするのです。
そうすることで、部下は日々何をすればよいか迷わずに済み、行動に移しやすくなります。もし目標達成までのステップが多すぎて消化しきれない場合は、優先順位の高いものから順に実行するよう指導するとよいでしょう。
行動計画を具体化し段階を追って示すことで、部下は着実に目標に向かった行動を積み重ねられます。
行動状況を定期的にチェックする
計画した行動がきちんと実行されているか、定期的なフォロー の仕組みも欠かせません。例えば週次あるいは日次で進捗確認の場を設け、上司が仕事の様子を観察したり1対1の面談でヒアリングしたりして、部下の行動を継続的にチェックします。
これにより、計画倒れやサボりを防止すると同時に、必要なら早めに軌道修正の支援を行うことができます。
上司との定期的なコミュニケーションを組み込むことで、部下も緊張感を持って日々の行動に取り組むようになるでしょう。
行動に基づくフィードバックを行う
部下へのフィードバックは意識ではなく「行動」に対して行います。
例えば部下に対し「最近やる気がないようだね」と内面を批判するのではなく、「今週の朝会に二度遅刻していたけれど何か原因があるかな?」といった具合に、具体的な行動事実に基づいてフィードバックすることが望ましいでしょう。
良い行動は具体的に評価・賞賛し、望ましくない行動には何が問題かを指摘して改善を促しましょう。
フィードバックの際にはいくつかポイントがあります。叱責する場合は、乱暴な言葉を使わない・大勢の前で叱らないなど相手の尊厳に配慮することが大切です。
逆に褒めるときは曖昧な表現を避け、「〇〇の対応が良かった」のように具体的に伝えることを意識します。
これにより部下は何を続け、何を改めればよいかを理解できます。
こうした行動重視のフィードバックを習慣化することで、部下の行動は少しずつ望ましい方向へ修正されていきます。
社員が自発的に動く組織文化・制度の構築
社員の自主性を高めるために有効な社内制度・文化づくりのポイントは、大きく5つあります。
それは、
(1)「失敗を責めず挑戦を称賛する文化」
(2)「上司が最終責任を負うと明言すること」
(3)「何でも言い合える風通しの良い環境」
(4)「権限移譲による迅速な意思決定」
(5)「仕事の意義を実感できる機会の提供」
です。
以下、それぞれについて詳しく見ていきます。

失敗を責めず挑戦を称賛する文化
社員が積極的に挑戦できる職場には、総じて「失敗を責めない」文化が根付いています。
変化の激しいビジネス環境では、新しい挑戦には失敗がつきものですが、社員の自主性を伸ばすにはチャレンジ自体を称賛し奨励する雰囲気が不可欠です。
たとえ結果がうまくいかなかったとしても、「成功のもと」である挑戦した事実と、そこから得た学びを評価対象にしましょう。
実際に、失敗してもチャレンジしたこと自体を人事評価でプラスに評価する制度 を取り入れている企業もあります。
このように失敗を罰するのではなく挑戦を肯定するカルチャーを築けば、社員は失敗を過度に恐れず行動に移りやすくなります。
上司が最終責任を負うと明言すること
社員の自主性が高い組織では、経営者が「失敗したら責任は私が取るから、思い切ってやってみろ」と公言しているケースがよくあります。
どれほど有能な社員でも、失敗した際に自分一人が責任を負わされると思えば行動を躊躇してしまうでしょう。
しかしトップが「最終的な責任は自分が取る」と明言すれば、社員は安心して思い切った行動ができるようになります。
自分に任された仕事は上司もちゃんと見守ってくれている、と感じられるためです。
このように上司がリスクを引き受けて部下を守る姿勢を示すことは、組織に心理的安全性を生み、社員のチャレンジ精神や自主性を大いに高めます。
何でも言い合える風通しの良い環境
自由に意見を言い合える風通しの良い職場風土も、社員の主体的行動には欠かせません。自主性の高い人材は行動力が強みですが、相談しづらい雰囲気ではせっかくの自主的な行動も空回りする恐れがあります。
そこで社内の公式・非公式なコミュニケーション機会を増やし、何でも言い合える関係性を築くことが重要です。
例えばある中小企業では、メールの代わりにチャットツールを導入し、業務外の雑談もできる専用チャネルを設けました。
その結果、普段は接点の少ない他部署の社員同士でもお互いの趣味や人となりを知ることができ、「意外な一面」を共有することで社内の人間関係が良好になったそうです。
このようにITツールの活用や社内イベントなどを通じて社員同士のコミュニケーションを活発化させることで、チームの一体感が増し、現場で助け合い・相談し合える土壌が醸成されます。
権限移譲による迅速な意思決定
自主性の高い組織を作るには、意思決定のプロセスをできる限り短縮することも必要です。行動力のある社員がせっかく提案や実行しようとしても、いちいち決裁に時間がかかっていてはモチベーションが削がれてしまいます。
そこで、可能な範囲で現場に権限を委譲し、スピーディーに動ける体制を作りましょう。例えば、新規事業開発に取り組む企業の多くは、一定の予算や意思決定権を現場の担当者に与えています。
社長の許可を仰がなくても現場判断で試行錯誤できる余地を作るのです。
もちろん経営者は事業の方向性が逸れないよう節目で助言・承認を行いますが、適度な権限委譲によって部下は自分の裁量で動けるようになり、主体性と責任感が高まります。
意思決定のスピードアップは市場環境への素早い対応にも直結するため、権限移譲による現場力の向上は組織全体の競争力にも寄与します。
仕事の意義を実感できる機会の提供
社員一人ひとりが自分の仕事の意義を実感できるようにすることも、内発的な動機付けを高める上で重要です。
自分のやっている仕事がどのように役立っているのかわからないと、仕事が単なる作業になってしまいモチベーションが下がってしまいます。
そこで、社員が自社の商品・サービスのエンドユーザーの声を直接聞く機会を設けるなど、仕事の成果を実感できる仕掛けを作りましょう。
例えば製造業の企業で、自社製品を使っているお客様の生の声を製造現場の社員が聞く機会を作ったところ、自分たちの製品がどのように世の中に貢献しているかを知り、社員からも顧客目線での改善アイデアが出るようになったそうです。
このように自分の仕事の意味を実感できれば、「もっと役に立ちたい」「より良いものを作りたい」という内発的な意欲が喚起され、結果的に自主的な行動が増えていきます。
小規模企業で「仕組み」による部下育成を実践するには
距離の近さを活かしてビジョンを共有する
社員数20~50名規模の会社では、経営者と従業員の物理的・心理的距離が非常に近いという特徴があります。
これは裏を返せば、トップの想いやビジョンを直接社員に伝えたり、社員の生の声を吸い上げたりしやすいということ。
大企業では階層を経由して伝わる方針も、小規模組織なら経営者自ら全員に語りかけることができます。
経営理念や会社の方向性を日頃から繰り返し共有し、各人の目標と会社の目標をしっかり擦り合わせるようにしましょう。
現場とのコミュニケーションを密にしやすい利点を活かして、経営者自身が先頭に立ち対話を重ねることで、仕組みづくりの施策もスピーディーに浸透させることができます。
例えば朝礼で経営理念やビジョンを繰り返し発信したり、ランチタイムに社員と気軽に会話したりと、小規模だからこそできる密なコミュニケーション手段を活用しましょう。
「属人型の経営」から「仕組み経営」へシフトする
創業社長の場合、これまでは自分のカリスマ性や経験に頼って組織を牽引してきたかもしれません。
しかし組織規模が拡大するにつれ、特定の人物に依存したマネジメント(属人型の経営)には無理が生じてきます。
いつまでも社長が一人ひとりの部下に目を配り続けるのではなく、仕組みで人が動く組織に転換していくことが求められます。
今回述べてきたような制度・ルール・文化を整え、社員が自律的に考え行動できる土台を作ることです。
属人性を排した「仕組み経営」にシフトできれば、社長不在の状況でも組織が安定して成果を出せるようになり、より大きな発展に繋がるでしょう。
特に創業経営者が世代交代を見据える場合、属人経営からの脱却は急務。
仕組みで回る会社にしておけば、経営交代時も業績を安定させやすく、事業承継も円滑に進むはずです。
従業員とともに仕組みを改善する
仕組みづくりを進める際には、現場で働く従業員の声を取り入れる姿勢も大切です。
経営者が一方的に新ルールを押し付けるのではなく、現場の課題や提案を吸い上げて一緒に改善策を考えるプロセスを組み込みましょう。
例えば定期的なヒアリングやアンケートで「働きにくい点」「こんな制度があればいい」などの意見を集め、小集団による改善チームでアイデアを出し合うといった取り組みが考えられます。
社員自身が仕組み改善に参加すれば、「自分たちで職場を良くしている」という当事者意識が芽生え、新しい制度に対する納得感・受容度も高まります。
現場の知恵を活かして仕組みをブラッシュアップしていくことで、より実効性のある組織改革が実現するのです。
例えば社内に提案制度を設け、従業員から改善アイデアを常時募集するのも良い方法です。優れた提案には表彰や報奨を与えればモチベーションも高まります。
トヨタ自動車などでも一人ひとりの現場社員が年間数万件規模の改善提案を行い、それが生産性向上に大きく寄与しています。
自社の規模に合わせて、社員のアイデアを引き出す仕掛けをぜひ作ってみましょう。
部門長は自部署のミニ組織をデザインする
部門長の方にも、自分の管轄する部門内での仕組みづくりに取り組むことをおすすめします。
たとえ会社全体ではまだ整っていない仕組みがあっても、部門レベルで先行して改善に着手することは可能です。
自部門の目標を明確に定めてチーム内で共有し、メンバーが自由に意見を言える風土を作り、独自の表彰制度や1on1面談制度を導入するなど、部門単位でできる工夫をどんどん試してみましょう。
小さな組織単位で成果を上げた仕組みは、ゆくゆくは全社展開され他部門にも波及する可能性があります。
自部署を「ミニ会社」と捉え、部門長が社長の視点で組織デザインを実践することで、部下育成と業績向上の両面で成果を出すことができるでしょう。
部門単位で成功した取り組みは他部署や全社にも広がり、組織全体の底上げにつながります。
まとめ:仕組みづくりは持続的成長への投資
適切な仕組みが整った組織では、社員は上司に指示されなくても自律的に動き、問題が起きてもシステムによって解決が図られるようになります。
上司は細かなマイクロマネジメントに追われず、本来注力すべき戦略立案やメンバーのサポートに時間を充てられるでしょう。
また社員にとっても、自分の工夫や努力が正当に評価され働きやすい環境があることで、仕事へのエンゲージメント(愛着心や没頭度)が高まります。
その結果、生産性向上や優秀人材の定着など組織全体に良い循環が生まれます。
まさに「仕組み」を変えれば人が変わり、組織が伸びるのです。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら