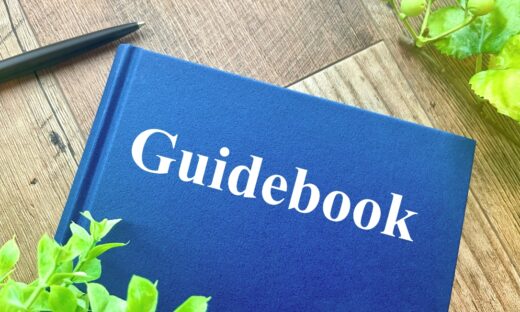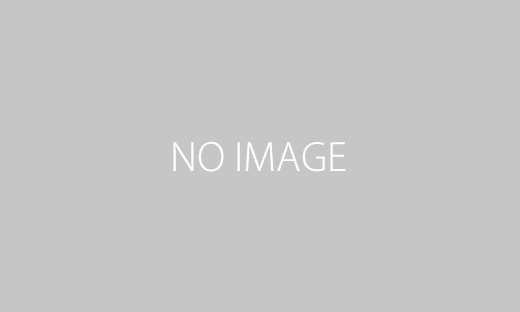助成金の申請代行を使うと手数料はいくらかかる?助成金申請代行業者の選び方や注意点を解説

助成金の申請手続きは専門知識が必要で時間もかかるため、外部の申請代行業者に依頼するケースが増えています。
しかし、依頼には手数料が発生する上、業者選びを間違えるとトラブルに巻き込まれる恐れも。
本記事では、申請代行の一般的な手数料相場や料金体系の具体例、悪徳業者の見分け方、優良業者の選定基準、利用するメリット・デメリットなどを網羅的に解説します。
目次
助成金申請代行の料金体系と手数料相場
助成金申請代行サービスを利用する際に最も気になるのが「いくらかかるのか」という費用面です。
ここでは、申請代行業者が採用している主な料金体系(成功報酬型、定額型、着手金+成功報酬型)や、一般的な手数料の相場について解説しました。
また、支払いタイミングや契約時に確認すべきポイントについても紹介。
初めて代行サービスを利用する企業が、無駄な出費を防ぎつつ安心して依頼できるようになるための基礎情報をまとめています。

成功報酬型と定額型の違いとは?
助成金申請代行の料金体系は大きく分けて**「成功報酬型」と「定額(固定)型」があります。
多くの業者では、まず無料相談を経て契約し、その後着手金(依頼時に支払う固定費用)や成功報酬(助成金を受給できた場合に支払う費用)が発生する仕組みです。
一般的には以下のようなパターンがあります。
着手金+成功報酬型
契約時に一定の着手金を支払い、さらに申請が採択され助成金を受給できた場合に成功報酬を支払う方式。
採択結果にかかわらず着手金は支払う必要がありますが、その分成功報酬率は低めに設定される傾向があります。
成功報酬のみ型
着手金は不要で、助成金を受給できた場合のみ成功報酬を支払う方式。
リスクは少ないように見えますが、成功報酬率が高めに設定されるのが一般的です。
着手金のみ型
助成金の種類によっては着手金のみで請け負う業者も存在します。
この場合、結果に関係なく定額の費用を支払います。
成功報酬が発生しない分、総額は予め確定しますが、不採択でも費用が戻らない点に注意が必要です。
いずれの方式にもメリット・デメリットがあります。
成功報酬型は不採択時の負担を抑えられますが、採択された場合の支払い総額は多めになりがちです。
一方、定額型(着手金のみ型)は費用を見積もりやすい反面、不採択でも費用負担が発生します。
そのため、自社の資金状況や助成金額、採択可能性を踏まえて適切な料金プランを選ぶことが重要です。
手数料の相場はどれくらい?
具体的な手数料相場は依頼する業者や助成金の種類によって幅がありますが、一般的な目安があります。
多くのケースで「着手金〇万円+成功報酬〇%」といった形で設定されており、成功報酬のみ型の場合は成功報酬率が高めです。
以下に代表的な相場を示します。

着手金+成功報酬型の相場
着手金は数万円~十数万円程度、成功報酬は受給額の約10~15%前後が一般的な目安です。例えばある社労士事務所では「着手金3〜10万円+成功報酬10〜20%」程度が相場とされています。
中小企業診断士や行政書士などが行う補助金代行でも「着手金10〜15万円+成功報酬5〜15%」程度が平均的と報告されています。
成功報酬のみ型の相場
成功報酬のみの場合、成功報酬率は受給額の15~25%程度とやや高めに設定されるケースが多いです。
着手金が不要な分リスクを業者が負うため、成功時の取り分を高くしているわけです。
例えば着手金ありのプランで成功報酬10%だったものが、成功報酬のみプランでは20%前後になるといった具合です。
実際の例を挙げると、補助金代行に強い税理士法人では「着手金15万円+成功報酬10%」程度の料金設定がされています。
また別の事例では、社労士事務所に助成金申請を依頼した場合「着手金なしで成功報酬20%」「着手金5万円+成功報酬15%」など、事務所ごとに様々なプランが存在します。
重要なのは、相場とかけ離れた極端に高額または安価な料金には注意することです(この点は後述する悪徳業者の見分け方でも詳述します)。
一般に、着手金の相場は数万円〜数十万円、成功報酬は数%〜20%台まで幅がありますが、依頼内容や難易度によって変動します。見積もりを依頼して複数社の料金を比較検討することが大切です。
支払いタイミングと契約内容の注意点
助成金申請代行サービスを利用する際は、料金の支払いタイミングや契約条件もしっかり確認しましょう。
一般的には以下のようなタイミングがあります。

契約時(着手金支払い)
着手金があるプランでは、契約締結時または業務開始時に着手金を支払います。
これは採択可否に関わらず必要なコストで、申請書類作成などにかかる労力への対価です。契約前に着手金額と支払時期を確認し、不採択時に返金がないことも理解しておきましょう。
採択決定時(成功報酬の請求)
成功報酬は通常、助成金の採択が決定した段階で請求されることが多いです。
採択通知が届いた時点で成功報酬○%を支払う契約になっているケースでは、実際の助成金交付(入金)前に費用負担が発生します。
例えば「採択時の補助金額×10%を成功報酬とする」と明記された契約では、交付金が振り込まれる前でも採択された時点でその10%を支払う義務が生じます。
資金繰り上、交付金受領後の支払いを希望する場合は、事前にその旨相談すると良いでしょう。
交付(助成金入金)時
業者によっては、実際に助成金が入金されてから成功報酬を請求するところもあります。この場合、事業完了後の実績報告まで含めて支援し、助成金が振り込まれて初めて成功報酬発生という流れです。
契約書で「成功報酬は交付時に発生」となっているか「採択時に発生」となっているかを読み違えないよう注意しましょう。
また、契約内容の細部も重要なチェックポイントです。
契約書には料金体系(着手金・成功報酬の額や率)だけでなく、業務範囲(例:申請書類の作成から提出代行、採択後の実績報告支援まで含むか)や不採択時の対応(例:再申請支援の有無、着手金の取り扱い)などが明記されているか確認してください。
優良な業者であれば、これらを明確に説明したうえで契約書を交付してくれます。
逆に契約内容があいまいだったり、口頭説明と書面記載が食い違っている場合は要注意です。
特に「不採択でも全額返金なし」「成功報酬の算定基準(採択額か交付額か)が不明確」など不安な点は事前に確認し、疑問が残る場合は契約を見送ることも検討しましょう。
悪徳な申請代行業者の見分け方と注意点
助成金申請代行サービスの利用増加に伴い、残念ながら悪質な業者(いわゆる悪徳業者)も存在します。
こうした業者に依頼すると「高額な手数料をだまし取られる」「ずさんな対応で結局助成金がもらえない」のみならず、場合によっては不正受給の共犯に巻き込まれるリスクさえあります。
助成金詐欺については以下の記事も参考にしてください。
「助成金詐欺に注意!企業が安全に助成金を活用するためのチェックポイント」
助成金受給を「簡単」に強調する業者に注意
「誰でも簡単にもらえる」「手続き丸投げで確実に受給できる」などと助成金の受給を過度に簡単そうに謳う業者は警戒が必要です。
助成金・補助金にはそれぞれ細かい要件や審査があり、申請すれば必ずもらえるわけではありません。
例えば人気の「ものづくり補助金」でも採択率は60%程度、「事業再構築補助金」では45%ほどと半数近くが不採択になる現状があります。
このように難易度が決して低くないにもかかわらず、「必ずもらえる」「絶対採択される」といった断言や、成功率を異常に強調する営業トークには裏があると考えましょう。
誠実な業者であれば、助成金獲得の難しさを正直に説明し、丁寧なヒアリングや書類作成で採択率を上げる努力をしてくれるものです。
※助成金は条件を満たしていれば必ずもらえます。
助成金と補助金の違いについては以下の記事も参考にしてください。
「助成金・補助金の申請代行はどこに依頼する?必要な資格や代行依頼先の判断基準」
資格や実績が不透明な「自称コンサル」に注意
助成金の代理申請には、厚生労働省管轄の助成金であれば社会保険労務士(社労士)の国家資格が必要です。
一方、経産省管轄の補助金については特別な資格は不要なため、誰でも「補助金コンサルタント」などと名乗ることができます。
この背景から、肩書きや名刺だけ立派な無資格業者も紛れています。
悪徳業者は「○○コンサルタント」「申請代行のプロ」などと謳っていても、具体的な資格や実績が確認できないケースが多いです。
依頼を検討する際は、必ず客観的な事実として以下をチェックしましょう。
●その業者または担当者は必要な資格を持っているか
(社労士・行政書士・中小企業診断士・税理士など)
●過去の採択実績や支援件数が公開されているか。
ホームページや資料で実績ゼロにもかかわらず「経験豊富」と称するなら注意が必要です。
●認定支援機関かどうか
経済産業省認定の「経営革新等支援機関」であれば一定の知識・経験が担保されます。
資格の有無だけで全てを判断はできませんが、少なくとも社労士資格を持たない業者が厚労省系助成金の代行を提案してきたら違法行為なのでアウトです。
また無資格のコンサル会社の場合でも、過去に何件採択を出したかなど実績の透明性が重要です。
問い合わせ時にあいまいな回答しか返ってこない業者は避けましょう。

相場を逸脱した高額(または異常に安価)な料金設定
料金設定が極端に高すぎる業者も悪徳の可能性があります。
一般的な相場は前述の通りですが、例えば「着手金40万円・成功報酬30%」など明らかに相場を逸脱する高額報酬を提示された場合は要注意です。
なぜその料金なのか納得できる説明がない場合、着手金を受け取った後に連絡が途絶える、あるいは高額報酬に見合うサービスを提供しないといったトラブルに発展しかねません。
逆に、不自然に安すぎる料金も注意が必要です。
相場とかけ離れた格安価格を餌に契約を取り、実際には書類をほとんど作り込まず雑な申請で落選…といったケースも考えられます。
「高すぎても安すぎても危険」という視点で、複数社の見積もりを見比べ、料金とサポート内容・実績が見合っているかを判断しましょう。
特に「前金のみ要求」の業者には厳重な注意が必要です。
前述のように通常は成功報酬型であれば採択時に報酬が発生しますが、詐欺業者は着手金(前金)だけ受け取って消えるケースがあります。
「全額前払い」を強調する契約形態は典型的な着手金詐欺の手口です。
契約時には支払いスケジュールにも目を通し、「着手金以外に成功報酬が設定されているか」「前金支払い後のプロセスが明記されているか」を確認してください。

サポート範囲が限定的で契約書に不備がある
悪質な業者は、サービス内容が不十分であるにもかかわらずそれを隠して契約させる場合があります。
「申請書の作成までしか支援しない」にもかかわらず、あたかも包括的にサポートするような説明をするケースです。
助成金は採択後にも実績報告書の提出や事後対応が必要となるものが多くあります。
申請代行のメリットは手間削減にあるのに、申請後のフォローが無ければ結局自社で手間を負担することになりかねません。
悪徳業者はこの点を曖昧にして契約を急がせ、後から「それはサービス範囲外」「追加料金が必要」といった事態を招きます。
契約前に「採択後のフォローはあるか」「事業完了報告までサポートするか」「追加料金が発生する場面は何か」を確認しましょう。
また、契約書の不備にも目を光らせる必要があります。
正式な契約書を交わさず口頭で済まそうとする業者、契約書に基本的な事項(依頼内容・料金・支払時期等)が明記されていない業者は信用できません。
口コミや評判も参考になりますが、悪徳業者は口コミ自体が少なかったり不自然に良い評価ばかり載せていることもあります。
インターネットで社名を検索し、他の企業からの評判やトラブルの有無を調べることも有効です。
少しでも「あやしい」と感じたら、各都道府県の中小企業支援センターや労働局など公的機関に相談するのも手段の一つ。
厚生労働省や中小企業庁も、不審な勧誘や詐欺について注意喚起を行っています。
企業側が被害に遭わないよう、慎重に見極めてください。

優良な申請代行業者の選び方・選定基準
悪徳業者を避ける一方で、信頼できる優良な申請代行業者を選ぶにはどんな点に注目すべきでしょうか。
ここでは、安心して依頼できる業者を見極めるための選定基準やチェックポイントを紹介します。
自社に合ったパートナー選びの参考にしてください。
公式の認定や資格を確認する
まず重視したいのが、その業者が公的な認定資格を持っているかという点です。
具体的には以下のようなものがあります。
社会保険労務士(社労士)資格
助成金(厚労省系)申請代行は社労士の独占業務であるため、雇用関係の助成金を依頼するなら社労士資格保有者は必須です。
社労士であれば労務管理の専門家として知識が豊富で、書類不備による不支給を防いだりスムーズな申請が期待できます。
認定経営革新等支援機関
経済産業省が認定する中小企業支援機関で、補助金申請に必要な専門知識・実務経験が一定以上あると認められた機関です。
税理士法人や金融機関などが取得しています。認定支援機関であれば不正の心配が少なく行政手続きにも精通しているため、安心材料になります。
依頼候補が認定支援機関かどうかは中小企業庁のサイトで検索可能です。
その他の資格・肩書き
行政書士、中小企業診断士、税理士、弁護士など、助成金・補助金に関連する専門資格を持つ業者も信頼度が高い傾向にあります。
資格自体は補助金代行の必須条件ではありませんが、資格保有=専門知識や倫理遵守への一定の担保と考えられます。
もちろん資格があるだけで無条件に優良とは言えませんが、無資格よりは有資格、無認定よりは公的認定ありの業者のほうが信頼性は高い傾向があります。
特に初めて依頼する場合は、資格や認定の有無を確認し、可能であればその証明(登録番号や認定番号など)を提示してもらうと安心です。
過去の実績と得意分野をチェックする
実績豊富な業者ほどノウハウが蓄積されており、採択率も高い傾向があります。
ホームページやパンフレットで過去の採択事例や支援件数を公開している業者は多いので、必ず目を通しましょう。
例えば「累計○○件の申請支援」「過去に●●補助金で採択率○○%」など具体的な数字があると信用度が増します。
口コミや紹介で評判を聞くのも有効ですが、公表されている実績のほうが客観的です。
また、自社が申請したい助成金・補助金の種類に強いかも重要です。
業者によって得意分野・不得意分野があり、例えばある社労士事務所は雇用関係助成金に強いが設備投資系補助金は経験が少ない、といったケースもあります。
申請したい制度が決まっている場合、その制度での採択実績がある業者に依頼するのが理想です。
まだ制度が決まっていない場合でも、「これこれの分野で多く支援している」という情報があれば参考になります。
問い合わせ件数や顧客数が多い業者も、それだけ選ばれている証拠と言えます。
ただし大手コンサルティング会社などは実績豊富な反面、費用が割高な傾向もあるため、実績と費用のバランスを考慮して決めましょう。
いずれにせよ、「助成金申請支援○年」「○○業界の支援実績多数」といったアピールポイントを持つ業者は信頼に値します。

料金とサポート内容の透明性が高い
優良な業者ほど、料金体系と提供サービス内容を明確に開示しています。
例えばホームページに料金プラン表を載せていたり、「着手金○万円・成功報酬○%(最低○円)」と具体的に記載している会社は安心できます。
実際、ある行政書士法人のサイトでは主要な補助金ごとの料金表を公開しており、ものづくり補助金の代行費用を「着手金126,500円+成功報酬12%(最低22万円)」など細かく提示しています。
このように透明性の高い業者は、契約後に「聞いていなかった追加料金」が出てくるリスクも低いでしょう。
また、サポート範囲についても事前に確認しましょう。
優良業者であれば、「申請書類の作成から提出代行、採択後のフォロー(実績報告書作成支援)まで含めて○○円」といった形でどこまでサポートするかを明示しています。逆に曖昧な説明しかしない場合は前述の通り注意です。
「採択後も最後まで支援します」「不採択の場合は再チャレンジサポート可能」など、心強いフォロー体制を明言している業者は安心感があります。
契約前の相談段階で、こちらから質問を投げかけてみるのも良い方法です。
「この助成金はうちの会社で要件満たせるか」「申請準備にどれくらい社内工数が必要か」など尋ねた際に、的確で具体的な回答が返ってくる業者は信頼できます。
反対に要領を得ない答えや「とりあえず契約しましょう」のように急かす態度の場合は再考しましょう。
無料相談の対応も含め、誠実で丁寧なコミュニケーションを取ってくれるかどうかも重要な選定基準です。
複数の業者から見積もりを取り比較検討する
一社だけで即決せず、複数の代行業者に問い合わせや見積もり依頼を行うのも賢明です。そうすることで、各社の料金や対応を比較でき、自社に合った最適なパートナーを選びやすくなります。
見積もりを取る際は、同じ条件(申請したい助成金の種類や希望するサービス範囲など)で依頼しましょう。
比較ポイントとしては以下が挙げられます。

料金面
提示された着手金・成功報酬の額や割合。
安ければ良いというものではありませんが、極端に高い場合はその理由を確認。
サービス内容
申請書類の作成以外に、要件の事前チェックや事業計画書のブラッシュアップ、採択後の報告支援などどこまで含むか。
対応速度や態度
見積もり依頼に対するレスポンスの速さ、質問への回答内容から、その会社の姿勢をうかがいます。
親身になって相談に乗ってくれるかもポイントです。
契約条件
成功報酬の支払タイミング、不採択時の扱い(再申請支援割引などあるか)も比較材料になります。
複数社とやり取りする中で、「この担当者は信頼できそうだ」「この会社は自社の業界理解が深い」など見えてくるものがあります。
相性や信頼感も大切な要素です。総合的に判断して、最も信頼できコストパフォーマンスの良い業者と契約するようにしましょう。
助成金申請代行サービスのメリットとデメリット
外部の申請代行サービスを利用することには、多くのメリットがありますが、一方でデメリットやリスクも存在します。
ここでは、経営者が知っておくべき助成金申請代行の利点と欠点を整理します。
メリット・デメリット双方を理解した上で、利用するかどうか判断しましょう。
助成金申請代行を利用するメリット
採択率・受給率の向上
プロの力を借りる最大のメリットは、助成金が採択される可能性を高められることです。社労士や補助金コンサルタントは最新の制度情報や審査傾向を熟知しており、要件の漏れや書類不備を防いでくれます。
自社だけでは気づかない改善点も指摘してもらえるため、結果的に採択に近づきます。
また、過去の成功事例に基づいたアドバイスや事業計画書のブラッシュアップにより、申請内容の質が高まり審査通過率アップが期待できます。
手間と時間の大幅削減
助成金申請は煩雑で時間がかかる作業です。経営者や担当者が日常業務の合間にやるには負担が大きいでしょう。
代行業者に依頼すれば、申請準備にかかる労力を大幅に削減できます。
書類収集や記入・オンライン申請手続きなどを任せられるので、その分本業に専念できます。
特に中小企業では、人手に限りがあるため、このメリットは非常に大きいでしょう。
最適な助成制度の提案を受けられる
助成金・補助金の種類は非常に多岐にわたり、自社にどれが使えるのか判断するだけでも難しい場合があります。
経験豊富な業者であれば、自社の状況をヒアリングした上で最適な制度を選定してくれます。
例えば「設備投資をしたいなら○○補助金、人材育成なら△△助成金が適しています」といった形で、プロの視点からアドバイスがもらえます。
中には「希望していた補助金より他の助成金の方が条件に合う」と判明するケースもありますが、社労士資格を持つ代行業者であれば補助金・助成金の両方を取り扱えるため、一括して相談できる利点もあります。
最新情報や制度変更への対応
助成金制度は年度ごとに改正や新設があり、情報のアップデートが欠かせません。
代行業者は日々情報収集を行っているため、最新の公募情報や要件変更に精通しています。自社でリサーチする手間を省けるとともに、チャンスを逃さず活用できるでしょう。
「知らない間に使える補助金の募集が終わっていた」という事態を防げるのもプロに任せるメリットです。
最新情報や制度変更への対応
初めて助成金申請に挑戦する企業にとって、専門家のサポートは大きな安心材料です。
申請書の書き方から必要書類の整備までマンツーマンで指導・代行してもらえることで、「これで大丈夫だろうか…」という不安が軽減されます。
仮に採択に至らなくても、業者からフィードバックをもらえるため次回以降の糧になります。
総じて、成功報酬を支払ってでも利用する価値があると感じる企業は多いようです。
助成金の種類については以下の記事も参考にしてください。
「中小企業向け助成金の種類と特徴!どの助成金が活用できる?」
助成金申請代行を利用するデメリット
費用負担が発生する
当然ながら、申請代行にはコストがかかります。
助成金は「返済不要の資金」ではありますが、代行手数料を支払う分、実質的な手元資金は減ることになります。
例えば100万円の助成金を受給できても、代行業者に成功報酬20万円(20%)を支払えば実質80万円の利益です。
特に助成金額が小さい場合、手数料負担が割に合わないこともあり得ます。
代行費用は決して安くないため、費用対効果を考えて依頼する必要があります。
悪質業者に当たるリスク
前述のように、運悪く悪徳業者に依頼してしまうと金銭的・時間的な損失が発生するリスクがあります。
全額前払いして書類も出さずに消えられた、ずさんな申請で不採択だった等、かえってマイナスになりかねません。
信頼できる業者選びさえできれば回避できるデメリットですが、このリスクゼロではない点は頭に入れておきましょう。
情報提供や準備に一定の社内工数が必要
外注すると言っても、完全にお任せで自分は何もしなくて良いとはなりません。
ヒアリングへの対応、会社の財務資料や計画資料の提供、必要に応じて見積書の取得や証憑書類の準備など、業者と協力して進める作業は発生します。
特に事業計画の構想部分などは自社で練っていく必要がありますので、ある程度のコミットメントは必要です。
ただしその負担は、自力でゼロから書類作成するのに比べれば格段に少ないでしょう。
活用事例:申請代行のサポートで受給に成功したケース
実際に助成金申請代行を活用して受給に成功した企業の事例を紹介します。
事例①:小売業(バイク販売店)W社
従業員23名のオートバイ販売店では、専門コンサルタントの支援を受けて複数の助成金・補助金申請を行い、合計1,933万円の受給に成功しました。
この中には雇用環境の整備に関する助成金と、新規サービス立ち上げに関する補助金が含まれており、同社は受給資金を活用して事業拡大と人材定着を同時に進めています。
外部の助成金コンサルのアドバイスにより、自社では気づかなかった補助制度にも申請できたことが大きな要因でした。
事例②:サービス業(保育事業)R社
従業員50名の保育関連サービス業では、社労士と中小企業診断士のチームに依頼し、計3,715万円もの助成金・補助金を獲得しました。
保育士の処遇改善加算(厚労省系助成金)や事業拡大のための設備投資補助金など、複数の制度をフル活用しています。
これにより人材確保と事業規模拡大を同時に実現し、地域ニーズに応えるサービス拡充につなげました。
小売・サービス業ならではの注意点
小売業・サービス業で助成金申請代行を活用する際には、いくつか業界特有の注意点もあります。
助成対象経費や要件を正確に理解する
助成金・補助金によっては「小売業は対象外」の経費項目があったり、サービス業ならではの要件(例:最低賃金引上げの実施など)が設定されている場合があります。
業者と相談しながら、自社の計画が本当に補助対象になるか事前によく確認しましょう。業界の慣習で見落としがちな点もプロなら指摘してくれます。
繁忙期と申請時期の調整
小売・飲食などサービス業は繁忙期が明確なことも多いです。
例えば年末商戦や繁忙期と申請準備期間が重なると社内対応が難しくなります。
代行業者に早めに相談し、公募開始前から準備を進めることで余裕を持って対応できるようにしましょう。
繁忙期に無理なく進める計画を立てることも大切です。
補助事業の実施と営業の両立
補助金は採択後に実際の事業を行い、報告する必要があります。
店舗改装やシステム導入などを行う際、通常営業との両立が課題になります。
計画段階で、事業実施による休業や影響を最小限にする工夫が必要。
代行業者から他社の事例を聞いて、工事期間の調整や代替措置などのアドバイスをもらうと良いでしょう。
人手不足対策と助成金
サービス業では人手不足が慢性化している業種も多く、雇用関係の助成金(例えばキャリアアップ助成金)を活用するケースが増えています。
ただし、助成金で雇用した人員の処遇改善を図ったり、新規雇用を創出する際は、助成期間終了後も雇用を維持できるかを考える必要があります。
短期的に助成金目当てで人を増やしても、後で負担になっては本末転倒。
業者とも相談しながら、無理のない計画を立てましょう。
不正受給への注意
特に雇用調整助成金などで過去に不正受給が問題になったことから、行政のチェックも厳しくなっています。
代理申請の業者が「このくらい大丈夫」と言って不適切な書類操作を提案してきたら要注意。
最終的な責任は事業主にあることを忘れず、不正につながる行為は断固避けてください。信頼できる業者であればコンプライアンスを守った申請支援をしてくれるはずです。
助成金の不正受給に関する記事として以下のものも参考にしてください。
「助成金は返還のリスクあり?経営者が知っておくべき助成金の注意点」
まとめ:助成金・補助金は企業の心強い強い味方
助成金・補助金の申請代行サービスは、中小企業にとって心強い味方です。
手数料相場は着手金数万円+成功報酬10~20%前後が一般的であり、料金プランごとのメリット・デメリットを理解して選択する必要があります。
悪徳業者に騙されないためには、「簡単に受給できる」と甘言する業者や資格・実績不明瞭な業者、高額すぎる報酬を要求する業者を避け、契約内容をしっかりチェックすることが重要です。
逆に優良な業者は公的資格や認定を持ち、実績豊富で、料金・サポート内容の透明性が高い傾向にあります。
複数社の見積もり比較や無料相談を通じて、自社に最適なパートナーを見極めましょう。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら