地方(近畿・中国・四国)で開業するならこの助成金!地域創生に活用できる制度とは?

地方で飲食業やサービス業の開業を目指す中小企業経営者にとって、自治体の助成金・補助金制度は心強い味方。
国の制度は対象外として、都道府県や市町村レベルで用意されている支援策を上手に活用すれば、開業時の資金負担を大きく軽減できます。
例えば、家賃補助や改装費補助により初期投資の一部が賄われれば、開業時のリスクを大幅に減らし安心して事業を始められるといった効果が期待できるでしょう。
本記事では、近畿地方・中国地方・四国地方の自治体が提供する主な創業支援制度について、「制度名・内容・対象条件・支援金額・申請方法・申請期間」などを紹介。
また、各地域で実際に制度を活用して成功した事例や、利用状況のデータがある場合はあわせて紹介します。
目次
地方自治体の創業支援策とは
地方自治体による創業支援策には、大きく分けて
(1)起業支援金(創業補助金)
(2)空き店舗活用支援
の二本柱があります。
前者は主に新たに創業する事業者に対し設備投資や運転資金の一部を補助する制度、後者は商店街等の空き店舗で出店する際の改装費や家賃を補助する制度です。
多くの自治体ではこれらを組み合わせ、移住や第二創業にも対応した支援メニューを用意しています。
起業支援金(創業補助金)は都道府県が中心となって実施している制度で、起業にかかる経費の1/2(上限200万円程度)を補助するものが一般的です。
例えば三重県や広島県では、地域課題の解決につながる事業を県外から移住して起業する場合などに経費の一部を補助します。
この制度は「地方創生起業支援金」として国の交付金を受けて実施されており、補助上限は概ね200万円、補助率は1/2が標準です。
対象条件として、大都市圏以外の地域での起業であること、一定期間内に法人設立または個人開業することなどが定められています。
また事業計画の審査があり、社会的事業やデジタル技術活用など地域にもたらす付加価値が重視される傾向です。
申請方法は各都府県の指定先(産業振興財団等)への書類提出で、年度ごとに公募期間が設定されています。
申請期間は自治体によりますが、例えば三重県では2024年度は6月下旬から11月中旬まで募集を行いました。
郵送での書類提出が必要で、持ち込みは不可といった注意事項も公式に案内されています。
一方、空き店舗活用支援策は市町村レベルで盛んに導入されています。
シャッター街対策として、店舗改装費や家賃の補助を行うことで商店街への新規出店を促進する制度です。
対象は小売業・飲食業・サービス業など店舗ビジネスを営む中小企業者で、自治体内の空き店舗や空き家を活用して開業するケースが該当。
例えば山口県下関市では、空き物件を活用して市内で飲食店等を始める事業者に対し、店舗改装費の1/2(上限100万円)と開業後3か月分の家賃の1/3(上限20万円)を補助しています。
補助を受ける条件として「開業後速やかに商店街組合に加盟し、商店街活動に積極参加すること」などを求める自治体も。
申請は随時または年度内に数回の審査会方式で受け付けられ、書類審査・面接等により採択される仕組みです。
さらに移住支援金といった移住促進策も併用可能です。
東京圏から地域に移住して就業または起業する人に対し、一律100万円(単身の場合は60万円)を支給する「移住支援金」制度は全国共通で用意されており、起業支援金と合わせて活用すれば最大300万円の資金援助を受けられるケースもあります。
対象地域や要件は自治体ごとに細かく規定されていますが、地方で起業する場合、起業支援金(最大200万円)+移住支援金(最大100万円)をセットで受給できる可能性があることは覚えておきたいポイントです。
それでは、以上のような創業支援制度が具体的に各地域でどのように展開され、活用されているのか、近畿・中国・四国地方ごとに見ていきましょう。

近畿地方の創業支援制度
近畿地方(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県、※三重県含む)の自治体は、全国的にも創業支援に積極的です。
ある調査によれば、近畿の自治体は「地域で起業が盛んだ」と感じている割合が全国で最も高いという結果も出ています。
背景には、大都市圏である大阪・京都を中心に起業熱が高いことに加え、各府県・市町村が独自色のある支援策を講じていることが挙げられます。
以下、府県別に主な制度を紹介します。
大阪府・大阪市など(大阪起業家グローイングアップ補助金、空き店舗補助 等)
大阪府は将来の大阪経済を担う有望なスタートアップを支援する目的で「大阪起業家グローイングアップ補助金」を実施しています。
これはビジネスプランコンテストで選抜された優秀な提案者に対し、最大100万円(優勝者)、50万円(準優勝者)の補助金を交付するものです。
対象は大阪府内で起業予定の事業者で、販路開拓や人材育成など成長加速にかかる経費を支援します(創業後3年以内の中小企業等が主な対象)。
応募・審査のプロセスが特徴的で、専門家によるブラッシュアップ支援やピッチコンテストを経て補助対象者が決定されます。
一方、大阪府内の各市町村も多彩な創業支援策を展開しています。
例えば高槻市では、新規出店する店舗の内装改装費を最大50万円補助する「高槻“魅力あるお店”応援プロジェクト」を実施し、魅力的な飲食店や小売店の開業を後押ししています。
泉南市でも「空き店舗対策家賃補助事業」により商店街の空き店舗への出店者に対し家賃補助を行っており、開業初期の負担軽減につなげています。
大阪市内各区でも、商店街振興組合と連携した空き店舗活用支援や、中小企業融資制度による創業資金の利子補給など、地域事情に合わせた支援策が整っています

兵庫県・神戸市など(起業家支援事業、商店街新規出店支援補助金 等)
兵庫県は県全体として「起業家支援事業(一般事業枠)」を実施し、新事業展開に挑む創業者に対し最大200万円規模の補助を行っています。
加えて特徴的なのが、商店街の活性化と創業支援を組み合わせた**「商店街新規出店・開業等支援事業補助金」です。
これは商店街の空き店舗に新規出店する若者(概ね50歳未満)や女性に対し、店舗改装費・ファサード整備費・賃借料の一部を補助する制度で、補助率は県1/6・市町1/6(合わせて経費の1/3)・上限75万円までと定められています。
補助を受けるためには出店後に商店街団体へ加盟し活動に積極参加することが条件となっており、単なる金銭支援にとどまらず商店街の担い手として育成する狙いがあります。
県内各都市でも独自の創業支援が活発です。神戸市では新産業創造を掲げ、スタートアップ企業のオフィス賃料補助や、商店街での若者・女性出店チャレンジ補助金などを展開しています。
例えば神戸市の「商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業」では、兵庫県の制度と連携して市独自に上乗せ補助を行い、若手起業家の飲食店開業などを積極支援しています。姫路市や尼崎市もオフィス賃料補助や空き店舗改装補助を用意しており、県南部の都市を中心に創業支援メニューが非常に充実しています。

京都府・京都市など(起業支援金、チャレンジショップ補助金 等)
京都府は独自色のある支援策として「産学公の森推進事業補助金」や「危機克服対応ビジネス創出支援事業」を実施し、新技術や大学発ベンチャーの創出を後押ししています。
これらは伝統産業が盛んな京都ならではの施策で、大学・公的機関と連携したイノベーション創業を支援する内容です。
さらに一般の創業者向けには、京都府中小企業信用保証制度を活用した融資支援や、移住創業者への補助金(例:南丹市の移住者起業支援事業)などもあります。
京都府の起業支援金も他府県同様に最大200万円・補助率1/2で公募されており、地域課題解決型のビジネスに重点が置かれています。
京都市や周辺市町村でも、クリエイティブ産業や伝統産業の開業支援、空き町家の活用などユニークな施策が見られます。
例えば綾部市では「チャレンジショップ支援事業費補助金」を設け、一定期間お試し出店する店舗に対し家賃補助などを行っています。
城陽市の「明日のかがやく産業創出補助金」では、新規性ある事業計画に対し最大50万円を助成し、将来の市内産業の核となる企業の育成を図っています。
京都市自体は伝統的に金融支援(融資・信用保証)が中心ですが、隣接する都市を含めたエリア全体で多様な創業支援のネットワークが構築されています。

滋賀県(滋賀県起業支援金、空き店舗活用補助 等)
滋賀県では「滋賀県起業支援金」を通じて、県内で新たに起業する人を公募により支援しています。
直近では令和6年度に第二次募集も行われ、地域の創業機運の高まりがうかがえます。
支援内容は他府県同様補助率1/2・上限200万円で、滋賀県産業支援プラザが窓口となり事業計画の審査・伴走支援を行います。
対象条件には、県内で課題解決型ビジネスを起こすことや一定期間の事業継続計画などが盛り込まれています。
市町の施策では、大津市が「創業促進事業補助金」を設け創業準備経費の一部を助成しているほか、長浜市は城下町の空き店舗対策に熱心で、「まちなか出店支援事業補助金」により中心市街地で新規開業する店舗に最大100万円規模の補助を行っています。
また草津市では大学発ベンチャー誘致のためインキュベーション施設入居補助を出すなど、地域特性に合わせた創業支援が展開されています。
滋賀県は地理的に京都・大阪のベッドタウンでもあるため、都市圏からのUターン起業や若者の地元定着を促す施策が目立つと言えるでしょう。

奈良県(起業家支援事業、移住創業支援金 等)
奈良県は2024年度より「奈良県起業家支援事業」を開始し、成長志向のスタートアップを支援し始めています。
また全国型の制度として「移住・就業・起業支援事業(移住支援金)」にも参画しており、東京圏から奈良へ移住して起業する場合に最大100万円の支援金を交付しています。
加えて県の制度融資「創業支援資金」では、創業期の事業者に低利融資を実施し金融面からもバックアップしています。
奈良県内の市町村では、小規模自治体まで含め創業支援の取り組みが広がっています。
奈良市は創業支援資金の融資あっせんや創業支援事業計画に基づく特定創業支援(専門家相談やスクール開催)を行い、新規開業者を育成中です。
五條市では創業者向け融資の利子補給補助金を交付し、御所市では創業に伴う店舗改装費等を補助する制度を設けています。
また生駒市や天理市など移住支援金制度を活用してUIJターン創業者を誘致する自治体もあります。
歴史ある奈良県において近年は若手のカフェ開業やITベンチャーも増えており、これら自治体支援がその後押しとなっています。

和歌山県(起業支援補助金、商店街開業支援 等)
和歌山県は2025年度に向け「地域課題解決型起業支援補助金」を準備しており、地域のニーズに応える社会起業家を支援する姿勢を打ち出しています。
この補助金も補助率1/2・上限200万円が想定され、地方創生の一環として実施されるものです。
さらに和歌山県はシニア・女性起業家支援にも力を入れており、和歌山市ではシニア・女性創業者向けの融資利子補給や、中心市街地での新規出店保証料の補助といった独自策を講じています。
各地域の例を見ると、田辺市は「商店街開業支援補助金」を設けて市内商店街で新たに開業する店舗の改装費等を助成しています。
橋本市では移住者が起業する場合の安定化補助金(家賃や設備費補助)を交付し、過疎化が進む地域へのビジネス誘致を図っています。
過疎地域が多い和歌山では、町村レベルでも紀美野町や広川町が創業支援補助金を用意し、UIターンでカフェ開業した若者などを支援した事例があります。
総じて和歌山県では、都市部とは異なる「地域コミュニティ維持のための創業」が重視されており、移住定住とセットになった支援が目立ちます。
以上、近畿地方の主な創業支援制度と事例を紹介しました。
近畿では自治体ごとの制度数も多く、ここに挙げた以外にも各市町村商工課等で独自の補助を用意しています。
続いて中国地方の状況を見ていきましょう。
中国地方の創業支援制度
中国地方(鳥取・島根・岡山・広島・山口)では、人口規模が小さい県も含まれますが、その分地域の課題解決型の起業を強力に後押しする制度が整っています。
各県が実施する起業支援金は、東京圏からの移住創業者に重点を置いたものが多く、地域課題に挑む起業家に最大200万円を補助する点は共通です。
一方、市町村レベルでは中心市街地の再生や後継者不足対策を目的とした補助金が特徴的です。
それでは、県ごとに主な取り組みを見てみます。
鳥取県・鳥取市など(とっとり起業化促進事業、空き店舗家賃補助 等)
人口最少県の鳥取県ですが、創業支援策は非常に充実しています。
県は「鳥取県スタートアップ創出加速化補助金」など複数の補助金メニューを用意し、事業の各ステージに応じた支援を行っています。
特にユニークなのは「設立・開業一年後支援金」という制度で、創業直後だけでなく開業1年後に追加支援金を交付する仕組みです。
これは開業から軌道に乗るまでの継続支援を意図したもので、創業後もフォローする点が特徴です。
鳥取県内では、市町村も積極的に創業補助を展開しています。
鳥取市は「伴走型スタートアップ支援補助金」を設け、創業計画策定から開業後まで専門家が伴走しつつ資金支援を行っています。
また「まちなか・コミュニティビジネス支援補助金」により、中心市街地で地域コミュニティに資する事業を起こす場合に助成を実施しています。
米子市や境港市でも創業支援資金融資や創業補助金を独自に運用しており、小規模自治体まで創業支援ネットワークが行き渡っている印象です。
商工会等と連携し空き店舗の家賃補助や改装費補助を行う例(若桜町など)もあり、鳥取県全体で創業者を温かく迎える土壌ができています。

島根県・松江市など(島根起業支援補助金、チャレンジショップ事業 等)
島根県も地方創生の一環として「地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金」を実施しています。
これは地域の困りごとをビジネスで解決しようとする創業者に対し資金を補助する制度で、例えば高齢者支援サービスや地域産品の新事業開発などが対象となります。
同様に「スモール・ビジネス育成支援補助金」では、小規模ながら輝くビジネスを立ち上げる起業家に焦点を当て、初期投資の一部を支援しています。
自治体レベルでは、松江市が島根県と協調して「チャレンジショップ事業費補助金」を提供している点が注目されます。
これは空き店舗を一定期間借り上げ、新規創業者に低リスクで店舗営業を体験してもらう制度です。
松江市では県と共同でこのチャレンジショップを運営し、販路開拓の場として活用されています。
浜田市では「創業者支援資金補助金」により創業時の諸経費を助成し、出雲市や益田市でも商工会議所と連携した創業支援融資や空き店舗改修補助を実施しています。
特筆すべきは、隠岐の島など離島地域でも小売店等開業支援補助金が用意されている点で、人口減少が深刻な地域ほど創業支援に力を入れている状況がうかがえます。

岡山県・岡山市など(地域課題解決型起業支援金、創業促進助成金 等)
岡山県は2023年度より「地域課題解決型起業支援金」をスタートさせました(※中国地方知事会の資料より)。
これは全国型の地方創生起業支援事業の一環で、岡山県内で地域課題の解決に寄与する分野(例えば医療福祉、農林水産、観光振興など)で起業する場合に補助金を交付するものです。
具体的な補助額は他県同様最大200万円程度と見られます。
加えて岡山県は「おかやま創業サポートデスク」を設け、専門家相談や創業スクール開催などソフト面の支援にも注力しています。
市町村では、岡山市が「創業促進助成金」を実施しており、市内で創業する人に対し店舗取得費や設備費の一部を補助しています。
また倉敷市では独自の商業振興策として、商店街空き店舗への出店や販路開拓イベントへの出店に補助金を交付し、新規創業者の販路拡大を支援しています。
津山市や玉野市でも創業拠点整備や創業奨励金の制度があり、県南から北部まで広くカバーされています。
特徴的なのは、商工会議所や商工会など民間支援機関が補助金事業を受託・実施するケースがあることです。
岡山南商工会が行う「創業サポート補助金」などがその例で、地域の商工団体が地元創業者を伴走支援しながら資金面もバックアップしています。

広島県・広島市など(広島県起業支援金、スタートアップ立地補助 等)
広島県は中国地方の中核県らしく、創業支援のリソースが充実しています。
県が実施する「令和6年度起業支援金」では、東京圏からのUIターン起業や第二創業・事業承継による起業を対象に、経費の一部補助と専門家伴走支援を行っています。
具体的には、広島県商工会連合会が窓口となり、起業に要する経費1/2・上限200万円を補助するとともに、計画策定から実行まで寄り添った支援(メンタoring等)を提供します。このように地方創生の「起業支援金」制度を活用しつつ、県独自にフォロー体制を敷いている点が特徴です。
広島県内の市町でも多様な支援があります。広島市(政令市)自体はベンチャー支援拠点(スタートアップ施設整備やアクセラレーションプログラム)に力を入れており、直接的な補助金は少ないものの創業融資制度や賃料補助などを用意しています。
一方、尾道市や三原市など中核市は、「開業支援事業補助金」「創業支援補助金」といった名称で創業時の費用補助を行っており、内装工事費や設備導入費に対する助成が受けられます。
東広島市では人口減少地域で創業する場合に手厚い補助(移住創業支援金)を設け、過疎地域への起業誘導を図っています。
さらに廿日市市や福山市などでは、UIJターン創業者向けの支援金、インキュベーション施設利用料補助、創業者同士や支援機関との交流促進事業など、資金面とネットワーク面の両面から創業を支える取り組みが見られます。

山口県・下関市など(創業支援補助金、空き物件活用補助金 等)
山口県では県単独の起業支援金こそ目立ちませんが、その代わり各市町村が工夫を凝らした施策を実施しています。
最西端の下関市は、その好例として「空き物件活用ビジネス支援事業費補助金」を令和6年度に創設しました。
これは前述の通り、市内で小売・飲食・サービス業を空き店舗等で始める場合に、改装費の1/2(上限100万円)と家賃の1/3×3ヶ月(上限20万円)を補助する制度で、若手飲食店オーナーなどの活用事例が今後期待されています。
実際、下関市ではこの補助金を活用して古い空き店舗がカフェや雑貨店に生まれ変わる成功例が次々と生まれており、補助開始から半年で7件の個性的な店舗オープンにつながったと広報されています(※市発表資料より)。
その他、山口市は商店街活性化の一環で「湯田温泉回遊促進事業補助制度」などユニークな補助金を用意し、温泉街での新業態開発を支援しています。
萩市や防府市では創業支援補助金を設け、創業者に対する設備費補助や移住支援金の交付を行っています。岩国市や周南市でも移住創業促進補助金や創業支援事業を運用しており、
県東部から周防大島などにかけて地域の実情に合わせた制度が展開されています。
山口県は広島や福岡の都市圏に挟まれ人材流出が課題ですが、その分UIターンで地元に戻る起業家を厚遇する傾向が見られます。
例えば柳井市では奨学金返還補助を用意して若者のUターン起業を促すなど、創業支援と人材確保を両立する施策も登場しています。
以上、中国地方の創業支援制度を紹介しました。
続いて四国地方について見ていきます。
四国地方の創業支援制度
四国地方(徳島・香川・愛媛・高知)は人口規模こそ小さいものの、各自治体が創意工夫に富んだ支援策を打ち出しています。
UIJターンの促進や後継者難の解消といった地域課題が深刻なだけに、創業支援も単なる補助金交付に留まらず、移住支援・チャレンジショップ・伴走型サポートなど多面的です。以下、県別にポイントを見ていきます。
徳島県・徳島市など(スタートアップ創出促進補助金、中心市街地出店支援 等)
徳島県は近年スタートアップ支援に力を入れており、「スタートアップ創出促進補助金」や「ベンチャー企業等事業化促進事業」を展開しています。
これらは新技術・新産業の創出を目指す起業家に試作開発費等を補助する内容で、徳島発のベンチャー企業育成を目的としています。
一方、東京圏からの移住起業者向けには「徳島わくわく移住支援事業」による起業補助もあり、移住支援金(最大100万円)と連動して地方創生起業支援金を活用できる仕組みです。
市町村単位では、徳島市が「中心市街地出店支援事業補助金」を設けているのが目立ちます。
徳島市の中心市街地で新規開業する際、店舗改装費や家賃の一部を補助する制度で、商店街の空洞化対策に寄与しています。
同様に鳴門市や阿南市も空き店舗活用や移住支援の補助金を運用中です。
特に阿南市の「わくわく移住支援事業補助金」はUIターン希望者に手厚く、地方移住から創業まで一貫して支援する内容です。
徳島県は全域で創業支援事業計画(産業競争力強化法に基づく計画)を策定しており、小さな町村でも創業相談窓口や保証制度を整備しています。
例として三好市では「創業・空き店舗再生支援事業」として補助金を交付し、過疎地域の中心部にチャレンジショップを誘致した実績があります。

香川県・高松市など(起業スタートアップ支援補助金、空き店舗活用支援 等)
香川県は四国内でも積極的に企業誘致・創業支援を進めており、「起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)」を運用しています。
これは香川県内で地域課題の解決に資するビジネスを起こす場合に経費の1/2・最大200万円を補助する制度で、2024年度も公募が行われました(香川産業創出機構が窓口)。
また、県全体で東京圏からのUIJターン起業を支援するため「移住支援事業補助金」を設け、起業者を含む移住者に最大100万円の支援金を交付しています。
県内自治体では、高松市が移住支援金の独自上乗せ(東京圏からUIターン転職・創業者への補助)を行っているほか、善通寺市が「中小企業振興支援事業」として創業者に設備費補助や経営相談を提供しています。
善通寺市では加えて「空き店舗等活用支援事業補助金」を用意し、空き店舗に出店する際の改修費や家賃を補助する制度もあります。
観音寺市や丸亀市などでも創業支援事業計画に基づく利子補給や補助金制度が展開されており、小豆島町など離島部でも東京圏からの移住創業者に対する支援金交付が実施されています。
香川県は県土がコンパクトな分、県・市町の連携が取りやすく、ワンストップの創業相談体制やメールマガジンによる補助金情報発信など、創業者目線に立った細やかな支援が整っています。

愛媛県・松山市など(創業支援補助金、コワーキング利用補助 等)
愛媛県は他県に比べ県主導の創業補助金こそ目立ちませんが、その代わり各市町村が地域ニーズに即した支援策を用意しています。
県内最大都市の松山市では、「松山市創業支援事業」のもと、いくつかユニークな補助制度があります。
例えば「学生等起業奨励金」は若者の起業を促進するための奨励金で、学生やUIターンの若年創業者に上限額を定めて交付されます。
また「コワーキングスペース利用支援補助金」では、市内のコワーキングオフィスを利用して創業準備・営業を行う事業者に利用料の一部を補助し、創業初期の負担を軽減しています。
さらに日本政策金融公庫から融資を受ける創業者に対して利子補助を行う制度もあり、金融面でも手当てされています。
今治市では「スタートアップ創業支援補助金」を設け、地域産業(タオル・造船等)の新分野進出を図る創業者に補助金交付を行っています。
宇和島市や八幡浜市でも、商工会議所等と協力して新規創業者への設備投資補助を実施しており、過疎が進む南予地域での創業促進に力を入れています。
特徴的なのは、四国中央市のように創業と事業承継を一体で支援する補助金を用意している自治体があること。
これは、後継者不在の事業を引き継いで第二創業するケースなどに補助するもので、創業と事業承継の両課題を同時に解決する狙いがあります。
愛媛県ではこのように地域事情に応じたきめ細かな制度設計が行われており、創業希望者は各市町の商工担当課で相談すれば自分に合った支援策を紹介してもらえる環境が整っています。
高知県・高知市など(中山間地域創業補助金、チャレンジショップ制度 等)
高知県は山間部が多く人口減少も深刻なため、地域を選ばず起業できる環境づくりに特色があります。
県は「高知県中山間地域等創業支援事業費補助金」を制定し、中山間地域や離島地域で創業する場合に補助金を交付する要綱を整備しました。
これは他地域にはあまり例のない制度で、過疎地域で地域おこしに資するビジネスを興す場合に経費を補助するものです。
具体的な補助額や条件は公表資料では不明ですが、地域の商工団体と市町村長の推薦を要件とするなど、地域ぐるみで起業者を支える仕組みとなっています。
また高知県および高知市はチャレンジショップ制度にも注力しています。「高知市チャレンジショップ事業」では、市中心部の空き店舗を活用して一定期間試験出店できる場を提供し、新規開業者が低リスクで店舗経営に挑戦できるようにしています。
この制度では、チャレンジ期間中は賃料が減免または補助され、経営ノウハウについて専門家のアドバイスも受けられます。
チャレンジショップで実績を積んだ後、本格開業に移行した成功例も複数あり、県外から移住してカフェを開いた若者などのストーリーが地元紙で紹介されています(※具体事例:高知市帯屋町のチャレンジショップから生まれた飲食店など)。
高知県内の他地域でも、土佐清水市が「空き店舗対策事業(起業支援制度)」として起業支援補助金を用意したり、香南市が空き店舗活用補助や創業相談窓口を開設したりしています。
これら沿岸部の市町では、観光客向けの新しい土産物店やカフェが補助金を活用してオープンしたケースもあります。
総じて高知県は、「まずやってみる」精神を後押しする風土があり、小規模でも地域に根差したチャレンジを行政が応援するムードが感じられます。

支援制度の活用事例と地域別利用状況データ
各地域で紹介したように、自治体の創業支援制度を活用して開業にこぎつけた事例は数多く存在します。
その中からいくつか、特徴的な成功事例をピックアップしてみましょう。
空き店舗から地域拠点へ転身(北海道幕別町)
例えば北海道幕別町では、「商店街活性化店舗開店等支援事業補助金」を活用し、56年放置されていた旧理容室の空き店舗を大改装して複合施設「幕理(まくり)」をオープンした事例があります。
この施設はレンタルスペースや移住サポートセンター機能を備え、地域交流の拠点として再生されました。
補助金により改装費負担が軽減されたことで、地域おこし協力隊の建築士が中心となりプロジェクトを成功させています。
地方では補助金が起業の呼び水となり、空き物件が地域に新たな価値を生む好例と言えます。
商店街に若手カフェが続々誕生(兵庫県・山口県 等)
兵庫県の商店街新規出店補助制度では、ここ数年で神戸市や西宮市の商店街に若い女性オーナーの雑貨店やカフェが相次いで出店する成果が出ています(補助金対象者の約6割が女性起業家との報告あり)。
また山口県下関市の空き物件活用補助金では、制度開始からわずか半年で7件の新規店舗オープンにつながり、空き店舗だったテナントが次々と埋まり始めています。
このように比較的小額(数十万~百万単位)の補助金でも、開業初期の不安を減らす効果は絶大であり、結果として商店街全体の活性化に寄与しています。
移住×起業の成功例(徳島県神山町 他)
四国では、移住支援金と起業支援金を併用して都市部からの移住者が地方でIT企業やカフェを起業し成功している例があります。
徳島県神山町では、東京都から移住した起業家が県の起業支援金(200万円)と移住支援金(100万円)を活用してサテライトオフィス事業を興し、現在は町内に複数のクリエイティブ企業を呼び込むまでに至りました(神山町の事例は「創業支援の成功モデル」として総務省の地域創生事例集にも掲載)。
このように、地方の創業支援制度をフル活用し「移住起業」で成功したケースは全国各地に増えつつあり、近畿・中国・四国地方でも各県が注目・横展開しています。
創業支援制度の利用率データ
創業支援制度の利用率データについては、公的に集計・公表されたものは限定的ですが、一つの目安として「地域の起業件数」や「自治体担当者の実感調査」などがあります。
帝国データバンクの調査によれば、近畿2府4県(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)では2024年に27,056社の新設法人が確認され、2年連続で過去最多を更新しました。
これにより近畿の新設法人数は前年比0.7%増と堅調で、全国的にも東京圏に次ぐ水準となっています。
起業の裾野が広がる中、自治体職員を対象とした意識調査では「当自治体で起業は盛んだ」と答えた割合が近畿地方で46.7%と全国最高である一方、中国地方も「盛ん」「どちらとも言えない」が拮抗し起業機運が高まりつつあるとの結果が出ています。
四国地方はまだ「どちらとも言えない」が多数派でしたが、それでも各県で年間数百件規模の創業があり、多くの新規事業者が何らかの公的支援を利用しています。
制度の利用率(採択率)という観点では、各補助金ごとに公募件数と採択件数のデータがあります。
例えば北海道のある創業補助金では採択率約47%、東京都の創業助成事業では13%程度との報告がありますが、地方の起業支援金は比較的応募者が限定されることもありおおむね5~6割程度が採択されているとの推計もあります(地域によって差は大きいです)。
採択されなかった場合でも、自治体の創業支援担当者から他の融資制度や再チャレンジのアドバイスを受けられる場合が多く、書類準備や事業計画のブラッシュアップを経て再度応募して採択に至ったケースも珍しくありません。
まとめ:支援制度を賢く活用して地域での成功をつかもう
近畿・中国・四国地方の自治体が提供する多彩な助成金・補助金制度をご紹介しました。
制度の名称や内容は地域ごとに様々ですが、その根底にある目的は共通しています。
それは、「意欲ある起業家を応援し、地域経済に新たな息吹を吹き込むこと」です。
地方での創業は都市部に比べ課題もありますが、自治体の後押しを得ることで資金面・情報面のハードルを下げ、よりスムーズにスタートを切ることができます。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら









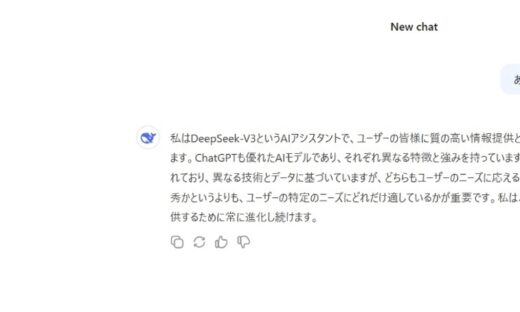
-520x312.jpeg)








