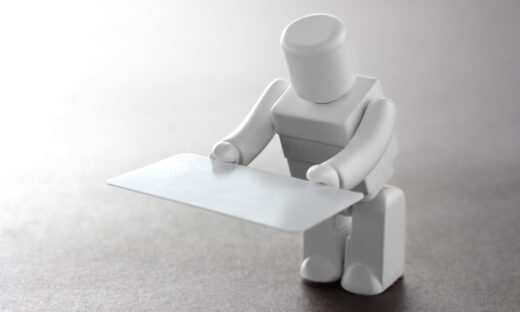研修費用を助成金でまかなおう!社員教育に活用できる支援制度

社員のスキルアップや人材育成は企業成長に欠かせません。
しかし、研修や教育には費用が伴い、中小企業にとっては大きな負担となりがちです。
そこで活用したいのが研修費用を補助してくれる助成金制度。
国や自治体が提供する助成金を上手に活用すれば、社員研修にかかる費用の一部をまかなうことができ、人材育成を推進しながら経営負担を軽減できます。
本記事では関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀)の中小企業経営者の皆様に向けて、社員研修・教育に活用できる代表的な助成金制度の種類や内容、申請方法、活用上の注意点について詳しく紹介します。
特に関西での活用例や自治体独自の取り組み、申請窓口にも触れますので、自社の社員研修にぜひ役立ててください。
※昨今では,AI研修を検討される方が増えています。AI研修の実施を検討している方は以下の記事で比較することもおすすめです。
「AI研修企業おすすめ15選|選び方や各社の特徴・強みを徹底解説」|株式会社KAGEMUSHA
目次
社員研修に使える助成金制度の基礎知識
社員研修に使える助成金とは、企業が従業員に対して行う職業訓練や能力開発に対し、国や自治体が費用の一部を支給する制度です。
助成金は融資や貸付と違って原則返済不要であり、条件を満たせば給付されるため、中小企業にとって非常に有用な支援策です。
まずは助成金制度の基本と押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
助成金と補助金の違い
一般的に「助成金」と「補助金」は似た意味で使われますが、行政上は若干ニュアンスが異なります。
助成金は厚生労働省系の制度に多く、要件を満たせば基本的に受給できるものが多いです。
一方、補助金は経済産業省系や自治体によるものが多く、採択方式(公募に対し審査・選考)である場合があります。
本記事では便宜上まとめて「助成金」と表現します。
いずれにせよ、中小企業の人材育成を経済的に支援してくれる制度である点は共通しています。
助成金を活用するメリット
助成金を活用する主なメリットは以下のとおりです。
●費用負担の軽減
研修費用や研修中の人件費の一部が補填されるため、限られた予算でも質の高い教育機会を提供できます。
●人材育成の促進
社員がスキルアップしやすい環境を整えることで、従業員のモチベーション向上や定着率アップにつながります。
●経営力の強化
社員の能力向上は生産性向上や新規事業への挑戦に直結し、結果として業績向上や競争力強化という経営メリットを生みます。
例えば、助成金を活用して社員に専門資格取得研修を受講させた企業では、費用の7割超が助成され、新たな取引先獲得につながったケースも報告されています。
国と自治体による支援制度の種類
社員研修に関連する助成金には、大きく分けて国(厚生労働省)の制度と自治体独自の制度があります。
国の代表的なものとしては後述する「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金」があり、全国共通の基準で利用できます。
一方、各自治体(都道府県や市区町村)でも、中小企業の人材育成を支援する独自の補助金を用意している場合があります。
本記事でも関西の自治体による取り組みを紹介しますが、自社所在地の自治体の制度もあわせて確認するとよいでしょう。
関西地域における特徴
関西エリア(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県)でも、国の助成金制度は全国同様に利用できます。
さらに関西の自治体では、人材育成支援に積極的な施策が展開されています。
例えば大阪府では2025年度から「中小企業従業員人材育成支援補助金」という新たな制度を開始し、中小企業が従業員を社外研修に参加させる際の費用を補助しています。
このように関西ならではの上乗せ支援もありますので、後ほど詳しく説明します。
では具体的な助成金の種類と内容を順に見ていきましょう。
中小企業が研修費用に活用できる主な助成金の種類
中小企業の社員研修に使える代表的な助成金として、厚生労働省所管の**「人材開発支援助成金」と「キャリアアップ助成金」がよく知られています。
ここではこれらを中心に、場合によって研修費用に充てることができるその他の制度も含めて紹介します。

人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、企業内で従業員に職務に関連する専門知識や技能を習得させる職業訓練を計画的に実施した場合に、研修費用(受講料等)や研修期間中の賃金の一部が国から助成される制度です。
以前は「キャリア形成促進助成金」と呼ばれていた制度が拡充・改称されたもので、従業員の能力開発を支援する代表的な助成金。
この助成金には複数のコースがあり、企業の取り組みに応じて選択できます。
主なコースには以下のようなものがあります。
人材育成支援コース
計画に沿ってOFF-JT(業務を離れて行う訓練)等の職業訓練を実施した場合に経費・賃金を助成。
一般的な社内研修や外部研修の受講に幅広く利用されます。
人への投資促進コース
DXや成長分野の高度な人材育成、定額制の研修受け放題サービスの活用、従業員の自主的な学び直し支援など、近年重要性が高まる分野の訓練を支援するコース。
デジタルスキル習得やeラーニング活用研修も対象です。
教育訓練休暇等付与コース
従業員に長期の職業訓練休暇制度や短時間勤務制度を導入して、自発的な能力開発を促した場合に助成。
例えば社員が仕事を離れて大学院に通う制度を設けた場合などに活用できます。
事業展開等リスキリング支援コース
新規事業や業態転換に伴い、従業員に新分野の知識・技能を習得させる訓練を行った場合に助成。
企業の事業再構築や新分野進出に合わせたリスキリング研修を支援します。
助成率・助成額はコースや訓練内容によって異なりますが、中小企業の場合、研修経費の45%~75%程度が助成されるのが一般的です(要件を満たし生産性向上が認められる場合は助成率引き上げあり)。
さらに訓練期間中に支払った賃金についても一定額(中小企業は1人1時間あたり760~960円など)を助成してもらえます。
例えば、ある中小IT企業(従業員30名規模)では社外の資格取得講座(OFF-JT30時間、受講料28万円)を受講させ、一人当たり経費21万円(28万円の75%)と賃金2万8800円(960円×30h)の助成を受けています。
このように研修費用の大部分を助成金で賄うことも可能です。
対象となる企業・従業員は、雇用保険適用事業所の事業主であることが基本要件。
中小企業・大企業を問わず利用できますが、中小企業のほうが助成率や上限額が優遇されています。
また研修を受ける従業員も原則として雇用保険の被保険者である正社員や契約社員が対象です(※新入社員研修にも活用可能)。
パートタイマーなど短時間労働者の場合は条件を満たせば対象になり得ますが、研修コースによって細かい要件があります。
申請手続きとして重要なのは、研修を開始する前に所定の計画届を労働局に提出し認定を受けることです。
具体的には、年間の職業能力開発計画を立てたうえで「職業訓練実施計画届」を訓練開始日の1か月前までに管轄の労働局(都道府県労働局)へ届け出ます。
計画が受理・認定されたら研修を実施し、研修終了後には支給申請を行います。
支給申請は研修終了後2か月以内など期限が決まっており、研修の実施記録や受講証明、かかった費用の領収書、賃金台帳など必要書類を添えて申請。
申請が適正に認められれば、後日助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、契約社員・パート・アルバイトなどの非正規雇用労働者の処遇改善やキャリアアップに取り組んだ事業主に支給される助成金です。
社員研修そのものを補助する制度ではありませんが、非正規社員を正社員化する際の研修支援や、昇給・資格取得支援など間接的に人材育成につながる取り組みに対して助成が行われるため、広い意味で社員教育・能力向上に資する制度といえます。
キャリアアップ助成金には企業が行う処遇改善の内容に応じて現在7つのコースがあります。
主なコースと概要は以下のとおりです。

正社員化コース
有期契約社員やアルバイト・パート、派遣社員などを正社員(無期・フルタイムの雇用)に転換または直接雇用した場合に支給。
支給額は中小企業の場合、対象者1人あたり57万円(※生産性要件を満たせば72万円)です。
例えば契約社員5名を正社員登用すれば最大で約285万円の助成を受けられる計算になります。派遣社員を受け入れて正社員化した場合や、ひとり親家庭の労働者を正社員化した場合、あるいは後述の人材開発支援助成金を活用した後に正社員化した場合などは加算措置もあります。
賃金規程等改定コース
非正規社員の基本給を一定率(2%以上)引き上げるなど給与規程を改定し実施した場合に支給。
例えばパート社員全員の時給を2%以上ベースアップすれば、人数に応じ定額の助成金(中小企業は1事業所あたり最大100人まで、一人あたり数万円規模)を受け取れます。
健康診断制度コース・諸手当制度共通化コースなど
非正規社員にも正社員と同等の健康診断受診機会や手当制度を導入した場合に支給。
福利厚生や待遇面の改善を図る取り組みです。
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
短時間労働者に社会保険適用を拡大した際に、企業独自に手当支給等で処遇改善を行った場合に支給されるコースです。
社会保険加入促進と処遇改善をセットで支援する内容です。
キャリアアップ助成金を活用することで、非正規社員の意欲向上や定着率アップに寄与し、結果的に人材確保や育成の土台強化につながります。
正社員化により従業員のキャリアパスを明確にすることで、研修への取り組み意欲も高まるでしょう。また正社員転換後6ヶ月以上雇用継続することが支給条件なので、計画的な育成・フォローが企業側にも求められ、結果として人材育成につながります。
対象となる企業・労働者は、こちらも雇用保険適用事業所であることが前提。
支給の対象となるのは非正規雇用の労働者(有期契約社員、パート、派遣社員、嘱託社員など)に対してキャリアアップ措置を講じた事業主です。
支給対象外となるケースもあり、例えば事業主や役員の親族(3親等以内)を正社員化する場合は対象外など、細かい要件が定められています。
また一事業所あたり年間○人までといった上限もコースごとにあります(正社員化コースは1事業所20人/年まで)。
申請手続きで特に重要なのは、事前に「キャリアアップ計画書」を作成・提出して労働局の認定を受けること。
これは助成金の対象となる非正規社員の処遇改善プランを定めた計画書で、正社員化や賃上げなど各取組を実施する前日までに提出が必要です。
計画認定後、就業規則の整備や実際の転換・昇給措置を行い、その後6ヶ月以上該当労働者に所定の待遇を継続提供します。
この6ヶ月経過後、速やかに支給申請を行う流れです。
手続き期間が長く、計画作成から受給まで1年程度かかるケースもあります。
そのため余裕をもったスケジュールで取り組むことと、計画段階で社内整備をきちんと行うことが肝要です。
雇用調整助成金(研修活用の特例)
雇用調整助成金は景気悪化などで事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、解雇を回避するため一時的に休業・教育訓練・出向などを行った場合に休業手当や訓練費用を補助する制度です。
本来は雇用維持策としての助成金ですが、「教育訓練」を行った場合には休業のみの場合より助成率が上乗せされる特例があります。
具体的には中小企業の場合、休業中に従業員へ職業訓練(スキルアップ研修)を実施すると、訓練中の賃金に対して通常の助成率に加え**訓練加算額(1人1日あたり額)**が支給されます。
コロナ禍など緊急時にはこの訓練加算が拡充され、在宅訓練にも適用されるといった特例措置も行われました。
平時でも、自社が一時的な業績悪化に陥った際には雇用調整助成金を活用しつつ社員研修を実施することで、雇用を守りながらスキルアップを図ることができます。
ただし雇用調整助成金は利用要件が「経営環境の悪化による休業等の実施」となっており、安定時には使えません。
あくまで緊急時の措置ですが、「研修を実施すること自体」が助成金受給のプラス要素になる点で、社員教育にも活用し得る制度として押さえておきましょう。
その他の研修関連助成制度
上記以外にも、状況によって社員研修に活用できる制度があります。
業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額引き上げる中小企業に対して、生産性向上のための設備投資や人材育成研修等にかかった費用を一部助成する制度です。
賃上げが目的の助成金ですが、研修実施も支給対象経費に含まれるため、賃金アップとスキル向上を同時に図る取組みに活用できます。
中小企業大学校の受講料助成
中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校の研修を受講する場合、自治体によっては受講料の一部を補助する制度があります。
例えば大阪府摂津市や吹田市では、中小企業大学校関西校の研修を受ける中小企業者に補助金を出す制度があるように、各地の自治体・商工会議所が独自に研修参加費を助成するケースもあります。
教育訓練給付制度(個人給付
社員個人が厚生労働省指定の講座を受講した場合に、受講料の一部をハローワークから給付される制度。
これは個人への直接給付ですが、会社が従業員の資格取得を奨励する際に活用できます。
社員が自己啓発で資格学校に通う場合などに、この制度を案内すれば結果的に企業の人材レベル向上につながります。
助成金制度の概要・条件と申請手順
それでは、前述した主な助成金制度について、改めて支給の条件(対象企業・従業員の要件)や申請手順を整理してみましょう。
助成金は制度ごとに細かな要件がありますが、共通するポイントも多いです。
ここでは代表的なものの条件と手続きの流れを中心に解説します。
人材開発支援助成金の条件と申請の流れ
●対象企業
雇用保険適用事業所の事業主であること。
研修計画の策定・届出を行い、計画に沿って従業員訓練を実施する意思と体制があること。中小企業・大企業いずれも利用可(助成率は中小企業が優遇)。
●対象従業員
原則として雇用保険被保険者である在職従業員。
正社員のほか、有期契約社員やパートでも被保険者で一定要件を満たせば対象になり得る。派遣労働者の場合は派遣元事業主が申請可能。
●対象となる研修
従業員の職務に関連した知識・技能を高めるためのOFF-JTやOJT、自己啓発支援、教育訓練制度の導入など。
研修の種類や実施方法はコースにより異なるが、基本的に業務に役立つ内容であれば外部セミナー受講から社内講師による研修まで広くカバー。
一定の時間数や受講証明など客観的な実施記録が必要。オンライン研修(eラーニング)も対象。
申請の流れ
●年間計画の策定・届出
まず社内で年間の職業能力開発計画や訓練計画を立て、所定の様式で「訓練実施計画届」等を作成します。研修開始日の1か月前までに管轄労働局(またはハローワーク)に提出し、計画の認定を受けます。
●研修の実施
計画どおりに研修を実施します。
研修の受講記録や写真、出席簿、講師謝金の領収書などエビデンスをしっかり残します。また研修中に支払った賃金(有給扱いにした場合など)も記録を取ります。
計画から外れる変更があった場合は速やかに計画変更届を提出します。
●支給申請
研修がすべて終了したら、必要書類を揃えて助成金の支給申請を行います。
提出期限は研修終了日の翌日から起算して2か月以内など決められています。
提出先は計画届と同じ管轄労働局です。
申請に不備がなく要件を満たしていれば、審査ののち指定口座へ助成金が支払われます(支給決定までは数か月程度かかります)。
※計画届から支給までの一連の手続きは、厚労省のオンラインシステム(雇用関係助成金ポータル)で電子申請も可能です。
初めての際は書式作成が煩雑に思えるかもしれませんが、厚労省や都道府県労働局が作成したチェックリストや手引きがありますので、それらを参考にするとよいでしょう。
キャリアアップ助成金の条件と申請の流れ
●対象企業
雇用保険適用事業所の事業主で、非正規雇用労働者の処遇改善(正社員転換、賃金UP等)に取り組む意思があること。
各コースごとに「○○の制度を実施」「賃金○%アップ」など具体要件を満たす必要があります。事前に労働局への計画書提出が必須。
●対象労働者
有期契約社員、パートタイマー、派遣社員、契約嘱託社員など非正規で雇用している労働者。正社員化コースの場合、転換前に同一事業所で6か月以上雇用されていること等の条件があります。
また事業主の親族や役員は対象外など除外規定があります。
●対象となる取組内容
コースにより異なりますが、「有期→正社員への転換」「基本給の2%以上昇給」「一定の手当制度導入」「短時間正社員制度創設」「非正規への健康診断実施」など非正規社員の待遇を正社員に近づける措置が中心です。
各コースとも所定の条件(例えば正社員転換なら賃金3%以上増額)を満たす必要があります。
申請の流れ
●キャリアアップ計画の作成・提出
まず取り組み開始前に「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の労働局またはハローワークに提出して認定を受けます。
計画書には対象労働者や実施内容、実施期間(3~5年間)などを記載します。
例えば正社員化コースの場合、転換予定者や転換時期、転換後の処遇を計画に盛り込みます。
●就業規則の整備・取組の実施
計画に沿って必要な制度整備を行い、実際に非正規社員への処遇改善を実施します。
正社員化なら就業規則に転換制度を明記し、労基署届け出後に対象者を正社員登用します。昇給なら新しい賃金規程を策定し周知した上で昇給を実施。
社会保険加入や各種手当支給も該当コースの要件に従い行います。
●一定期間の維持
正社員化や昇給等の措置を行った後、その状態を6か月以上継続します(コースにより1年の場合もあり)。
例えば正社員転換後は少なくとも6か月は継続雇用し、その間3%以上昇給後の賃金を支払い続ける必要があります。
●支給申請
維持期間を終えたら、翌日から起算して2か月以内などの期限内に労働局へ支給申請を行います。
申請には転換前後の雇用契約書や6か月分の賃金台帳、就業規則写しなど多くの書類が必要です。
申請後、審査を経て支給決定となれば助成金が支払われます。
なお、複数期に分けて支給されるコース(例えば正社員化コースの障害者転換は前期・後期の2回支給)もあります。
キャリアアップ助成金の手続きは、計画提出から支給まで長期に及ぶ点と、就業規則の変更を伴う点で煩雑です。
厚労省も手続きの迅速化に努めていますが、「初めてで不安」という場合は社会保険労務士など専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
申請先と相談窓口
国の助成金(人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金など)の申請窓口は、企業の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークです。
計画届や支給申請書類は労働局雇用環境・均等部門や職業安定部門に提出します。
不明点は労働局内の助成金相談窓口に問い合わせることができます。
関西エリアの場合、大阪労働局、兵庫労働局…と各府県に労働局がありますので、自社所在地の窓口を確認しましょう。
厚生労働省のウェブサイトにも各種様式や手引きが公開されています。
自治体独自の補助金については、それぞれの都道府県庁・市役所の担当部署(産業労働局や商工労働部門など)が窓口。
例えば大阪府の補助金なら大阪府の担当課、姫路市の制度なら姫路市役所の産業振興担当課への申請となります。
商工会議所等が窓口となるケースも。
各自治体の公式サイトに公募要項や問い合わせ先が掲載されていますので、利用を検討する際は確認してください。
助成金活用時の注意点とよくある落とし穴
助成金は条件を満たせば返済不要でもらえるありがたい制度ですが、申請・活用にあたって注意すべき点も多くあります。
最後に、助成金活用時の主な注意点や陥りがちな落とし穴を整理します。

計画書の事前提出を忘れない
もっとも多い落とし穴は「計画届の事前提出を忘れてしまった」ケース。
人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金では、研修や転換の実施前に計画書を提出して認定を受けることが必須条件となっています。
計画届を出さずに研修を実施してしまうと、事後申請は認められず助成金を受け取れません。
「助成金があると後から知ったが、既に研修を終えていた」という事態にならないよう、必ず事前に制度を調べ計画書を提出しておきましょう。
書類不備や手続き遅れに注意
申請書類の不備や提出期限超過も、助成金を受給できない原因となります。提出書類は種類が多く細かい記載が求められるため、記入漏れ・添付漏れがないかしっかり確認しましょう。
チェックリストを活用し、必要書類を事前に揃えておくことが重要です。
また支給申請の期限(研修終了後○日以内、転換後○ヶ月経過後○日以内など)を過ぎると不受理となります。
スケジュール管理を徹底し、余裕をもって行動してください。
実現不可能な計画はNG
助成金の計画を立てる際に、助成金欲しさに非現実的な数値目標を掲げることは避けましょう。
計画通り実施できなかった場合に助成金が受け取れないのはもちろん、極端な計画は後日不正受給の疑いを持たれるリスクもあります。
例えば研修未実施なのに実施したと見せかける計画は論外。
計画はあくまで自社が無理なく実行可能な内容とし、誠実に取り組むことが大前提です。
不正受給への厳しいペナルティ
万が一、意図的に虚偽申請や水増し請求など不正受給を行った場合、助成金の返還だけでなく刑事告訴や企業名の公表といった厳しい処分が科される可能性があります。
助成金は公的な税金・雇用保険料が原資です。
不正受給は絶対に行わないようにしましょう。
受給までのコスト・期間も考慮する
助成金は給付までタイムラグがあります。研修費用や賃金は一旦全額企業が立て替え、後から一部が戻ってくる形になるため、受給までの資金繰りも計画に入れておきましょう。場合によっては「最終的に助成金で補填されるから」と無理に高額な研修を実施すると、支給決定前に資金繰りが苦しくなる恐れもあります。
長期的に見ればプラスでも、短期的なキャッシュフローも念頭に置き、本末転倒にならないよう注意が必要です。
専門家や支援機関の活用
助成金の申請実務に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)や中小企業診断士など専門家に相談することを検討しましょう。
信頼できる社労士であれば、自社に合った助成金の選定から計画書作成、申請書類のチェックまで二人三脚でサポートしてくれます。
費用は発生しますが、結果的に確実に助成金を受給できる安心感と手間削減のメリットがあります。
また各都道府県の中小企業支援センターや商工会議所でも、助成金に関する相談窓口を設けている場合があります。公的機関の無料相談も積極的に活用しましょう。
最近では第三者のコンサルタントから「簡単に助成金をもらえる」と持ちかけられ、不正受給に加担してしまうケースも報じられています。
知らなかったでは済まされませんので、疑わしい提案には乗らないことです。
参考:「助成金詐欺に注意!企業が安全に助成金を活用するためのチェックポイント」
関西エリアにおける助成金活用事例と地域の取り組み
最後に、関西地域での助成金活用事例や自治体独自の支援策について触れておきます。
自社と近い地域・環境での成功事例や制度を知ることで、より具体的なイメージが持てるでしょう。
関西の中小企業における活用事例
関西エリアの中小企業でも、国の助成金を活用して社員研修や人材育成を推進している例が数多くあります。
例えば大阪市内のIT企業(従業員30名)では、人材開発支援助成金を利用して社外のプログラムマネジメント研修に社員を参加させました。
1人あたり30時間・28万円の研修に対し、経費の75%(21万円)と研修中賃金の一部約3万円が助成され、自己負担を大きく減らすことができました。
研修を受けた社員は高度なプロジェクト管理スキルを身につけ、同社は受注する案件の幅が広がり新規顧客の獲得につながったそうです。
また京都府の製造業A社では、契約社員5名を正社員登用する際にキャリアアップ助成金(正社員化コース)を活用し、約285万円(57万円×5名)の助成金を受給しました。
その資金を社員研修用の教材整備やOJT指導者の育成に再投資し、正社員となった従業員の戦力化を一層促進したとのと。
このように、助成金を上手に活用して人材育成と経営強化の好循環を生み出している事例が関西にも多数存在します。
大阪府の独自支援策:「中小企業従業員人材育成支援補助金」
関西の自治体の中でも特に大阪府は人材育成支援に熱心です。
令和7年(2025年)度から大阪府が新設した「中小企業従業員人材育成支援補助金」は、府内中小企業が従業員に社外研修を受講させた場合に研修費用の一部を補助する制度です。
具体的には、研修受講料の2分の1(50%)を府が負担します。
ただし、人手不足が深刻な運輸業・建設業関連の研修や企業ニーズが高いデジタルスキル研修については補助率が引き上げられ、なんと受講料の4分の3(75%)が補助されます。
しかもこれら特定分野の研修には1人当たりの補助上限額がなく、全額の3/4が補助対象。
その他分野の研修は1人あたり上限20万円までの補助となっています。
例えば大阪府内の企業が従業員を民間のDX人材育成講座に参加させ、受講料が10万円だった場合、7万5千円を大阪府が負担し企業の実質負担は2万5千円で済む計算です。
非常に手厚い補助であり、国の人材開発支援助成金と組み合わせて使うことも可能です(国の助成を受けた残り自己負担分について府の補助を受ける)。
大阪府のこの補助金は予算枠が限られており公募期間内の申請が必要ですが、関心のある企業様は大阪府の公式サイトをチェックしてみてください。
その他の関西自治体の取り組み
大阪府以外にも、関西の各自治体で人材育成支援の制度があります。
例えば兵庫県姫路市では「中小企業者等人材養成補助金」として、姫路商工会議所が開催する特定の研修を受講する中小企業に対し受講料の一部を補助しています。
対象研修に参加する場合、企業からの市への申請は不要で受講料が予め割引される仕組みです。
ラインナップには若手社員向け研修や管理職研修、営業力向上研修など実践的な講座が含まれ、1人あたり数千円~数万円の補助となっています。
また兵庫県尼崎市では「中小企業スキルアップ支援補助金」として、DX・IT化や業務効率化に資する研修受講や資格取得にかかった費用の一部を補助する制度を設けています。
申請は研修開始の2週間前までに行い、研修受講料や社内研修の講師謝礼まで幅広く経費補助対象となっています。
テーマもDX・IoT、内製化、受注拡大など明確で、中小企業の競争力強化につながるスキル習得を後押しする内容です。
京都府や滋賀県、奈良県、和歌山県でも、中小企業の人材育成や働き方改革に関連した補助事業が実施されています。
滋賀県では介護業界向けに研修受講支援の補助金や、DX人材育成に対する補助金など、業種・分野別の人材育成支援策があります。
各府県の中小企業支援策を調べると、研修費用助成に該当しそうなものが見つかるかもしれません。
まとめ:助成金を活用して人材育成を強化しよう
人材育成は、企業の成長と持続的な経営のために欠かせない投資です。
しかし、研修にかかる費用や時間が負担になり、なかなか踏み出せない中小企業も少なくありません。
そんな時に頼りになるのが、国や自治体が用意している各種助成金制度です。
「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金」をはじめとした制度を活用すれば、研修費用の一部だけでなく、研修中の賃金までも補助されるケースがあります。
加えて、関西地域では自治体独自の支援制度も充実しており、うまく組み合わせることで、自己負担を最小限に抑えながら効果的な人材育成が可能です。
助成金の活用には、計画の事前提出や正確な書類作成といった手続きが必要ですが、丁寧に進めれば確実に経営を後押しする強力な支援となるでしょう。
わからないことがあれば、社会保険労務士や地域の支援機関に相談するのも有効です。
私たちは 15年間で4,500社以上の助成金申請をサポートし、受給率99%以上 の実績を誇ります。
貴社に最適な助成金を見逃していませんか?
専門家が 無料で診断 し、申請から受給まで徹底サポート!
まずはお気軽にご相談ください。
Next HUB株式会社では、人材育成や経済・経営に関わる様々な情報も配信中です。
助成金については、資料のダウンロードもできますので、ぜひお気軽にサービス内容を確認してください。
—
サービス資料ダウンロードはこちら